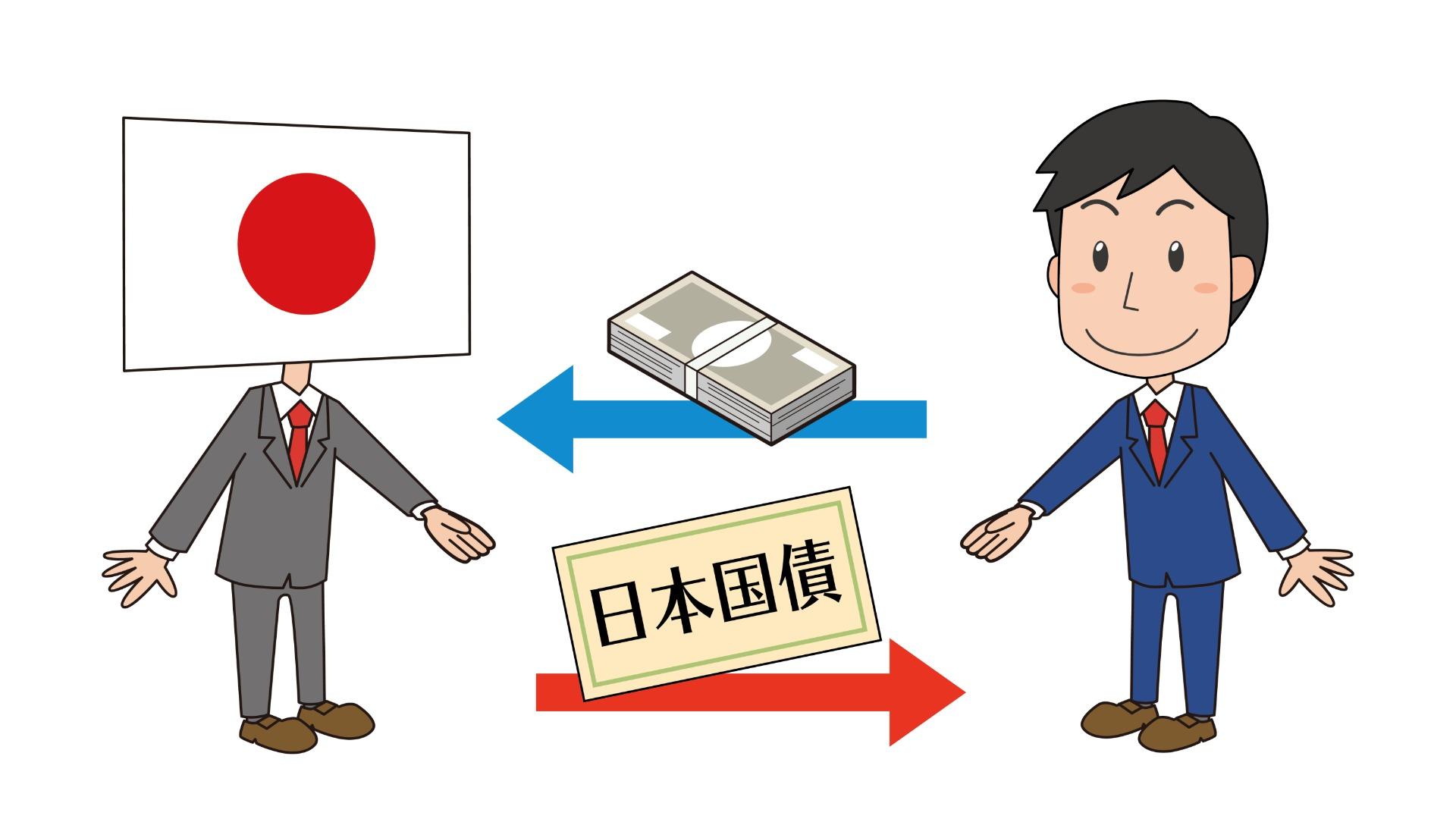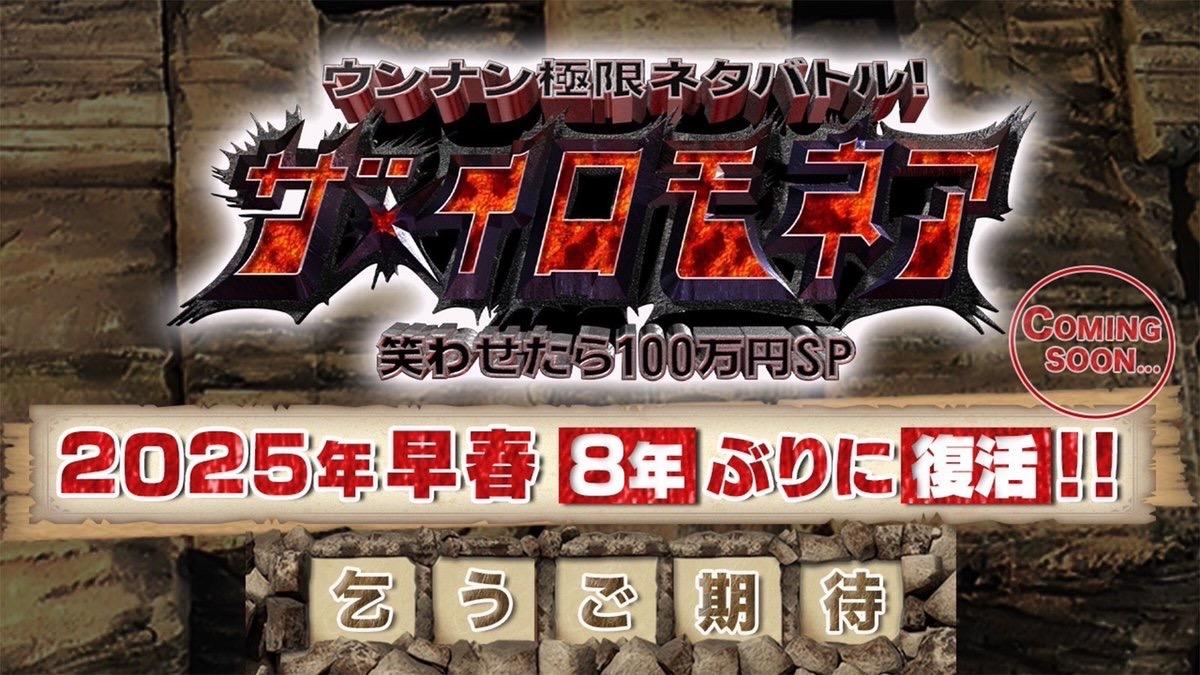行楽先で緊急通報できないことがある まさかスマホで助けが呼べないなんて!?

この大型連休に自然を満喫する方、多いかと思います。自然の中では水難事故等まさかのアクシデントがつきものですが、そんな時にスマホで助けが呼べなかったらどうしましょう?令和の時代にこんなことがあるなんて。
保津川下りの事故現場を視察しました
京都府亀岡市の保津川(桂川)の川下り船が転覆した事故については記憶に新しいところです。桂川の上流にある明治国際医療大学にはご縁があってよく訪れるものですから、山陰本線で京都駅から現場を経て鍼灸大学前駅に行く道中の(愛称)JR嵯峨野線からトンネルの切れ目を狙って今回事故現場となった川をこれまでも何度も眺めたものでした。
事故後の比較的天気のよい日曜日に、前述の明治国際医療大学の木村隆彦教授と共に現場の視察程度の調査に入りました。出発は嵯峨野線の馬堀駅からみて桂川の対岸からで、左岸川沿いの道伝いに事故現場に近づきました。途中、ハイキングコースにもなっている舗装のない道路を進んでいくと、春の陽気に誘われて目にまぶしい緑と可愛らしい小鳥のさえずりが聞こえて…くるはずだったのですが。土のむき出しになった道路上で日向ぼっこしていたのはおびただしい数のハエと大きなハチたちでした。
「これはえらい所に入り込んでしまったな」と後悔は先に立たず、顔の周囲を「ブーン」と音を立てて飛びまわる無数の虫が、息をする度に口に入ってきそうな恐怖感の中、2人で顔に飛びかかる虫たちを追い払いながら、なんとか事故現場に近づくべく前進あるのみでした。
木村教授は前職が消防の救急救命士だったので、「こんな所でハチの攻撃にあったらひとたまりもないで。すぐに病院にいかなショック死するで」と。その時にふとスマホの画面に目をやると「圏外」のマークが。
「気のせいか」とスマホから目をはなし、道路からの眼下に目を落とすと、崖の下には気持ちよさそうな川の流れが。ある所ではゆっくり流れ、またある所では白いしぶきをあげながらダイナミックに流れていました。水と戯れるのが大好きな筆者にとって、この流れの緩急がとても魅力的に映りました。
保津川下りの営業は現在休止中ですが、多くのカヌー愛好家が色とりどりのカヌーを操って川下りを楽しんでいました。ようやく事故現場にたどり着くと、動画1で確認できますが、堤防のように積み重ねられた2列に続く石の列の間をホワイトウオーターと呼ばれる泡交じりの水がダイナミックにかけ下りて、それに絡まるようにカヌーが下り、上りしている様子が何か陽春の生命の息吹を象徴しているようでありました。
動画1 桂川のダイナミックな流れの中でカヌーを楽しむ人々。カヌーの動きで川下り船の事故現場の流れの様子もよくわかる(筆者撮影、48秒)
スマホがつながりにくいことに気づいた
この日はある新聞社から取材の電話が入る予定だったので、スマホの呼び出し音がいつ鳴ってもよいように気を付けていたのですが、先ほどハチにまとわりつかれた現場に続き、事故現場の付近でも電波の感度は悪くて、アンテナ表示が1本ついたり消えたり。「振ると、つくかな?」などと工学部らしい?発想のもとで本体を手に持って高く上げて振ったところで感度は上がりません。
確かに報道によれば、事故当時、JR亀岡駅に近い保津川遊船企業組合に現場から「無線連絡をしたのにつながりが悪かった」と書いてあったので、「谷間の川面からだと業務用ハンディ無線機の電波のとびが悪かったのだろう」程度の認識だったのですが、まさか令和の最先端工学の叡智の結晶であるスマートフォンでも電波を拾うことができないとは。まさかのまさか。
ここで急遽、保津峡、つまり桂川の流域の電波の強さを簡易的に調べることにしました。あくまでも簡易的な調査ですから、筆者の所有するauのスマホ(Xperia SOV41)だけに特化した調査で、結果には全ての携帯電話で通用するような普遍性はありません。先にお断りして図1にその結果を示します。

順番に追っていきましょう。まず馬堀駅の桂川対岸では電波の強さは十分でした。何の支障もなく通話もできたし、ウエブの閲覧も可能でした。そこから下流、すなわち事故現場の方に川沿いに歩いていくと、しばらくは電波がしっかりとスマホに届いていました。地図上では青丸が3つ続いて、黄丸が現れます。その後すぐに赤丸となりました。ここからはアンテナ表示が1本かゼロ本でした。そのまましばらく同じような状況が続き事故現場に至りました。事故現場からさらに下流に向かうとJR嵯峨野線の橋があります。そのあたりで一時電波の状況がよくなりますが、ここからまた下流に移動するとスマホはほぼ圏外となりました。
このあたりの地形は、図の等高線をみるとおわかりのように左岸、右岸から山すそが交互にせり出してきています。そのため、結果的に桂川が蛇行することになります。平野の端に位置するトロッコ亀岡駅付近では携帯電話会社の基地局から見通せる範囲にあるために電波がスマホによく届くのですが、赤丸の位置は右岸(地図の下方向)から山すそがせり出しているので、結果として基地局から見通せないためにほぼ圏外になってしまったと考えられます。
基地局の位置はどこに?
図2をご覧ください。皆様が利用している時にスマホにやってくる電波は、ビルの屋上など比較的高い所に設置されているアンテナから送信されています。そのアンテナの下の方に設置されている箱が基地局です。
基本として、平野にいる人が安定して通話できます。アンテナからの見通し距離内にあるスマホには電波が届くのですが、途中に山があると電波が山を透過しないので見通し距離外には電波は届きません。
プラチナバンドだと山を少し越えて電波が届きます。プラチナバンドは携帯電話の使っている周波数の中でも比較的低い周波数なので、電波が回り込むためです。山頂を越えて山腹にいる人が通話できたりします。でも深い谷間にいる人のスマホには残念ながら電波が届きません。
スマホに電波が届かなければ、基地局を介して他の人の電話と通話することができません。緊急通報も消防署に当然かからないのです。

自分が目的地とする行楽先でスマホで電話が可能かどうか調べることができます。
大手携帯電話会社(キャリア)が自ら公開しているサービスエリアマップで保津峡を例に通話可能範囲に入っているかどうか確認してみましょう。
NTTドコモ(4G LTE)
au(4G LTE) 保津峡周辺にはご自分で移動を
ソフトバンク(4G LTE) 保津峡周辺にはご自分で移動を
いずれのキャリアにおいても、桂川が山間に入ってからJR保津峡駅のすぐ上流までサービスエリア外になっていることがわかります。
基地局の位置もおよそわかります。それを知るにはCell Mapperというツールが使えます。
NTTドコモ(4G LTE)
au(4G LTE)
ソフトバンク(4G LTE)
線香花火の先端みたいなマークがありますね。(もしマークが現れなかったら、地図を少し縮小してみてください。)これがおよその基地局の位置です。いずれのキャリアでも山間に入る手前と保津峡駅から下流にかけての位置に基地局があることがわかります。どちらのアンテナからみても山が邪魔して、この間にある保津峡ではスマホに電波が届きにくいということがわかります。
人がいないのなら、圏外でもいいのですが、桂川の流域では、毎年どれくらいの人々が行楽しているのでしょうか。報告を元に調べると、桂川に沿うように走るトロッコ列車(嵯峨野観光線)では運営会社発表で年間128万人(2017年度)、川下りも運営組合の発表で年間25万人。これだけでも合計153万人。1日平均のべ4千人強がこの流域を行楽で移動していることになります。そして、毎年150万人以上(10年でわが国の人口の1割強)の人が気づくか気づかないかわかりませんが、一時携帯電話の通話などがしにくい状況に陥ることになります。
もちろん事故がなければ、緊急通報でスマホを使う必要はないのですが。
実際に緊急通報の必要な事故が発生しています
これまでに保津川下りのルート上では緊急通報が必要だった事故がいくつか発生しています。そのうち、新聞報道された重大事故を列挙します。
2005年 京都市右京区の保津川で、川下り中の遊船の船頭から「人が岩に引っかかっている」と遊船企業組合を通じて右京署に通報があった。(中略)ヘリコプターで男性を救助したが、すでに死亡していた。水死とみられる。(読売新聞 2005.07.29)
2007年 保津川下りの船頭がトロッコ保津峡駅下流約0.9キロの河川敷で、ハイキング中に転落、負傷した男性を発見。遊覧船に乗せ、消防隊の救出地点まで搬送した。(中略)保津峡一帯では10月以降、中高年のハイキング客らがけがをしたり、迷ったりする事案が11件発生しているという。(読売新聞 2007.12.15)
2008年 西京区の松尾山から景勝地・嵐山や保津峡へと抜ける林道周辺で、ハイカーや観光客による救助要請が相次いでいる。(中略)松尾山には阪急嵐山駅方面、トロッコ保津峡方面、JR馬堀駅方面に抜ける主に三つの林道が存在する。高低差が少なくハイキング向きなことなどから、初心者でも歩きやすいとの印象が広まり、府内外からハイカーが集まる。(中略)中年夫婦が遭難して、保津川近くで衰弱した状態で座り込んでいるのを、保津川下りの船頭が見つけた。夫婦は救出後に「日没後に迷った上、思ったより道がきつかった」と漏らしたという。(朝日新聞 2008.04.19)
2014年 (保津川下りの)観光客約25人を乗せて川下り中、JR保津峡駅の下流約50メートルで溺れている男性を見つけた。もう1人の船頭と協力し、船を旋回して近くの岸につけ(中略)さおにつかまった男性を岸に引き上げた。男性は命に別条はなかったという。(京都新聞 2014.12.05)
2016年 保津川下りを運航する保津川遊船企業組合(亀岡市保津町)の職員3人が京都市右京区の保津川に流されていた女性を船で救助する事案があり(中略)作業船で航路を点検中、岸に落ちているバッグに気づき、約50メートル下流で水面に頭だけ出して流される女性を発見した。急流の中で船を操り、引き上げた上、土地勘を生かして道路が近い場所に接岸し、高さ約15メートルのはしごを上って救急隊に女性を引き渡した。(京都新聞 2016.12.29)
最後に残された秘境?
10年くらい前なら山間部に携帯電話の圏外エリアがあっても「仕方ないか」とあきらめることも選択肢に入ったでしょうが。技術立国と自負するわが国において、「行楽先というのは、緊急通報はできないものだ」と覚悟している市民は多いでしょうか。携帯電話が重要通信インフラとして受け入れられているこの令和の時代、「緊急時には、どこにいても助けを呼べる」と少なくとも陸地にいる人であれば、そのように期待しているし、ハチ刺され事故や水難事故のように救助までの時間が短いほど命が助かる現場では特にそうあってほしいものです。
大手キャリアのサービスエリアを日本全国に拡大してみると、150万人以上が年間行き来するような行楽地で2 kmにもわたって大手キャリアの携帯電話が圏外になるような所は筆者の目では探せませんでした。
「400年続く川下り船が駆け込み寺。そういう秘境が日本に1か所くらいあってもいい」のか。令和の時代になっても、こういうことがあるとは。