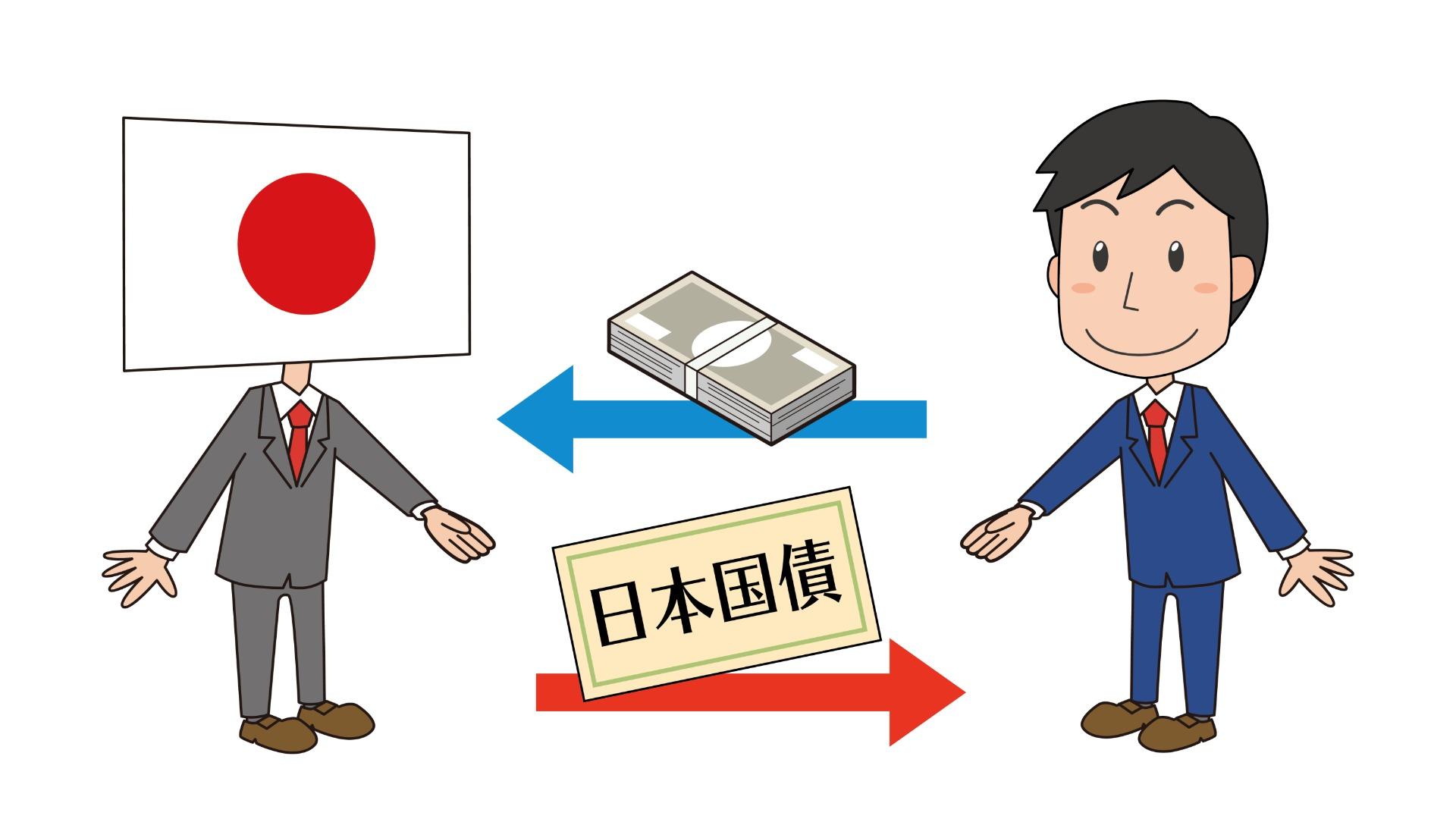ドーマーの命題と日本経済
単一通貨ユーロの参加に必要な収斂条件は、マーストリヒト条約に定められ、以下の4つの条件が存在する。
(1)物価安定: 直近1年間のインフレ率が加盟国中最も低い3か国の平均値を1.5%ポイント以上上回っていないこと
(2) 財政安定: 原則として、財政赤字(対GDP)が3%以下で、公的債務残高(対GDP)が60%以下であること
(3)金利安定: 名目長期金利が、加盟国中最もインフレ率が低い3か国の平均値を2%ポイント以上上回っていないこと
(4)為替安定: 加入前の2年間、通貨切下げを実施せず、直近1年間で通貨が欧州為替相場メカニズム(ERM)の許容変動幅内にあること
この4条件のうち、『2番目の「財政赤字(対GDP)が3%以下」という条件は、名目GDP成長率が5%以上の場合、「政府債務残高(対GDP)が60%以下」という条件と整合的』である。これは、「ドーマーの命題」から直ちに分かる。
ドーマーの命題とは、「名目GDP成長率が一定の経済で、財政赤字を出し続けても、財政赤字(対GDP)を一定に保てば、公的債務残高(対GDP)は一定値に収束する」というもので、次の債務の動学式から導出することができる。
d(t+1)-d(t) = -s(t)+(r-n)×d(t) … (1)式
ここで、d(t)はt期の公的債務残高(対GDP)、s(t)はt期の基礎的財政収支(対GDP)、rは長期金利、nは名目GDP成長率である。財政赤字(対GDP)は「-s+r×d(t)」であるから、一定に維持する財政赤字(対GDP)をqとすると、(1)式は以下に変形できる。
d(t+1) = q+(1-n)×d(t) … (2)式
そして、名目GDP成長率nがプラスの値のとき、簡単な計算により、公的債務残高(対GDP)の収束値は初期時点の公的債務残高(対GDP)には依存せず、以下の値となる。
公的債務残高(対GDP)の収束値=q / n … (3)式
(3)式において、財政赤字(対GDP)が3%(q=0.03)かつ、名目GDP成長率が5%(n=0.05)のとき、公的債務残高(対GDP)の収束値は60%(q/n=0.6)となることから、上述の『 』が確認できる。
また、ドーマーの命題やその導出の過程は、日本経済に様々な示唆を与える。以下では、簡単に2つの示唆を紹介しておこう。
まず第1は、成長率低下のインパクトの大きさである。これを、政府が先般(2014年7月25日)公表した「中長期の経済財政に関する試算」(以下「中長期試算」という)で考えてみよう。
同試算には、経済成長の見通しに楽観的な「経済再生ケース」と慎重な「参考ケース」が存在する。そして、試算の推計は2023年度で終了し、2020年度頃から23年度にかけて、名目GDP成長率は一定となっている。再生ケースは3.7%、参考ケースは1.9%である。
また、2023年度の財政赤字(対GDP、国と地方の合計)は、再生ケースが5.8%、参考ケースが7.2%である。いま簡略化のため、23年度以降も、それらと同じスピードで成長し、同じ財政赤字が継続するとしよう。
このとき、(3)式から、公的債務残高(対GDP)の収束値は、再生ケースで157%、参考ケースで379%と求められる(注:2014年度は193%)。つまり、収束値は2倍以上も異なるのだ。なお、中長期試算について、現政権では、実質GDP成長率が平均2%で推移する「再生ケース」を基本シナリオと位置づけている。
しかし、2000年以降の実質成長率は0.8%程度であり、再生ケースは楽観的であるとの批判も多く、1.3%で推移する「参考ケース」の方が現実に近い。
よって、もし基本シナリオの目算が狂い、参考ケース等の成長率に低下した場合、公的債務残高(対GDP)はその収束値に向けて膨張していくことを意味する。
第2は、名目GDP成長率の符号の重要性である。数学が得意な読者なら既に気づいていようが、(2)式で名目GDP成長率がマイナスの場合、公的債務残高(対GDP)は雪ダルマ式に膨張し、その極限は発散する。
しかも、少子高齢化で急速に労働人口が減少する中、各機関における最近の試算では、2020年~40年代で、日本の実質GDP成長率はマイナスに陥る可能性があるという試算が出てきている。
「名目GDP成長率=実質GDP成長率+インフレ率」であるから、もし実質GDP成長率がマイナスに陥っても、それを上回るインフレ率を実現できれば、名目GDP成長率をプラスに維持できる。
しかし、インフレ率を思い通りに制御するのは容易でない。過度に悲観する必要はないが、もし名目GDP成長率がマイナスに陥る場合には財政赤字は許容されず、公的債務残高(対GDP)を一定に維持するためには、対GDP比で「-n×d」の財政黒字を生み出す必要がある。