【濱口桂一郎×倉重公太朗】「労働法の未来」最終回(労働法は何を守るのか?)
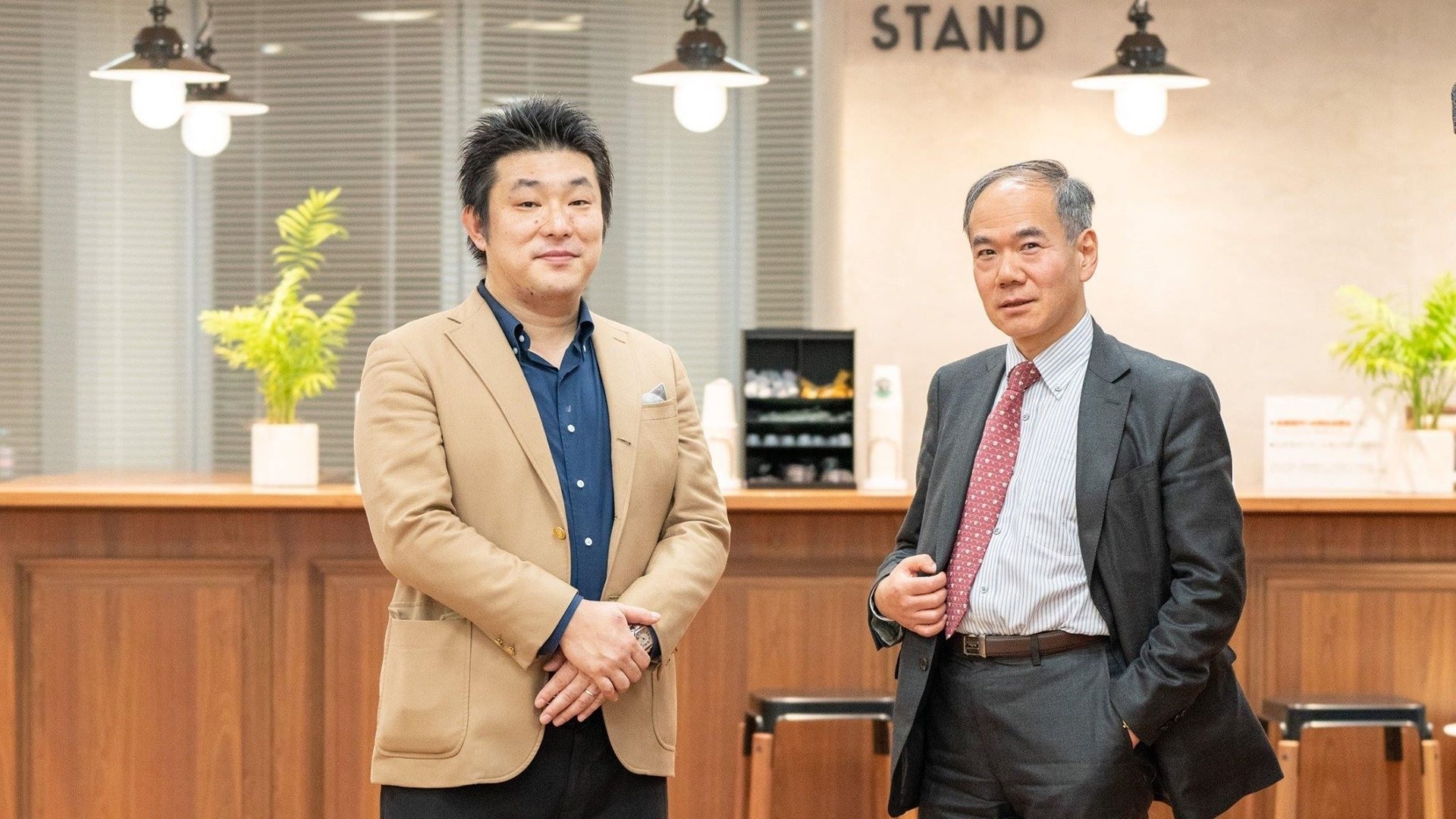
倉重:対談最後のテーマになります。 最後と言えばやはり、雇用法制の中の雇用終了の場面をお伺いしたいと思っています。濱口先生といえば、名著の『日本の雇用終了』(労働政策研究研修機構)というのがあります。
やはり現在の日本の雇用紛争、終了に関する紛争処理システムというのは、これでいいのかという議論もずっとあり得るところです。また、厚労省も検討会をやっていますけれども、別に具体的なものは当面はないのですか。
濱口:名前がやたらに長い、解雇の金銭解決を打ち出した検討会の報告書がありますね。
注:透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会
倉重:解雇の金銭解決ですね。
濱口:その報告書が出た後、2018年になってから、今度は解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会なるものが始まって、いま議論がされています。ただ、そこでやっている議論はまさに法的・技術的問題点を細かく詰めるような議論であって、あまり本質に突っ込むようなものではありません。この問題の根本は、日本の労働社会全体の中で、現に起こっている解雇等の雇用終了のうち、多くの人々が議論するときに念頭に置いている裁判例というものは、本当に氷山の一角に過ぎないということです。いやそれも正確ではありません。なぜなら、氷山というのは9分の1が水面上に出ているので、氷山の一角といえども結構割合は大きいのです。解雇の裁判例というのは氷山の一角などではなくて、そのまたごく一部に過ぎません。裁判所に訴訟として持ち出されるのは、世の中全体の解雇や雇用終了事案のほんの0.何%ぐらいです。しかも訴訟になったものの半分以上は和解で解決していて、半分以下がようやく判決にたどり着きます。
倉重:年間100件ぐらいですかね。判決まで行く解雇事件は。
濱口:それが、労働判例や、労経速などに載って、やがて判例集に収録されることになります。それだけでもって、みんな「解雇法制はこうだ、ああだ」と論じるわけです。その下に99.何%の。
倉重:それほどの量がありますか?
濱口:労働局の相談件数でいえば、解雇、雇止め、退職勧奨などの雇用終了事案で、年間約7万件あり、斡旋まで行くのが2千件くらいでしょうか。もちろん、そういうことが、理解されていないわけではありません。こういうことを言うと、「いや、それは分かってるよ」と言われます。あることは分かっているけれども、でも結局、解雇法制をどうするかという議論になると、一番上に突き出た、小指の爪の先みたいなところだけを取り上げて「ああだ、こうだ」という議論になります。今の、法的・技術的問題点の検討なるものも、そういうことです。一番上にちょこんと突き出た所について、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないものはすべて無効であるという法理論を大前提にして、あたかも全ての年間数万件、労働局の窓口にすら来ないようなものまで含めたら、もしかしたら数十万件もの解雇にも適用される議論をしようとしている。
倉重:もちろんそうです。
濱口:しかし、そのような圧倒的大部分は、無効だの何だのという話とは関係ない世界で動いているわけです。
倉重:本当に、細かい話を延々議論している方はそういう世界で生きていないのですよね。
濱口:解雇が無効などというのは、本当に氷山の上にいるペンギンぐらいの話に過ぎません。なぜ解雇法制をめぐる議論がおかしくなるかというと、現実には氷山の上のペンギンまで行って初めて無効だという話になるからです。それを全部の、水面下の氷の大部分の所まで、解雇が無効であることを前提として、議論を構築しようとするから、おかしな議論になるのです。訴訟であれば、弁護士を立てて、裁判をやって、和解もせずに、最後の最後まで行って判決が出れば、労契法16条で無効だという話になります。しかし世の解雇の圧倒的大部分は、そんなところに行かないのです。ということは、解雇が無効であることを前提にした議論は、誠に観念的な話だということです。実態は何で動いているかというと、まさに今言われた『日本の雇用終了』に書いてあるとおりです。「いや、ちょっとこれは、問題だから」ということで、10万円とか、20万円、たまに多いものがあって50万円などという金額で解決しているわけです。
倉重:日本の雇用終了は、たくさんのあっせん事例が出ていますけれども、本当にひどい解雇なのに10万、5万程度の解決金で和解しているケースがあります。「これで10万かよ」って思いますね。
濱口:そもそも、あっせんまで来ないものが大部分です。
倉重:そうです。それでもあっせんに行っているだけ、まだましなのですよね。
濱口:私に言わせれば、あっせんが氷山の一角なのです。
倉重:そうです。あっせんの土俵にのればようやく「氷山」ですね。
濱口:水面上に出ている氷の部分があっせんです。裁判まで行くのは、まして判例集に載っているのは、その上のペンギンなのだと私は思っています。
倉重:そうですね。そこで、要は、弁護士のよくある意見として、それで解雇法制を変えるべきだと言っているのです。
一方で、やはりそれは「弁護士の制度が、まだ利用が周知されていないだけである」、「法の支配が行き届いていないのだ」、「われわれ弁護士が、やはり紛争をきちんととことん戦って、解決することこそが素晴らしいのである」と、こういうふうに思っている方が、弁護士業界でもたくさんいるのです。果たして本当にそうでしょうか。
濱口:これは、法哲学や法社会学の問題になると思うのです。要するに、全ての体の不調に対して全て医者が対応するべきだと。小さな、ちょっと風邪を引いた程度の病気に対しても、医者が出てこないで、薬を飲んで治すのは、「けしからん」、「おかしいのではないか」と言っているような感じがします。
倉重:確かに、その例えはいいですね。本当ですね。全部が全部、大学病院の大先生ではなくていいよね、という話です。
濱口:しかも解雇の無効などというのは、外科医が体を執刀するような話でしょう。全てについて、そのような大げさなことをやっているわけではないです。
倉重:本当ですね。
濱口:むしろ薬局の薬すら買わず、つまり、『日本の雇用終了』で取り上げたようなあっせんにも行かないような、もっと闇に埋もれたものが世の中にたくさんあります。それは一体どこにあるのかと言われても、これですと見せることもできませんが、当然あるはずです。例えば雇用保険の特定受給資格者は年間約22万人います。それを考えたときに、日本の解雇を巡る議論というのは、あまりにも落差が大きいです。氷山の上に乗っているペンギンだけを使って全てを議論しているという、このおかしさをもう少し考えてほしいという気はします。
倉重:全くですね。よくこういうことを、例えば、解雇に関する解決金みたいな制度のこと、法制化のことを言うと、「じゃあ、そのお金はどうやって払われるんだ」みたいな議論も結構あるのです。この技術的な点は置くとして、例えば、「何ならもう労基署がいったん払いますよ。それから事業主に対して取り立てる、そういう仕組みにすれば誰でも簡単に受け取れるだろう」と思っているのです。あくまで技術的な問題は置いています。例えばの話です。
要するに取り立ての手間を本人に与えるなという話です。あとは、設計的には、雇用保険などから徴収してしまえばいいだろうというふうに個人的には思っております。そうなってくると、やはりわざわざ訴えて、また、今の制度であればなおさらです。仮に、例えば「何カ月分支給する」みたいな制度になったとしても、その履行を求めて提訴するみたいなことは、手間であることには変わりません。その手間を何とかしてあげないと意味がないでしょう。それが面倒くさいから、「もういいよ。さっさと転職する」、「泣き寝入りする」など、そういう人が一定数どころか、むしろ大多数います。それをなんとかできないかなと、個人的に常に考えています。国がそこを、支払いに関しては失業保険的に、労働者のためにやってあげようとできないかと思います。
濱口:その発想は未払い賃金の立替払いみたいな話ですね。
倉重:正にそのイメージです。
濱口:今聞いていて、そのような感じがしました。
倉重:おっしゃるとおりです。それを拡大してできないかと思うんですよね。そうすると、労働者は何も手間なく、解雇の保証金的なものを受け取れます。事業主に対する徴収もよいでしょう。もし回収できないで倒産してしまったところがあれば、それは税金負担になります。それは国として雇用社会を支えるのだということでいいのではないかと、個人的には思っているところです。
濱口:今初めて聴いたので、法技術的にどこがどういう権限でもって、何をどういうふうにやるのか、なかなか難しいかもしれないです。しかし面白い話です。
倉重:技術的には、いろいろ困難は伴うでしょう。ただ、技術的な点を置くとして、そういう、そもそも大半の人が、紛争にすらなっていないということを問題にすべきなのです。紛争になったとしても、非常に低廉な価格で、解決金で終了しています。これは、あっせんもそうですし、労働審判もそうですよね。
濱口:労働審判は解決水準があっせんよりひとけた上だと言いながら、それでも実は100万円ぐらいなのです。
倉重:平均的にはそんなイメージですよね。もちろん中には高い額というのもありますけれども、平均でいうと、せいぜいそのようなものなのです。
3カ月分、6カ月分、8カ月分という厚労省の検討もありました。そういう何カ月分でもいいのですが、要は、一定程度のお金をさっさともらえる制度ができたほうが、お互いにとって合理的ではないかというふうに、普段から考えてます。そうすると、一定数仕事がなくなる弁護士がいます。それはそれで、いろいろ反対も、お叱りの言葉も、私も頂戴するわけです。それでも雇用システム、社会システムとしては、そちらのほうが合理的だろうと思っています。それが、『雇用終了』を読んでの率直な感想です。
濱口:その辺は、そういうふうな感想を持たれるだろうな、と思いながら、あの本を書きました。
倉重:なるほど。でも、そうは書いていないです。あの本はただ淡々と事実だけを書いていますね。
濱口:淡々と書いたのは、事実の重みだけで、読ませようと思ったからです。
倉重:なるほど。さすがですね。まんまとはまってしまいました。
濱口:まんまと、笑
倉重:そろそろお時間も終了に近づいてきました。日本の雇用問題に関して、採用の話、同一労働、同一賃金の話、そして、雇用の終了の話と、いろいろ話しました。今は非常に時代の転換点といいますか、変わりつつある時代なのでしょう。時代のちょうどターニングポイントなのだろうと思っています。そういう意味では、今まで高度経済成長期、そして失われた20年、30年と経て、日本という国自体がどういう方向に向かうのか、その中で雇用社会というのはどうあるべきなのかという議論が、非常に大事な時期なのではないかと思います。最後に、日本の雇用は今後こうなっていくというところで、思いがあればぜひお願いしたいです。
濱口:話がぽーんと飛びますが、日本だけではなくて、恐らく今、世界共通に、19世紀から20世紀にかけて築き上げられてきた、労働社会のあり方が、大きく変わりつつある可能性があります。
倉重:デジタル、AIですね。
濱口:それこそ、今本屋に行くと、その手の本が山積みです。中には「AIで全部仕事がなくなるからBIだ」みたいな怪しげな話もあります。しかし、間違いなく仕事のスタイルは大きく変わっていくでしょう。1つは、働く上での時間や空間の制約というのがなくなっていくということです。いつでもどこでも、仕事ができるようになる。もう1つは、ある程度まとまりのある職務を単位に、ある程度の期間、継続的な雇用契約を締結し、仕事と報酬を交換する仕組みが揺らいでいくということです。むしろその職務が、ジョブからタスクに分解され、そのタスクごとに個別に発注して、その成果に報酬を払うという仕組みが拡大していきます。もちろんこれまでも社会の周辺部には、請負的な働き方は見られたのですが、それが雇用の世界と相互浸透していくのです。これはもう、日本だけではなくて、世界共通に見られる現象です。労働法というもの自体、元々はイギリスで19世紀に工場法で始まり、それがだんだん広がってきました。ところが、いつでもどこでも、しかも請負的に働く人が増えていく中で、労働法は一体、今後どういう形になっていくのかが問われます。人によっては、例えば、神戸大学の大内伸哉先生みたいに、「もう労働法なんて、なくなるよ」みたいなことを言う人もいます。そうかもしれません。狭義の労働法というのは、なくなっていくかもしれません。しかし、やはり現実に人が働いて問題が起こるのであれば、それに対処する法律は必要なはずです。
倉重:労働者と言うかどうかは別として、働く人を保護するという役割ですね。デジタル時代の労働法といいますか。
濱口:「AIで仕事がなくなるからBIだ」というのは、私はあまり信用していません。やはり、仕方は大きく激変するけれども、人々が仕事をして生きていくというあり方自体は、そんなに変わらないでしょう。ただ、今までの労働法のあり方とは、相当変わることは間違いない。いつでもどこでも請負的に働く人たちを守るといっても、何をどう守るのでしょうか。労働時間規制をやたら厳格に適用し、裁量労働制や高プロをたたきつぶしたところで、いつでもどこでも仕事ができてしまうという実態は変わりません。笑い事ではなく、本気で労働時間規制を適用しようとしたら、家でも、喫茶店でも、電車の中でも、すべて「おまえは今ちゃんと仕事をしているのか。仕事をしていないのか」というのを、モニタリングしてチェックしなければいけないということになってしまいます。これは、逆に言うと恐ろしいディストピアです。そこまで人は、見張られたいのですか。いつでもどこでもできる仕事に対して、労働時間か労働時間でないかを厳格にチェックしろという話になると、そういう結論にならざるを得ません。それはおかしいでしょう。ということは、やはり、労働法規制、労働者を守るために労働法で規制するということの、ありようを変えていかなくてはいけません。労働者の何を守らなくてはいけないのかということを、これは世界共通の問題として、今みんなが一生懸命考えつつあるところです。
倉重:まさに「Uber」化する労働、ということだと思うのです。そういう中で、私も、昨年の4月にシンガポールの労働組合へ意見交換に行ってきました。そこでも、そういうデジタルワーカーのことに関してどう思いますかという話をしました。
その時には、シンガポール労働組合の方は、ワーカーである以上は、これは労働組合というかどうかは別として、「われわれの団体の」という言い方をしましたけれども、われわれの団体の保護対象であると言われました。それはそうだろうと思います。
ただ一方で、やはり、技術的な問題かもしれませんけれども、Uberなり、いろいろなサービスがある中で、雇用主なのか、要するに、命令を出しているものが、その国内にいないわけです。その人にどのようにして規制を出すのかという問題です。もしかしたら、それは一国だけでは解決できない問題なのかもしれません。
濱口:あとはその国の中で、労働法とは何を守るのか?という話です。その守る対象は国民であることは間違いないですが、その相手がいるのかいないのかすらも、分からないという話だと思います。Uber化していけばいくほど、時間によって、どの仕事をやっているのかもばらばらです。雇用主的な人もばらばらということになります。今の労基法的に言えば、労働時間の通算なのかもしれません。そのようなことが現実的に可能なのかというところを考えると、「労働法とは何だ」という問いは、まさにこれから世界共通で考えていかなくてはいけない問題だと思います。
倉重:全く仰るとおりだと思います。
濱口:先ほどまでの話とは一段階超えた、大きい話になってしまいました。
倉重:そうですね。まさに、2019年の幕開けにふさわしい、大きな問いを残して終了という形になります。今日はどうもありがとうございました。
濱口:こちらこそ、ありがとうございました。
(おわり)
【対談協力 濱口桂一郎氏】
1958年生れ
1983年 東京大学法学部卒業、労働省入省
2003年 東京大学客員教授
2005年 政策研究大学院大学教授
2008年 労働政策研究・研修機構統括研究員
2017年 労働政策研究・研修機構研究所長










