ルールを上手に破る銀行が勝つ
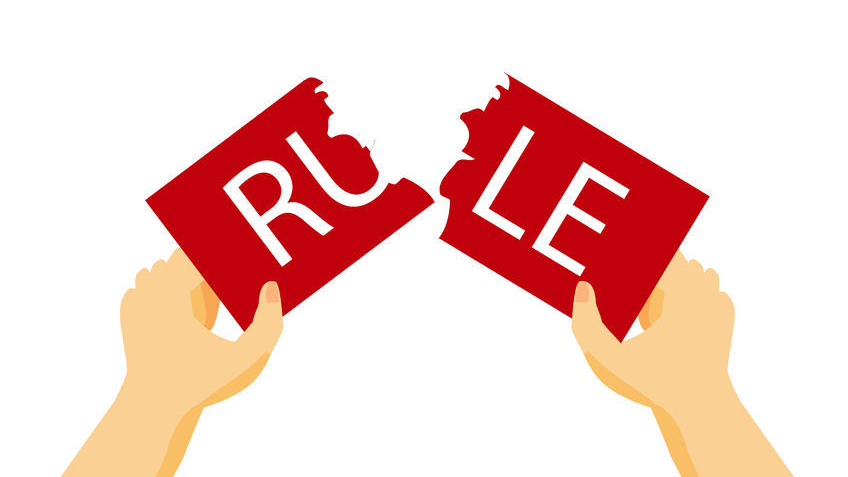
ルールを上手に破ることは、ルールを単に破ることではなく、上手に破ることであって、ルールを破るという表現よりも、新しいルールの提案といったほうがいいでしょう。新しいルールの提案とは、とりもなおさず革新であり、新文化の創造のことであって、革新こそ勝利の必須の要件であることは自明です。では、上手なルール破りとは、どの点においてルール無視やルール知らずと違うのか。
鮨屋の包丁

日本の包丁は片刃です。当然のことながら、鮨職人は片刃の包丁を使います。しかし、海苔巻、特に太巻きを切るときに、両刃の洋包丁を使う人がいます。片刃で真っ直ぐに切れば、斜めに切れてしまうからです。敢えて片刃で真っ直ぐに切ろうとすれば力を片寄せて切ればよく、実際、修練を積んだ人は何の問題もなく片刃の包丁で海苔巻を真っ直ぐ綺麗に切ります。さすが職人の技です。しかし、海苔巻を切るときは、その高度な技を使う必要は全くなく、両刃の洋包丁を使うほうが便利で合理的です。
また、鮨屋が使う海苔はぱりっとした上等なものですから、包丁の刃を痛めて研ぐ手間が増えるのだそうです。そういう意味もあって、研ぐ手間の楽な包丁を使うほうがいいのです。同様なことは、鮨に限らず伝統的な日本料理に共通で、食材や切り方に応じて、適宜、洋包丁を使う板前は珍しくもありません。
これは、伝統に固執する立場からいえば、ルール違反です。しかし、ルール違反というよりも、伝統の創造的革新というほうが適切ではないでしょうか。決定的に重要なことは、このルール違反は、料理の質に全く影響を与えていないことです。加えて、職人の技術にも全く影響を与えていないのです。どの職人も片刃の包丁だけで仕事をする技術をもっているからです。故に、伝統に対するルール違反が許され、それが合理的な新ルールの創造になっているわけです。
ところが、片刃の包丁で海苔巻を切る技術のない未熟な人が両刃を使ったら、それは許容され得ない単なるルール違反でしょう。ここには、手抜きと合理化の本質的な差が明瞭にみてとれます。片刃を使えない人が両刃を使うのは手抜きであり、片刃を使える人が状況に応じて適切に両刃を使うのは合理化であり、革新なのです。
手抜きと革新の微妙な差

真の合理化は、意図的なルール破りであり、上手なルール破りであって、むしろ新ルールの創造であるのに対して、手抜きは、ルール知らず、もしくはルール無視なのであって、新規創造の基礎となるべき根幹を破壊することなのです。
神ならざる人間には、無から何かを創造することなどできはしないのです。創造は現に形成されてある文化の基盤の上にしかなされ得ないのであって、旧文化の体現者にしか、新文化の創造はできないのです。あるいは、旧文化を創造的に破壊し得るものは、旧文化の真の理解者であり、同時に、そこでの技法を身体的に体得している達人だけなのです。
上手なルール破りとは、達人だけに許された高度な遊びであり、高度な遊びだからこそ、そこに創造があって感動を呼び起こすのであって、その感動が革新の動因となるのです。
しかし、現実には、世の中で革新や合理化の名のもとに行われていることは、手抜きにすぎないものが多いのでしょう。手抜きを真の合理化や革新と区別することは、表層的には顕著な差がない以上、極めて困難なのでしょう。しかし、その微妙な差は、時間の経過とともに、手抜きの破壊的効果と、革新と合理化の創造的効果に分解していき、次第に顕著な差となって現れるわけですが、そのとき、手抜きが与えた深刻な打撃は、おそらくは、治癒不能のものとして初めて認識されるのでしょう。そのときは、もう、手遅れです。
銀行は手抜きをしているのか

さて、日本の金融は手抜きにより機能低下したといえるか。この点については、手抜きによる機能劣化を明確に示すことができるとは限りませんが、それでも、非常に興味深い論点を提起していることは間違いありません。代表的な事案として知られているのは、銀行等の融資の審査です。金融庁の行政方針では、銀行等の融資審査に関して、非常に厳しい指摘をみることができ、要は、金融庁は、あからさまに現状を手抜きだといっているようなものなのです。
つまり、本来は、融資にあたって銀行等が判断すべきものは、企業の未来に向かって生きている動態、金融庁の用語でいえば事業性であるべきだが、現実には、死んだ過去の財務諸表や担保資産に基づく判断がなされており、その結果、理論的には融資を受けられるはずの企業も、実際には融資を受けられない状況、これも金融庁の用語でいえば「日本型金融排除」がある、これが金融庁の所見なのです。
背景として、銀行等が合理化を推進してきた過程で、融資審査を本部に集中して、その手続きを標準化してきたことがあります。標準化とは、即ち数量化であって、数量化するためには、いきおい過去の財務諸表に偏重せざるを得ないわけです。こうした標準化が審査の革新として、合理化を通じた審査能力の高度化を志向したものとしてなされたのか、あるいは、単なる費用削減のための手抜きだったのかは、現時点においてすら、判断困難です。
昭和期の金融

昭和のバブル期の乱脈に対する反省として審査の高度化を志向したもの、少なくとも、金融庁にとっても、銀行等にとっても、公式見解は、そういうことです。
しかし、論点は、むしろ、バブル期以前において、即ち高度経済成長期において、銀行等の融資は、今の金融庁がいうところの事業性評価に基づくものとして、なされていたのかということです。もし、そうならば、手抜きどころか、バブルという一時期の失敗に対する対策として、融資の文化の根底を破壊してしまったということでしょう。
しかし、別の見方も可能であって、高度経済成長期において、銀行等は、必ずしも、厳格な技法に裏付けられた融資の文化を確立していたわけではなく、産業全体に広く前向きに融資を行っている限り、経済全体の成長のなかで、大きな誤りを犯すことなく、やってこられたのかもしれず、融資の文化が未成熟だったからこそ、バブル期の誤りに簡単に陥ってしまったのかもしれないのです。ならば、バブル崩壊後、徹底した審査の標準化と形式化がなされたことは、新しい金融の文化の創造として、革新であり、真の合理化であったということです。
歴史の総括は、いずれ学者がやってくれることとして、現下の金融界の喫緊の課題は、事業性評価という新たな文化の創造です。
もしも、事業性評価という文化が高度経済成長期にもあったのなら、新規創造というよりも復興でしょうけれども、高度成長経済と超成熟経済という極端な環境の差がありますから、復興といっても実質的には全くの新規創造になるでしょう。しかし、いうまでもなく、新規創造は無からの創造ではなく、現に確立している文化を基礎にして、その延長において、新しい文化の提案としてなされるのでなければなりません。要は、ルール破りをするのです。
ルール破り
ルール破りは、ルール無視でもルール知らずでもありません。金融庁の指摘にもかかわらず、それなりに精緻に標準化され、客観化された現在の審査のあり方を根底から否定することなど、できはしないし、してもならないのです。課題は、その上に、新たなルールを、例えば金融庁がいうような事業性評価を創造的に付加することです。それが上手なルール破りということです。
例えば、未来へ向けた企業の事業性、即ち事業キャッシュフロー創出能力を評価して融資しようとするときは、過去に起因する損失の結果として財務基盤が著しく脆弱であること、場合によっては債務超過であることは、必ずしも決定的な阻害要因にはならないということであって、仮に債務超過の企業に融資すれば、明らかに従来のルールには違反するわけです。しかし、これは、ルール無視でもルール知らずでもなく、新たなルールの創造として、上手なルール違反となるわけです。
プリンシプルとルール

ここで、大きな問題は、ひとたびルール違反を認めたとき、銀行等の経営統制上、どのようにして、上手なルール違反を単なるルール無視やルール知らずから区別するのかということです。
金融庁の模範解答は、それが経営のプリンシプルだということになります。片仮名の好きな金融庁はプリンシプルといいますが、要は、経営の原則であって、日本料理の板前が片刃の包丁を使うのを原則にしているのと全く同じ意味において、原則なのです。板前の原則が確立しているからこそ、洋包丁の限定的利用が許容されるのと同じように、銀行等において融資の原則が確立しているからこそ、限定的にルール違反が許容されるのです。
金融庁は、ここ数年、ルール主義からの脱却を繰り返し熱心に説いてきました。なぜなら、ルール墨守からは革新が生まれないからであり、金融の革新なくしては、超成熟社会の課題が山積している日本産業の現実から脱却できないからです。
金融庁がいっていることは、ルールの背景には、その合理性を支える原則があるはずであって、その原則に常に立ち返ることなくしては、表層的なルール墨守から脱却できないということです。上手なルール違反とは、ルールの背後の原則に徹底的に忠実であるとともに、表層的で形式的なルールには縛られないということなのです。これは達人の境地です。
達人の境地
さて、銀行等に、達人たれと叱咤することは、不可能を強いることになるのか。不可能を強いられていると感じる銀行等は、金融庁の見込みでは、自然淘汰されることになっているようです。一方で、淘汰が進んでいくと同時に、他方で、不可能なことなどないという気概で達人の境地を目指す銀行等が成長すれば、日本の金融構造は短期間で抜本的に変革する、これが金融庁の目論むところです。
実際、修練の道に不可能はないわけです。修練を積めば達人の域に達する、そう信じて修練した人が達人になるわけで、達人とは、定義により、一定の要件を充足した人ではなくて、その要件を創造的に高めていく人ですから、誰でも達人の道を歩むことはできるのです、もちろん、到達するところは、それぞれに異なるでしょうが。
AIの可能性

最後に、流行りのAIの導入、例えば審査をロボット化する努力については、どう考えるべきか。
どれほど処理データ量を増やしても、処理速度を速くしても、百倍、千倍というような桁違いに処理能力を高めても、固定された推論のルールをもつシステムである限り、それは、本質的な革新としてのAIではなく、従来からあるものの単なる程度における進化にすぎません。真にAIと呼ばれるべきものは、上手にルール違反ができるものだけです。つまり、真のAIはプリンシプルでしかなく、ルールは全て自らが生成するのでなくてはならないはずです。
このようなAIは、もちろん可能でしょう。人類の英知は無限です。しかし、現在、銀行等が導入しようとしている審査ロボットとか、資産運用の助言ロボットなどについて、それが真のAIなのかどうかは知りません。達人の道を放棄した銀行等が開発するロボットは、おそらくは、偽物のAIでしょう。
人間が実践した達人への険しい道をロボットが完全に学習し、その先に究極のルール違反、即ち、機械が人間を超えるというルール違反を犯したとき、真のAIになるのでしょう。










