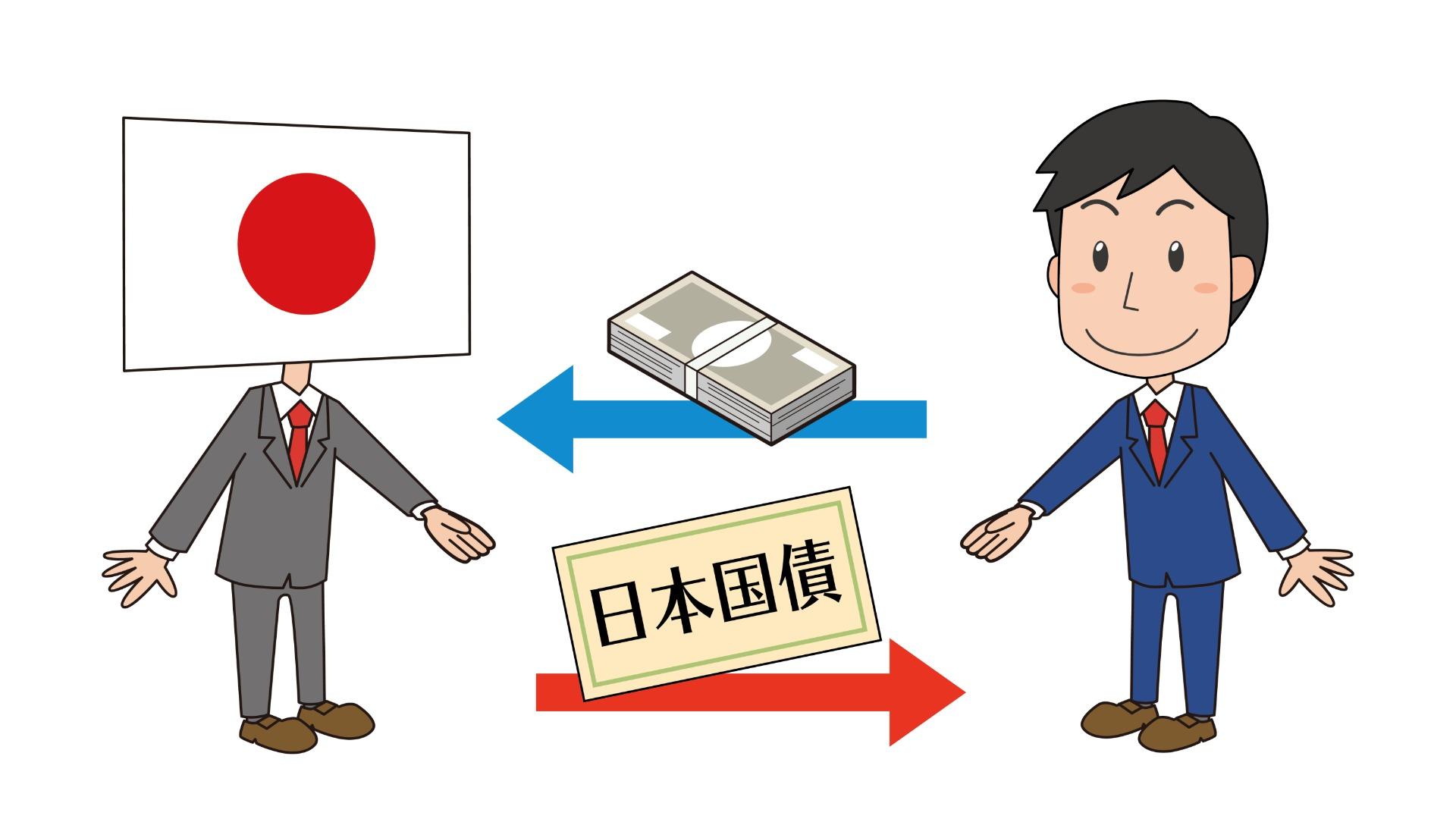ジミー大西の閉ざされた世界を開かせた“初恋”

7月20日よりNetflixで全世界190カ国に一挙配信された光野道夫監督による『Jimmy ~アホみたいなホンマの話~』。
これは明石家さんまが企画・プロデュースしたドラマ。1980年代の大阪を舞台に、さんまに出会い数奇な人生を歩むことになったジミー大西の実体験を描いたものだ。
ジミーを中尾明慶が見事に演じ、さんまを玉山鉄二、村上ショージを尾上寛之、Mr.オクレを六角慎司、大竹しのぶを池脇千鶴と実在の人物が多数登場している。「芸人A」として木村拓哉がサプライズ出演していることも話題だ。
さんまプロデュースといっても、いわゆる“名義貸し”みたいなものだろうと思われがちだが、決してそうではない。キャスティングから脚本の手直しまで行い、時間が許す限り撮影に立ち会い、中尾や玉山にはジミーとともに実際に再現して見せアドバイスも送った。
中尾「途中で帰ることは絶対にされず、どんなに夜遅くなろうと、全部見届けてから帰っていかれるんです。カッコいい方だなと思いました」
当然ながら、ドラマではジミーがさんまと出会いお笑い芸人になっていく様を描いているので、ジミーが大人になってからがメインだが、時折、その子供時代のエピソードも挿入される。
とりわけ印象的なのは、小学校の頃の初恋の話だ。『Jimmy』では、そこから吉本新喜劇での「理子さん」への恋心のエピソードに重ねられていくドラマ序盤屈指の名シーンのひとつだった。
花いちもんめ
そんなジミーの初恋の話は、2008年8月24日にNHKで放送された『わたしが子どもだったころ』や自身のエッセイ『天然色日記』などで詳細に描かれている。
「言葉の記憶っていうのがホントに僕の中ではないんですよ」と述懐するジミー大西。
人とも話さず、空想の世界に浸りきっていた少年時代。
他人と話さなかったからもちろん友達もいなかった。
頭にカナブンを乗せれば空も飛べるはずと思い屋根から飛び降りて足を怪我したり、イスを神輿に見立て担いで遊ぶ「一人神輿」など一人遊びに興じる家族から見ても変わった子供だった。
そんな少年をあたたかく見守る二人の人物が、その後のジミー大西の世界を大きく変えていくことになる。
一人は、彼の担任の先生だった。
不正解ばかりのテストの答案用紙の裏に彼が描いた落書きに五重丸を与えるような先生だった。
写生の授業中、明らかに周りの児童とは違う画を描く少年を、他の子供たちは一斉に囃したてた。
「大西くんにはこう見えるんやからこれでいいの」
先生はそう言って彼の画を認めた。
もう一人も、そんな大西少年の画を興味深く覗きこむような少女だった。
彼女はいつも彼を気にかけてくれた。
いつしか少年は、常にその少女のそばにいるようになった。
小学校3年の時だった。
「僕はその女の子としか、しゃべれなかったのです。ほかの子がしゃべりかけてきても、まったくしゃべれなかったのです。僕はその子としか、遊ぶことができませんでした」
普段はみんなの輪に入れなかった、いや入ろうともしなかった。
だが、「花いちもんめ」だけは別だった。
彼女が彼の手をひっぱり、みんなの輪の中に入れてくれたのだ。
決まって彼が最後まで残った。
「花いちもんめ、まきさんがほしい」
少年は彼女の名前を呼んだ。
「花いちもんめ、大西君はいらない」
みんながそう言って、「花いちもんめ」は終わった。
少女は休み時間が終わった後、少年の国語のノートに落書きを残した。
「花いちもんめ、大西君がほしい」
少年は少女に恋をした。
遠足のときも、朝礼の時も、周りから注意されても、彼女から離れなかった。
夢中になると周りが見えなくなる彼は、彼女への想いを抑えきれなくなった。
突然授業中、みんなの前で叫んだ。
「まきさん、好き」
まきさんと出会って、告白したことで、他の同級生とも少しずつ心を開けるようになった。
自分の閉ざされた世界を開かせるために、まきさんはこの世界に生まれてきてくれたのかな、とジミー大西は述懐している。
そして夏休み。
それは、少年にとって長い間、彼女に逢えないことを意味した。
我慢が出来なくなって少女の家を訪ねても、その家には誰もいなかった。
それから、夏休みの間中、彼女の家の前で待ち続けていた。
ある日のこと、いつものように呼び鈴を鳴らすと母親が出た。
「ごめんね、まきは今、田舎に帰ってるの」と言った。
はじまった世界と終わった世界
待ちに待った新学期が訪れる。
少年はやっと彼女に逢えるという気持ちの昂ぶりで、母親の化粧水を服につけて学校に行った。
しかし、いつまでたっても彼女は学校に来なかった。
「明日は逢える」
そう思いながら再び化粧水をつけて登校しても、彼女が少年の前にあらわれることはなかった。
それから数日経った9月16日のことだった。
朝礼の時間になり、空席のままのまきさんの机を見つめていると先生が口を開いた。
「実は悲しいお知らせがあります。昨日、まきさんは病気のためお亡くなりになりました」
ジミー大西はその時の感情を振り返る。
「あまりにも衝撃的過ぎましたね。
亡くなったっていうのは、ホントに逢えないっていうのは、これほどないくらい衝撃でした。
僕にとっては人が死ぬとか、生きる死ぬっていう意味がわからないんですよね。
(最初は)あぁ、転校するのかぁ、とかそういう感覚でしたね。
死ぬという実感が全く無くて」
出典:『わたしが子どもだったころ』「ジミー大西」編
ふと教室の扉の外に気配を感じて振り向くと、彼女が廊下に立っているのが見えたりもした。
だから、もう逢えないなんて信じられなかった。
クラスのみんなでお葬式に行くことになった。教室に集まっていると、少年は少女の気配を感じた。
少女は、教室の外の廊下に立って、彼に微笑んでいた。
「まきさん、まきさん!」
彼が叫ぶと、クラスメイトは「きもちわるー」と言った。
それが、少年が少女の姿を見た最後だった。
そして、少女の机の上に花が置いてあるのを見てようやく彼女の死を実感した。
少年の世界ははじまったばかりなのに、もう少女の世界は終わってしまった。
彼は、公園などで、きれいな花を見つけては、机の上のその花瓶にいけていた。
もしかしたら、まきさんに喜んでもらえるかもしれない。
もう逢えないことは解っていても、それだけが心の支えだった。
誰よりも早く教室に行き、花の水を変えるというのが日課になった。それをやっていることをみんなに知られたくなくて、一度家に戻りみんなと一緒に登校していた。
いつしか「花がかってにふえている」とクラスメイトの中で噂になった。
「みんなが帰ったあと、先生が花をいけているのです」
先生は少年を慮って言った。
クリスマスイブの日だった。少年は先生に職員室に呼び出された。
「この二学期で、机の上に花をかざるのはやめて、席替えをしようと思ってるの。いい? 大西くん」
二学期の最後、席替えをした。
大西少年は偶然、まきさんが使っていた席に座ることになった。
机の中には一枚のハンカチが残っていた。
そのハンカチは少年の宝物になった。
それから、30年余りの年月が過ぎた。彼は画家としてマルタに移り住んでいた。
ジミー大西は『わたしが子どもだったころ』で彼女への想いを綴り、その手紙をマルタの美しい海に流した。
Dear マキ
僕はマルタで楽しい日々をすごしています。長い夏休みです。
マルタの空はブルーに少し黒を混ぜた色です。まるで、先生に怒られてビンタを喰らわれた後のブルーです。
夜の飾らない星が大好きです。その星の中でもひとつキラッと光っている星があります。
それがマキ星です。
マキ星は笑っています? それとも怒っています?
満月の時は怒っているんだろうなぁ。なぜなら星はくすんでいるから銀色にグレーを混ぜた星です。
星をずっと見ていたら寝不足になります。
マキ星は罪な星です。
あなたは僕のために生まれたみたいですね。
ありがとう。 from ヒデアキ