詰め込みを拒否する教育を求めて~ホリスティック教育~
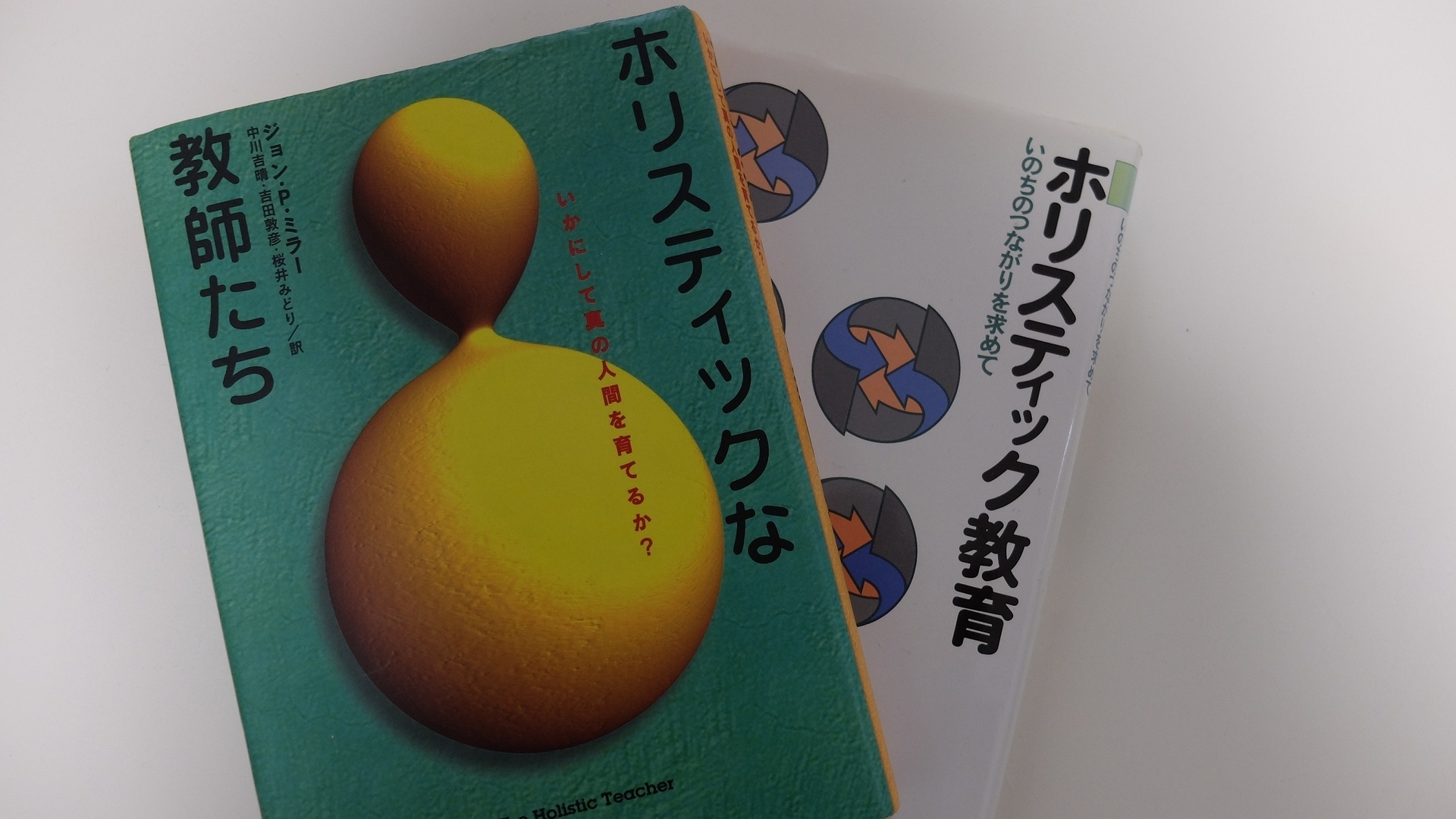
詰め込みへの不満から誕生した学校
知識偏重による詰め込み方式の教育は問題を指摘されながらも、改められるどころか、ますますエスカレートする傾向にある。それによって、子どもたちは成長の機会を狭められていると、わたしは考えている。詰め込み方式から日本の教育が変わる、そのためのヒントが「ホリスティック教育」にあるのかもしれない。
わたしが「ホリスティック教育」という言葉を初めて知ったのは、自由学園学園長である高橋和也さんのFB(フェイスブック)への投稿からだった。同学園を会場にして「ホリスティック教育/ケア学会」のシンポジウムが開かれた、という内容だった。
自由学園は、日本における女性初のジャーナリストであり思想家としても知られた羽仁もと子と夫の吉一によって1921(大正10)年に創立された学校で、幼児生活団幼稚園という幼稚園、小学校にあたる初等部、それぞれ中学・高校にあたる男子部と女子部、さらに大学に相当する最高学部を有している。創立当初は東京都西池袋にあったが、現在は東京都東久留米市にキャンパスを移している。都心にも遠くない距離なのだが、木々にかこまれた自然豊かな環境のなかで学園の時間は流れている。

羽仁夫婦が自由学園を創立した理由を、『よく生きる人を育てる』(羽仁翹・著)は「自分の2人の娘が受ける教育を見て、当時の知識習得偏重の教育、すなわち詰め込み教育に、非常な不満を持った」からだと説明している。
詰め込み教育への不満から生まれた学校だから、現在でも詰め込み教育が主体にはなっていない。ただし、文部科学省(文科省)の定めた学習指導要領も尊重しての授業が行われている。
そんな自由学園で、ホリスティック教育のシンポジウムが行われたというのだ。それなら、「ホリスティック教育とは、詰め込みとは一線を画す教育にちがいない」と、わたしは考えた。そこで、自由学園とホリスティック教育について、学園長の高橋さんに話を聞いてみることにした。
学園の精神を一歩すすめるためのホリスティック
'''――創立以来、自由学園でやってきた教育がホリスティック教育、ということなのでしょうか?
'''
高橋:違います。「ホリスティック教育」を最初に提唱したのは、カナダのトロント大学大学院オンタリオ教育研究所のジョン・ミラー教授でした。彼は、著書『The Holistic Curriculum』(邦訳『ホリスティック教育 いのちのつながりを求めて』)で、その理論と実践を紹介しました。その本が出たのは1988年ですから、1921年創立の自由学園とは直接に関係はありません。
ただし、無関係でもありません。ホリスティック教育を簡単に言ってしまえば、「知識偏重ではなく、心と身体と魂を育てる教育であり、人間の全体性を重視する教育」です。これは、自由学園の教育にもつながるものです。
――どういうところが?
高橋:私は自由学園の男子部と最高学部で学び、そして、ここの教員になりました。自由学園の教育は、単に暗記力だけに頼って「覚えさせる授業」ではなくて、頭だけじゃなくて手と身体と心を使った学びなんです。
たとえば私が国語の教員をやっていたころ、漢字テストをやっていました。それが、すごく苦手な子もいるわけです。
その子が、学期末テストで、漢字問題で答案用紙にいっぱい書き込んでいました。「がんばってるな」と私はみていたんですが、テストの終了間際になって、その子が書いたものを、ぜんぶ消していた。消しゴムで、答案用紙がグチャグチャになるくらいに、ゴシゴシ消している。その子の「怒り」が私に伝わってくるようでした。そして私は、「ただ覚えさせるような授業をしていてはいけないんだ」と大いに反省しました。
それから、漢字の成り立ちから追体験する授業を始めたんです。文字無しで情報を伝える方法を考えさせると、いろいろな絵文字だったり記号だったり、さまざまな工夫が飛びだしてくるんですね。それを分類していくと表音文字とか表意文字とか、漢字の分類につながっていく。
そういうことをやっていくと、ただ漢字を覚えるのではなくて、漢字そのものに子どもたちが興味をもっていく。そうなると、漢字だって覚えますよね。
――心と身体と魂をつかって学び、成長させていく。まさにホリスティック教育なわけですね。
高橋:そうです。私だけでなく、自由学園の教員は、それぞれいろいろなかたちで心と身体と魂を使い、育てる教育をやっています。それが自由学園の創立以来の精神でもあるわけです。
――そこに、わざわざホリスティック教育を取り込もうとしている理由は?
高橋:意味を問わなくても、伝統の継承はできるんですね。しかし自由学園の精神を現在に活かすには、意味づけをきちんとしていかないと、深まらないし、さらなる一歩につながらない。それを考えていたときに、ミラー教授の『ホリスティック教育』を読んで、「これだ!」とおもいました。

――いちばん、どこに惹かれたんですか?
高橋:「つながり」があり、全体として捉えなければいけない、という考えです。教科ごとに分断されていたり、テストの点をとるだけのために授業あるのではなくて、教科と教科はつながっているし、それから社会の問題にもつながっている。勉強はテストで点数をとるためのものではない、というところです。
今は、地球規模でモノを考える人が求められています。それは、自由学園が創立されたときには無かった意識です。地球規模で考えられる子どもたちを育てていくには、自由学園の伝統を守っていくだけでなく、それを一歩すすめていく考えが必要だとおもいました。それがホリスティック教育にある、と考えています。
――これから、ホリスティック教育が自由学園にとって重要な存在になっていくようですね。
高橋:ホリスティック教育を知ることで、自由学園がやってきたことの正しさを再認識できました。同時に、自由学園ではっきり示されていなかった全体像を見せてくれた、と感じています。
それによって、ただ伝統を継承するのではなく、いいものは受け継ぐし、止めるものもでてくるかもしれません。いずれにしろ、自由学園の精神を一歩すすめていくことにつながっていくはずです。そのための準備をすすめているところです。










