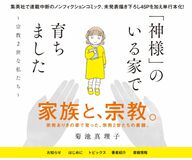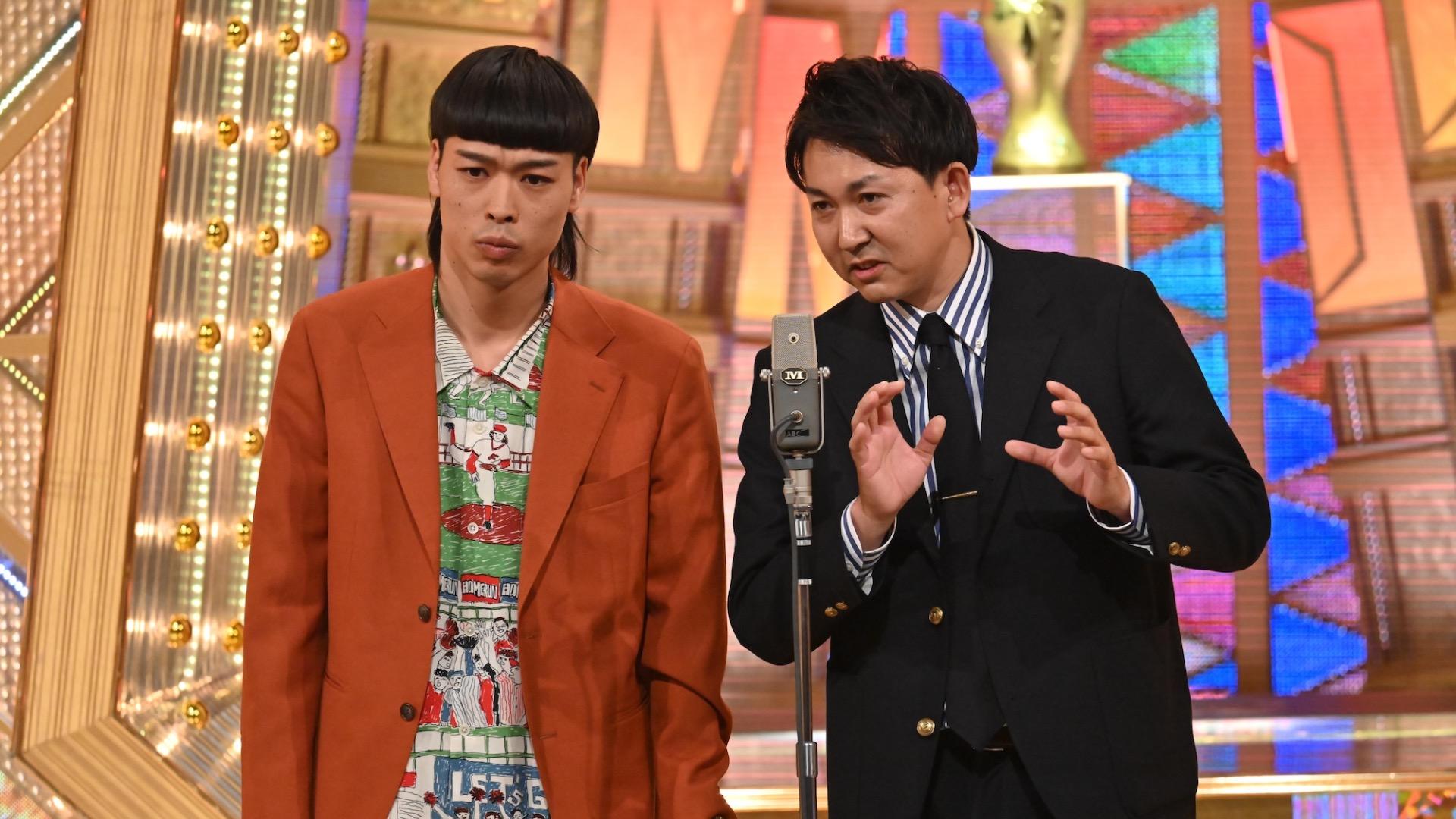「原爆の父」オッペンハイマーはどのような人物か グラフィック・ノベルから読み解く人物像

オッペンハイマーを描くグラフィック・ノベル
2023年7月21日、クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』が全米で公開された。本作は「原爆の父」として知られる科学者ロバート・オッペンハイマーの伝記映画である。
今年5月に広島で開催されたG7サミットでは、アメリカのバイデン大統領ら各国の首脳たちが原爆資料館を視察。6月には入館者数は過去最多を記録し、外国人入館者数は前年度比では22倍になっているという。ウクライナ情勢で核兵器使用の危険性が高まる昨今の事情を鑑み、世界的に核兵器への関心が高まっている。
同映画はカイ・バート、マーティン・シャーウィン著『オッペンハイマー:「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇』(PHP研究所)を下敷きとしているが、同書を参考文献とするアメリカのグラフィック・ノベルもある。
それが『私は世界の破壊者となった 原子爆弾の開発と投下』(ジョナサン・フェッター - ヴォーム著)である。日本では2013年にイースト・プレス社から翻訳版が発行された。

『オッペンハイマー』と「共通の祖先」を持つ本書は、原爆をどのように扱い、そしてオッペンハイマーをどのように描いているのだろうか。
グラフィック・ノベルの特性
その前に、グラフィック・ノベルについて述べておきたい。
グラフィック・ノベルとは、アメリカ発のマンガジャンルのひとつである。アメリカのコミックといえば、いわゆる「アメコミ」が有名だが、アメコミより対象とする読者の年齢層を高めに設定し、社会的な関心事をテーマにすることも多いのがグラフィック・ノベルだ。
その代表例はアート・スピーゲルマンの『マウス―アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』だろう。ナチスのホロコーストを生き延びた父親を題材とする同作品は、1992年にはマンガ作品で初めてピューリッツァー賞を受賞した。

日本のマンガが「連続するコマで“動き”を表現する」ことに向いているのに対し、グラフィック・ノベルでのコマは映画におけるカット割りに近く、「映画の絵コンテ」のような印象を受ける。ただし、マンガと同様にコマの大きさが変化するので、さしずめ「画角の自由な映画(のシーンの連続体)」といったところか。
読む際のテンポ感はマンガというよりは小説に近く、日本のマンガに慣れ親しんでいると、最初はやや読みづらさを感じるかもしれない。しかし、「マンガとは別物」として接すれば、すぐに読み慣れるはずだ。
『私は世界の破壊者となった 原子爆弾の開発と投下』の原題は『TRINITY』。「トリニティ」とは、1945年7月16日、米軍による人類最初の核実験と、その実験が行われた場所につけられた暗号名である。
物語のあらすじ
本作の前半部分は、原子爆弾の開発までを描く。キュリー夫人によるウランの発見から、核分裂や連鎖反応、臨界のしくみを、さながら教科書の副読本のような丁寧さで図説する。やがて原子爆弾の開発を目的とした「マンハッタン計画」が始動すると、最高責任者のレスリー・グローブス将軍は、オッペンハイマーの「強烈な野心」に押し切られ、彼を科学部門の指導者に迎え入れるのであった。
そして、ニューメキシコ州ロスアラモスで「トリニティ実験」が行われる。実証実験に立ち会ったオッペンハイマーは、みずからが作りだした兵器の破壊力に圧倒され、本作ではその時の感想が以下のように語られる。
「私はヒンズー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』の一説を思いだした……」
『我は死なり』
『我は世界の破壊者なり』
このセリフは、1965年に米NBCのドキュメンタリー番組「The Decision to Drop the Bomb(爆弾投下の決断)」のなかで、オッペンハイマー自身が述べた言葉からの引用である。
その後、物語後半は、科学の領域から戦争・政治の領域へと舞台を移し、広島・長崎に投下されるまでの経緯が描かれていく。
オッペンハイマーの人物造形
本作は「マンハッタン計画に参加した人々の群像劇」である。したがってオッペンハイマーは、単独の主人公というよりは、「主要登場人物のひとり」といった役どころだが、その人物造形に注目したい。
彼は一大プロジェクトを推進する野心家で、トリニティ実験の結果を見てもなお、大統領の暫定委員会に「直接的な軍事利用以外に、受け入れ可能な代案はありません」と具申する。そこには、みずからの研究成果を世に知らしめたいという、科学者としての功名心や自尊心が見え隠れするだろう。
だが、原子爆弾がもたらした災禍を知ったのち、核兵器の使用に警鐘を鳴らし、大統領から遠ざけられてしまう。偉大な発明をしたヒロイックな存在としては描かれておらず、オッペンハイマーの責任を有耶無耶にしていない。
また、作中のオッペンハイマーは「我々が作りだしたものは、きわめておそるべき兵器です。それは世界の性質を、急激に、根本的に変えました」とも語る。
そこからは、兵器の脅威のみならず、人類をけっして戻ることのできない世界へと導いてしまった後悔が読み取れる。その自責の念は、作中ではナレーションベースで、以下のように語られる。
彼らはついに答えを手に入れたが、それは何年ものあいだ問い続けた疑問だった——
「できるだろうか?」
しかし、マンハッタン計画の終了後は、多くの科学者たちがそれまでなじみのなかった問いかけを迫られた——
「やるべきだったのか?」
倫理を無視した科学者の研究と、それがもたらす不可逆的な世界。もはや「核のない世界」に引き返すことはできない。
つまり本作は、原爆投下の意思決定者(トルーマン大統領)とは別に、開発者の罪も問いかけていることになる。
余談だが、スティーヴン・スピルバーグ監督の映画『ジュラシック・パーク』(1993)では、パークの全システムを管理するシステム・エンジニアのネドリー(ライバル企業に内通する)のパソコンモニタに、オッペンハイマーの写真が貼り付けられている。遺伝子操作という禁断の科学技術に手を出すと、引き返せない世界に脚を踏み入れることになる……と、暗に仄めかされているようだ。

原爆投下を正当化していないか、どうか
それから日本人の読者としては、原子爆弾を題材にする海外作品に接する際には、原爆投下が正当化されていないかどうかも気になるところだ。
そもそも、アメリカ人は、原爆投下をどのように捉えているのか。アメリカの小学生用教科書での記述を引用したい。
President Truman knew that the Japanese were trained to fight to the death. He believed that Japan could be invaded only at a huge cost in American lives. So in order to force the Japanese to surrender, Truman ordered the dropping of two atomic bombs on Japan.
トルーマン大統領は日本人が死ぬまで戦うよう訓練されていることを知っていました。また日本に攻め込めば、多くのアメリカ人が犠牲になると確信していました。ですから、日本に降伏させるために2発の原子爆弾を投下するよう命じたのです。
『アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書』ジェームズ・M・バーダマン、村田薫[編](株式会社ジャパン・ブック)
引用元である『アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書』は、アメリカの教育学者エリック・ドナルド・ハーシュ(バージニア大学の教育および人文科学の元名誉教授)が制作した教材「コアナレッジ・シリーズ」の、アメリカ史の部分を抜粋したものである。
おそらくこれが、アメリカ社会におけるもっとも一般的な「原爆投下の理由」だろう。要するに、原爆は戦争終結を早めるための「必要悪」だった、と。
『私は世界の破壊者となった 原子爆弾の開発と投下』でも、原爆投下に至るまでのプロセスで、トルーマン大統領が上記と同様のロジックを用いている。しかしながら、戦後のオッペンハイマーは、原子爆弾を「邪悪な存在」と述べている。こちらは原爆を「絶対悪」としているわけだ。
本作では実際に発言された(記録された)両論を併記することで、少なくとも原爆投下を正当化する言説には加担していない。
描き出した原爆の非人道性
そして忘れてはならないのが、原爆の非人道性である。
本作では広島と長崎の、原爆投下後の惨状をまざまざと描いている。川の中に漂う無数の原爆被害者を見開きで描き切ったページは圧巻である。また、放射線障害や後遺症についても言及されており、兵器としての非人道性が際立つ。
原子爆弾を「必要悪」と考えるのが支配的なアメリカ社会で、これほど原爆の被害状況を詳述した作品は稀有ではないだろうか。アメリカにもこのような作品があることは、知っておきたい。
オッペンハイマーの功罪、原爆投下の是非、兵器としての非人道性。
以上の観点から、本書『私は世界の破壊者となった 原子爆弾の開発と投下』は、原爆に誠実に向き合った作品と言える。
映画『オッペンハイマー』に触れる際にも、上記の3点は、どうしても気がかりなところだ。2024年に日本公開されることが正式に発表された(配給はビターズ・エンド)が、日本の社会はこの作品をどのように迎え入れるのか。あわせてクリストファー・ノーランはオッペンハイマーをどのような人物として描き、どこまでチャレンジできたのか。心待ちにしたい。