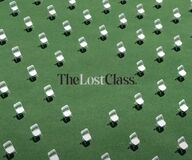東京五輪・パラの開閉会式。4つの式典でパラ開会式「片翼の少女の物語」の評価が一番高かった理由とは

オリパラの開閉会式はなぜ重要か?
東京オリンピック・パラリンピックが閉幕した。コロナ禍の中、開催への賛否は激しく割れたが、連日繰り広げられる熱戦に感動し、声援を送った人も多いだろう。筆者もその一人である。
だが、広告やデザインなどの表現分析を専門とする私が、スポーツ以上に注目して観ていたのは、両大会のセレモニー(開・閉会式)とそこで行われるショーだ。
スポーツの競技大会という観点から見ると、セレモニーやショーはおまけのように思えるかもしれない。だが、オリパラは世界に開催国のカルチャーやメッセージを発信する文化の祭典でもある。
言うならばセレモニーは商品の"パッケージ"であり、書籍で言うなら"表紙カバー"のようなもの。そこに大会の理念やビジョンが正しく表現されていなければ、イベント全体の価値も減ずる。
美味しい食品も、高機能なプロダクトも、面白い読み物も、それにふさわしい包装がされていてほしい。いいものだからと言って、そのまま差し出されても困ってしまう。
社会的存在としての「ブランド」とはそういうものだ。着るものや表情が"らしさ"になる。表層が深層を表現する。
それはともかく、多くの人材とべらぼうな費用を投入し、パンデミックという未曾有の事態の中で実施されるビッグイベントの価値を、世界から低く見積もられてしまっては、日本国民の損失となる。
ゆえに開閉会式のショーとその演出(クリエイティブ)は重要であり、そこは日本の発信力が試される場ともなる。
4つの式典を通して見ると、「TOKYO 2020」の成果と同時に、我々が抱えるいくつかの課題が浮き彫りになってくる。今後、様々な観点から、時間をかけて検証していく必要もありそうだ。
筆者としては、大会の熱もまだ冷めやらぬこのタイミングで、4つのセレモニーの演出(ショー)を振り返り、これからに向けての論点を提示、考察してみたい。
日本の発信が陥りやすい罠

まずはオリンピックから。ご存知のようにオリンピックでは、開閉会式の全体を統括するクリエイティブ・ディレクター、そして音楽家や演出家による過去の差別的発言や行動に批判が集まり、降板・更迭となる異例の事態が生じた。
報道等でその成り行きを見守りつつ、不安と一抹の期待がないまぜになった心情で本番を視聴したが、想像以上に退屈だった。ネット上の評判を見ていても、散々なものが多数見受けられ(特に閉会式)、それらの意見は筆者もうなづけるものが多かった。
50にも及ぶ競技種目ピクトグラムの"実演"や1824機ものドローンで構成される"地球儀"など、部分的には見どころもあった(開会式)。パフォーマーも実力のある演者たちだ。
しかし、全体として何を言いたいのかがいまいち伝わってこない。つまり、東京五輪をうまくパッケージできていない。
開会式の「United by Emotion」、閉会式の「Worlds we share」といったコンセプトはどこに表現されていたのか。"こじつけ"めいたメッセージでは、世界のオーディエンスの共感が得られるとは思わない。
ここには日本のクリエイティブが陥りやすい罠がある。
筆者はこの10数年来、カンヌ国際クリエイティブ祭を取材している。世界から3~4万もの広告事例が出品され、その中から各部門のグランプリや金・銀・銅賞を決める。毎年開催ではあるが、言うなれば"クリエイティブ五輪"とでも言えそうな祭典である。
ある年のこと。海外の某有名広告代理店に勤務するクリエイティブ部門のトップと会場で雑談をしていると、不意にこんなことを言われた。
「アワードに出品される日本のクリエイティブを見ていると、とても美しいと思う。信じがたいほどビューティフルだよ。だけど、ひとつ問題がある……何が言いたいのか、よくわからないんだ」
もちろんこれは皮肉だ。だが他人事ではない。このコメントには、日本にとっての宿年の課題が秘められている。職人的な細部の表現は素晴らしいのだが、統一された強いメッセージがないーーと指摘されているのである。
オリンピックのセレモニーも、その罠に陥ってしまったのかもしれない。海外に伝わらないどころか、国内からも「何が言いたいのか、よくわからない」というリアクションを招いてしまった。

仏紙フィガロのように「簡素だったが感動的だった」と、好意的に評価した海外メディアもあるが、これはおそらく次期開催国による"社交辞令"というものだろう。本気で褒めたいのなら「簡素だったが」とは前置きしない。実際、特に「簡素」なショーでもなかった。
コロナで五輪が1年延期となり、主要スタッフの降板などのゴタゴタもあって、当初のアイデア・企画から変更に次ぐ変更を余儀なくされたのだろうと推察はする。
だが、理由はどうであれ、あまりチグハグなメッセージを発信してしまうと、世界から誤解を招くおそれがあり、下手するとダメージさえこうむることになる。日本という"ブランド"に傷がつくことにもなりかねない。
そこに公金も投入されている以上、我々はセレモニーやショーで何が行われているのかを注意深くウオッチする必要があるし、疑問に感じたことについては声に出す権利がある。
パラリンピック開会式が一番良かった理由
一方、パラリンピックのセレモニーは、おおむね好感を持って受け入れられたようである。ネットでは「オリンピックより良い」の感想がトレンド入りするなど、オリパラで評価がきっちり割れた印象がある。
海外メディアも軒並み高評価だ。「色彩と祝賀に満ちた内容」(英BBC)、「活き活きした雰囲気」(米CNN)、「選手は逆風でも飛べるとの精神を示した」(中国・国営新華社通信)など、アメリカから中国まで絶賛に近い状態だ。
これにも私はほぼ同感だが、では具体的にどこが「オリンピックより良かった」のかは気になるところ。筆者なりの視点で考察してみたい。
まず指摘できるとすれば、パラリンピックのセレモニーはともに「WE HAVE WINGS」(開会式)、「Harmonious Cacophony」(閉会式)というコンセプトにきちんと向き合っていると感じた。
つまり「何が言いたいか」がよくわかった。簡単なことに思えて、つくり手の立場からするとこれが一番難しい。

片翼の少女の物語を描いた開会式の演出プランは、プロのクリエイターにとって、実は勇気がいるものである。
パラリンピックという場を考えたとき、あまりにストレートな"見立て"への反発も予想されるからだ。「飛行機だから空港」という舞台設定もありきたりと言えば、ありきたりである。
となれば「WE HAVE WINGS」というコンセプトを、もっとヒネって解釈することもできたはずだが、演出家は考え抜いた上で、この「わかりやすさ」を選択したのではないか。
その捉え方にブレがないからこそ、この開会式は創造的にも飛べた。共感性の高いストーリーへの落としこみが成功し、電飾ギラギラの"デコトラ"といった日本的モチーフ(美術)や個性あふれる数々の衣装、それをまとう出演者たちも生きてきた。
すぐれた演出の力とはそういうものだろう。オーケストラをまとめる指揮者に近い。
映像の中にさりげなくインサートされる「TOKYO 1964」へのオマージュ・ビジュアルなど、ディテールも効いていた。陸上競技でスタートダッシュする選手たちの一瞬を捉えた、有名な五輪ポスターのパラ・アスリート版を披露したのだ。
ダイバーシティ&インクルージョンへの本気度が問われている
パラ閉会式のほうは、開会式とは演出家やスタッフがほとんど異なっているようだが、こちらは音楽とダンスのパフォーマンスが圧巻だった。開会式のような「物語」ではなく、コンセプトを伝える「身体表現」に賭けていた印象を受ける。
「Harmonious Cacophony」というのは、"調和する不協和音"という意味らしいが、言葉で理解するのが難しい概念を、理屈抜きに体感させる演出になっていた。

4つのセレモニーをすべて通しで見て、筆者が改めて認識したのは、コンセプトの重要性だ。どんなコンセプトを考案し、そのテーマにどこまで真摯に向き合って実行するかで、プロジェクトの成否はほぼ決まってくる。
「何をいまさら」と言われそうな結論ではある。しかし、コンセプトやビジョンは"飾り"や"置物"になりやすい。ビジネスシーンでもよく経験することではあるのだが。
もうひとつ感じたのは、「ダイバーシティ&インクルージョン」(D&I)は、こうした国際舞台ではいまや絶対に避けて通れないテーマであること。
先にふれたカンヌ国際クリエイティブ祭でも、このテーマへの理解と洞察を欠いた広告キャンペーンや企業プロジェクトは、近年では評価されないどころか、軽蔑の眼差しを向けられかねない。そんな時代がすでに来ている。
近頃日本でも耳にすることが増えたD&IやSDGsといった理念は、欧米圏においては企業コミュニケーションの現場でも、すでに本格的な実施フェーズに入っている。
日本と欧米では、その本気度に温度差があり、かねてより懸念を抱いていた。日本国内の空気感は、そのまま海外に出すと受け入れられない。くわえて国内での人気者のほとんどは、海外では無名である。タレントに依存したコミュニケーションも成立しない。
オリンピックとパラリンピックのセレモニーの明暗を分けた根本の理由は、そのあたりにあると見る。演出チームの差別的言動があそこまで大炎上したのも、この時代性と関わりがある。
インターネットでのセレモニー評を見ていると、こうしたD&Iの価値観は、日本でも着実に根付きつつあると感じる。全員が全員ではないが、ネットユーザー(市民)の意識のほうが、国や企業より前に進んでいるのかもしれない。
オリンピック的価値観(感性)からパラリンピック的価値観(感性)のほうへ、時代は急速にシフトしていると見ることもできる。
ちなみに「TOKYO 2020」の4つのセレモニーを通じての共通コンセプトは「Moving Forward」らしい。その言葉通り、そろそろ本気で前に進むときなのでは? という感想も浮かんだ。