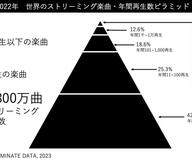iPodで進化したジョブズの組織づくり〜スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(2)

去る10月5日、スティーブ・ジョブズが亡くなって6年が経過した。彼の足跡を讃え、全7回に渡ってジョブズが音楽に残した影響を振り返ってゆく。第2回は、iPodの開発で培われたジョブズの最強の経営術だ。尊敬するSonyの盛田昭夫から学び取ったモノづくりのための組織づくりを、彼はいかにしてApple流の経営術へと進化させていったのであろうか。
■尊敬するSonyを超えろ
ジョブズは、リサーチをあまり信じない。消費者が気づきもしなかった何かを実現するのが、革命的なモノづくりだと信じていた。
「T型フォードが登場するまでは、自動車がほしいか消費者に尋ねても『いや、もっと速い馬がほしい』としか言わなかったろう」
というヘンリー・フォードの言葉をよく引用していた。だが、iPodの開発リーダーとなった若きトニー・ファデルのリサーチを止めることはなかった。かつてそれでも大失敗をやらかしたことがあるからだ。
Appleを追放された後、大学でワークステーション(PC程度のサイズの業務用コンピュータ)が普及すると決めつけ、NeXT社を創業。だがそんな市場は存在せず、苦境の中もがき苦しんで過ごすことになった。彼は少しずつ、自分のやり方を変え、若きロックスターのような経営スタイルから史上最強の経営者に自らを変えていったのだ。
潜在市場はほんとうにあるのか。あっという間にこちらを蹴散らす競合はほんとうにいないのか。リサーチでリスクを計ることは受け入れていた。しかし―――
ファデルが、パワーポイントを駆使して市場分析をジョブズの前に繰り広げていたときだった。ジョブズは明らかに退屈そうにいらいらしていた。そして話題がSonyの調査結果に入るとすぐさま遮った。
「Sonyは気にしなくていい。俺たちはやるべきことが分かっているが、連中は分かってない」
メモリースティックWalkmanにSonyの陥ったジレンマを見て、ジョブズはチャンスを直覚直感した。だから、確かにSonyの説明は不要かもしれなかった。ファデルを質問攻めにした後、大好きなプロダクトプランニングに移った。
■iPodのデザインに見るApple必勝の方程式
お手本があった。SonyのWalkmanだ。Walkmanは、テープレコーダーから余計な機能を削り、「再生専用」にしたときに誕生した。そして音楽は部屋から解放され、ひとの歩くところすべてを音楽の市場にする画期的なイノヴェーションをもたらした。
ソフトウェアとデザインの力で、驚くほどシンプルな操作性を実現する。そうすれば、mp3プレイヤーはギークのものから音楽ファンのものになる。シンプルを追求して非消費者を消費者に変えるのだ。そこには、初代マッキントッシュの開発で培ったApple必勝の方程式があった。
そのためにガジェットは再生専用とする。
ジョブズはハードとソフトを融合させることで、Walkmanを超えるつもりだった。むずかしい操作はガジェットから思い切り省き、ぜんぶパソコン上のiTunesにまかせてしまう。デジタルガジェットでAppleがSonyに敵うところは無いか。必死に考えて、iMovieに辿り着いた後に得たのが、このアイデアだった。
1000曲をポケットに持ち運べるよう、1.8インチHDDを採用する。
フラッシュメモリは当時64〜128MB程度だった。10〜20曲しか持ち運べないなら、Sonyの大賀典雄が創ったMD Walkmanを超えられない。MDを超えるためには、GB単位で小型のハードディスクを使うのが最適だった。
そしてFirewire 1本で、高速充電と高速転送を実現する。
FirewireはAppleの開発したAV機器やコンピュータを接続する技術だ。USB1.1だと4時間以上かかるのが、Firewireなら1000曲を10分で転送できた。CD-Rを焼いたり、ラジカセでMDに録音したりするより早い。もう「焼く」「ダビングする」は古くなる。充電もAC要らず。革命的に便利なはずだ。
ここまでのアイデアはロジカルに出せたが、肝心な問題が残った。UI (ユーザーインターフェース) だ。
1000曲も入っていたら、どうやって聴きたい音楽を選べばいい? ボタン方式だとひたすら連射しなければならない。ジョブズはファデルたちの用意した様々なモックを触ったが、この点だけはどうもしっくり来るアイデアが出てない気がした。彼のため息で、重苦しい空気が会議室を流れた。
「私のアイデアも見てもらえませんか?」
空気を変えるような声と共に、マーケティング責任者のフィル・シラーが新しいモックをいろいろ抱えて来た。どのモックにもあのスクロールホイールがついていた。スクロールホイールなら、大量にボタンを押すかわりにくるくる回すだけでよい。シンプルでエレガントなアイデアだった。
「それだ!」
ジョブズは叫んだ。この瞬間、スゴイものができあがると彼は確信した。
■Apple流。ベンチャーのように大企業を経営する
2001年4月のこの会議は、後のAppleの運命にとっても、人類の音楽生活にとっても決定的なものだった。それはAppleがパーソナルコンピュータの次にあるものへ踏み出した瞬間でもあったからだ。
ジョブズはこのプロジェクトのために、A+の人材だけを少数集めた。ハード担当のルビンシュタイン、プロデューサー候補のファデル、マーケティング担当のシラー、そしてデザイン担当のアイブなどだ。
ジョブズにとって会議は、「ビートルズのレコーディングセッション」のようなもので、真剣勝負だった。
ジョブズのようなビジョナリーのもとで、Aクラスの特別チームが、ベンチャーのように自由闊達にアイデアをぶつけあう。そして最高のプロダクトプランニングを生み出す。この時空こそが、新たな顧客価値が生まれる瞬間であり、会社の価値が生み出される場所だった。
大企業の組織の中心に、ベンチャースピリットを持ったAクラスのチームを創り、ビジョナリーが鼓舞し続ける。目標は利益ではなく、すごいモノづくり、すなわちプロダクトオリエンテッドだ。
営業志向でもない。技術志向でもない。まして経理志向でもない。すごいモノづくりを目指すプロダクトオリエンテッドこそ、バラバラになった組織を情熱でまとめ上げ、イノベーションの精神で蘇らせる唯一の道だと彼は見出していた。
それは10数年の流浪の末に編み出した、ジョブズ流のイノベーションのジレンマ克服の道でもあった。やがてその黄金の精神は、インターネットの登場でジレンマの陥穽に嵌ってしまったレコード産業を巻き込んでいくことになる。
■世界一の萌芽。iPodに見るジョブズのイノヴェーション理論
ジョブズの愛読した『イノベーションのジレンマ』の著者、クリステンセン教授の理論では、AppleやかつてのSonyは垂直統合に向いたクローズド志向の統合型モデルだ。一方、MicrosoftやGoogleは水平統合に向いたオープン志向の専業型モデルになる。
ジョブズがトニー・ファデル(元Apple社員、現在Googleグラスの次世代版の開発責任者)をプロジェクトのマネージャーに選んだとき、Appleの統合モデルはクリステンセン教授のそれから進化したように思う。
ジョブズは「クリスマス商戦に間に合うよう、6ヶ月ですごい音楽プレイヤーを完成させる」という目標を設定してきた。PCメーカーのAppleにとってデジタルガジェットは門外漢だ。94年にコダック社とデジカメを創ってしくじったこともある。
至高を求めてやまないジョブズの理想を解決するには、社内外の全ての力を結集しなければ不可能だった。ジョブズはiPodの開発を通じ、従来の統合型モデルをオープン志向に変えていかなければならなかった。
後に「ポッドファーザー(iPodの父)」と呼ばれることになるファデルは、ハンドヘルドデバイス(携帯可能な情報端末)の専門家だった。音楽配信と音楽プレイヤーを融合した会社を作ろうとちょうど動いていたこともあり、mp3プレイヤーに強いデベロッパーを知っていた。
ファデルはポータブルプレイヤー社を選び、Appleに連れてきた。
様々な会社のmp3プレイヤーを設計していた専門会社で、SDK(開発キット)を備えたFirmwareファームウェア(ハードウェアを制御するためのソフトウェア)を持っていたのが魅力だった。SDKがあれば、上に載せるソフトウェアにAppleは専念できる。しかもこの会社は、mp3プレイヤーの製造に必要な様々なパーツメーカーとつながっていた (※1)。
「これでAppleは10年後、コンピュータ会社ではなく音楽会社になりますよ!」
ポータブルプレイヤー社を連れて、Appleの経営会議に乗込んだファデルはそう吠えたという。実際それは5年も経たず実現してしまうのだが、ポータブル社のメンバーはそのせりふに驚愕したという。
さらにファデルは、携帯電話向けのOSを開発しているピクソ社を連れてきた。iTunesの基となったサウンドジャムと同じく、元Apple社員の創った会社だ。
Appleから出て行った人間を裏切り者扱いするのではなく、社外のノウハウを学んだ人間として積極的に取り入れる度量を、復帰後のジョブズは身につけた。社員に留学してもらったり、大学院で勉強し直してもらったりするより、効果的な方法かもしれない。
ピクソ社のOSにはUIを構築できるライブラリも入っていた(※2)。このOSをポータブルプレイヤー社のFirmwareファームウェアの上に乗せれば、AppleのソフトウェアエンジニアはUIとなるアプリと、Mac側とのつなぎ込みに専念できる。
ポータブルプレイヤー社のノウハウで、省電力化のために32MBのメモリも搭載することになった。メモリに曲をいくつかキャッシュしておけば、電池食いのハードディスクを止めておくことができる。
ハードディスク、メモリ。そしてファームウェア、OS、アプリ。
お気づきになった方もいると思うが、iPodの本質は音楽専用の小型コンピュータだ。後に登場するiPhoneの本質も、電話機ではない。電話もできる小型の汎用コンピュータだ。MPU(マイクロプロセッサー、コンピュータなどに搭載される処理装置)がコアで、OSが載り、様々なアプリが走る。
2001年当時の技術ロードマップでは、iPhoneのようなポケットサイズの汎用コンピュータは実現不能だったが、用途を絞ってパーツの性能をピーキーに引き出せば、ポケットサイズの専用コンピュータなら実現できたということだ。
それは、統合型モデルの会社が最も得意とする破壊的イノベーションのパターンでもあり、専用コンピュータという手法は、ちょうどその頃Sonyがゲームのジャンルで成功させていた。Playstationの名は、ゲーム専用ワークステーションを意味していた。
iPodが後にiPhone、iPadへつながり、『ポストPC』の時代を切り開いたのは、ここのあたりに秘密がある。
ムーアの法則(半導体や記録媒体の集積率は18か月毎に2倍になるという経験則)はCPUやストレージを小型化し、コンピュータをポケットに入る段階にまで推し進めようとしていた。そしてまず汎用ではなく専用で閾値に辿り着いた。
そして音楽が、『ポストPC』の時代へ向かう扉を開こうとしていた。
■ジョブズの人間的成長が、新しい経営手法を生み出した
iPodの開発を、新生Appleは外部ベンダーをフル活用して実現した。それはすべてを自分でやりたがる完璧主義者だった彼の成長の証でもあった。
「なんでも自分たちでやろうとしたのが、Appleが衰退した理由のひとつだ」
と復帰後のジョブズは語ったことがある。「ウォズ(スティーブ・ウォズニアック)と僕が何でもやっちゃったからね」と。
NeXT社でも、工場のデザインからパーツの製作まで、すべてを自社で完璧にやろうとして大失敗した。開発コストが上がり、バカみたいな値段となってしまい、NeXT社のワークステーションは全く売れなかった。
「いくら完璧でも、売れないプロダクトはクソだ」
と復帰後、ジョブズはウォズニアックに語るようになったという(※3)。ウォズニアックはこれをジョブズの成長と讃えた。ジョブズは学び、完璧主義の発展的な修正を目論むようになった。
そしてジョブズは統合型モデルを、外部の力を組み込む形で進化させた。オープンイノベーションを採用したのだ。だがジョブズは単純に、ファブレス企業のように外注に頼る会社にしたのではない。
「iPodのプロジェクトはベンチャー企業の立ち上げみたいだった。でも本当のベンチャーだったら、こんな短い時間でiPodを作れなかっただろうね。全社の助けがあったからこそできたんだ」
外部から来たファデルをサポートするため、彼とチームを組んだApple社員のスタン・イングはそう語る(※4)。電源の問題が起こればPowerBook(Appleがかつて製造していたノート型Macintosh)のチームに相談し、ドライバーに問題がでればOSのチームに相談した。ディスプレイの問題があれば、ディスプレイの部隊が協力した。Appleがデジタルガジェットを創るのは確かに初めてだったが、「ゼロからのスタートではなかった」とルビンシュタインは振り返る(※3)。
「ちょっと助けて欲しいんだ。秘密のプロジェクトだから、全部は話せないんだけどね…」
そう話せばどの社員もよろこんで解決に尽力してくれた。ジョブズの直下に作られたプロジェクトチームの方針を、社内外の人間が一個の有機体のように一丸となって実現していく。「完璧なモノづくり」というビジョンのもと、プロジェクトは完璧にコントロールされることを求められる。大企業になっても、ジョブズはマネジメントの創意工夫で、小さい組織にしかできない完璧な社内コントロールを実現しようとしていた。
大企業の筋力とベンチャーの身軽さを併せ持つ組織。これこそが、ジョブズが編み出した「すごい会社」だった。こうしたことが出来るように、ジョブズはまずプロダクトラインをごっそりリストラしていた。
「君たちは優秀だ。優秀な人間がこんなクソなプロダクトに時間を削いじゃいけないんだ(※4)」
自分たちの子供ともいえる製品を切られて怒るエンジニアをそう説得して、社内のスタッフに余力を創った。
さらに事業部別の勘定を撤廃。
たったひとつの勘定で動く会社にして、どの部署も協力しあえる組織に変えた。ジョブズはもともと「すごいモノづくり」のことはわかっていたが、それだけではダメなことを流浪の10年で学んだ。すごいモノづくりを続けるには、すごい組織を創らなければならなかったのだ(※5)。
「会社自体が最高のイノベーションになることもあるとわかったんだ。…Appleに戻るチャンスを手にした時、この会社がなければ僕に価値はないとわかった。だから、とどまって再生しようと心に決めたんだ(※4)」
PixerもNeXTも廃業寸前までいったが、10年かけてようやく育て上げた。父としての成長が、iPodの開発に結実しているように思う。モノづくりのための組織づくり。それはやがて彼の最高傑作となるiPhoneの誕生に欠かせぬ「秘伝のレシピ」となっていった。
失敗に次ぐ失敗の10年でジョブズは知恵を得た。その知恵は、『イノベーションのジレンマ』に書かれたジレンマ克服のソリューションを超えたものになろうとしていた(続く)。
関連記事:
iPhoneを予感していた29歳のジョブズ〜iPhone誕生物語(1)
iPod誕生の裏側~スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(1)
■本稿は「音楽が未来を連れてくる(DU BOOKS刊)」の一部をYahoo!ニュース 個人用に編集した記事となります。
※1 日経エレクトロニクス iPodの開発(第5話)http://nkbp.jp/1a8gJUf
※2 日経エレクトロニクス iPodの開発(第3話)http://nkbp.jp/19MdhSO
※3 『スティーブ・ジョブズの流儀』第7章
※4 『スティーブ・ジョブズII』第24章
※5 『ビジョナリー・カンパニー4』第4章