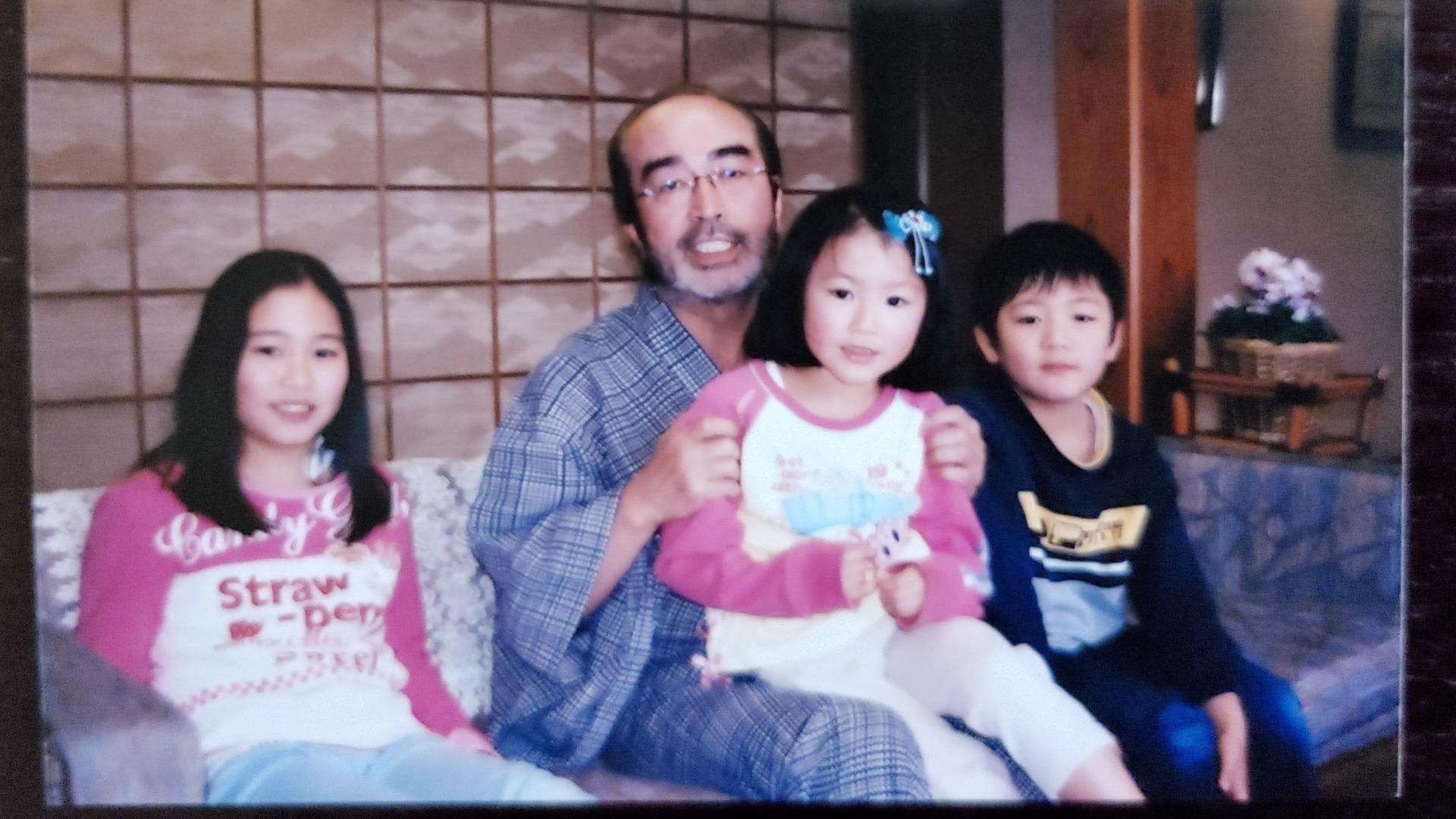「産金コスト=安値限界」の嘘と本当
世界の中央銀行がディスインフレや景気減速への対応として新たな金融緩和策の導入を迫られる中、世界経済の中で一人勝ちとも言える米国は着実に金融政策の正常化プロセスを歩んでいる。ドル増刷政策の終了に続いて利上げ着手時期を巡る議論が活発化する中、有事対応としての金(Gold)を保有する必要性は薄れており、投機マネーは国際基軸通貨たるドルに回帰する動きを強めている。
ドル建て金相場は2011年9月の1オンス=1,923.70ドルをピークに13年、14年と2年連続でダウントレンドを形成し、足元では1,200ドルの節目割れを打診する相場展開になっている。
こうした中、金市場では金価格が下げ止まるラインを考える際のヒントとして、産金コストが注目を集めている。概ね5年前の価格水準に回帰する中、どこまで下落すると産金業界が耐えられなくなり、供給環境に異変が生じるのかが注目されている訳だ。株式の場合だと、企業の解散価値とも言える純資産倍率(PBR)=1倍が底値判断の一つの目安になるが、コモディティ市場では産金コストが、安値限界ラインを示す指標として重視されている。
金の場合だと、金価格がダウントレンド形成を開始した時点では1,200ドルというのが一つの目安とされていた。貴金属調査会社GFMSによると、2012年の世界全体での産金コスト(All in cost)は1オンス=1,272ドルとされており、多少のブレがあっても1,200ドル水準から大きく下落することはないだろうという、漠然とした信頼感があったためだ。しかし、昨年10~12月期の金相場はこの1,200ドル割れを打診する展開となっており、今年もまた1,100ドル台での取引が増え始めている。
「産金コスト=安値限界」の理論は間違っていたのだろうか?
■急低下するバリック・ゴールドの産金コスト
この問題を考えるヒントは、産金会社の決算の中に隠されている。例えば、産金業界最大手のバリック・ゴールド(Barrick Gold)が発表した2014年12月期決算では、2014年通期の生産コストは864ドルとされている。
ここで注目して欲しいのは864ドルという数値ではなく、2013年の915ドルから51ドル(5.6%)も低下していることだ。金価格が12年連続の上昇相場を形成した最後の年である2012年の場合だと945ドルであり、実は産金コストは急激な圧縮が進んでいるのである。しかも、バリック・ゴールドが13年末時点で計画していた14年の産金コストは920~980ドルであり、864ドルという実績は当初計画を56~116ドルも下回っている。
金価格はこれまで強力な上昇トレンドが形成されていたため、産金業者にとっては金を掘削・精錬すればする程に利益が計上できる環境にあった。マーケットではその時点の生産コストを金価格の下値目処と考えていたが、実際にはコスト削減の余地が多く残されており、金価格の急落局面でも利益を計上できるように、産金会社は経営構造を急激に変えてきたのである。
実際にワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)によると、2014年の世界産金量は13年の3,050.7トンから3,114.4トンまで増加し、過去最高を更新している。従来との比較で増産ペースが鈍化したことは間違いないが、経営効率の向上によって産金量ベースでは増産傾向が維持されている。
バリック・ゴールドは、15年の産金コストを860~895ドルと横ばいから微増で計画しているが、全産金量の60%相当は725~775ドルに留めるとするなど、金価格の更なる低迷に対応すべく環境整備を進めている。
以上はあくまでもバリック・ゴールドの産金コスト環境であるが、他のニューモントやアングロゴールド・アシャンティなどにも同様の傾向が見受けられ、15年も産金量の過去最高更新は達成される可能性が高いと考えている。
産金コストの議論は分かり易いために素人受けし易いが、実際には一つの産金会社でもコスト分布には大きな幅が存在し、かつ、価格低下局面ではコスト削減努力が行われることになるため、必ずしも信頼性の高い指標ではない。これは、原油価格が従来ではあり得ないと言われる価格水準に到達しても、シェールオイルの増産がなかなか止まらないことからも確認できるのではないだろうか。