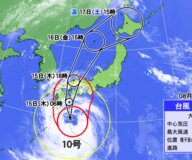気象予報士制度20年 防災に活かすには
気象予報士試験が始まって、20年を迎えました。試験に合格し、予報士として登録しているのは7月1日現在で9055人。早ければ、あと数年で1万人に達します。
気象予報士は、許可を得れば、一般向けに広く独自の天気予報を出すことができる国家資格です。一方で、気象庁からの警報を伝えるなど、防災の一翼も担います。
情報の意味を伝える役割
「予報」とは、「現象の予想」を「報じる(発表する)」ことです。そのうち、「予想」の部分に関しては、精度・的中率など注目されがちですが、いくら予想が当たっても、「報じる」部分で意味が伝わらないと、当たったことにはなりません。
たとえば、先日の広島や昨年10月の伊豆大島の大規模な土砂災害では、発生前に「土砂災害警戒情報」が出されました。気象庁が3年前に公表した全国での住民調査では、土砂災害警戒情報の役割の認知度は12.5%です。
メディアで気象予報士が解説している気象情報では、「土砂災害警戒情報とは…」など意味や、その時の大雨の切迫度を合わせて伝えることもできますが、ただ発表されただけでは、意味や切迫度が分からないという人が多いということです。
今後、防災情報を「分かりやすく」という改良はされていくでしょうが、それでも「分からない」という人は完全にはなくならないでしょう。避難行動につなげるには、この「伝わる」部分のロスをどう減らすかです。
土地に根ざした濃い気象情報
また、これは全国を対象にした放送をして感じることですが、災害につながるような現象が起こる場合、危機の察知の早さや、情報の中身の濃さは、その土地に根ざして普段から情報を発信している気象予報士には、かないません。
気象情報は、広く大勢の人に伝える意味もある一方、範囲が狭くなればなるほど、内容は濃くなるものです。
最終的には、一人一人が自分のいる場所の状況に合わせて、避難などの判断をすることになりますが、都道府県単位、市町村単位などの狭い範囲で、情報の噛み砕き役、橋渡し役をする気象予報士がもっと増えても良いのではないでしょうか。
多くの命を預かる人へのサポート
気象予報士は、メディア以外でも、防災を担っています。
たとえば、大勢の人が参加する屋外イベントなどでは、主催者は気象会社と契約し、荒天時の中止や中断の判断に活用しています。気象状況を正しく判断できなかった場合、多くの人を危険にさらすことになってしまうためです。
求められるのは、「気象情報の解釈」です。ネットを見れば、たくさんの気象情報・防災情報が確認できる時代ですが、結局、その場所への危険度はどれくらいなのか、予測見解と合わせ、情報の噛み砕きが求められます。
ここ数年、屋外イベントの主催者にかぎらず、自治体や学校、企業など、大勢の人の命を預かる方の意識が向上していると、予報の依頼時に感じることが増えてきました。
一方で、気象情報の意味や、危機感を理解して頂けていない方が意外と多く、その独自の判断で決行を決めていたら…とゾッとすることもあります。そういう人達をどう減らし、サポートしていくか、考えさせられます。
気象災害は昔に比べて減ってはいるものの、ゼロにはほど遠い状況です。私たちは、今ある情報を活かして、やれることを、やりきっているのでしょうか?気象予報士にできることは、まだまだあるはずです。