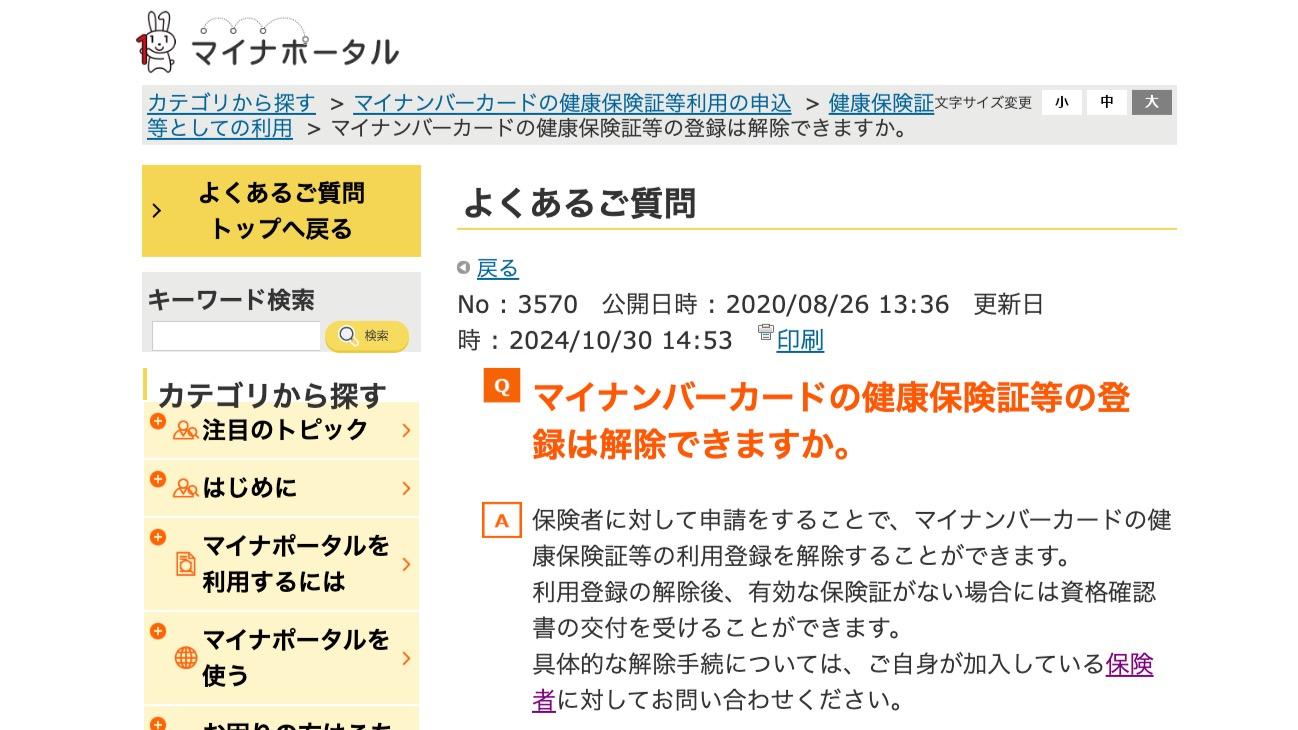ポスト「イスラーム国」を展望する

イスラームの暦で断食月(ラマダーン)が始まり、イスラーム過激派、特に「イスラーム国」による「テロ」が活発化することが心配されている。とはいえ、2016年のラマダーンも含め、この時期に彼らが実施した作戦行動で、欧米諸国などでのものも含め、「イスラーム国」の政治目的を達成するのに貢献するような戦果を上げたものは一つもない。作戦を契機に、「イスラーム国」に世界中から供給されるヒト・モノ・カネのような資源の量が増えるとか、脅迫に屈した国があってそこでの政策や世論が「イスラーム国」に有利な方向へ変化するといった影響は出なかったし、おそらく今後も出ないだろう。そうなると、「天国の門が開く」云々のラマダーンが持つ宗教的・精神的意義としては、「イスラーム国」にとっては最末端の自爆要員・特攻要員に行動を促す材料ではあっても、組織として政治的得点を上げる効果はさして期待できないだろう。
イスラーム過激派の広報活動を観察していると、実は2016年4月ごろに「イスラーム国」にはとどめが刺されたといってもいいほど広報の量・質が低迷している。それ以前の「イスラーム国」は、政治・社会的なできごとや幹部の演説の一節などを題材に「広報キャンペーン」を活発に行っており、一つのお題に対し各「州」が一斉に動画を発表し、1日あたり10件を超す動画が出回ることも珍しくはなかった。その「広報キャンペーン」が2016年4月以降全く行われなくなり、時折機関誌で「広報キャンペーン」を煽る記事が掲載されても、それに呼応する「州」はほとんどなくなったのである。この状況は、政治目的を達成するために専らテロリズムに依拠する「イスラーム国」にとっては致命的である。暴力行為を契機に敵方に対し要求や主張を突き付け、動揺・屈服につなげることがテロリズムの核心だとすると、既に「イスラーム国」は自らの要求や主張をまともに発信できなくなっているのである。そんな彼らが「延命」しているのは、「イスラーム国」の存在を国内の政局の材料に転換したり、彼らの意図や意義を過度に深読みする報道・解説が行われたりして、外部の主体が「イスラーム国」に政治的意義を与えていたことである。
みんな「イスラーム国」鎮圧後のことを考えている
実際、イラクやシリアの状況を見ると、「イスラーム国」の敗勢は動かしようがない。多少欧米諸国などで戦果を上げたとしても、この敗勢は挽回不能である。イラクでは、「イスラーム国」の最大の拠点であるモスル(「イスラーム国」に「首都」が本当にあるのなら、こちらだろう)のほとんどがイラク軍などに制圧されている。また、シリアにおいても拠点や占拠地域がシリア政府軍やアメリカの支援を受ける武装勢力諸派によって連日制圧されている。これは、従来「イスラーム国」の資源供給経路だったシリアとトルコとの国境地帯が全て「イスラーム国」の手から離れたこと、2016年12月31日のイスタンブルでの襲撃事件などを契機に、トルコ領内での活動や通過が難しくなったことと関係していよう。
ここで注目すべき点は、イラクやシリアの政局や紛争において、ほとんどの当事者はもうポスト「イスラーム国」に向けて動いていることだ。イラクにおいては、「イスラーム国」討伐後に外国軍の戦闘部隊を残留させるか否か、残留させる場合はその役割をどうするのか、という問題が政治勢力間の議題となっている。また、シリアとの国境地帯やシリアへ向かう幹線道をシーア派民兵が着々と制圧しているが、これは「イランの勢力伸張」という、「イスラーム国」とは本質的には無関係の別の国際問題の文脈で解釈されている。シリアにおいても、アメリカ軍などの特殊部隊が、ヨルダンやイラクとの国境地帯に配下の武装勢力を引き連れて展開し、これに対して国境地帯や幹線道路を制圧しようとするシリア政府軍やロシアとの緊張が高まっている。この国境地帯をめぐる競合も、「イスラーム国」対策というよりは、シリア・イラク間の往来を掌握することにより、将来の影響力行使や競合で有利に立つためである。今や、問題は「イスラーム国」を鎮圧できるか否か、ではなく、どの当事者が、いつ、どのように鎮圧し、それがその後の地域・国際情勢にどのように作用するかなのである。
今後の展望
そうはいっても、もちろん「イスラーム国」の構成員・支持者・模倣者が世界各地で襲撃事件などを起こすのを完全に防ぐことは難しい。また、「イスラーム国」が世間の注目を集めるために用いた様々な技術や手法を学び、さらに発展させる新たな犯罪集団が流行することにも警戒しなくてはならない。しかし、「イスラーム国」による襲撃事件などは、実は2011年以降にイスラーム国」への人員の供給源となっている諸国で「のみ」発生しているのであり、全く予測不能な場所で、予測不能な者たちによって引き起こされているのではない。例えば、フランス、イギリス、ドイツはヨーロッパ諸国の中では「イスラーム国」への大口の人員供給元だし、人口100万人当たりの送り出し数という観点からはベルギー、スウェーデン、オーストリアも有力な人員供給元だったことがわかる。ロシア、タジキスタンをはじめとする旧ソ連諸国も多数の「イスラーム国」構成員を送り出した。アジアに目を転じれば、インドネシア、バングラデシュが大口の送り出し国であり、オーストラリアについても懸念すべき点がある。つまり、今後「イスラーム国」が「国際的な」事件を引き起こす確率は、これまで「イスラーム国」に人員を供給した国において高くなる、ということだ。
これは、「イスラーム国」への人員の送り出しには、勧誘、ある程度の教化、旅券の偽造などの旅程の手配など、相当に手の込んだ準備が必要であり、多数の人員を送り出した諸国にはその準備をする能力がある組織やネットワークが強固に存在しているからである。こうした組織やネットワークが、地元での作戦行動に決起すれば、「イスラーム国」への人員供給元の諸国で事件が起こるのである。ただ、そのような場合は「イスラーム国」への資源供給が疎かになるので、世界各地で「イスラーム国」がはびこっているかのように見える現象も、実は長期的には「イスラーム国」の衰亡の証である。もっとも、2016年7月以前のバングラデシュのように、当局が「イスラーム国」への人員供給の事実を頑なに否定し、送出し数の把握などの捜査協力に応じなかった例もあるので、現在明らかになっている送出し実績を基に脅威の予測を立てる手法も万能ではない。
この点を考慮したとしても、ポスト「イスラーム国」の局面で重要となるのは、「イスラーム国」に多数の人員を送り出した諸国が、人員の送り出しのための組織・ネットワークを摘発できるのかである。また、SNSなどで「イスラーム国」の広報に加担した人々をどのように抑えるかである。ヨーロッパでの「イスラーム国」の人員勧誘は、宗教施設に限らず、アルコール依存症や賭博からの更生組織に偽装・寄生して行われていた例も少なくないことから、慈善団体も含む様々な団体をどう扱うのかという難題も残されている。