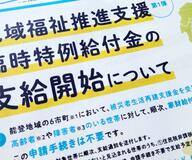災害で自宅が被災したらどうすればいい?「罹災証明書」「仮設住宅」知っておくべき公的支援の手続と注意点

突然起こる自然災害は誰にとっても他人事ではありません。特に災害によって住まいが被害を受けた際、適切な公的支援を知っているかが途方に暮れることなく、生活再建に向けて一歩を踏み出す上で大きな鍵となります。本記事では「罹災証明書」の取得、その後の住まいの確保に至るステップなど基本的な情報と利用する際のポイントを紹介します。

■まずは「罹災証明書」を知って
まず知ってほしいのは、「罹災証明書」(りさいしょうめいしょ)という制度です。根拠は「災害対策基本法」です。被災者は、市町村に対して、罹災証明書の発行を申請することができます。申請を受け付けた市町村は、住宅の被害の程度を調査して、その被害認定結果を記載した罹災証明書を発行する義務があります。
罹災証明書それ自体は、紙の証明書でしかありませんが、多くの被災者支援や災害救助は、自宅の損壊の程度によって使える制度が異なってきます。ですから、まずは、自宅の被害状況を確認する罹災証明書の発行申請手続きを行っておくと、今後の手続きに非常に便利に使えます。また、罹災証明書の発行は、市町村の法的義務になっています。この国の制度が、被災者を見捨てていないというメッセージのようにも思えます。
被災した時には、罹災証明書を市町村の窓口で申請するものなのだと知っておくだけでも、災害後に一歩を踏み出す希望になると信じています。
発行された罹災証明書には、自宅の損壊程度が記載されています。現在は、「全壊」(損壊割合50%以上)、「大規模半壊」(同40%~50%未満)、「中規模半壊」(同30%~40%未満)、「半壊」(同20%~30%未満)、「準半壊」(同10%~20%未満)、「一部損壊/準半壊に至らない」(同10%未満)に区分されています。なお、水害発生時には便宜上「床下浸水」「床上浸水」などの区分が設けられることもあります。被害認定に不服がある場合は、その算定根拠となった資料の開示を求めたり、より詳しい2次調査・再調査を求めたりすることもできます。
■罹災証明書の申請に写真や本人確認書類は必要ない
罹災証明書を申請する際に、自宅の損壊状況をスマートフォンなどで写真撮影すると、一見して全壊であることが明らかな場合などには、認定が早く進み、早期発行につながるケースもあります。ただ、住家被害認定の義務はあくまで市町村にあるので、被災者が写真を用意することは必須ではありません。自治体がこれを必要資料として添付などを求めることも誤りです。
また、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)も必須とまでは言えません。口頭で本人確認ができて、住民基本台帳情報などと照合できれば、それで十分です。過去の災害では、市町村が誤解して本人確認書類の持参が必須と読めるような呼びかけをしていたケースがありました。
自宅の被害状況の写真があれば、解体や修理後のトラブル防止に役立つ可能性はありますが、災害時には、身の安全の確保や健康の維持が最優先事項です。無理な写真撮影や本人確認書類の探索等を優先させることがないようにしてください。
■仮設住宅は大きく2種類ある
自宅が被害に遭った場合、ひとまずは公共施設などの避難所に身を寄せる場合も多いでしょう。また、やむを得ず損壊している自宅で在宅避難をする方や、車中泊を余儀なくされる方もいるかもしれません。いずれの被災者も、次の段階として、仮の住まいを探す必要があります。そのとき、法律に基づく公的な支援制度として知っておいてほしいのは、「応急仮設住宅」です。いわゆる「仮設住宅」のことで、「災害救助法」が根拠になっています。災害救助法が適用されるのは、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合」など一定規模以上の災害です。
応急仮設住宅(仮設住宅)には大きく2種類あります。「建設型応急住宅」と「賃貸型応急住宅」です。賃貸型応急住宅は「みなし仮設」とも呼ばれます。
建設型応急住宅には、様々なバリエーションがあります。プレハブ住宅であったり、移動式のトレーラーハウスであったり、木造の一戸建てタイプや、2~3階建てのアパートタイプの施設が建設される場合もあります。また、「福祉仮設住宅」といって、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造の仮設住宅が建設されるケースもあります。知らないと申請や入居申し込みを逃すおそれがあるので、ぜひ名前だけでも覚えておいてください。
賃貸型応急住宅(みなし仮設)は、民間の集合住宅や一戸建てを自治体側で借上げ、そこに被災者が住むタイプの仮住まいです。既存の住宅を利用するので、設備などは十分に整っていることが多いのがメリットです。なお、エアコンなどの最低限の住宅設備等が不足している場合に公費で設置された実例もあります。
■仮設住宅の入居要件が緩和される場合も
仮設住宅への入居が認められるのは、原則として、自宅が「全壊」(損壊割合50%以上)、または流失・焼失等の被害を受けた場合に限ります。しかし、実際は「半壊」程度以上の被害を受けていれば、入居を柔軟に認める運用がなされてきました。この記事の図表でも、半壊の場合には応急修理制度だけではなく、仮設住宅のほうへも矢印を伸ばしています。
また、住宅の建物被害が軽微でも、著しい地盤被害、インフラの断絶、二次被害の発生のおそれ等の理由で住むことができない場合には、柔軟に仮設住宅への入居が認められてきた実績もあります。場合によっては、被災者自らが、被害の実情を訴えて、積極的に自治体に対して入居申請を求めていかなければならない場面もあり得ます。
■応急修理制度の利用には注意が必要
住宅が「準半壊」以上(損壊割合10%以上)の被害認定を受けた場合で、修理が可能な場合には、「応急修理制度」が使える場合があります。これも災害救助法が適用された場合の公的支援です。被災住宅について日常生活に必要な最小限度の部分の修理支援を行う制度です。
「半壊」以上(損壊割合20%以上)の場合には、現在の基準では、70万6000円までの支援を受けることができます。それ以上の修理は自己負担となります。
「準半壊」(損壊割合10%~20%未満)の場合には、現在の基準では、34万3000円までの支援を受けることができます。それ以上はやはり自己負担です。
ここで注意が必要なのは、応急修理制度は、補助金や給付金を受け取れる制度ではなく、現物支給の修理サービスであるということです。すなわち、被災者が自治体に対して修理支援を申請し、自治体のほうから修理業者が派遣され、上記の基準額の範囲内で、重要な部分に限った修理を行うという仕組みになっています。自分で修理業者と契約してお金を払ってしまった場合に、あとから基準額のお金がもらえるというわけではありません。制度の利用を希望する場合は、十分に注意が必要です。
■応急修理制度を利用すると仮設住宅には入居できない
もう一点、気をつける必要があるのが、応急修理制度の利用と、仮設住宅の入居は、そのどちらかしか選べないのが、現在の災害救助法の原則的運用だということです。例えば、とりあえず住宅の応急修理制度を利用して住宅の修理を試みたが、予算内で思うように修理できなかったので、やっぱり仮設住宅への入居を希望したい、などということはできないのです。理不尽な運用にも思われるかもしれませんが、これまでの運用実績からすれば、応急修理制度と仮設住宅入居は二者択一的であると知っておく必要があります。
近年、例外的に応急修理に時間がかかる場合に、その期間中に限って、仮設住宅への入居を認めるという運用が行われるようになりました。しかし、いずれにせよ応急修理制度の利用をしてしまうと、年単位での仮住まいに仮設住宅を選ぶことができなくなることに変わりはありません。応急修理制度の利用には、慎重な検討が必要になります。
■被災後の「仮住まい」を考えよう
これまでの研究成果によれば、南海トラフ地震や首都直下地震などの巨大災害が発生すると、90万人以上の被災者が、仮設住宅や公営住宅に入居できない可能性があると指摘されています。民間の賃貸住宅候補や建設予定の仮設住宅を合わせても、仮住まいの絶対数が不足してしまうのです。もし、自然災害で自宅に住めなくなってしまったら、私たちはどこに「仮住まい」を求めたらよいのでしょうか。災害救助法による仮設住宅の支援のみならず、自助によるセカンドハウスや期限付き移住、自治体連携による受け入れ自治体への広域避難、マンション内部での在宅避難など、様々な選択肢を考えておく必要があります。
〈参考文献〉
岡本正『被災したあなたを助けるお金とくらしの話 増補版』弘文堂
【この記事は、Yahoo!ニュース エキスパート オーサー編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】