諸外国の人達はどの媒体でニュースを目にしているのだろうか
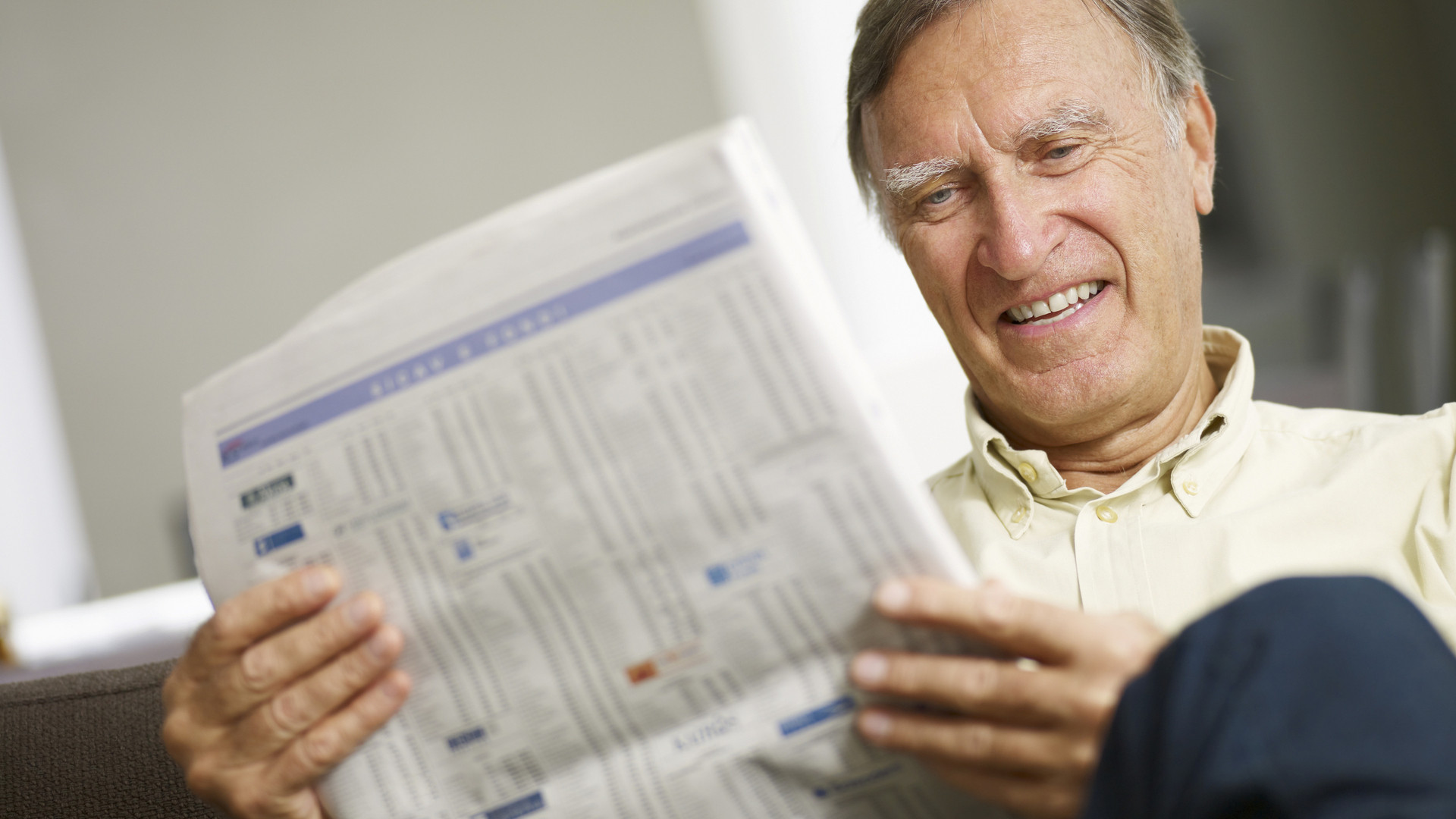
・2018年における諸国のニュース取得のために使われている媒体はテレビがトップだが、中国ではインターネットのニュースサイトがトップ。
・アメリカ合衆国やイギリス、フランス、韓国ではインターネットのニュースサイトの値が高く、SNSは低め。フェイクニュース問題が影響している可能性。
・ニュース取得の利用媒体としてのテレビとインターネットのニュースサイトの属性別傾向は大よそ相反している。テレビ利用者が多い属性ほど、インターネットのニュースサイトの利用者は少ない。
中国だけがインターネット経由トップ、他はテレビ
日々生じるさまざまな出来事の内容を迅速に取得し正しい判断をするために、人々は多様な手段を使ってニュースを確認する。インターネットの普及浸透に伴い、ニュースの取得確認のスタイルも大きな変化を遂げている。今回は新聞通信調査会が2018年3月に発表した、アメリカ合衆国やイギリス、フランス、中国、韓国、タイへのメディアに関する世論調査「諸外国における対日メディア世論調査(2018年調査)」(※)の報告書の内容から、諸国におけるニュース取得の利用媒体の違いを確認していく。
次に示すのは各国の人達がニュースを取得する際に、どのような媒体を用いているかを複数回答で尋ねた結果。インターネット経由調査では無いので媒体によるバイアスは生じない。ニュースを取得する意気込みなどにも左右されるが、各国の情報取得の方法論、実情を推し量るよい指標となる。

大よその国でテレビが群を抜き高い値を示しており、今でも情報取得の普遍的なツールとしてテレビが有効であることを改めて認識させる結果となっている。それに続くのはインターネットのニュースサイトやSNS(ソーシャルメディア)のような、インターネットを用いたサービスで、インターネットによる情報取得が当たり前となりつつある状況がうかがい知れる。
そのインターネットサービスだが、アメリカ合衆国やイギリス、フランス、韓国ではインターネットのニュースサイトの値が高く、SNSは低め。昨今のフェイクニュース問題が影響しているのかもしれない。他方タイや中国ではSNSも高め。特に中国ではSNSはテレビに近い値にまで達しており、インターネットのニュースサイトにいたってはテレビを抜いて最大の値を計上している。中国の調査が都市部限定で行われているのも一因だが、同国のインターネットへの傾注度の高さが見て取れる。
新聞や雑誌、ラジオなどは低めだが、フランスはそれらも高めの値を計上している。ニュース取得の意欲は他国よりも高く、多方面で取得する傾向があるようだ。
テレビとインターネットニュースの詳しい実情
報告書ではそれぞれの媒体に関して属性別の値も公開している。そこでテレビとインターネットニュースに限るが、その内情を見ていく。
まずはテレビ。なお中国では70代以上の回答者が1名しかいないので統計上のぶれを考慮し、該当部分は空白となっている。

タイが異様に高くどの属性もほぼ9割超え。高齢層では100%との値が出ている。フランスもそれに続く値を計上しているが、若年層ではやや落ちる。
タイが異様に高くどの属性も8割超え。高齢層では90%台後半から100%との値が出ている。フランスもそれに続く値を計上しているが、若年層ではやや値が落ちる。
男女別では男性よりも女性、未成年者と中堅層以降が高めに出るのはどの国でもさほど変わり無く、テレビの実情を推し量れるよい資料となる値の動きを示している。他方中国では中堅層が高めで高齢層はむしろいくぶん値を落とす傾向が出ているのは興味深い。

インターネットのニュースサイトではテレビと大よそ逆の傾向が出ているのは注目に値する。男女別では男性が、年齢階層別では若年層が高い値を示している。10代でやや低めの値が出る国があるのは、利用機会が得られていない、興味関心がわいていないからだろうか(テレビは多分に受動的に取得する機会があるが、ネットニュースでは原則的に能動的で無いと取得は不可能)。
他方中国では男女・年齢階層を問わず高い値が維持されている。今件は都市部限定とはいえ、インターネット経由では無く面接調査で実施されており、メディアによるバイアスが存在しないことを思い返せば、大いに注目すべき結果には違いない。
■関連記事:
地震情報で見直される「ラジオ」、評価を受ける「ソーシャルメディア」、そして……
※諸外国における対日メディア世論調査
直近年分はアメリカ合衆国、イギリス、フランス、中国、韓国、タイに対し、2017年12月から2018年1月に行われたもので、アメリカ合衆国・フランス・韓国は電話調査、イギリス・中国・タイでは面接調査で実施されている。調査地域は中国・タイは都市圏、それ以外は全国。対象年齢は中国以外は18歳以上、中国も同様だが70代以上の回答者は1名のみのため属性別では除外されている。回収サンプル数は各国約1000件。過去の調査もほぼ同様の調査スタイル。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更を加えたものです。










