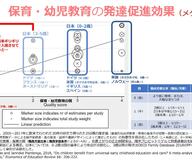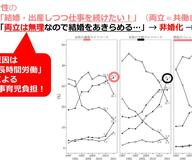児童手当の「多子加算」と「上乗せ」は効果比較できるか?

「多子加算」と「上乗せ」は効果比較できるか?
自民党が、児童手当の「所得制限撤廃」に向けて動き出しました。
その上で、児童手当拡充の方法について、自民党は、「上乗せ」(1人目からの一律増額)ではなく、「多子加算」(1人目は月最大1.5万円で現状維持、2人目は月最大3万円、3人目は月最大6万円にまで増額。追加年間予算は2~3兆円)を検討しているようです。
「多子加算」と「上乗せ」のどちらのほうが、現在の希望出生率1.75をより効果的に実現できるのでしょうか?
私の知るところでは、「多子加算」の(出生率・出生数に対する)因果効果については、日本では実証研究がありません。そもそも、日本では「児童手当」の因果効果についての実証研究がないのです。
より視野を広げて「現金給付」の因果効果を見ると、「出産育児一時金」の因果効果についての実証研究があるのみです。(この研究では、下位50%の低所得世帯でのみ出生率引き上げ効果があったという結果が得られています。この結果を用いて私が行った効果試算については、以前の記事をご参照ください。)
また、東京大学の山口慎太郎教授の既存研究レビュー(『子育て支援の経済学』2021年、第2章)によれば、海外でも、「多子加算」と「上乗せ」の因果効果を比較した実証研究はないようです。
2025年までがラストチャンス
少子化対策は、2025年までがラストチャンスです。出生数は2000年頃から減少していて、2025年以降は20代人口が急減していくからです。2025年までに、20代にとって結婚・出産しやすい環境を、政府は早急に整える必要があるでしょう。
もし自民党案の「多子加算」を最大限に想定して、「1人目には総額約200万円(現状)」「2人目には総額最大540万円(=仮に月3万円が15年間続く場合)」「3人目には総額最大1080万円(=仮に月6万円が15年間続く場合)」という給付金額になったとしても、「全て公立でも教育費に(塾代なども含めて大学卒業までに)約1,000万円かかる」という現状では、20代の若者が「1人目を産む(ために結婚する)」ためのインセンティブとしては、少し弱いかもしれません。
他方で、(先述の『子育て支援の経済学』でも紹介されている)カナダ・ケベック州での実証研究によれば、「2人目」やとりわけ「3人目以上」に手厚くする多子加算を中心とした児童手当拡充は、「1~3人目のすべて」の出生率を上昇させました。具体的には、児童手当拡充(主に多子加算)による出生率上昇幅は「1人目<2人目<3人目」(Table 7)、また、児童手当拡充の「1,000カナダドルあたりの費用対効果」は「2人目>1人目>3人目」だったようです(Table 8)。
この結果がそのまま日本にも当てはまるわけではないですが、日本でも、自民党案の「多子加算」によって、2~3人目だけでなく、1人目の出生率も上がる可能性があります。2~3人目への加算は、1人目を産むことへのインセンティブにもなるからです。
とはいえ、「多子加算」と「上乗せ」の効果を比較した研究はないため、どちらのほうが出生率を効果的に引き上げるのかは、分からない状況です。
「多子加算」が最大限成功する想定で「上乗せ」と比較すると?
そこで仮に、自民党案の「多子加算」によって、夫婦の現在の「理想子ども数」が実現すると(楽観的に)仮定してみましょう。
(夫婦の「理想の子ども数」自体が増える可能性や、女性有配偶率が増える可能性もありますが、それらの未知の可能性を加味すると試算が不可能になるため、ここではそれらの可能性を敢えて加味せずにおきます。私が行った「上乗せ」の効果試算も同様の仮定に基づきます。)
その場合、2021年出生動向基本調査(夫婦調査)の結果の数値を使うと、有配偶女性の出生率は、(夫婦の平均理想子ども数2.25人-妻の年齢が45~49歳の初婚同士夫婦の出生子ども数1.81人=)「0.44人」ほど増えると予想されます。(ただし、ここの1.81人は若年の妻の将来の45〜49歳時子ども数が反映されていないため過大評価されており、0.44人は過小評価されています。)
45~49歳女性の有配偶率が、今後「70%」(2020年国勢調査)のまま不変と仮定すると、合計特殊出生率は(0.44×0.70=)「0.31」ほど増える計算になります。この場合、費用対効果は下記のようにまとめることができます。
「多子加算」(楽観的仮定による最大効果):「第1子は月額最大1.5万円で現状維持、第2子は月額最大3万円、第3子以降は月額最大6万円まで増額」(自民党案)(追加年間予算2~3兆円 )→(楽観的仮定で)出生率0.31上昇[追加年間予算1兆円あたり出生率0.10~0.15上昇]
また、カナダ・ケベック州とイスラエルでの児童手当(いずれも多子加算型)の「出生率引き上げ効果」の因果推論の推定結果(給付金額が1%増えると出生率が0.1~0.2%上昇/山口慎太郎『子育て支援の経済学』36, 40頁参照)が、日本に当てはまると仮定すると、費用対効果は下記のようにまとめることができます。
「多子加算」(カナダ・ケベック州とイスラエルでの因果推論の推定結果が日本に当てはまると仮定):「給付金額が1%増えると出生率が0.15%(0.1~0.2%)上昇」→[追加年間予算1兆円(給付金額50%増)あたり出生率0.10(0.07~0.13)上昇 ](「給付金額が増えても費用対効果は逓減しない」という楽観的仮定に基づく)
そして、「上乗せ」の費用対効果は、以前の記事をふまえると、下記のようにまとめることができます。
「上乗せ」:「月額3万円上乗せ」(所得上位50%の世帯には「月額3~1万円上乗せ」)(追加年間予算4.3~5.2兆円)→出生率0.31上昇[追加年間予算1兆円あたり出生率0.06~0.07上昇](「給付金額が増えても費用対効果は逓減しない」という楽観的仮定に基づく)
以上の楽観的仮定では、「多子加算」は、「上乗せ」を上回る費用対効果となりそうです。
実際には、「多子加算」によって育児の経済的負担が減ることで、夫婦の「理想の子ども数」が増えたり、「女性有配偶率」が増えたりする可能性もあり、それらの場合には、「追加年間予算1兆円あたり出生率上昇幅」も増えることになります。そうなると(とくに「理想の子ども数」が増えた場合には)、上記の楽観的仮定での「多子加算」の費用対効果は、「上乗せ」よりもさらに大きくなります。
まとめ
以上のようにエビデンスは極めて乏しいですが、「多子加算」が「上乗せ」よりも(希望出生率1.75実現のための)費用対効果が高くなる可能性もあります。
自民党がすでに大幅な「多子加算」に前向きである好機を活かすならば、「上乗せ」よりも「多子加算」を支持する、というのも一つの考え方かもしれません。
いずれにせよ、この論点については、さまざまなエビデンスにもとづく更なる議論が必要であることは確かでしょう。