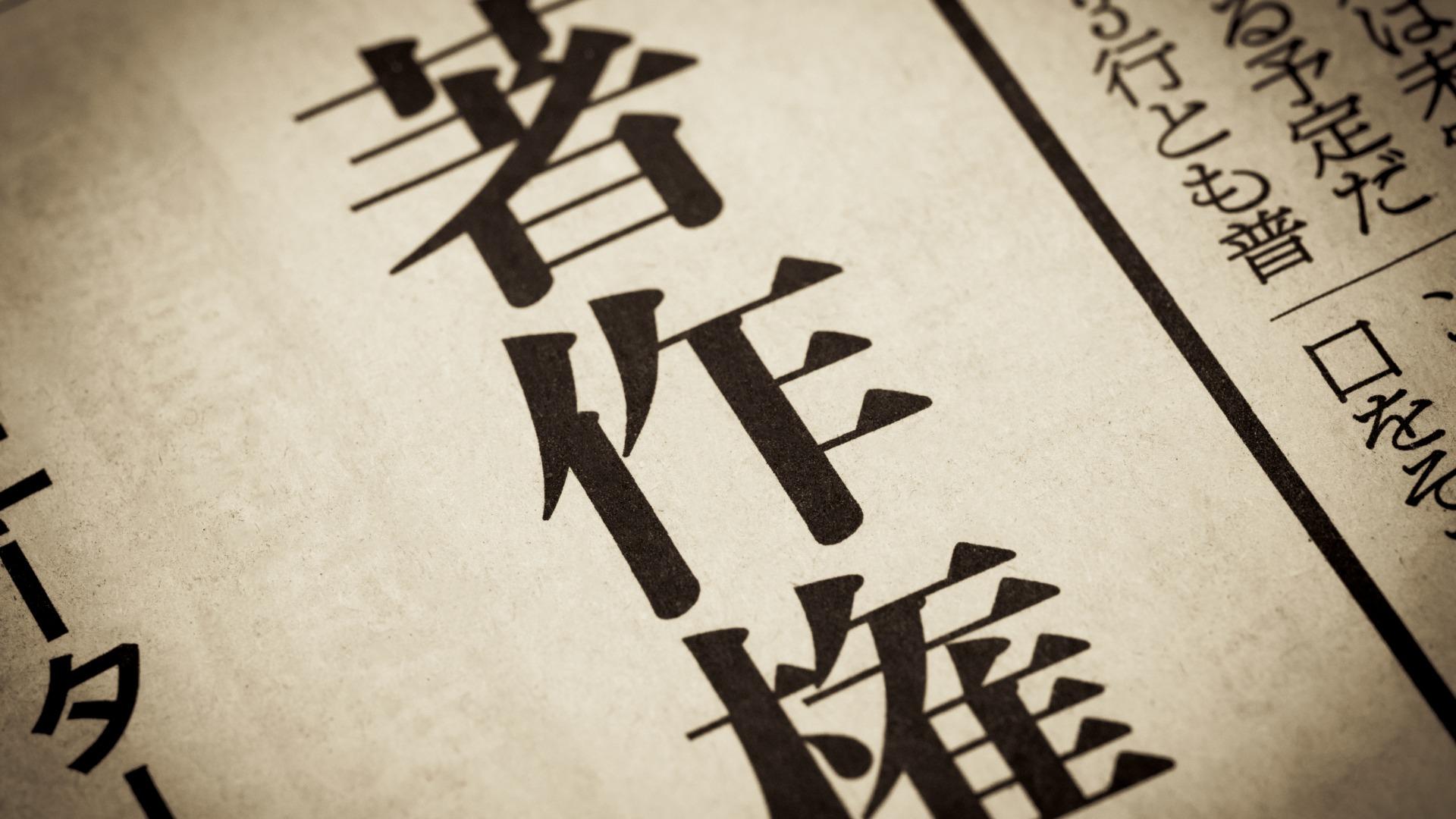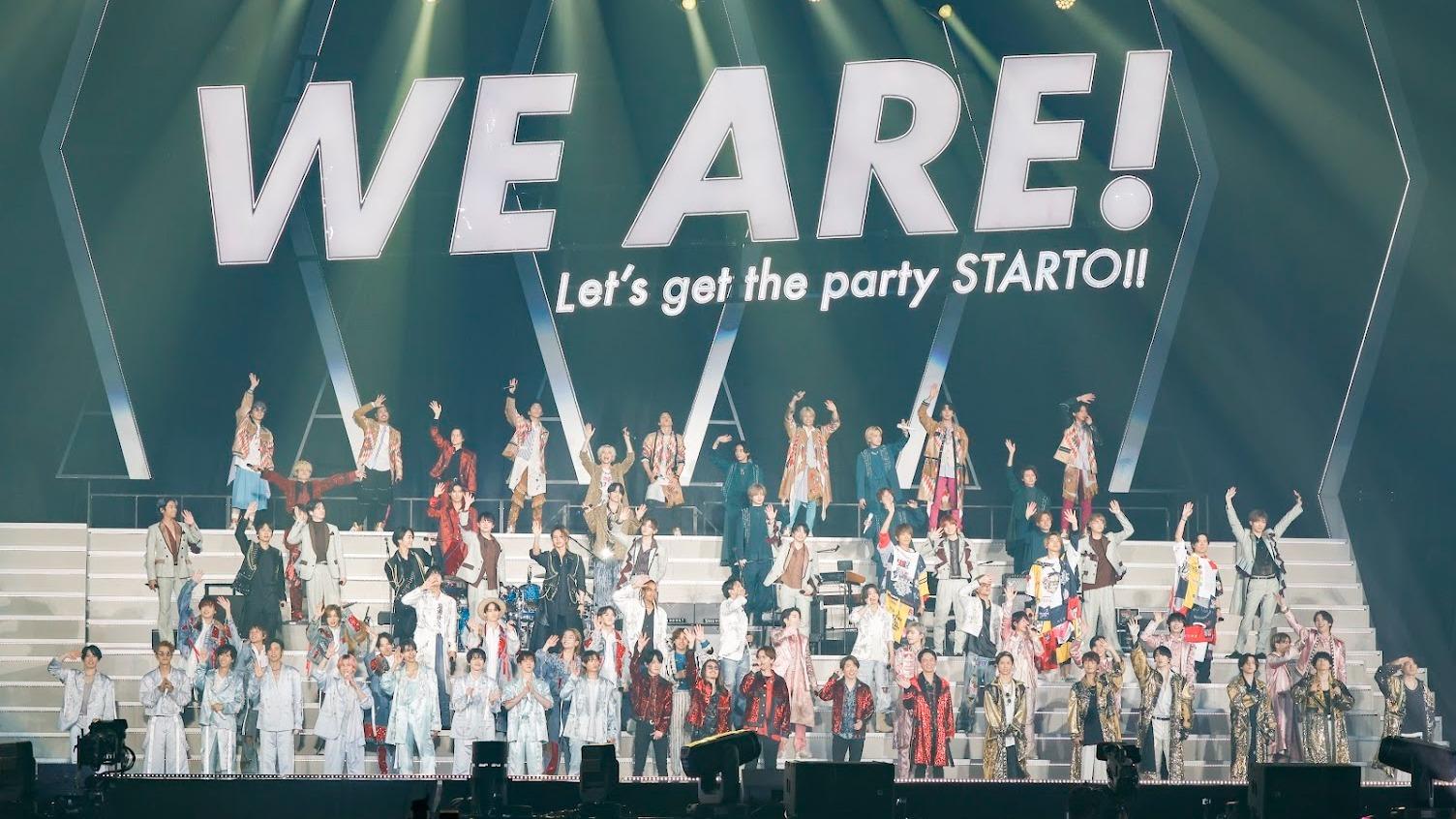日本企業は長期金利の上昇について懸念か

2月のロイター企業調査によると足元の長期金利の上昇について、「懸念している」と回答した企業は55%となり、「懸念していない」の45%を上回った。また、10年国債の金利上昇はどこまで許容できるかとの問いに、「0.25%」と回答した企業は40%となった。「0.50%」と回答した企業も38%とほぼ同水準となり、次いで「1.0%」までとの回答が12%だった(17日付ロイター)。
どうやら日銀が長期金利コントロールを導入後、企業の金利観もだいぶ変わってきてしまったようである。
景気回復に力強さを欠く中、長期金利のさらなる上昇は銀行貸出や住宅ローンなどにも影響し、経済活動を抑制させる恐れがあるとロイターは指摘している。
予想は下回ったものの、内閣府が15日発表した2021年10~12月期のGDP速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で年率換算で5.4%増となっていた。
しかし、経済活動が正常に稼働しているなかにあって、金利だけが異常な水準に維持されることが本当に必要とされているのか。
金利を押さえ付けて助かるのは債務者となる。典型的なのは国であろう。企業も当然債務を抱えているところも多い。社債の発行などにも影響は出よう。
しかし、事業法人が保有する現預金残高は、300兆円を超えている。むしろ金利上昇の恩恵が受けやすいはずである。
足下の消費者物価指数は前年比で0.5%であるが、携帯電話料金の引き下げによる影響等を除くとプラス1.7%程度となる。実際には携帯電話料金の引き下げによる影響は4月にならないと剥落しないため、数字には表れないものの、現状はそれほど低いものではなく、今後さらに物価が上昇してくる可能性も高い。
そもそも企業としては、企業物価指数が前年比で8%を超す上昇となっていることで、物価と金利の乖離にむしろ疑問を抱いてもおかしくはないはずである。
どうも低金利に慣れすぎてしまったことで、金利の上昇ということに対しては期待よりも懸念のほうが強くなってしまっているように思われる。