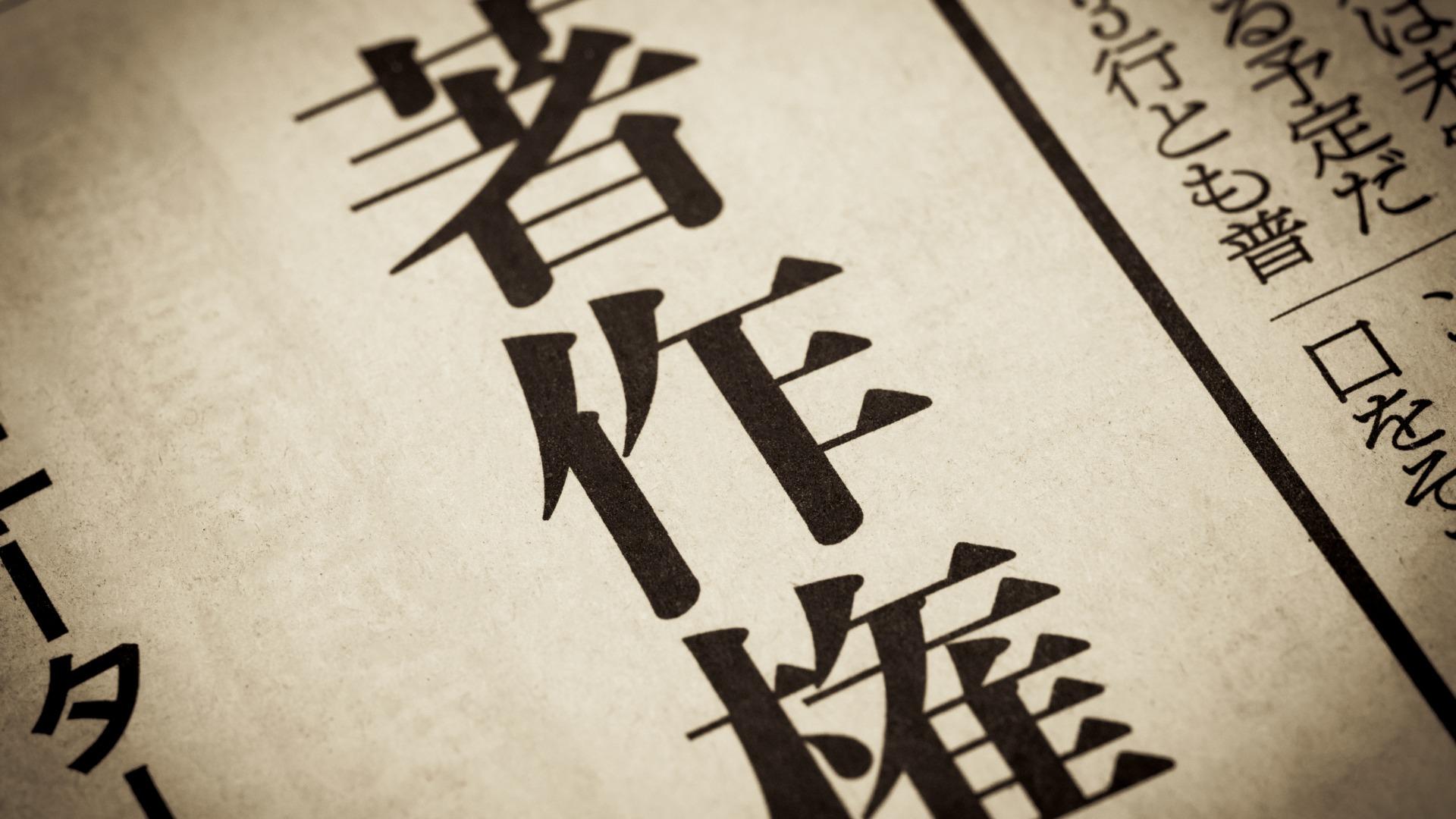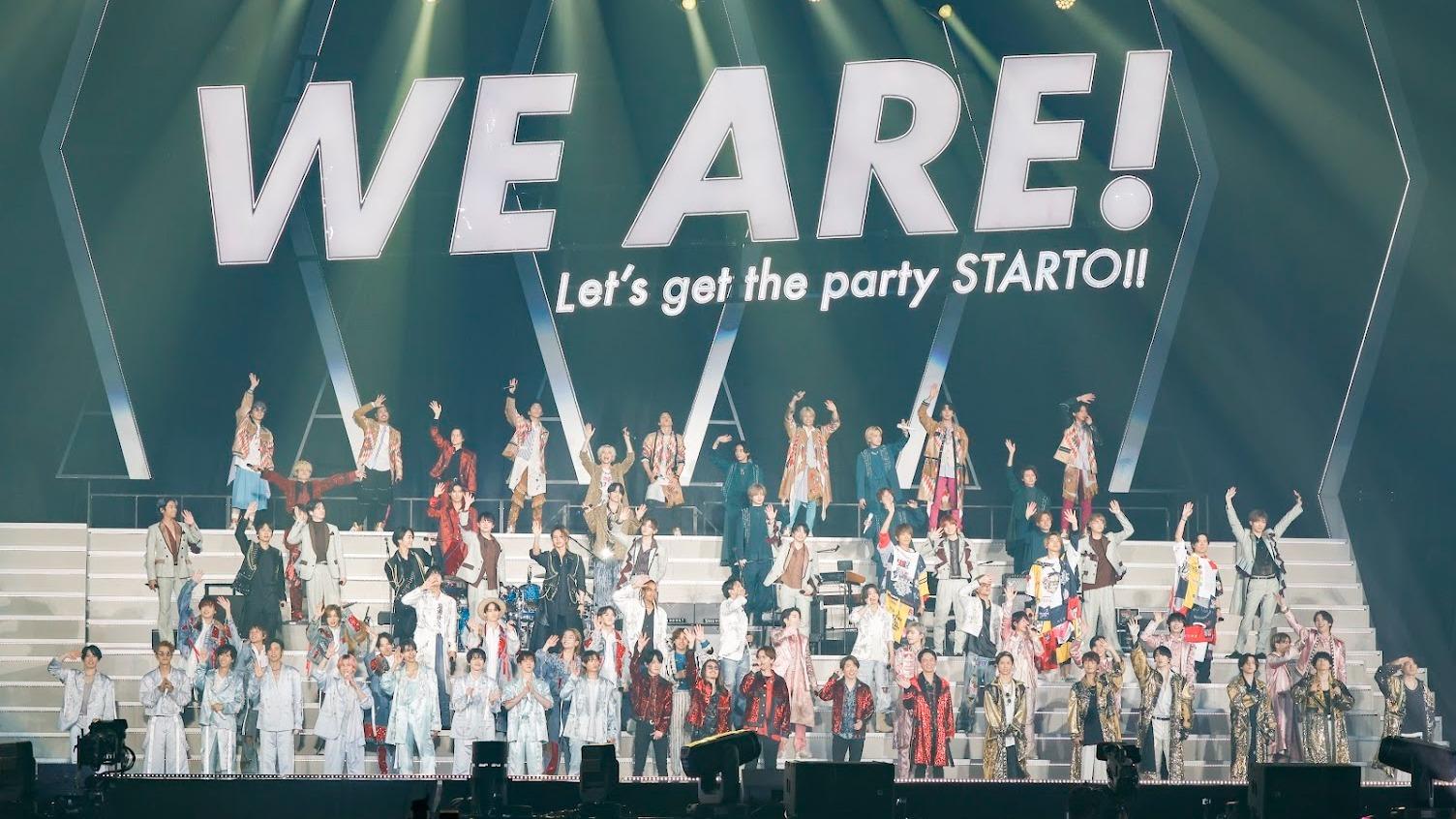円と株と債券の連動性、ヘッジファンドが市場を動かす?
ここにきて外為市場と日本の株式市場と債券市場はどうやら三すくみの状態にあるようである。外為市場では日本国債の動向に注視し、株式市場はこの外為市場を見ながら動いている。債券市場は株式市場を見ながらの動きとなっている。
これはお互いが材料視されているというよりも、5月に入り特にドル円が100円を付けたあたりから、海外ヘッジファンドなどによる円と株先と債先に仕掛け的な動きが入っていたためとみられる。債券市場を中心にその間の状況を追ってみたい。
5月10日にドル円が100円台に乗せたことをきっかけに、10日の債券先物は144円45銭の寄り付き後サーキット・ブレーカーが発動し、143円43銭まで下落した。この日の現物債で大きく利回りが上昇したが10年債であり、2月25日以来の0.7%台乗せとなった。完全に地合が変化しており、かなりまとまった売りが10年債主体に持ち込まれた可能性がある。
5月13日に債券先物はさらに下落し、4月5日の直近安値で下値の節目とも言えた143円10銭を割り込んだ。4月5日のレンジ内に収まっていた債券先物が、そこから脱してきたことで、これで相場の地合が完全に変化した。日銀は国債買い入れをオファーしたが、予想通りのオペが入ったことで、むしろあらためて売りも入りやすくなり、実際に後場に入ると再び下げ足を速め、債券先物は142円70銭まで下落し、サーキット・ブレーカーが発動した。10年債は0.800%まで利回りが上昇した。
14日の債券先物は買い戻しが先行した。30年国債入札そのものは無難な結果となったものの、その結果を確認しての売りが入った。10年債利回りは0.850%、そして5年債利回りは0.400%に上昇した。0.400%は5年債としては2011年7月以来の水準となる。債券先物は一時前日比1円安となったが、当該値段以外で5分間取引が成立しない場合という基準に満たなかったことでサーキット・ブレーカーは発動しなかった。
15日の債券先物は前日比93銭安の141円18銭と大きく下落して寄り付いた。14日の米10年債利回りは1.97%に上昇していた。5年債利回りは0.455%、10年債利回りは0.920%に上昇し、2012年4月以来の0.9%台乗せとなった。日経平均は2008年1月4日以来15000円台を回復した。
16日と17日には債券先物に押し目買いも入り値を戻している。17日に10年債利回りは0.8%割れとなった。
再び動きが出たのが20日である。朝から外為市場は大荒れとなった。17日の欧米市場でドル円は103円台をつけていたが、朝方の参加者が薄い時間帯に、一時102円を割り込んだ。その後、102円台後半に戻すなど荒っぽい展開に。東京株式市場は米株の上昇などから買いが先行し、日経平均は15300円台に上昇。債券は先物主導で売り圧力を強めた。日銀の黒田東彦総裁が20日の月例経済報告等に関する関係閣僚会議で、経済・物価の先行き見通しの改善で「金利が徐々に上昇していくのは当然」などと述べたことが伝わると、さらに下げ足を速めることになり、先物は先日比91銭安の141円78銭まで下落。現物10年債利回り一時0.875%に、また5年債利回りは0.405%と再び0.4%台に乗せた。
21日の40年国債入札は最高落札利回りが1.955%となり、事前の予想をやや上回ったことから、債券先物は売られ141円59銭まで下落した。ただし、10年債利回りが0.895%と0.9%に接近したことから、押し目買いも入り下げ渋りに。
22日の日銀の金融政策決定会合では長期金利についての言及等はなく、これが嫌気されたのか債券先物は決定会合の結果発表後、141円60銭まで下落した。10年債利回りも0.900%に上昇した。
22日にバーナンキFRB議長は、議会証言後の質疑応答で、景気指標の改善が続けば債券購入のペースを減速させる可能性があると指摘。4月30日~5月1日に開催されたFOMC議事要旨でも、複数の議員が早ければ6月にも資産購入を減額したいとの意向を示していた。バーナンキ発言等を受けて22日の米国債券市場で米債は下落し10年債利回りは2.02%と2%台に乗せた。
23日の債券先物はサーキット・ブレーカー発動し140円70銭まで下落した。現物10年債利回りは0.985%の出合い後、1.000%と昨年4月5日以来の1%台乗せとなった。東京株式市場は外為市場でドル円が103円台をつけるなど、円安ドル高が進み、これが好感されて日経平均は一時16000円に接近した。
日銀がシグナルオペとなる1年物共通担保資金供給(全店、固定金利方式)と国債入札日にも関わらず国債買い入れをオファー。これをきっかけに債券先物は買い戻し圧力を強め、10年債利回りは1.000%から0.825%に。債券先物は140円70銭から142円74銭に大きく切り返した。
株式市場では中国の5月製造業PMIの低下などもあり(実際の要因は債券先物の可能性も)、今度は売り圧力が強まり、急速に地合が悪化。一気に利益確定売りなどが膨らみ、一時日経平均先物は震災後の2011年3月15日以来のサーキッド・ブレーカーが発動。日経平均は1000円以上も下落した。
24日の東京株式市場は買いが先行し、日経平均は一時15000円台を回復。この株の反発も意識されて10年債利回りは一時0.905%に上昇、債券先物は一時141円64銭まで下落した。日銀は午前10時10分に国庫短期証券買入1.5兆円と、残存5年超10年以下と残存10年超の国債買い入れをオファー。国債買い入れは、残存5年超10年の案分利回り格差がプラス0.000%と実勢に比べてかなり強かったことから、後場に入ると債券先物は前日比4銭安の142円50銭まで上昇した。これに対して日経平均は次第に上げ幅を縮小させ、円が再び買われドル円が101円近辺をつけたことで、日経平均は一時14000円を割り込むなど、前日に続き波乱含みの展開となった。
5月10日のドル円の100円台乗せあたりからの様子を確認してみた。4月4日の異次元緩和を受けての国債の下落は、当初は中期ゾーンから長期ゾーンにかけて、途中から流動性が意識された超長期債が大きく下落していた。つまりそれぞれ銀行などの投資家の売りが要因とみられた。ところが5月の「債券相場の変」は債券先物主体であり、株先や為替の動向との連動性もあり仕掛け的な動きと思われる。債券先物は10日以降、出来高も建玉も大きく膨らんでいた。
どうやらヘッジファンドなど投機家が、当初は円売りとともに債券先物の売り、株先買いを仕掛けていたとみられる。22日のバーナンキ議長の出口を意識した発言などをきっかけとした23日の日本の長期金利1.000%台乗せ、ドル円の103円近辺への動き、日経平均の16000円接近で、それぞれいったんピークアウトし、これまでのポジションを一気にひっくり返してきたとみられる。そのきっかけは日銀によるシグナルオペを意識した債券先物の買い戻しであった可能性もある。
円売り・株先買い・債先売りから、今度は円買い・株先売り・債先買いに転じた。この株先売りが効いたため、特に11月以降、下げらしい下げがなかった株式市場が動揺をみせてしまった。この一連の動きから、外為市場や株式市場は日本の国債市場の動向にも、より注意を払うようになってきた。