1970年生まれ。東京大学法学部中退。地中美術館(香川県直島)、岡山県議会議員などを経て、2013年、ローカル・シンクタンク「一般社団法人つながる地域づくり研究所」(岡山県岡山市)を設立。自治体と民間と住民をつなぎ、地方創生やまちづくりの現場を伴走支援する。「官民連携まちづくり推進協議会」「文化と教育の先端自治体連合」など、共通するテーマに取り組む、全国の自治体団体の事務局も務める。地域や自治体、企業の声を聞き、「しごとコンビニ」や「放課後企業クラブ」などの新たなしくみを生み出している。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜12件/12件(新着順)
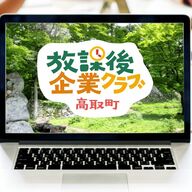 都市部企業の社員が、キャリアのヒントを地方で見つける~「放課後企業クラブ」
都市部企業の社員が、キャリアのヒントを地方で見つける~「放課後企業クラブ」 「その日が来たら。」会いに行きたい人がいるまちを探す【#コロナとどう暮らす】
「その日が来たら。」会いに行きたい人がいるまちを探す【#コロナとどう暮らす】 コロナ禍でもオンラインでつながる地方自治体
コロナ禍でもオンラインでつながる地方自治体 新型コロナと向き合い、行動する地方自治体
新型コロナと向き合い、行動する地方自治体 「トランプ大統領誕生」や「ブレグジット(EU離脱)」が起きなかった日本における地方創生の意味
「トランプ大統領誕生」や「ブレグジット(EU離脱)」が起きなかった日本における地方創生の意味 地方創生は「どうせうまくいかない」のか?
地方創生は「どうせうまくいかない」のか?- 【ふるさと納税】自治体間競争の厳しさに背筋が凍りました
- 合計特殊出生率2.81?!
 【2015統一地方選】誰に投票するか選ぶための材料
【2015統一地方選】誰に投票するか選ぶための材料 【2015統一地方選】地元の選挙に誰が出てるか知る方法
【2015統一地方選】地元の選挙に誰が出てるか知る方法 18歳選挙権という切符
18歳選挙権という切符 2015年、地方は分かれ道を歩き出す
2015年、地方は分かれ道を歩き出す
- 前へ
- 1
- 次へ
1〜12件/12件





