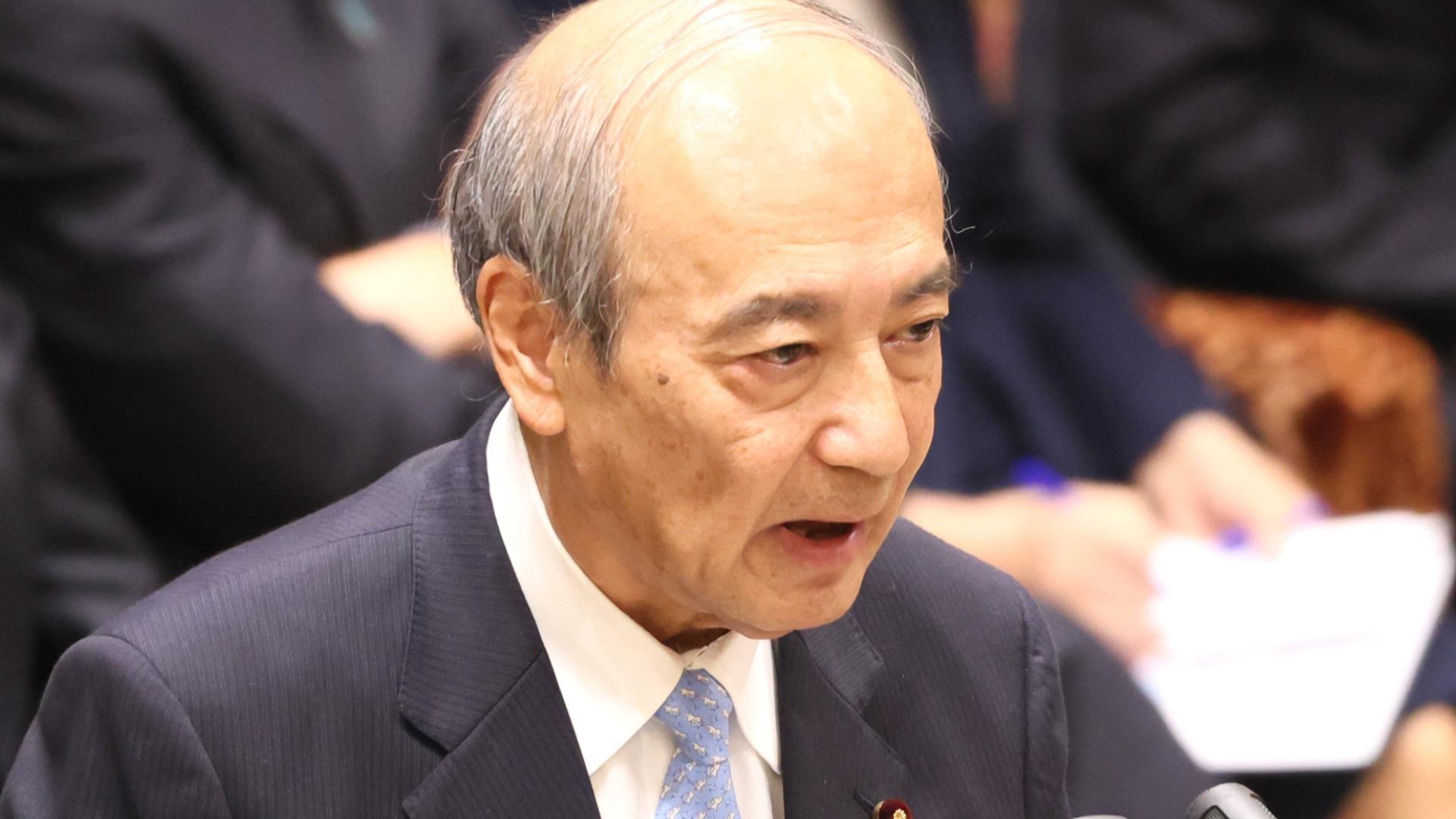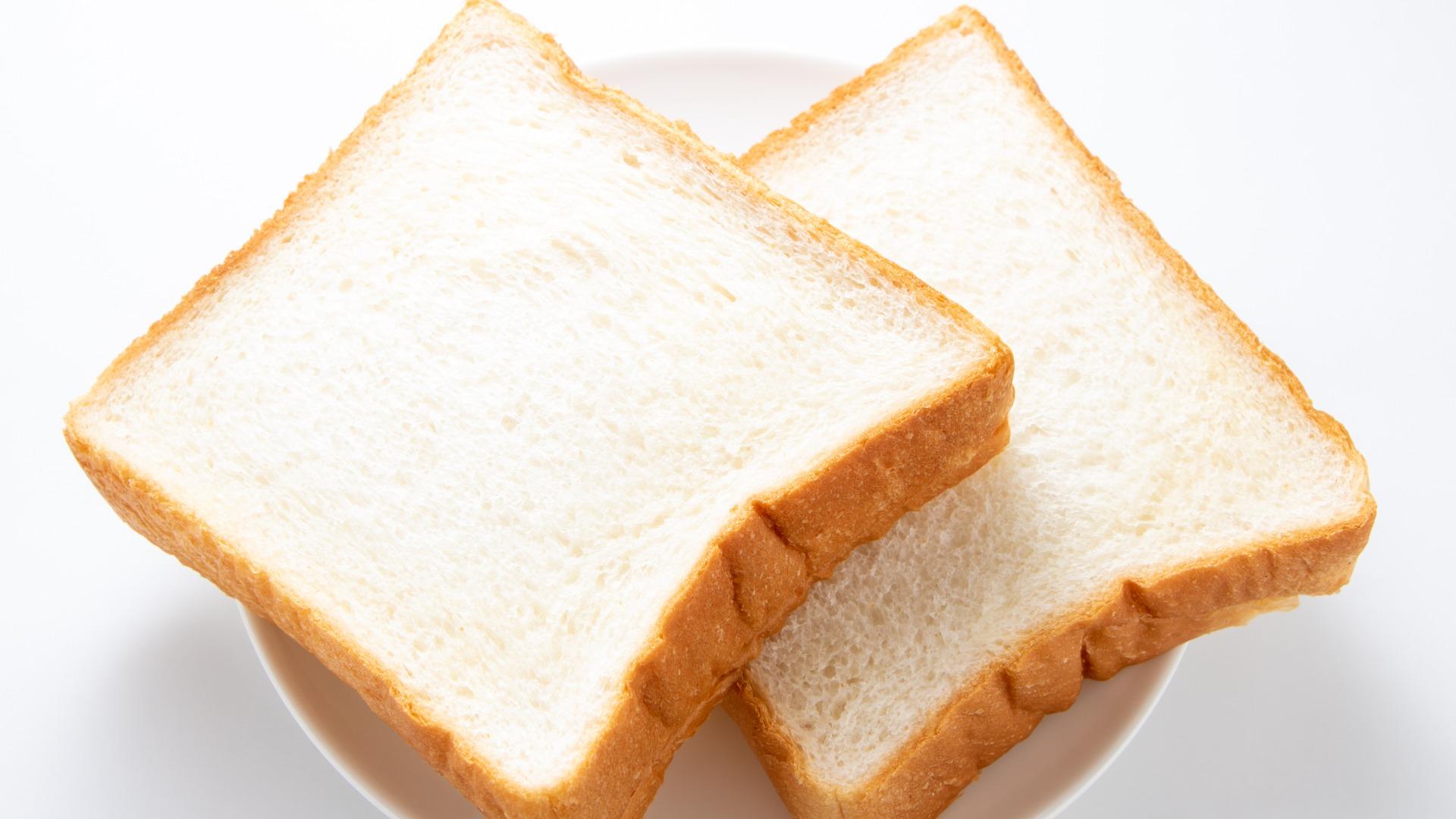自宅通いは2/3近く…大学生の自宅・下宿住まいの実情をさぐる

大学生活をはじめるにあたり、少なからぬ人が楽しみにしている事柄の一つに「(下宿での)一人暮らし」がある。実態として、大学生のうちどの程度の割合の人が、下宿での生活をしているのだろうか。独立行政法人日本学生支援機構が2022年3月に発表した「令和2年度学生生活調査」(※)などから、その実情を確認する。
同じ大学生でも居住形態が異なると通学時間は大きな違いを見せる。さまざまな事情があるにせよ、一般的には実家通いの方が通学時間は長い。

そこで実際にどれ程の割合の大学生が実家通いなのか、下宿通いなのかを見比べたのが次のグラフ。直近となる2020年度では大本の資料には国立・公立・私立それぞれの値のみが記されており、全体としての平均値は無い。そこで全体の平均は文部科学省の学校基本調査の該当年分(2020年度分)から大学生の数を確認し、その値を用いて加重平均で算出した。
それによるとすべてを合わせた大学昼間部全体の推移だが、全般的には自宅が5割前後、学寮が1割足らず、下宿などが3~4割程度となる。直近の2020年度分では大学の種類別のものもグラフを作成し、状況の把握を試みる。


まず全体の経年動向だが、少しずつ自宅通いが増え、学寮や下宿などの利用者が減っている。直後にグラフ化するが、国立・公立大学生の自宅通い率はほぼ横ばいのままなので、私立大学生の自宅通い率の増加が全体にも影響を及ぼしている。2016年度の自宅割合の減少はイレギュラーだったようだ。
そしてその私立大学生だが、直近の2020年度では2/3近くが自宅通い。下宿などの利用者は3割足らずに過ぎない。国立の下宿利用率6割近く、公立の5割強とは大きく差が開いている。これは大学の立地・地域性(私立大学は国公立大学と比べると数が多く、地域分散度合いが大きい)にもよるが、それ以上に学費負担の大きさが影響していると考えてよい(見方を変えれば、費用負担の面で公立・国立大学だからこそ、下宿などが許されやすいともいえる)。
私立大学生は元々自宅通いの比率は高かったが、さらに増加の動きを示している。公立・国立に大きな変化が見られないのと比べ、特異な動きといえる。

私立大学生の自宅通い率は2000年度から2020年度にかけて9.5%ポイントの増加。グラフ化は略するが(2010年度までは)学寮利用率はほぼ横ばいで、下宿利用率が確実に減っていることを併せると、実家世帯では学費などの負担が重く、さらに負担が予想される下宿での修学を断念し、実家通いの選択をする事例が増えていることが考えられる。
また国立大学生も直近6年間においては、増加の動きが見受けられる。これが一時的なものなのか、傾向だったものなのかは、もう少し見定める必要があるものの、注意すべき動きには違いない。
■関連記事:
【生徒・学生の平均通学時間は1日往復53分・高校生は長めの傾向(最新)】
【雑誌読む 時間は意外に 就寝前 通勤通学 あまり読まれず】
※令和2年度学生生活調査
2020年11月に大学院、大学学部および短期大学本科の学生(休学者および外国人留学生は除く、社会人学生は含む)の中から無作為抽出方法によって抽出された学生に対して調査票方式で調査されたもの。有効回答数は3万7591人。調査そのものは2年おきに行われており、現時点では2020年実施の結果が最新のデータ。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。