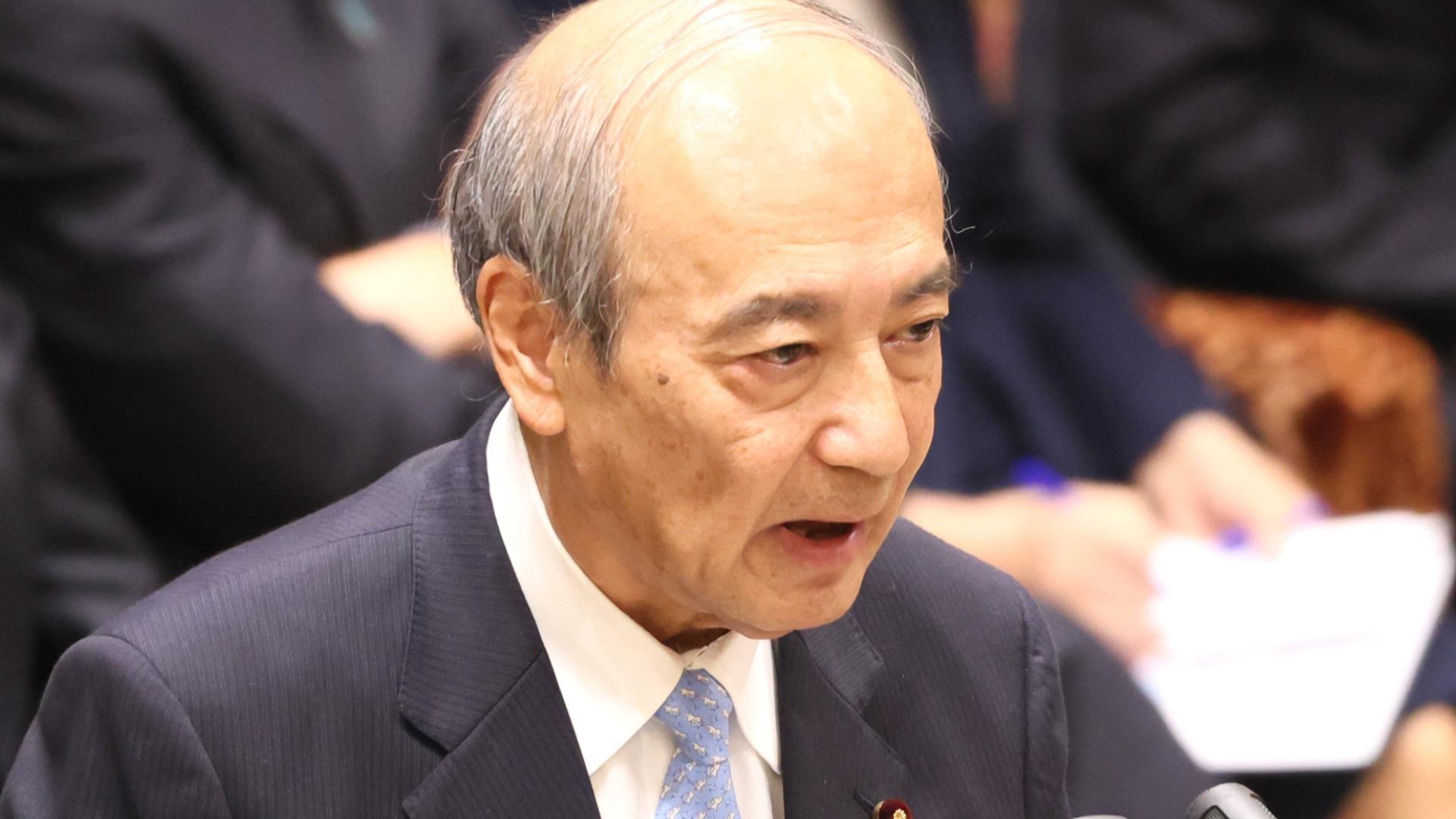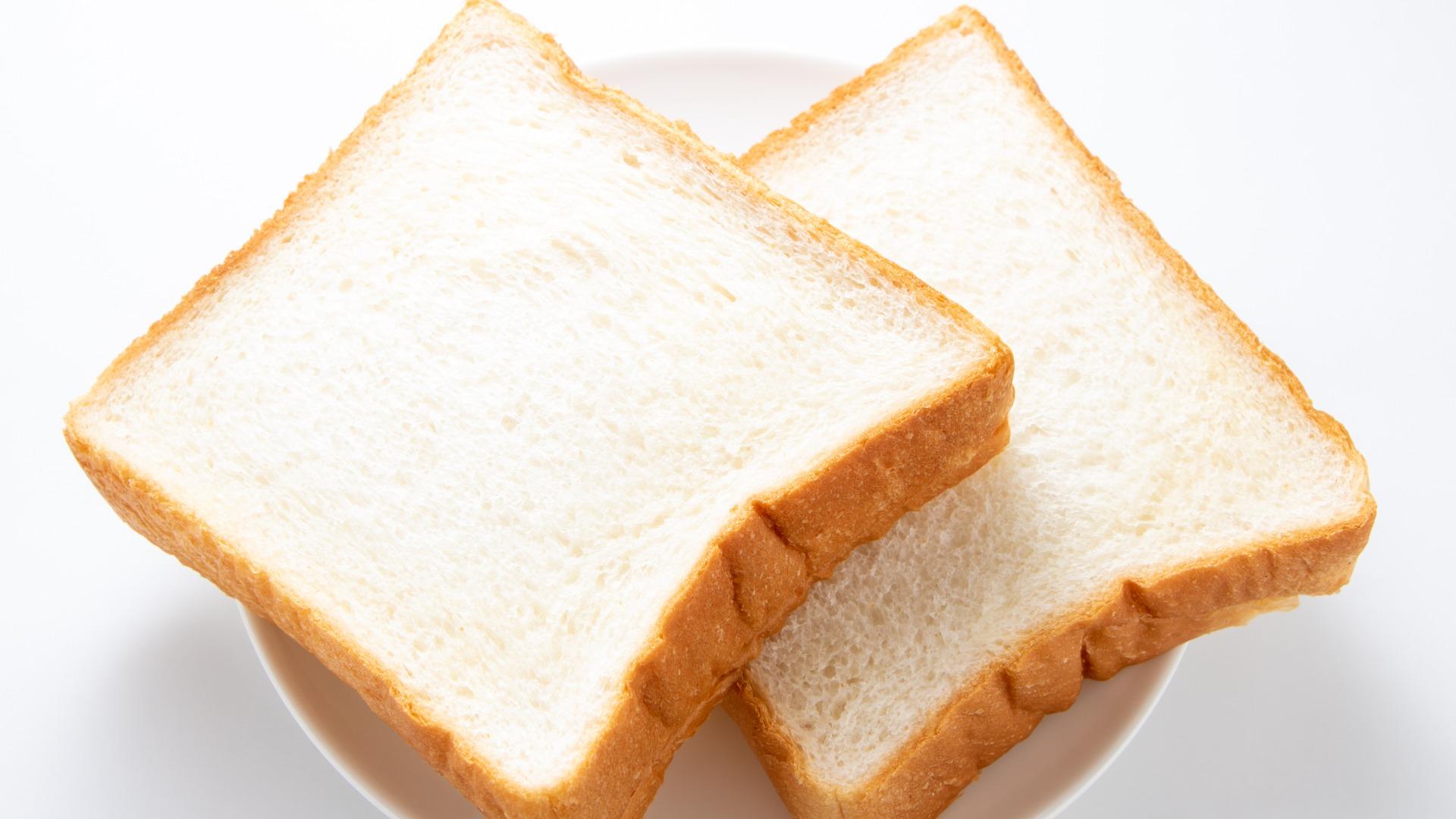仕送り金は減る傾向に…大学生のふところ内部事情をさぐる

大学生活では多様な出費が生じるため、それをまかなうための収入が不可欠となる。それでは大学生はどのようにして収入を得ているのだろうか。独立行政法人日本学生支援機構が2022年3月に発表した「令和2年度学生生活調査」(※)などから、その実情を確認する。
今調査母体において直近年度では8割強がアルバイトに従事している。

アルバイトなどの仕事をすれば当然収入が得られることになる。しかしその手取りだけで学生生活の支出をすべてまかなえる人は少数(「まれ」のレベルだろう)。ほとんどは奨学金、実家からの仕送り、さらには貯蓄を取り崩して生活をすることになる。今項目ではそれら学生の収入事情をグラフにしたもの。
収入項目を大きく「家庭給付(仕送り)」「奨学金」「アルバイト」「定職(収入)・その他」に区分し、それぞれの収入推移と、収入全体に対する比率を経年でグラフ化したのが次の図。全体額の漸減、そして家庭給付が大きく減少しているようすが分かる。


今件データではアルバイト従事の有無、奨学金取得の有無毎の区分された値は無い。それぞれの年度全体としての平均であり、実際には個々の就学状態で大きく変化しうることを記しておく。例えばアルバイトをしていない学生は当然バイト料は手に入らず、実家通いで家賃や食費の一部を浮かせることができなければ、お財布事情はさらに厳しいものとなる(ちなみに直近の2020年度における大学昼間部の居住形態別学生数比率は、全体で自宅59.2%・学寮6.8%・下宿やアパートなど34.0%である)。
全体の傾向としては、
・全体額の漸減。特に2010年度の減りが大きい。2012年度と2018年度はかろうじて増加しているが、アルバイトや奨学金の積み上げによるもの。
・家庭給付の額はほぼ横ばいだったが、2008年度から2010年度にかけて大きく減っている。その後も漸減は続く。
・アルバイトの額は横ばい、しかし2010年度には減る動き(アルバイト従事者の比率減少が一因)。2016年度以降は増加(アルバイト従事者の比率増加が一因)。
・奨学金額は2010年度に大きく増加し、その後はほぼ横ばいから漸減へ。
などの動きが見える。特に2008年度から2010年度にかけては大きなマイナス方向の動きがあり、2007年夏に始まる直近の金融危機、経済不況による影響が大きく出ていることがうかがえる。
詳しくは機会を改めて確認するが、とりわけ家庭給付の額の減少傾向が生じている。消費者物価指数の動向に大きな変化は無いことから、純粋に実家・親元のお財布事情が厳しくなったか意向の変化によって、仕送りが減らされたことがうかがえる。ちなみに2008年度から2010年度の急落だが、居住形態別推移を見ても、自宅通学の人が増えて下宿者が減ったからと説明するには減少額が大きすぎる。
気になる動きとしてもう一つ留意したいのが、奨学金比率の増加。これは奨学金の額面が増額しているわけではなく、受給者率が上昇しているからに他ならない。今件は大学昼間部のデータだが、2002年度では全学生のうち31.2%が奨学金受給者だったものの、これが2020年度には49.6%にまで増加している。仕送り額の減額やアルバイト事情の厳しさを奨学金で少しでも穴埋めしようとの動きと言える。もっともここ数年においては漸減傾向にあるのもまた事実ではある。
■関連記事:
【日本学生支援機構の奨学金は有利子83万人・無利子52万人…奨学金事業の推移(最新)】
※令和2年度学生生活調査
2020年11月に大学院、大学学部および短期大学本科の学生(休学者および外国人留学生は除く、社会人学生は含む)の中から無作為抽出方法によって抽出された学生に対して調査票方式で調査されたもの。有効回答数は3万7591人。調査そのものは2年おきに行われており、現時点では2020年実施の結果が最新のデータ。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。