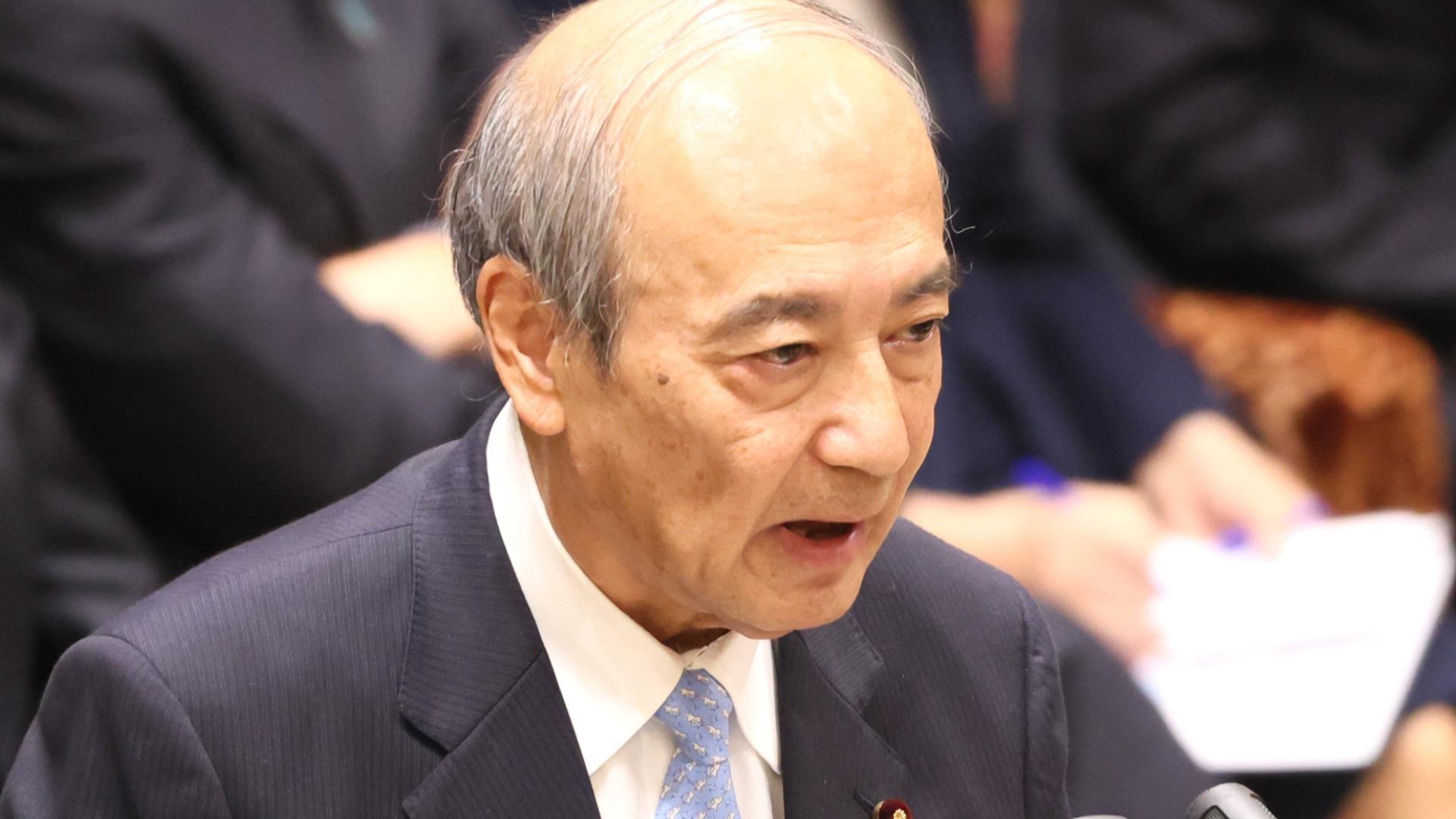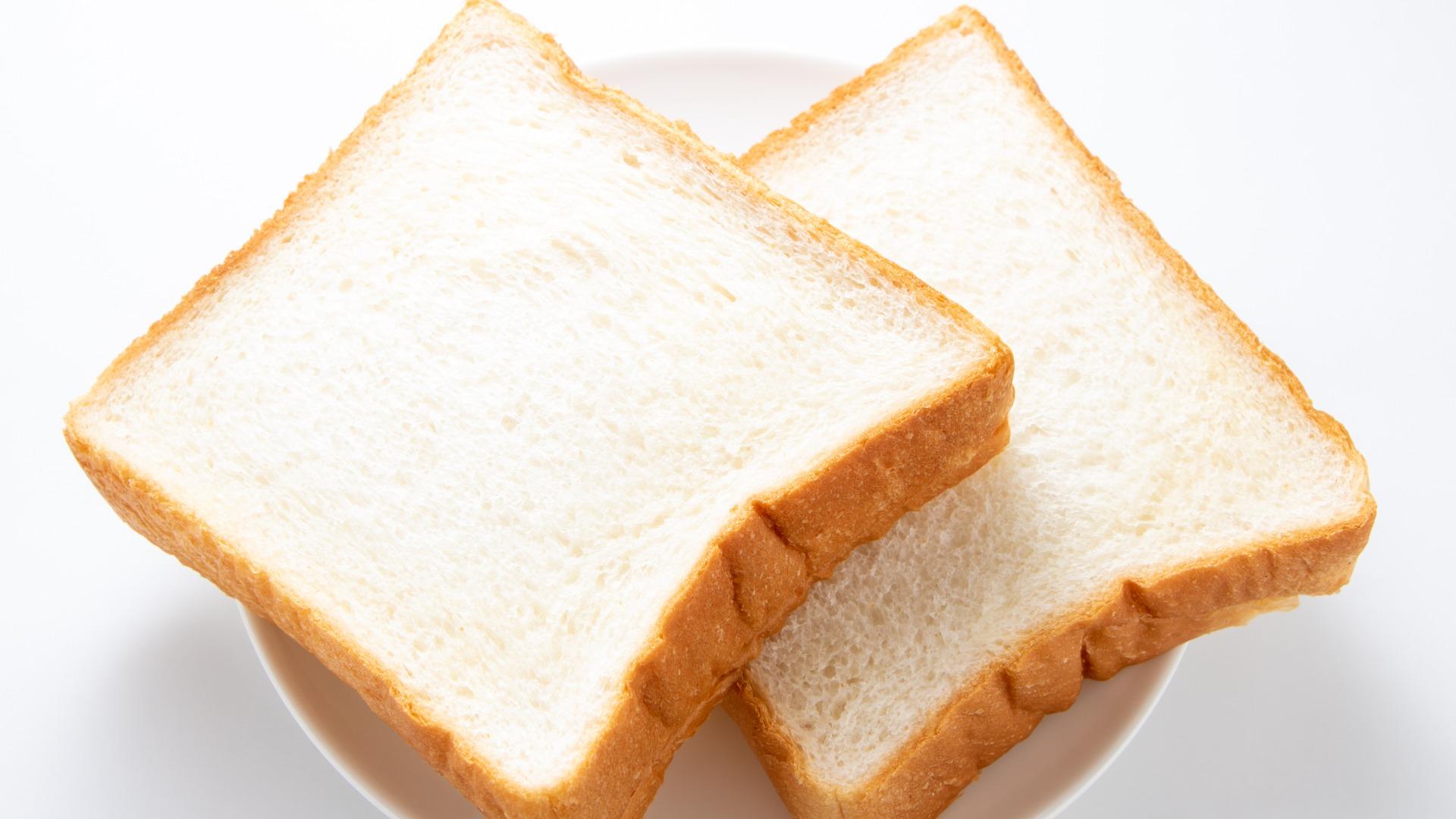「若者のパソコン離れ」はアメリカでも起きているのだろうか
パソコン87%、スマホは73%
日本では若年層が最初に触れるネット端末・スマートフォンの機能充実ぶりに満足し、パソコンを使わなくなる傾向にある。デジタル機器の先進国ともいえるアメリカ合衆国でも同じような現象は起きているのだろうか。同国の民間調査会社Pew Research Centerが2015年4月に発表した調査結果「Teens, Social Media & Technology Overview 2015」(主調査は2014年9月~10月に実施。対象は13~17歳のアメリカ在住者とその保護者で、インタービュー形式)を元に、その実情を確認する。
次に示すのは調査対象母集団における、該当端末を自分自身で所有しているか、何らかの形で自由に利用できる立場にある人、つまり実質的に利用状態にある人の割合。
パソコンの利用者は87%。非常に高い値を示している。恐らくは保護者が利用するために自宅にあり、子供自身も自在に使える状態なのだろう。家庭用ゲーム機の81%を超える値を示している点でも、大いに注目すべき結果。
他方スマートフォンは73%で大よそ3/4。パソコンと比べればプライベート性が高く、こちらはパソコンよりは回答者自身の所有物である可能性が高い。またタブレット型端末の58%との値も、日本と比べれば驚くべき値ではある。
携帯電話とパソコンの利用状況の詳細
携帯電話の所有状況につき、「スマートフォン(と従来型携帯電話)」「従来型携帯電話のみ」「携帯電話そのものを持っていない」の3パターンに仕切り分けし、現状について属性別に尋ねた結果を見たのが次のグラフ。改めてアメリカの未成年者におけるスマートフォンの浸透ぶりがうかがえる。
男女別では女性の方がスマートフォンの利用率が高いのは日本と同じ。13~14歳、日本では中学生に相当する世代ですでに68%がスマートフォン持ち。携帯電話そのものを利用していないのは18%でしかない。
一方、家庭環境におけるデジタル機器利用上のギャップも見えてくる。アメリカの調査結果では特に保護者の学歴と世帯年収は連動する関係があるため、世帯年収と保護者の学歴でほぼ同じように、「低学歴≒低年収」ほど携帯電話そのもの、そしてスマートフォンの利用率が低い。要は保護者の財布が固く、スマホが調達できない次第。
そして日本では低迷が懸念視されている、パソコン、そしてタブレット型端末の所有・利用率。
全体では87%がパソコンを、58%がタブレット型端末を利用している。その頻度までは確認できないが、設問様式からは「過去に触ったことがある程度」などでは無いのが確認できる。大人ならともかく、日本なら中高生に相当する年齢でこの値が出ているのは、少々驚きでもある。
世代別では年上の方がパソコンの値は高い一方で、タブレット型端末は低め。同調査別項目では年上の方がスマートフォンの利用率が高い結果が出ているので、タブレット型端末からスマートフォンにシフトしているのかもしれない。
世帯が高年収なほど、そして親の学歴が高学歴ほど、タブレット型端末もパソコンも利用率が高くなる傾向がある。世帯そのものに金銭的余裕がある人ほど、利用する機会を得やすい次第。いわゆるデジタルデバイド(デジタル機器の所有・利用格差)では金銭面による差が大きく出ることが指摘されているが、それが如実に表れる結果といえる。とりわけ高単価となりやすいパソコンでは、顕著に表れているのが特徴的である。
調査方法や「所有・利用」に関する定義が異なるため、一概に比較するのはリスクが高いが、それを抜きにしても日本の中高生と比べ、パソコンの利用率が高いのは注目に値する。アメリカでは税制の問題から一般世帯におけるパソコンの必要性が高く、結果として子供が触れる機会が多くなるのも一因だが、未成年時におけるパソコンへの接触機会の多少が今後どのような影響をもたらし、相違を示すことになるのだろうか。日米双方の動向を注意深く見守りたいところだ。
■関連記事: