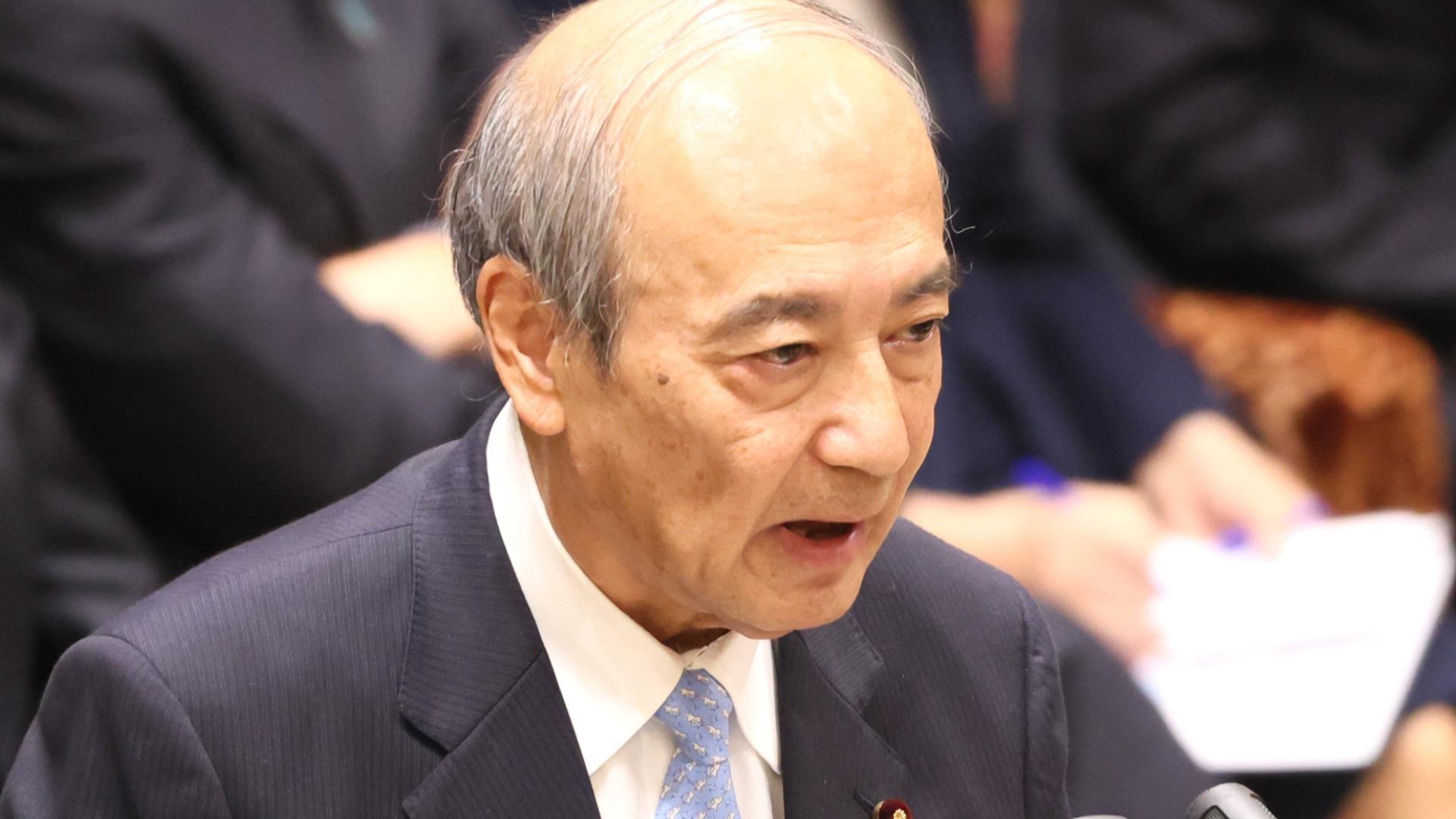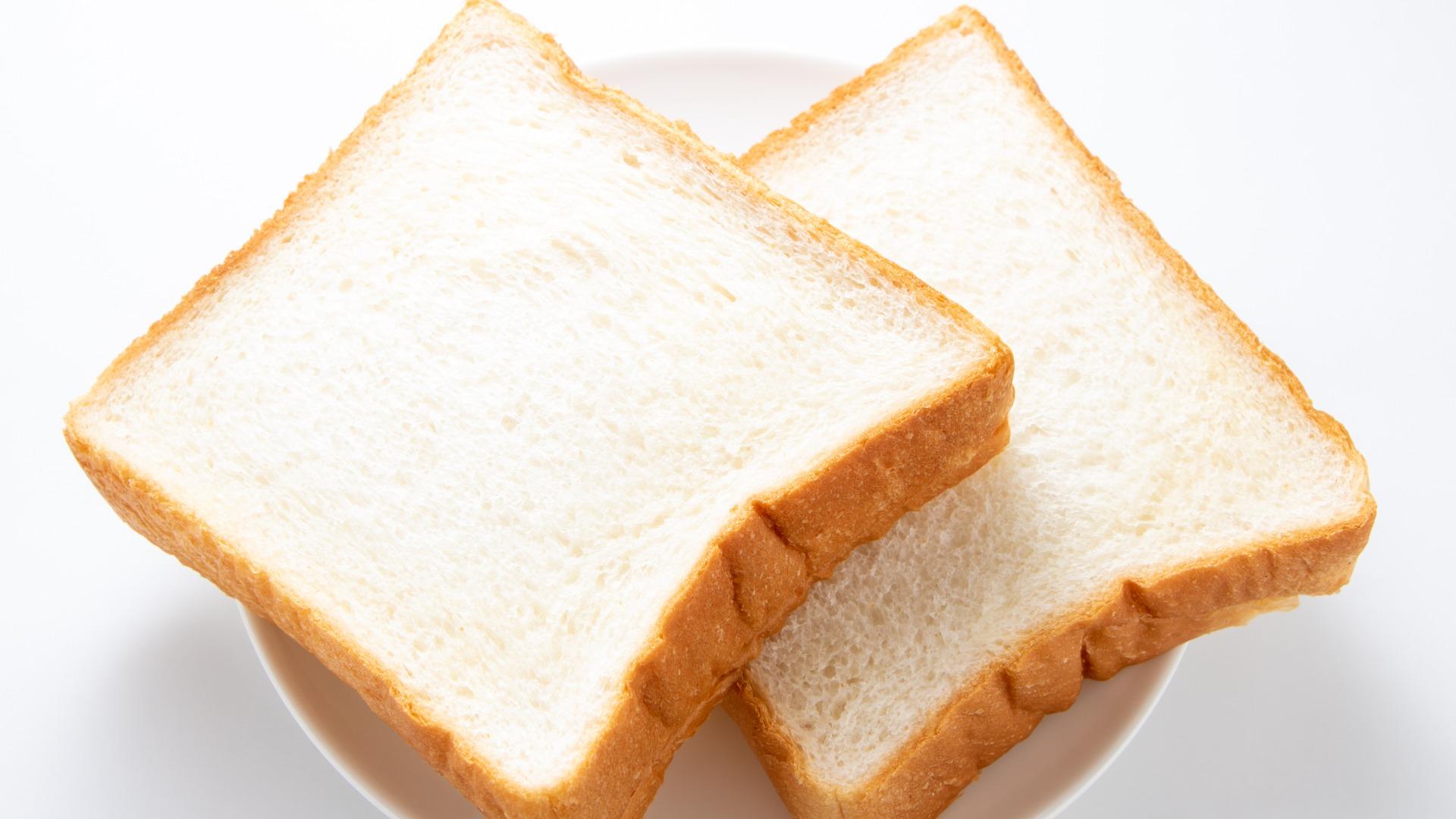企業がソーシャルメディアにかける期待と厳しい現実
総務省が先日発表した「平成25年版情報通信白書」には、国内の情報通信の現状を推し量れる調査結果・資料が多数盛り込まれている。今回はその中から、企業によるソーシャルメディアへの期待と、その現実を指し示すデータを見ていくことにする。
自社で実際にソーシャルメディア(Facebookやmixi、ツイッターやLINE。さらにはYouTubeやブログなど、広義の意味でのものも含む)を利用している企業に対し、その活用の際の見込み効果、そして実際の測定効果を尋ねた結果が次のグラフ。得てして見込みよりも実効果の方が低い結果が出ている。
世情トレンドの情報収集、トレンドを反映した生産調整、そして商品やサービスの情報発信など、ソーシャルメディアに対する期待は高い。しかし実情としてはトレンドの把握とそれを用いた生産調整がもっとも有益で、次いでトレンドの情報収集、さらに顧客個人に合わせた応答情報の発信が続いている。
「ソーシャルメディアは口コミメディアだから、上手く事が運べば爆発的な情報発信と認知度の強化が望める」という期待は多分にある。しかし概してそれ系の期待は裏切られている。今結果でも口コミによる情報拡散、ブランド強化などは低めの値でしかない。また、リスク周りの予防策についても、期待したほどの効果は得られていないように見える。
これら「期待と実態の差異の大きさ」について今白書では「情報の収集及び発信と双方向のコミュニケーションを取れること」を期待したものの「実際に得られた効果については、当初の見込みほど得られていないとの傾向が見られる」と分析している。この解釈に誤りはない。一方で見方を変えると、「企業側の期待が過度」「企業側の方針があいまい」「利用ツールや担当者の能力・権限不足」などの事情も想定できる。
企業がソーシャルメディアを用いた場合、担当者の不用意な行動により、企業イメージを著しく損なってしまうこと(俗にいう「炎上」)、与えられた経営リソースが不足しているのが原因で、半ば放置されたまま運用されている事例すらある。
また「無回答」が「実際の効果」で4割強に達しているのも注目に値する。要は「ソーシャルメディアに色々と期待をして使ってみたが、何の効果が出たのか出なかったのかすら、明確な判断すら出来ない」状態の企業が4割を超えていることになる(余りにもさんさんたる結果で、答えたくないという事例もあるかもしれない)。効果測定の手段すら持ち合わせておらず、希望的観測でゴーサインを出してしまった感が強い。
新しい事業を興す場合、適切な知識と技術を持つ人に、倫理観を守るよう指示した上で、適切な方針のもと、必要な経営リソース・権限を持たるのが、成功のための最低限必要な条件である(もちろんこれら条件がすべて整っていても、成功する保証はない)。
ソーシャルメディアを即効性のある「魔法の道具」と思い違いをしている人は多い。しかしその認識が間違いであることは言うまでもない。
……まるでかつてウェブサイトが「ホームページ」と呼ばれブームになった頃の状況が、繰り返されているようですらある。
■関連記事: