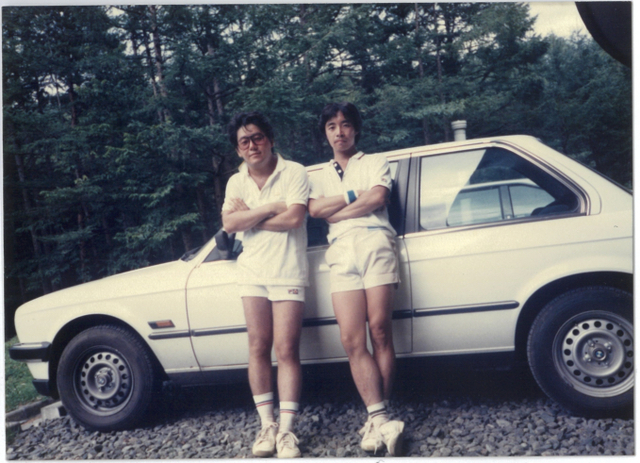「幸せは冷蔵庫の残り物で作る料理にある」――秋元康が語るスター、ヒット、自分
受験勉強に勤しむ暇もなく、大学附属高校から中央大学に内部進学する。大学を中退するころ、サラリーマンの父親の年収を超えていた。 稼いだお金は「あぶく銭」で、仕事はいつまでも続かないと思った。 「専門的な何かを学んだとか、そういうことがないまま、自分の感覚だけで作ってきた。いつまでも通用するわけがないと思っていました。『戦争を知らない子供たち』を書いた作詞家の北山修さんが好きで。ミュージシャンとしても作詞家としてもあれだけ売れている時に、何の未練もなくやめて、大学に戻って、精神科医になられたという生き方に憧れました。父の影響だと思うんですけど、どこかで『ちゃんとした生活』をしないといけない、『ちゃんとした生活』とは何だろうと考えていました」
周りを見れば才能あふれる人がいて、「多くの天才が僕を思考停止にした」と語る。その一人がタモリだ。 「タモリさんの『オールナイトニッポン』で下っ端の構成作家をやってたんです。本来、放送作家の役目は、タモリさんに刺激を与える、ヒントになる企画を考えなきゃいけない。でも、タモリさんが雑談の中でワーッと言うことに全然かなわなかった。何にもお役に立てなくて、自分がいる意味がないと思いました」 コンサートの構成や演出もするようになり、そこで歌われる外国曲に訳詞をつけたことが、作詞業のスタートだった。音楽番組『ザ・ベストテン』などの構成を担当しながら、稲垣潤一の「ドラマティック・レイン」、長渕剛の「GOOD-BYE青春」を皮切りに、小泉今日子の「なんてったってアイドル」、本田美奈子の「1986年のマリリン」、おニャン子クラブの「セーラー服を脱がさないで」、とんねるずの「雨の西麻布」など、ヒット曲を生み出す。
30歳で結婚後、ニューヨークに渡る。イーストリバーを眺めて書いたのが、美空ひばりの「川の流れのように」である。 日本に戻ってからは『とんねるずのみなさんのおかげです』『おしゃれカンケイ』『うたばん』など、多くの番組で構成を担当。セガのゲーム機「ドリームキャスト」の宣伝戦略を担い、「湯川専務」のCMが話題を呼んで、社外取締役に就任したりもした。映画『着信アリ』の企画・原作を手掛け、産経新聞に小説『象の背中』を連載したほか、漫画、ドラマなどのメディアミックスを展開するなど、幅広く活動した。 そして2005年、秋葉原に「AKB 48劇場」をオープン。「会いに行けるアイドル」はやがて社会現象となった。拡大していくAKB 48グループ、坂道シリーズの総合プロデューサーという役割を務めつつ、ほぼ全ての作詞を手掛ける。