「過ごさなきゃよかったと思う時間は、1秒もない」。宮沢りえは人生を振り返って、そう断言する。10代から脚光を浴び、一人の人間として、役者としてもがいてきた。母との死別を経て、今、家族との時間を大切に過ごしている。「娘に対しても、自分の生きざまを、一番の教育として見せられたらいいな」。若き日の混乱や孤独をどう乗り越えたのか。いばらの道を歩む、生き方を語る。(取材・文:塚原沙耶/撮影:岡本隆史/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)
コンプレックスだった容姿が一瞬で強みに
「私、『明けない夜はない』っていう言葉、すごく好きで。本当につらい状況は、ずっとは続かない。そこに影がさしていたら、絶対にその影をつくる光が見えるときがあると思うんです。自分もそういう人生だったし。影が濃ければ濃いほど、光は強い。7回転んだとしても、8回起き上がればいい。ずっと転ばないで生きていくなんて難しいし、私はそんな人生、つまらないと思ってますから」
今年、47歳を迎えた宮沢りえ。11歳でモデルデビューして以来、スポットライトを浴びて生きてきた。光も影もさした年月を「面白い人生」と振り返る。

1973年、東京の練馬区に生まれる。幼少期はいつも男の子に間違えられた。
「幼稚園のときは活発で、髪も短くて。いとこのお兄ちゃんたちについていって、木に登ったりして遊んでいました。リカちゃん人形をもらっても、すぐに洋服を脱がせてお風呂で遊んじゃうような子で」
日本人の母親とオランダ人の父親を持ち、父親の顔を知らずに育つ。母から父のことを聞いていたが、自身のルーツは気にならなかった。
「子どもなので、別れる理由とか具体的なことは聞かなかったけれど、とても素敵なラブストーリーを話してくれていたし、それ以上知ろうとはしなかったんですね。自分に半分流れている血を持つ人に会ってみたいという気持ちは、もっと後になって、30過ぎたぐらいからあったかなと思いますけど」

小学校3年生くらいになると、周囲から容姿の違いでいじめられた。
「いろんな教育があると思いますが、母親は学校に無理やり行かなくていいというスタンスだった。でも、私は行かないという選択はしなかったんですね。いじめられているときは、人を観察していたと思う。なぜそういうことを言うんだろうなとか。卑屈にはならなくて、冷静だった気がする」
「『あいの子』って言われていじめられたことがあって。その言葉を私は知らなかったんです。嫌な響きで言われているのは分かるけど、なんだろうなと。母に聞いたら、『愛される子のことだよ』って。そのとき、『あ、そうなんだ、じゃあみんな私のことがうらやましいんだな』と思った。そうじゃないことに気付いたのは、意外とすぐでしたけど(笑)、でも救おうとしてくれた母親の気持ちを汲んだ気がするし、本当の意味を知ったとき、母親に言わなかったと思う」

コンプレックスだった容姿が、ある日、一瞬で強みに変わった。
「初めてモデルをやったとき、メイクさんが『こんなにきれいな髪の色を見たことがない』って言ってくれたんですね。他人から褒めてもらえたことが、すっごくうれしくて。今まで生きてきたテリトリーから、こう、フワッて広がったんですよね。視野というか、考え方が。そのときのことを、今でも思い出します。一番のコンプレックスだったものが、強みになった瞬間。仕事をし始めたら、不思議といじめられることもなくなりました」

11歳、初めてモデルをしたときの様子
『Santa Fe』は今見ても美しい作品
雑誌の表紙モデルを務め、CMでも注目を集めたが、もともと目指すものがあったわけではなかった。
「子どもの頃、これといった夢はなかったんです。ケーキ屋さんに行って優しいお姉さんがいると、ケーキ屋さんになりたいし、幼稚園の先生が優しいと、幼稚園の先生になりたいし。近所に住む人がエージェントのお仕事をされていて何度かお誘いをいただいたんですけど、やりたい気持ちにはならなかった。母親は私を尊重してくれて、『娘がやりたいと言い出したらやります』と断ってたんですね」
「ただその頃、資生堂のCMにモデルの山口小夜子さんが起用されていて。そのCMに、私はすごく夢を感じた。モデルさんになったら、ああいうことができるのかな、というくらいの感覚で始めたんだと思います」

「三井のリハウス」のCMで「白鳥麗子」役を務めたことが、女優の道へつながっていく。1988年、『ぼくらの七日間戦争』で映画に初出演した。
「『三井のリハウス』は『今度、朝日ヶ丘にリハウスしてきました……』っていう、初めてせりふがある仕事だったんです。そのCMを見た方が映画をオファーしてくださったんですけど、正直、自分の声もモコモコしていて嫌いだったし、お芝居は初めてだし……。主要メンバーで合宿して、初めてエチュードをやったんです。『ここに海があります、砂浜に座っています』と言われても、『海なんかないし!』って。撮影中も緊張していて、2行以上のせりふがあるとやりたくない。苦手意識ですね。自分に役者さんはできないと、ずっと思っていました」
自己評価に反して、この作品で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞する。89年、小室哲哉の楽曲提供で歌手デビューを果たすと、翌年にNHK紅白歌合戦にも出場。そして91年には、写真集『Santa Fe』を刊行する。米国ニューメキシコ州のサンタフェで、篠山紀信がヌードを撮影。新聞にもヌード写真の全面広告が展開された。
「『Santa Fe』を出したときは、仕事で海外にいたんです。帰ってきたら空港の人に『こんなに人が集まったのは、マイケル・ジャクソン以来です』って言われたんですけど、『へえ……』と思って。意外と、『そうなんだ』っていう感じでしたよ」

騒動をよそに、本人は冷静だった。
「自分にとって記念になる、大事だと思える作品がつくれたという気持ちでした。エイトバイテンというカメラで撮ったんですね。写真館のおじさんみたいに幕をかぶって、一枚一枚フィルムを入れて撮るんです。当時、外国の雑誌に、自分の憧れるトップモデルのヌードが載っていたりして、子どもながらにきれいだなと思っていました。その感覚だったんですよね。毎日、撮った写真をホテルの部屋に並べていって。それを見て、『あ、素敵な写真集になるだろうな』って素直に思いました」
「正直最初は、ヌードを撮ることに対する抵抗はありました。でも、サンタフェという土地や、気心知れたスタッフ、自分が美しいと感じていたヌード写真への憧れが、ものすごくタイミングよく合わさったんだと思う。もちろん恥ずかしくないわけでは全くないけど、撮った写真を見て、心がほどけていったような気がします」

『Santa Fe』は150万部を超えるベストセラーになった。
「私は今見ても、すごく美しい作品だなと思う。最後に開いたのは、いつだったか忘れたけれど。18歳のときに撮ってもらっている最中に感じていた気持ちと、今の気持ちは、そんなに変わらない」

(デザイン:REVEL46)
過熱する報道に反論しなかった理由は
次々と旋風を巻き起こす宮沢りえのマネジャーは、2014年に逝去した母親だった。宮沢は母のことを「もっとも敬愛する人」だと語る。なぜ母は、既存の芸能事務所に託すのではなく、自ら娘をプロデュースしたのか。
「危険だと思ったんじゃないんですか(笑)。まあ、責任じゃないですかね。責任じゃないか、うーん……。決して、好んでやっていたとは思えない。『娘がやりたいと言うから助けなきゃ』という気持ちが、根底にあった人だと思います」
「挨拶ができない」「お礼が言えない」。母からはよく叱られた。
「ブーブー言うと、『だったらやめればいい』ってすぐ言われました。『眠い』とか『寒い』とか言ったりすると、『いつやめてもいいよ』って。その言葉が怖かったですね。学校を卒業して間もなく華やかな世界に入って、人気が出れば、みんながチヤホヤしてくれる――チヤホヤっていう言葉はよくないけど、あえて使います。自分を見失わないでいられる人なんて、いないと思うぐらいの世界。見失わないように母が導いてくれていた。人間として、いろんなことを教えてもらった気がします」

宮沢に注目が集まるほど、「りえママ」にも世間の関心は及んだ。婚約解消などプライベートでも話題を呼ぶと、母娘への報道は過熱した。
「自分のことを言われるのも嫌だったけど、母親のことを言われるのが、とっても嫌だった。それも嘘ばっかり。母親は私と比べものにならないぐらい、優しくて、穏やかな人だった。一般人ですし、この世界で娘の価値観をきちんと保ちながら、人間として普通に生きていくのは、生半可なエネルギーじゃなかったと思う。本当に大変な思いをさせたなと思います」
「相手への伝え方が、芸能界のルールに沿っていないこともあったと思うんですね。そういうことが脚色されて書かれるのは、本当に嫌だった。母親を守りたいという気持ちにもなりましたし、私は言葉で反論したかった。でも母親は『絶対に反論はしないほうがいい。いつか分かるときが来るから。それに対して抵抗するのは、いい仕事をすることだと思う』って。『えー』って思ったけど、母親も意思が固かったし、信じようって。反論はせずに、ひたすら――ひたすらという言葉がすごい合ってると思う」
「いい監督や共演者の方に出会えて、私が作品の中で認めてもらうことが増えていったら、あんなに悪魔だって言われていた人が、いいことを書かれてたりして。私に対しても賛同してくれる傾向になってきたとき、母親が言っていたことが、10年、20年単位だけど、理解できた気がします」

20代前半、宮沢は母とともに米国ロサンゼルスへ移住。しばらくの間、仕事を離れて過ごす。やがて米国と日本を行き来しながら作品への出演を重ね、帰国して一人暮らしを始めた。2001年、香港映画『華の愛〜遊園驚夢〜』でモスクワ国際映画祭最優秀女優賞を受賞。『たそがれ清兵衛』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞したころには、30歳を迎えていた。
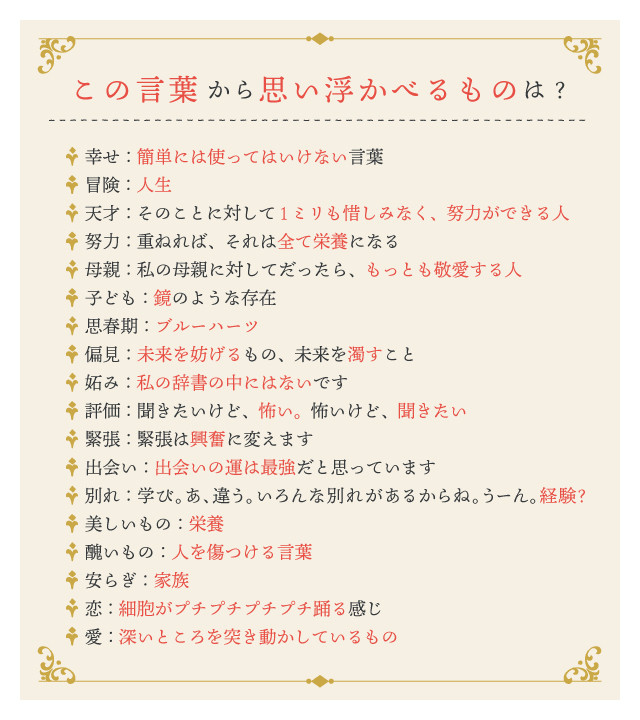
(デザイン:REVEL46)
言葉にできないほど混乱した長い思春期
10代から20代にかけての日々を「長い思春期」と語る。
「今、だいぶ落ち着きましたけど、ものすごい多感だったと思うんですね。説明のできないエネルギー、自分の中からあふれる感情、そのコントロールがうまくいっていなかった。だからこそ、いい部分も悪い部分も激しかった。そのエネルギーが、ふとした瞬間に作品に向かったり、そうじゃないこともあったり。歯車がやっと合い始めたのは、20代後半なのかもしれない」
痛みを感じているとき、相談する人はいたのだろうか。
「相談するほど、具体的な言葉にできなかったんじゃないかな。説明のつく感情だったら、そんなに混乱してなかったと思う。怒りっていうような一つの感情ではなくて、もっとカラフル。思春期のときの気持ちって、今でも説明はつかない。ちょっと長い思春期だった気がするんだけど――怒りもあったし、理不尽も感じていたと思うし、抵抗も不安もあっただろうし。孤独でもあった。周りに人がいないとかじゃなくて、自分の心の中は、相手と100%共有できるものじゃないっていう孤独さ」
感情やエネルギーを作品にぶつけることもあれば、「ブルーハーツのコンサートに行ったり、キャンバスにパンチするぐらいの気持ちで絵を描いたり」。そういう時間をかみしめた。
「ああいう時期がなかった今の自分はどうなってるかなと思うと、あってよかったなって思います。今、人の痛みやつらさ、混乱を理解しようとする気持ちがあるのは、そういう自分がいたからだと思うんですよね。だから本当に、過ごさなきゃよかったと思う時間は、1秒もない」

30代は、どっぷりと演劇に向き合った。野田秀樹や蜷川幸雄など、演劇人との大きな出会いを通して、舞台役者として開眼していく。
40歳を迎えた頃、舞台『おのれナポレオン』で急遽代役を依頼される。わずか2日の稽古で膨大なせりふの役を演じきり、終演後は5分間におよぶスタンディングオベーション。かつて「2行以上のせりふ」に戸惑った少女が、遠くまでたどり着いた。役者としての歩みを、「ゆっくり坂を上がるように、今があるっていう感じがする」と宮沢は言う。
「積み重ねてきた(キャリアの)長さと、自分の考えている実力に、ギャップがあるときがあるんですね。みんなが『きっとできるだろう』と思ってくださった役を、『こんなに難しい役はできない』と思います。そのギャップといつも闘っている感じ。とにかく役を誰よりも愛して、理解する努力をします。寝ててもせりふが言えるぐらい、体に落とし込む。努力って、それぐらいしかしてないかな。魔法はないの」
「蜷川幸雄さんが、ある役者さんに対して『自分をもっと疑いなさい』とおっしゃったんですね。自分に向けられた言葉ではなかったけど、ものすごく響いて。ものをつくるうえで、自分を疑うことをやめたら終わり。いくら拍手をしてもらって、褒めてもらっても、もっとできたんじゃないかという心がいつもある。手放しで、『ああ、幸せ』っていうふうにはならないなあ」

(デザイン:REVEL46)
母を亡くした喪失感とカーテンコール
2014年9月23日、舞台『火のようにさみしい姉がいて』に出演していたとき、母が肝腫瘍で他界する。
「具合が悪かったので、覚悟はしていたんですけど、でも、そんな覚悟は覚悟ではなかったぐらい、想像もつかない喪失感がありました。病院に行きたくないという彼女の意思があったので、自宅で療養していたんです。自宅で朝亡くなって、その後、喪主としていろんなことを決めなければならなかった」
共演者には明かさず、プロデューサーだけに伝えて、いつも通り舞台に立った。

「とにかくその日の芝居をやり遂げなきゃいけないという気持ちで。できなければ、それは母親が一番悲しむことだし。踏ん張って、踏ん張って、2回公演をやって。プロデューサーの方の計らいで、一番前の席に椅子が置いてあったんです。亡くなった母が見に来られるようにと、用意してくださったんですね。2回目のカーテンコールで、初めてその席が目に入った。今日の芝居が無事にできたという気持ち、母親を亡くしたという気持ち、いろんな気持ちが覆いかぶさって、ものすごい涙が出ちゃった」
「千秋楽でもないのに涙が出るなんておかしいから、絶対に共演者の人にバレちゃいけないと思って、涙がこぼれそうになると、お辞儀して、涙を下に落として。顔を上げて、また涙が出そうになると、顔を下げて。とにかくお辞儀しました、バレないように」
舞台に立っていたときの気持ちを尋ねると、記憶をたぐり寄せ、目を見開いた。
「忘れてました。大竹しのぶさんと段田安則さんと共演していたんですけど、ものすごく緊張感のある芝居で。尊敬する、手ごわい二人。その人たちと舞台に立てている、負けないように芝居をしなきゃいけないっていう気持ちが強かったですね。芝居中、母親のことを思い出すことはなかったです」

蜷川幸雄演出の舞台『火のようにさみしい姉がいて』。左から、宮沢、段田安則、大竹しのぶ(撮影:谷古宇正彦)
その翌月、7年ぶりに主演した映画『紙の月』で、東京国際映画祭の最優秀女優賞を受賞。「出会いの運は最強」と断言する宮沢は、以降も人や作品との出会いを積み重ねている。出会いを引き寄せるコツは、「好奇心があって素直であること」。ひとたび巡り合えば、崖から飛び降りるような潔さで挑む。
「守るものはないですね。いつも綱渡りのような感じです。このぐらいのことならできるなと思ってやるのは、一番つまらない。できないかもしれないけど、やってやる。死ぬまでそうでありたい。限界というラインを自分でつくると、思いもよらないことなんて起こらない。今、47になりました。死というものは、必ず私にも訪れる。その時期はいつなのか分からないけど、そのときまで、生きるということをまっとうしたい」
11歳になる娘を育て、2018年には再婚した。家族との時間を大切に過ごしている。
「一番の軸は、人間であって、女であって、母親であって、妻であるという時間。それが自分の中で一番満ち満ちとしている時間だなと思います。幸せは家族と過ごす時間の中で感じることが多いかもしれないですね」
「死ぬときになって、人間として満たされていたい。そのときに役者をやっているかどうか分からないけど、まだ自分の中に、これをやってみたいということがいくつかあるから、挑戦もしていきたいし。家族を守りながら、家族を大切に生きていきたいし」

今年はコロナ禍で、稽古を重ねた舞台が中止になった。
「自分にとって大切なものはなんだろうということを、すごく考えた一年でした。これまでは本当に、駆け抜けてきた人生だった。もう少し人間として豊かさを持ちたいし、知性を育みたい。役者として人に影響を与えることももちろん大事にしたいけど、自分の生き方を通して、皆さんにメッセージを送れたらいいなと思う。娘に対しても、自分の生きざまを、一番の教育として見せられたらいいな」
最後に、こう尋ねた。「生まれ変わったら、もう一度、宮沢りえに生まれたいですか」
「そうですね。うん。面白い人生ですから。もう1回、宮沢りえ、やってみたいです。いいことも悪いことも、ポジティブなことも、ネガティブなことも、光も影も含めて、もう一度やりたい」


「情緒不安定の人の絵みたいになってますけど、まあこれが私ですから。椅子に描くなんて怒られることをやっているという、喜びがありますね」

「絵を描くときは直感です。下書きはしたことないですね。怒っているときもあるし、すっごくワクワクしているときもあるし。カラフルな感情で描いています。自分の好きなときに始めて、自分の好きなときに終われるという仕事は、なかなか他にありません。そういう意味では、絵はとっても自由だなと思います」
宮沢りえ(みやざわ・りえ)
1973年、東京都生まれ。近年では、2015年に『紙の月』、2017年に『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。2018年、舞台『足跡姫〜時代錯誤冬幽霊』『クヒオ大佐の妻』『ワーニャ伯父さん』で読売演劇大賞の大賞・最優秀女優賞を受賞。映画『日本独立』が公開中。
【RED Chair】
常識を疑い、固定観念を覆す人たちがいます。自らの挑戦によって新しい時代を切り開く先駆者たちが座るのが「RED Chair」。各界のトップランナーたちの生き方に迫ります。
最終更新日時:2020年12月23日14:58











