「僕が死んだ後は、すっとこどっこいな面白いドラマができるんじゃないかと思いますね」。国際的に活躍する現代美術家、村上隆(58)。作品が約16億円で落札されるなど、アートマーケットにおいても話題を呼んできた。村上はこの夏、自身が代表を務める会社が倒産危機に直面していることを明かした。世界を舞台にどう道を切り開いてきたのか、そして現在進行形でもがき続ける日々について聞く。(取材・文:塚原沙耶/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)
倒産危機で「いなくなりたい」
この7月、村上隆は、自身が率いるアートカンパニー「カイカイキキ」の倒産危機をインスタグラムで明らかにした。監督を務める映画『めめめのくらげ2 マハーシャンク』に莫大な予算を費やしたことが要因だ。結局、同作の製作と公開を断念する。
「2月から4月がやばかったですね。毎日『この世からいなくなりたい、死にたい』みたいな、そんな感じでした。朝3時半に起きちゃって、ツイッターで『起きた』って書くと『おはよう』って誰かに言われて『あ、ありがとう』とかリアクションして、便所に行ってコーヒー飲んで。いつの間にか気分が上がってきたりとか、われながらお気楽な人間だなあと思いましたけどね」

危機に直面するのは、今に始まったことではないという。
「僕の会社には財務の人間がいないんです。会社がそのレベルに達していないんだなあ、なんでそういう人材来てくんないのかなあ……と自暴自棄になります。だから経営状態がよく分からないんですね。ある日経理から『資金がショートしそう。十何億足りない』って言われて、『えー』みたいな。もうコメディーです。それが倒産危機で、で、そこから何とかしていくわけです」
「まあそういう感じで15年くらい性懲りもなくやり続けているのがうちなんで。ずーっとお金が足りないので、売るための作品をつくるみたいな。そんなドタバタなんで、58歳の今でも現役なのかなあ。僕が死んだ後は、すっとこどっこいな面白いドラマができるんじゃないかと思いますね。当人は死にたいくらいつらいですけれども」

苦しい時は浪人時代の夢を見る
1962年、東京・板橋区に生まれた。
「ウチの前に長屋があって、七輪で魚焼いてるおばちゃんがだーって並んでました。夕方になると、カーボン工場から真っ黒なおじさんたちがどどどどって出てきたり。で、若い頃の母親にちょっかい出してきたりして。『巨人の星』で星飛雄馬の暮らしが貧乏一家として描かれてるんですけど、『これ、うちやん。周りにもっと貧乏な人もいるし』みたいな。両親がつらそうでしたからね。夫婦げんかもよくしてたし、耳を傾けるとお金の話だし」
少年時代の夢は漫画家だった。夢中になったのはギャグ漫画で、『ハレンチ学園』『トイレット博士』『がきデカ』『マカロニほうれん荘』、それから『天才バカボン』。『ゲゲゲの鬼太郎』の妖怪も好きで、よく模写をした。小学校6年生の時、『あしたのジョー』の最終巻を親に買ってもらい、ぼろぼろになるまで読んだことが記憶に色濃く残っている。
「生まれて初めて本を読んで泣いたんですよね。お話、物語に没入して、漫画はただゲラゲラ笑う楽しいものではなく、感激もするものだと知りました」

やがて自分には物語をつくる能力がないと悟り、漫画家をあきらめる。アニメーターなど、絵だけを描く仕事に就こうと思った。絵もスキルが高くないことに直面するが、結果的に美術大学を志す。
「高校3年の1学期の成績が、1学年550人中、530番以下だったんです。それでも大学に行きたいと思った。行かないとおまんま食い上げるって親に刷り込まれてたんで。おやじは高卒で、おふくろは中卒。それで苦労してるって言ってたんで。大学に行きたいって進路指導の時に言ったら、先生方に鼻で笑われて」
「駅に代々木ゼミナールの美術予備校のポスターが貼ってあったんです。母親に『普通の大学には合格できそうもないので、絵の勉強でもさせてくれ。バカでも行けるかもしれんので』って言ったら怒られて。でも、親もわらにもすがる気持ちなので、その週末に代々木ゼミナールへ連れていってもらいました」
高校卒業後、2浪して東京藝術大学に入学する。
「お金の事情で行けるのは国立しかなかったので、仕方なく藝大だけ受けていました。合格した時が、人生で一番うれしかった瞬間かもしれないですね。浪人中の2年が、世間に自分の立つ場所がなくて非常につらかった。苦しい時、会社がつぶれそうになった時とか、必ず浪人時代の夢を見ます。でもあの時よりはつらくない」

頭を殴られたような衝撃を受けた日
藝大では、受験の時に一番簡単そうだと思い、日本画を専攻した。
「日本画科は、油画科やデザイン科からバカにされてるんです。正直、内容のない学科でした。『西欧列強に文化面から対抗すべし』と岡倉天心が創立した東京美術学校。その天心の肝いりで『日本の絵画を作るべし』と生まれたのが日本画なのですが、僕が在籍した時の先生たちの間では金儲けと権威主義が横行し、さらにそれがドグマ化して、メディアを巻き込んだ内ゲバのような状況になっていた」
悶々と過ごしていたが、20代半ば、現代美術家の大竹伸朗に衝撃を受け、方向転換する。
「展覧会を見て、頭を殴られたような状態になりました。コールタールをべちゃべちゃ塗ったり、絵の中から音が出てたり、見たことのない文脈の作品が所狭しと並んでいて。自分は1枚の日本画を描くのに3カ月ぐらいかかったんです。ここにある大竹さんの全作品はたぶん1年以内に仕上がっているだろうから、どういうこっちゃと思って。僕のペースでつくると、20年ぐらいかかるなと」

藝大時代の村上。1981年頃(写真提供:カイカイキキ)
それまで現代美術には関心がないどころか、むしろ嫌っていた。
「現代美術が好きな藝大生って、ややこしいことばっかり言ってるわりに、何にもやらない人がけっこういて。頭でっかちの人間のたまり場だと思ったんですね。だけど、大竹さんの作品は『とにかく俺は絵が描きたいんだ!』という感じで、ややこしくなくてよかった。これだったら、参加すると楽しいかもしれないと思ったんです」
「展覧会を見て3日間ぐらい、ほんとに何もできなくて。その後、絵の具とキャンバスを買って、絵の具をべちゃべちゃ塗って喜んでました。でも何を描けるわけでもなく。これはやばいなと思って、友達に聞いて本を読んだりして、現代美術の勉強を始めました。ちんぷんかんぷんな世界に2年ぐらい浸り、だんだん理解していってデビューしました」
1990年代初頭、個展で作品を発表するようになる。

1991年に発表した《ポリリズム》。合成樹脂の塊に、タミヤのプラモデルの兵隊が乗っている(写真提供:カイカイキキ)
「インスタントに現代美術でござい、と作品をつくって展示して売れたりして。そういうのを見て、友達に絶交宣言されたり、日本の美術評論家から最低な評価を受けたり。でも作品はボンボン売れたんですよね。貧乏からの脱出が頭にあるので、売るのは必須でした」
「評論家が『村上は日本では受けているようだが、海外ではからっきしだから価値などない』みたいなことを専門誌に書くので、僕も美術関係の出版社とかにファクスを送り付けてました。評論家がどんだけバカか、バカな僕がバカバカしい文章で書いて。美術評論の雑誌は喜んで、コラムで掲載してくれたりして、作品もますます売れた。のちに海外で成功したら評論家たちは絶句してザマアミロでした」
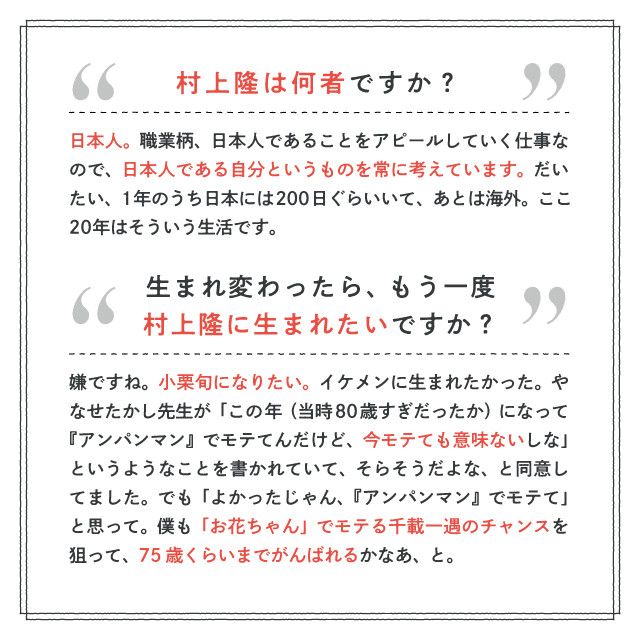
勝算20%。アメリカで認められるまで
32歳の時、ロックフェラー財団のアジアン・カルチュラル・カウンシル助成金プログラムでニューヨークに留学する。
「西武新宿線の野方駅に両親が見送りに来てくれて。『銀河鉄道999』の鉄郎とメーテルみたいに『行ってきます』と。西武新宿線内で泣いてました。バカみたいですね。不安の塊でした。行ってからは英語のしゃべれなさ加減が半端じゃなくて、パン1個買うこともできませんでした」
ホームシックになりながらも、活動の場を開拓していく。

ニューヨーク留学時代(写真提供:カイカイキキ)
「通訳と弁護士を雇って、2年目ぐらいにギャラリーに作品を持ち込めるようになりました。でも通訳の人はアートの世界を知らないから、うまく伝えられない。自力で英語をしゃべるしかなくて、カタコト交信を始めました。ニューヨークの生活は、浪人と同じぐらいつらかったですね。ニューヨークでどれだけ日本人の立ち位置が悪いか、暮らすまで知らなかった。日本人ってプライドが高いんですよ。日本語を操っていると、それが世界だと思っているけど、ほとんどの国で知られていない言語。そういう事実を僕は知らなかった」
「当時、西洋のアートの世界で、アジア人の居場所なんかなかった。日本人アーティストがニューヨークに行くと、4軍ぐらいから上がっていかないとダメ。知り合いや友達は誰もそんなことを教えてくれなくて、自力でデビューメソッドを探したことが成功のきっかけでしたね。運がよかったのは、ワールド・アートが流行り始めて、欧米以外のアートを求めるムーブメントが始まったことでした。文脈をうまくコーディネートして、ニューヨークデビューしたんです」
1996年、34歳のときに等身大フィギュア《Ko²ちゃん(プロジェクトKo²)》を発表。この作品は2003年に6800万円で落札されることになる。

《Ko²ちゃん(プロジェクトKo²)》1996年(撮影:Kozo Takayama)
「あっ、とひらめいたんですよ。ギリシャ彫刻からずっと、美の形式は出自が西洋ですが、アニメのフィギュアには西洋がまるっきり入っていない。ラムちゃんを立体化したいとか、セクシュアルなリビドーに忠実で。これを西洋の芸術のフォーマットに乗せたら、ものすごくショッキングだとひらめいたんです。ただ、日本のフィギュアのままでは、セクシュアル度数が強すぎて。だから、セクシュアリティーを薄めたりしながらつくると、オタク的には『生ぬるい。なんじゃこれ!』の作品になっちゃうんですよね。でもアート界では『ストライク!』となりました」
「あの頃、誰もやってなかった。エポックメイキングであることが一番大事なので。とはいえ、巨乳の女の子が母乳で縄跳びをしている等身大フィギュアの《ヒロポン》をつくっている時は、自分は頭がおかしくなったんじゃないかって、心の中で苦笑したりして」

前例のないものをつくるなかで、不安になったり躊躇したりすることはないのか。
「勝算は20%くらい。残り80%はうまくいかないだろうと思ってるんで。自分があきらめるまで何度もやって、それでダメだったら敗退すればいい。アメリカで仕事をするにあたっては、フロンティアスピリットに尽きます。それをやり続けていると助けてくれる人が出てくる」
「自分の能力は、過去の記憶が抜け落ちていくこと。だから嫌な記憶がないんです。くり返し失敗しても、何かをやり遂げるまで耐えられる。記憶障害による、客観的に見ると根気強く見えるような作業が、自分の特性かなと思います」

インタビューは「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」の展示会場で行った。同展は2021年1月3日まで森美術館で開催
一方で、「自分の才能には全く自信がない」と語る。
「宮崎駿さんが『未来少年コナン』を初監督した時、インタビューで自分は才能がないと言っていました。なぜなら過去の遺産を真似ることしかできていないと。僕らにとってはすごく面白かったけど、本人が言うんだからそうなのかな、と思いました」
「ただ、ある時クリエイターは化けるんですよね。『風の谷のナウシカ』のアニメーションをつくってヒットした時、変身して巨匠になっていった。自分は、オークションですごい値段が出た時に化けたのかなあ。ただ、自分をよく知っているのは自分自身です。社会的な立ち位置は化けても、自分は別に変わっていない。才能の有無の評価軸は自分で考える」
日本でプレーしても意味がない

フランスのヴェルサイユ宮殿で開催された「MURAKAMI VERSAILLES」。2010年(撮影:Cedric Delsaux)
村上は欧米や中国を中心に活動し、作品の多くが海外の美術館やコレクターの手にわたっている。
2006年、「リトルボーイ」展で全米批評家連盟によるベスト展覧会賞を受賞。2008年には等身大フィギュア《マイ・ロンサム・カウボーイ》が約16億円で落札された。回顧展「©MURAKAMI」を世界各地で開催するほか、ルイ・ヴィトンや、カニエ・ウェストなどのアーティストとのコラボレーションでも注目される。
「日本では全く売れなくなりました、高くなりすぎちゃって。でも、別に日本のアートリーグでプレーしても評価が上がることはないし。大リーグでプレーして、今年も年俸もらえるかな、という感じでやってきたので。金を外国から持ってきて、日本に納税してるわけです。日本人に買ってもらうことは、98%ないですね」

ニューヨークのジャパン・ソサエティーで開催された「リトルボーイ」。2005年(撮影:Sheldan Collins)

2019年、ビリー・アイリッシュのMVをプロデュース。「アーティストやクリエイターとコラボすると、その人の頭の中が自分の頭の中と直結する瞬間がある。非常に深いエクスタシーに浸れるので楽しいですね」。Billie Eilish - you should see me in a crown (Official Video By Takashi Murakami) © 2019 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd./The Darkroom/Interscope Records. All rights reserved.
自身の作品が「売れる」理由をどう捉えているのか。
「時代の風潮とか、よーく目を凝らすようにして、自分から何が発信可能かを探ります。例えばSpotifyでアメリカの流行歌をたくさん聞いて、人心に寄り添って、『今、何を欲してるのかな』『じゃあ自分は何ができるのかな』と考えれば、誰かに伝わるメッセージをつくれると思います」
コロナ禍で作品制作も変化した。世の中のムードを感じとり、素早く切り替える。
「展覧会に行くのは難しくなっていたので、スマホで買えるような、でもこだわりのある版画とかがマッチしてるんじゃないかなと思って、版画工房をつくりました。心の時代になることは確実だと思って、テーマはシリアスにし始めています。人間はつらい状況になればなるほど芸術を欲するというのは、歴史を振り返っても明らかです」
「大事なのは、今考えていることを正直に表現すること。純度が高いほうがいいんです。うそが混じることなく、美の争点を浮き彫りにしていく。でも正直すぎる表現ばかりだと自我が壊れるので、長く制作するなかでは、時流と自分の距離にいつも気を付けて、継続し続けられる塩梅を大事に考えています」

STARS展では「阿吽(あうん)の像」を出展。「当初は他の作品を出す予定だったんですけど、コロナ禍が深刻になったので急遽変えました。奈良の大仏も疫病がはやった頃にできた。大仏の門前にある阿吽の像も恐ろしい顔で、病気を怖がらせて退散させようとしている。それをやろうと思い、鬼の像を持ってきました」
『めめめのくらげ2』の製作時は「自我が壊れていた」と振り返る。なぜ映画にこだわるのか。
「映像表現は、世界を1個まるごとつくれる。うそ八百の世界をつくれた瞬間、絵を描くよりもはるかに大きなカタルシスがある。絵は職業というか、畳屋が畳を縫うみたいな感じで。『すばらしい畳ですね』って言われることは少ない。いろんな要素を組み上げて一つの世界にすることが、人々に訴求可能なのかなあと。それが映画表現だと思っているのです」
「でも映画にはいろんな芸術を指揮する才能が必要で、僕にはそれが備わっていませんでした。製作しているとうれしくなって、あれもこれもぶち込みすぎて、何を言ってるのかさっぱり分かんなくなる。芸術に憧れてる人が絵を描くと、ぐちゃぐちゃなものができちゃったりするのと同じ流れです。プロフェッショナルとしての整理整頓能力が身に付くとイイのかもですが、いつちゃんとした手応えを得られるのか分からない。でもあきらめきれない。やり続けるしかありません」

『めめめのくらげ2 マハーシャンク』の一場面。「子どもたちに『人間は自然災害に翻弄される無力な存在だ』というシニカルなメッセージを楽しく伝えたかった。子どもの頃に見た『ウルトラマン』『ウルトラセブン』で、そういうメッセージを受け取った気がしたんです」(写真提供:カイカイキキ)
生前は雑音。評価は死後まで分からない
そもそも作品の評価というものについて、どう考えているのだろう。
「挑戦する軍資金が入らないと困るので、今現在の評価は必要ではありますが、自分が生きている間の評価、値段ともに高くても仕方がない。僕らの仕事は、アーティスト自身の死後が一番大事で、生きている間は大して意味がないんです。生前はこうやってインタビューを受けたりして、人が興味を持つきっかけをつくれますけど、死ぬと能動的な姿勢が取れない。にもかかわらず作品が残るなら、それは作品の純粋な強さと関連性があるわけです。作家の生前は雑音に惑わされる。芸術の世界における本質的な評価は、作家が死ぬまで絶対に真価を問うことができない」
「作品の全てに時限装置を組み込んでいます。自分がつくったシナリオが死後に起動するかどうかは、時限装置の設計図の実力次第。つくりきった後は、野となれ山となれ、です」

今年、58歳を迎えた。
「動物が生殖する前の、鳥がパタパタ恋のダンスを踊るような時が一番美しい。人間も生物的に美しいそういう時期は一瞬しかない。その瞬間を芸術として残そうとしたのが裸像を描くことなんだなと、最近つくづく実感するんです。若い頃は、裸の絵って何やろうなと思ってたんですけど」
「自分が老いてきて、若い頃と相対化すると、絶望的に何もいいことがない。老いはやっぱり醜怪なものだと思います。でも、それを知り、美との相対化をする時に芸術は生まれたりするんです」
アーティストとして最終的に目指す像は明確にある。ゴールを思い描いたのは10年ほど前、大作《五百羅漢図》を描いていた頃だという。

2015年、森美術館で開催された「村上隆の五百羅漢図展」。五百羅漢とは釈迦の教えを広めた500人の聖人のこと。全長100mにおよぶこの作品は、世界の絵画史上最大級といわれる。東日本大震災後に支援を表明したカタールへの感謝を込めて、2012年にドーハで発表した(撮影:Kozo Takayama)
「白隠和尚が死ぬ直前に描いた禅画みたいなものを描けるようになりたい。西洋では、マティスやモネなど、最晩年の作品がすばらしい芸術家は、枯れた瞬間が自由そのものなんです。醜怪な生き物が残す枯れ果てた痕跡が、生きている人間を癒やすのも真実。自分をそういうコンディションに追い込みたいと思っています」
アートにできることとは、何だろうか。
「時間を旅するエンタメの提供ですね。ガウディとか、奈良の大仏や仁王、モーツァルトやショパンも時間を旅することができる。人間という動物の非論理的な活動分野がなぜあるかといえば、脳みそが発達しすぎて、エンタメが必要不可欠になったから。そのエンタメの究極が芸術だと思うんです。時を行ったり来たりするにも知識が必要で、知識を自分にインストールすれば楽しめるし、しないとそんなに楽しめない。時間の中を、未来に向かって旅していく。それが芸術の本質かと思います」


「RED Chair」では椅子に揮毫(きごう)してもらう。「『芸美革新』は北大路魯山人がよく書いた言葉です。芸術の美は、革命を起こす新しいムーブメントでなければいけない。僕、魯山人がほんとに好きで。口が悪くて、人に迷惑をかけ続けたといわれているんですけど、日本の美を究極に理解していた人。僕も日本の美を常に心の中に持って生きていきたいので、魯山人の言葉を胸に抱いております」
村上 隆(むらかみ・たかし)
1962年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。日本画において初の博士号を取得。制作工房、ギャラリー等を含めたアートの総合会社である有限会社カイカイキキ代表。オタクカルチャーやキャラクターと日本の美術史を接続し、「スーパーフラット」という概念を発明。「スーパーフラット三部作」と称される3展の最終章「リトルボーイ」展(2005年、ニューヨーク)は、全米批評家連盟によるベスト展覧会賞を受賞した。
©Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.
【RED Chair】
常識を疑い、固定観念を覆す人たちがいます。自らの挑戦によって新しい時代を切り開く先駆者たちが座るのが「RED Chair」。各界のトップランナーたちの生き方に迫ります。











