芸術の秋。各地で多くの美術展が開かれている。名画を前にしてこう思ったことはないだろうか。「この絵、いったいいくらなんだろう」。今年5月、日本人実業家がジャン=ミシェル・バスキアの絵画を約123億円で落札したことがニュースになった。その買い物は高いのか安いのか。アートに携わる4人にそれぞれの立場から「アートの価値」を語ってもらった。
(ライター・長瀬千雅/Yahoo!ニュース 特集編集部)
アートの値段は労働の対価ではない
ミヅマアートギャラリーディレクター 三潴末雄さん
コレクターというよりパトロンでありたい
ストライプインターナショナル社長、石川文化振興財団理事長 石川康晴さん
「バブル期のトラウマ」を脱して新しい時代に
AKI ISHIZAKA代表、元サザビーズジャパン社長 石坂泰章さん
「歴史に残るかどうか」が判断基準
東京国立近代美術館主任研究員・保坂健二朗さん
アートの値段は労働の対価ではない
ミヅマアートギャラリーディレクター 三潴末雄さん
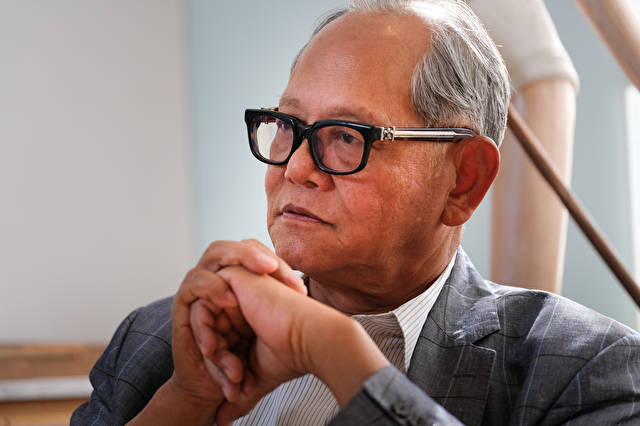
みづま・すえお/1946年東京都生まれ。1980年代からギャラリー活動を開始、1994年にミヅマアートギャラリーを開廊。日本、アジアの若手作家を中心に育成、発掘、紹介を行っている。著書に『アートにとって価値とは何か』、『MIZUMA 手の国の鬼才たち』(撮影:田川基成)
私の手元に、初期の村上隆の作品があります。本人が展覧会のプロポーザルをしに来た時に、持参していた作品を買ったものです。支払った金額は1万円でしたか。作品が売れた時の彼のうれしそうな表情は今でも忘れられません。手放すつもりはありませんが、今マーケットに出回れば数十〜数百倍になることは間違いないでしょう。
作品の最初の値段をつけるのがギャラリスト(画廊主)です。それによって作品は作家の手を離れ、アートマーケットを流通し始める。しかし、アートが、コンテキスト(文脈)を離れて単なる金融商品のようになりつつある状況には疑問を持っています。

三潴さん所有の村上隆作品(撮影:田川基成)
アートの値段は労働の対価ではありません。たとえばiPhoneがいくら創造性に富んだプロダクトであったとしても、工業製品である以上、材料原価、人件費、流通コストなどを計算した結果として販売価格が決まりますよね。アートはそういうものとは一切関係がない。キャンバスにすっと一本の線を引いただけで、ものすごい価値を持つことがある。経済合理性では測れないのです。
ギャラリストとして活動を始めたのは1989年、すぐにバブル崩壊。全然売れない。でも売らなくていいと思っていた。PRの会社を別に経営していたから、売れなくても困らなかった。今でも自分が買いたいと思わない作家の作品は扱いません。
金儲けしたい、一刻も早く有名になってこの貧乏な状態を脱したいと思っている作家もいますが、多くの作家にとって描くことや作ることはそのまま「生きること」です。我々の契約作家のひとりである会田誠はこう言っています。「美術であろうがなかろうが、作りたいものを作る。その痕跡として何かが残る。そのようなものしか後世には残らないだろう」。これには私自身がハッとさせられました。

池田学展「誕生」の展示風景(撮影:宮島径、Courtesy Mizuma Art Gallery)
ただ、時代が変わっているのも事実です。ゴッホのように死んでから評価されるということはもう起こらないでしょう。なぜなら、グローバルに巨大なマーケットが成立しており、かつインターネットを通じて世界中の情報が瞬時にとれるからです。昔より発表や発掘が簡単になった分、同時代の評価を受けざるを得ない。
そんな中で、作家のコンセプトやビジョンに寄り添い、その価値をマーケットの論理に変換し、プロモーションしていくのがギャラリストの役割です。
そうそう、今日、久しぶりにギャラリスト魂に火がつくような出会いがあったんですよ。一目見て、これはいい、この作家をプロデュースしたいと思った。そういうことは頻繁には起こらない。見たことのないものを見たいんです。

東京・市ヶ谷のミヅマアートギャラリーにて(撮影:田川基成)
世間が評価しないことに不安にならないかって? 逆ですよ、それは。作家はみんなナルシストで「俺は最高だ」と思っているわけですが、ギャラリストも同じです。「俺がいいって言ってるのにわかんないんだな、みんな節穴だな」と思うわけ。その確信がなければギャラリストはできません。
アートも、市場原理に従う一商品に過ぎないという宿命からは逃れられません。その中で、作家の創作スタイルと市場の趨勢のギャップをいかに埋めるか。私たちギャラリストの永遠の課題です。
コレクターというよりパトロンでありたい
ストライプインターナショナル社長、石川文化振興財団理事長 石川康晴さん

いしかわ・やすはる/1970年岡山市生まれ。1995年、婦人服販売のクロスカンパニーを設立。1999年に自社ブランド「earth music&ecology」を立ち上げる。2014年に石川文化振興財団を設立。2016年に社名をストライプインターナショナルへと変更(撮影:田川基成)
初めて現代アート作品を購入したのは2012年です。国際的に高く評価されている現代美術作家・河原温(かわら・おん)の作品と出合ったことがきっかけでした。「デイトペインティング」と呼ばれるシリーズの12点セットのものです。
アメリカ、中国、インド……世界中のコレクターが欲しがる作品です。簡単に買えるものではありません。ある時、旧知のギャラリストから、「ある事情があって所有者が手放したがっている。しかしこれほどの作品が国外に出ていくことは大変な損失だ。もし現代アートが好きで、コレクターとしての第一歩を踏み出すならば、最初にこれを買うことをおすすめします」という提案をいただいたのです。僕にはそれがとても腑に落ちた。

ストライプインターナショナルの社内。ピエール・ユイグ/フィリップ・パレーノの作品「ノー・ゴースト・ジャスト・ア・シェル」(撮影:田川基成)
当時は、経営する会社の年商1千億円が見えてきて、創業者として不自由のないお金も入り、社会的な立場や責任も認められてきた時期でした。すなわち、名誉やお金に興味がなくなってきた。
僕は、洋服の買い付けに自ら世界中を飛び回っていた頃から、ロンドンへ行けばテート・モダン、パリへ行けばポンピドゥー・センター、ニューヨークへ行けばメトロポリタン美術館やMoMA(ニューヨーク近代美術館)というように、足繁く美術館に通っていました。40歳をすぎてこれからの人生を考えた時、自分にとって欠かすことのできないアートを通じて人とのつながりを築いていきたいと思ったのです。

ストライプインターナショナルの社内。ライアン・ガンダーの彫刻作品「お母さんに心配しないでと言って(ⅲ)」(撮影:田川基成)
コレクターとしての僕のポリシーは、生きている作家の作品を買うことです。河原温の次に購入したのはピエール・ユイグという作家ですが、彼と話した時はおもしろかった。ポンピドゥー・センターの隣のカフェで手描きのドローイングを見せられて、生態系とアートを融合させることに挑戦したいけど、誰もお金を出してくれない、と言うのです。それで、その話にのる人がいないなら僕がやりましょう、と。
僕が生まれ育った岡山は、倉敷に実業家・大原孫三郎が創立した大原美術館があり、香川県の直島を「アートの島」として有名にした福武總一郎さん(ベネッセホールディングス最高顧問)の出身地でもあります。大原、福武の流れに石川が続きたい。

「岡山芸術交流2016」で展示されたピエール・ユイグの作品「Untilled(未耕作地)」。頭部は本物の蜂の巣になっている(写真提供:石川財団)
投機目的ですか? まったくありません。そもそも売る気がありません。そんなことをすれば作家との信頼関係は築けないし、それに、「経済は文化のしもべである」と言い切るような福武さんがそばにいて、高値で売買して利益を得ようという感覚にはならないです。
ただ、所有するアートの価値を地元に還元するという側面においては、経営的な感覚は必要だと思います。
一昨年、市や県とともに実行委員会を立ち上げて、「岡山芸術交流2016」という国際展を開催し、総合プロデューサーを務めました。行政からは難解だ、市民参加型のイベントにすべきだと何度となく言われましたが、なかば強引にハードコアなコンセプチュアルアート展にしました。

リアム・ギリックの作品「任意空間」(The anyspace whatever...)(撮影:田川基成)
理由は2つあります。「岡山市民・県民のアートリテラシーはそんなに低くない」という信念と、「世界中から人が来るイベントにしたい」という思いです。
岡山市は人口70万都市ですが、ほぼ同じ規模の都市が世界中で800あります。その中でコンセプチュアルアートに特化した地域振興を行っているところはなかった。「他で成功しているからうちもやろう」ではなく、「誰もやっていないことをやろう」と考えたほうが人は来る。そこはマーケティングですね。「岡山芸術交流2016」には23万人が来場し、経済波及効果は20億円と推計されています。自治体としては安い投資だったのではないでしょうか。
「バブル期のトラウマ」を脱して新しい時代に
AKI ISHIZAKA代表、元サザビーズジャパン社長 石坂泰章さん

いしざか・やすあき/1956年東京都生まれ。総合商社勤務の後、1987年〜2005年画廊経営。2005年サザビーズジャパン社長に就任(〜2014年)、数々の大型取引を手がける。現在はアートアドバイザリーおよびアートディーラーとして活動する。著書に『巨大アートビジネスの裏側』など(撮影:田川基成)
アート産業が他のビジネスと決定的に違うのは、圧倒的に供給不足だということです。名作は常に足りない。それゆえ、オークションハウスでは、マスターピース(傑作)を探すこと、それを出品してもらうことが最も大事な仕事になります。
オークションハウスは売り手(出品者)と買い手(落札者)の双方から手数料を取りますが、売り手の手数料がほぼ10パーセントであるのに対し、買い手の手数料はおよそ12〜25パーセント。高価格帯の出品になると売り手に対しては割引がある一方、買い手に対してはたとえ女王陛下であってもまけないと言われるほど、売り手が強い。
日本では、文化的な話をする時にお金のことに触れてはいけないという風潮がありますね。全国紙でもアートとお金の話をきちんと取り上げた記事はほとんどない。あるメディアオーナーになぜかと尋ねてみたことがあるのですが、「庶民感覚とかけ離れているから」という説明でした。でもそれならばプロ野球選手の年俸だって庶民感覚とはかけ離れていますよね。

(撮影:田川基成)
投資じゃないんだ、本当に絵が好きで買うんだと言っても、誰だってすぐに安くなるものより、資産として目減りしないものがいい。しかしかつて美術愛好家がこぞって買った日本画、洋画の価格はバブル時のピークの5分の1、10分の1。これでは美術品を新たに買おうにも軍資金は出ないし、国内のマスコミではアートとお金の情報が不足しているので必要以上に安く売る羽目に。そのうえ、子どもや孫に「まったく無駄づかいして。もう美術品は買わないで」と言われる始末。不幸な悪循環です。
一方で、今年の春に開かれた「草間彌生」展(国立新美術館)では40分待ちの行列ができていました。総入場者数は50万人を超えたと聞きます。これほどアートを「見る」ことが好きな国民も珍しい。

「草間彌生展」開催中、国立新美術館の前庭で休む人々(写真:AP/アフロ)
日本は「見る文化」と「買う文化」が極端に分かれています。思い浮かぶ理由は2つあって、ひとつは、先述した「買う」ことに関してメディアからの情報が少ないこと。もうひとつは、バブル期のトラウマです。
バブル期の象徴的な出来事として、大昭和製紙(現在の日本製紙)のオーナーがゴッホの「医師ガシェの肖像」を約124億円で落札して話題になりましたが、それが悪いと言いたいわけではありません。今だったら2倍くらいはするでしょう。その後、あの作品に匹敵するクラスのゴッホ作品は市場に出ていません。
では「トラウマ」とは何かというと、数多くの有名作家の二級品を買っていたことと、少なくない人が「借金」で絵画を購入していたことです。

1990年5月、クリスティーズニューヨークでオークションにかけられるゴッホの名画「医師ガシェの肖像」(写真:AP/アフロ)
アートは短期投資には向きません。長期投資には適していますが、それがあてはまるのはどんな有名作家であってもその作家の一級品のみです。そして、どの作品が後世に残る傑作なのか、美術史や美術市場を知らずにそれを見分けるのは非常に難しい。
また、日本の富裕層の資産を欧米と比較すると、ほとんどが自社株や不動産で、キャッシュフローが少ないのが特徴です。そのためバブル崩壊で株価・地価が急落した際、多くが資産を切り売りする羽目に陥りました。その中にはこぞって購入した印象派の作品が多く含まれました。
「アート=バブル」のイメージはこのようにして作られたわけですが、いずれもアート市場に関する充分な知識があれば防げたことです。

(撮影:田川基成)
しかし、この1年ほどで日本のアート市場を取り巻く空気はものすごく変わっていると感じます。今までと違うのは、「ゴッホが欲しい」とか「ルノアールが欲しい」というブランド主義ではなく、「自分の感性を表現したものが欲しい」というマグマを男女問わず幅広い年齢層から感じるのです。
アートを始めるきっかけはなんでもいいと私は思っています。投資目的でも、単に好きだからでも構わない。そういう人が十人いたら、その中から一人か二人、本当のコレクターが育っていく。その人たちは、アートから刺激を受けることを楽しみ、それを自らのクリエイティビティーに変えていくことができる人たちなのです。
「歴史に残るかどうか」が判断基準
東京国立近代美術館主任研究員・保坂健二朗さん

ほさか・けんじろう/1976年生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程(美学美術史学分野)修了。企画した主な展覧会に、「フランシス・ベーコン」(2013)、「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である」(2015)、「日本の家」(開催中〜10月29日まで)など(撮影:田川基成)
国公立美術館の財源の大半は、基本的に税金です。勤務先の東京国立近代美術館の本館(美術館)場合、ここ数年は平均約1億円以上の購入予算があります。それとは別に国立美術館のうちコレクションをもっている4館(東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館)全体に割り当てられる特別購入予算も今はあります。国内の他の公立美術館に比べれば恵まれていますが、諸外国と比べた場合に、ものすごく潤沢というわけでもない。
昨年度(2016年度)に特別購入予算で当館が購入した作品のひとつにパウル・クレーの油彩画《破壊された村》がありますが、金額は約2億5千万円でした。クレーは日本でも人気のある画家ですが、僕ら学芸員からすると、知名度や完成度の高さに鑑みると、クレーの作品はリーズナブルだと言えます。

「日本の家」展の準備真っ最中の展示室で(撮影:田川基成)
一方、2013年度にはChim↑Pomの《気合い100連発》(2011年に福島県の被災地域で撮影された映像作品)を購入しています。クレーに比べたら格段に安かったですが、ある意味では、クレーを買うよりも「気合い」がいりました。
主観で買える個人コレクターと違い、国公立の美術館の学芸員が判断基準にするのは客観的な評価、つまり美術史です。常に「歴史に残るかどうか」「歴史のどこに位置するか」「歴史に照らし合わせるとどんな解釈ができるか」を考えている。同時代の作家は美術史上の評価がまだきちんと定まっていません。それゆえ、たとえ値段、つまり市場価値がつけられていても、美術史の観点からするとまだ値段が定まっていないとも言えるのです。そのような作家の作品を美術館が購入するという判断は、その価格が妥当かどうかということよりも、その作家や作品を歴史に残すべきだと考えているというメッセージになる。その責任は大きい。

展示室内には、建築家・清家清(せいけ・きよし)の名作「斎藤助教授の家」が実物大で再現された
私見では、1970、80年代ぐらいまではマーケットで「お墨付き」を与える機能は批評家やキュレーターが担っていたように思います。でも今のコレクターは、批評を待つことなく作品を買います。むしろ「あのコレクターが買ったぞ」ということのほうが「評価」になっていくことすらある。
欧米の場合、そうして先駆的なコレクターが買った作品が美術館に寄託、寄贈されて、コレクション展の中で展示されていたりしますし、また、小規模であっても若手のアーティストの個展を継続的に開催して、マーケットを含めたアートワールドをもり立てていこうという気風があったります。

「日本の家」展、展示風景(撮影:田川基成)
一方日本の美術館の場合、マーケットに関係することがあまり望まれていないのかもしれません。そして、だからこそ漫画や建築の展覧会が美術館でできるのだとも考えられます。たとえば今、当館では「日本の家」展を開催していますが、この展示によって彼ら建築家への注文が増えたりはしないでしょう。
こうしたケースにおける美術館の役割は、日本のクリエイティビティーを国内外に向けて発信することにあります。もともと「日本の家」展は、日本で企画され、ローマとロンドンを巡回した後に東京でも開催されている展覧会です。数年前、ローマで日本の現代文化を紹介する展覧会を企画しようという話がもちあがった時、僕は、建築しかない、それも「家」だろうと思いました。「住まう」ことは洋の東西を問わず共通の営みですから。

(撮影:田川基成)
「アートワールド」の中心はやはり欧米です。いや、今は中国が強力なので、欧米と中国というふたつの中心を持つ楕円構造になっているとも言えます。日本は依然として周縁です。そうした中で、日本の文化の底力を正しく世界に示したいと考えた時、建築は非常に重要なコンテンツになるのです。アートや文化だけでなく、キュレーションも、そのように、ソフトパワーとして国力に資する役割も担っているのです。
長瀬千雅(ながせ・ちか)
1972年愛知県生まれ。編集者、ライター。「AERA」編集部などを経てフリー。
[写真]
撮影:田川基成
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝






























