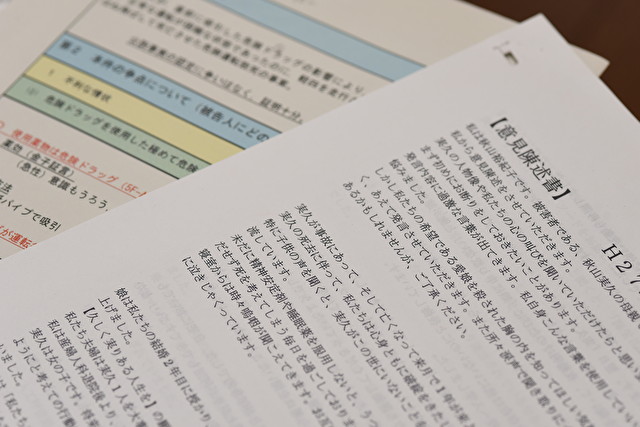悲劇はある日突然訪れる。それは決して、他人事ではない。病気や事件・事故、あるいは災害で最愛の人を失ったとき、人はどうやって立ち直っていけばいいのか。深い悲しみに暮れる遺族たちの「心のケア」が、いま社会的に求められている。それがどういうものなのか、大切な娘を事故で失った香川県の両親や、タレントの風見しんごさんに話を聞いた。(鈴木毅、高鍬真之/Yahoo!ニュース 特集編集部)
破れた日記帳
日記帳のそのページは、娘の名前を何度も何度も繰り返し書いた筆圧で、ところどころ破れていた。
「この日記帳は、娘の容体を正確に記録に残すために交通事故の直後からつけ始めたものです。娘が亡くなった後も、加害者の刑事裁判が終わるまで、ずっとつけ続けました。当時は、『実久』と娘の名前を何度も書かないと落ち着かなくて。無心で書いているうちに破けてしまったんですよね……」
事故で亡くなった実久ちゃん(撮影:高鍬真之)
母親の秋山裕紀子さん(48)はそう語ると、日記帳をパラパラとめくって見せた。
事故の直後から書き留めてきた日記帳は、感情の起伏がそのまま表現されていた。殴り書きもあれば、強く書きすぎて破ってしまったこともある。裁判での加害者の主張に腹が立ち、ページをペンで突き刺したこともあった。「いまだに読み返すとつらいです」と、裕紀子さんは言う。

秋山裕紀子さん(撮影:高鍬真之)
暴走車にはねられた長女
最愛の一人娘を奪った事故は2014年1月29日午後、香川県善通寺市の県道で起きた。実久ちゃんは当時11歳の小学5年生。いつものように友だちと小学校から自宅へ向かう帰り道のことだった。
父親の隆志さん(50)が振り返る。
「その日、私は仕事が休みで、家でテレビを見ながら実久の帰りを待っていたんです。すると、同じ小学校の女の子が玄関に駆け込んできた。『実久ちゃんが事故に巻き込まれた! 早く来て!』。慌てて飛び出して車で現場へ向かうと、レスキュー隊員が実久に心臓マッサージをしているところでした」
県道を暴走してきた軽自動車は、実久ちゃんをはね飛ばし、縁石に乗り上げていた。横たわる娘に隆志さんが駆け寄る。「実久! 実久!」。しかし、返事はない。実久ちゃんはくも膜下出血を起こし、呼吸も止まった状態だった。

緩やかなカーブの県道を暴走車はそのまま直進し、突っ込んできた(撮影:鈴木毅)
懸命の治療によって再び心臓が動き始めた実久ちゃんだったが、意識が戻ることはなかった。どんなに声をかけても、どんなに触っても、静かに寝たまま——。そして9日後、寝ずの番で看病を続けた両親の前で息を引き取った。
心を支配した「怒り」の感情
運転していた男は、車内で危険ドラッグを吸引した直後に事故を起こしていたことがわかった。当時29歳の無職で生活保護を受ける身だった。危険運転致死罪に問われ、事故からほぼ1年後の2015年1月26日、高松地裁で懲役12年(求刑15年)の実刑判決を言い渡された。
実久ちゃんの仏壇は、たくさんの写真と花で飾られていた(撮影:高鍬真之)
突然、暴走してきた車によって、なんの罪もない子どもが犠牲になる——。近年でも、2019年4月に起きた池袋暴走事故や、その翌月に起きた大津市の園児死傷事故など痛ましい事故が相次いでいる。遺族にとってこんな理不尽なことはない。
秋山さん夫婦の場合、最初に心を支配したのは、加害者に対する「怒り」の感情だった。判決が出るまでの日々はつらく苦しいものだったが、裁判は娘に対するけじめだと自分自身を奮い立たせた。
しかし、看護師だった裕紀子さんは、自分の心の動きに不安を持っていた。裁判が終わったとき、自分はどうなってしまうのか。喪失感に押しつぶされそうになりながら、自分の心に必要だと感じていたのが、知識として知っていた「グリーフケア」だった。
父親の隆志さん(左)(撮影:高鍬真之)
事故後の1年間は裁判との闘いだった(撮影:高鍬真之)
気持ちを分かち合う「場」
「グリーフ(grief)」は、英語で「悲嘆」のこと。悲嘆ケアとも呼ばれるグリーフケアは、事故や病気などで愛する家族や友人を亡くし、深く悲しむ人や苦しむ人たちに寄り添い、「心のケア」をすることで心身を少しずつ回復させる取り組みだ。
1960年代に米国で始まったとされるが、日本では95年の阪神大震災を機に導入され、2005年のJR福知山線脱線事故で広く知られるようになったという。11年の東日本大震災でもグリーフケアの取り組みが重要視された。
グリーフケアのワークショップでは、当事者である遺族とともに、同じような経験をした遺族や医療・福祉関係者、心理士などが集い、気持ちを分かち合う。遺族は、ふだんは表に出せない悲しみや怒りの感情を解放し、自分たちの心の動きが“異常ではない”ことを知る。そうした体験が、傷ついた心の回復につながるという。

東日本大震災で犠牲者に手を合わせる遺族たち(写真:ロイター/アフロ)
大切な人を失ったとき、人の心はどんな反応をたどるのか。
東京にある一般社団法人「日本グリーフケア協会」の会長で、東北福祉大学教授の宮林幸江さんは、4つの段階を経ると語る。
「まず極度の緊張感から悲しみをあまり感じず、死去に伴う事務手続きなどを淡々とこなす『ショック期』(およそ半年間)を迎えます。一段落して日常生活に戻ったころから、喪失感や不安、混乱、怒り、孤独などさまざまな感情が入り交じった状態の『喪失期』『閉じこもり期』(およそ4、5年)になる。そのつらい期間を経たあと、ようやく故人を懐かしく、愛しく感じる追慕の時期を迎え、『癒やし・再生期』に向かうのです」
大切な人を失ったときの4つの心の動き
「ショック」期を越えたころからの心の動きの特徴を、宮林さんはやはり4つに分類している。
亡くなった人を思い起こして“愛しい”“悲しい”という感情にのまれ、故人の気配を感じたり、話しかけたりする「思慕」。どうせ誰もわかってくれないと思い込み、人とかかわることに気後れしてしまう「疎外感」。不眠、食欲減退、無関心、無気力、不安、恐怖など“うつ”と似た症状が起きる「うつ的不調」。そして、無理に自分自身を奮い立たせようとする「適応・対処の努力」。
日本グリーフケア協会会長の宮林幸江・東北福祉大学教授(撮影:高鍬真之)
「この4つの心の動きは、それぞれが天秤のように連動しながら持ち上がってはおさまる、という動きを繰り返します。失った人を思い出して、恋しくなったり、負い目を感じたりするのは誰にでも起こる感情で、抑え込む必要はありません。悲しいときは悲しみに浸っていいのです。その感情に寄り添い、気持ちを分かち合う時間と場所、それがグリーフケアです。自分の心や体に起きている変調はだれにでも起きることで、自分だけが特別なわけではない——。それを知ることで、前向きに人生を歩みだす助けになるのです」
協会では、遺族らに向けて仙台市、東京・赤羽、新潟・越後湯沢の3カ所で、定期的にケアのためのワークショップを開いている。その一方で、「グリーフケアアドバイザー」の資格を用意し、ケアする側の人材育成にも取り組んでいる。資格取得者は、ほぼ全員が死別経験者だという。
ワークショップでは、遺族らに①言い残したこと②やり残したこと③自分の悲しみのプロセス④自分の死生観⑤亡くなった人との人生、などを書いてもらい、それをもとに話し合う。そうして自分の心の状態を認識し、人生や死について自分の考えを整理するきっかけになるのだという。

(写真:Duits/アフロ)
「悲嘆」のプロセスを認識する
秋山さん夫婦にとって“救い”となったのも、このグリーフケアだった。
裕紀子さんがインターネットで「日本グリーフケア協会」の存在を知ったのは、事故から半年ほどたったころ。さらに、事件・事故の被害者やその家族の支援活動をする公益社団法人「かがわ被害者支援センター」(高松市)やNPO法人「いのちのミュージアム」(東京都日野市)の取り組みも含めて、同じように子どもを交通事故で失った遺族たちと知り合うことができた。
「いっぱい泣いたらええよ」「私もその時期あったわ」——。裕紀子さんは、同じ悲嘆経験者たちと話すことで“初対面なのに心がほっとする”感覚になったという。そして、そうした体験を通じて「人に“甘える”強さ、助けてと言える強さを持った」と語る。
(撮影:高鍬真之)
「それまで私は、『人からかわいそうと思われたくない』『まわりは幸せで、自分だけ孤独感、疎外感を感じている』という気持ちを持っていました。だから、親子連れを見るのもつらかったし、テレビでランドセルのシーンや、正月の家族団らんのシーンを見るのもつらかった。だけど、そうした気持ちをまわりの人たちに言うことはできませんでした。わかってもらうのは難しいし、困らせてしまうだけですから」
裁判も終わり時間が経つにつれ、周囲からは、もう終わったんだから前向きに生きていきなさい、という“暗黙”の空気を感じるようになった。娘と仲良くしていた同級生たちも、中学生、高校生になって自分たちの生活が忙しくなり、会って話す機会は少なくなっている。きっと彼女たちも私に会うのがつらいんじゃないか——。
「そんなことをいろいろと考えてしまい、常に人の顔色を見ながら会話するようなことになってしまうのです」
そんななか、心を許して話せる場所となったのが、グリーフケア協会などでの活動だった。
「グリーフケアを知って、自分は正しい流れで悲嘆のプロセスのなかにいると認識できました。悲嘆経験はだれもが通るもので、自分だけが苦しんでいるのではない。であるならば、いま落ち込んでいても、いずれはもとに戻れる。それがわかると、気が楽になりました」
現在、裕紀子さんは「グリーフケアアドバイザー特級」の資格を取り、同じような境遇になった人たちの心のケアをする立場にもなっている。
「私たちにとってグリーフケアの場で話すことが唯一のよりどころだったように、ほかの遺族の方々の心のケアに少しでもなればと思っています。そしてそれは、いまも悲嘆のプロセスのなかにいる自分たちにとってのグリーフケアにもなっているのです」
事故現場の前に立つ隆志さん(撮影:高鍬真之)
いつまでもふさがらない穴
13年前に長女を交通事故で亡くしたタレントの風見しんごさん(57)も、ほかの遺族たちとの交流によって“救われた”ひとりだ。
「もともと、時間が経てば、心にぽっかり空いた穴がふさがるんじゃないか、そこから前に向かって生きていけるんじゃないかと思っていました。だけど、ぜんぜんふさがらない。そんなときに、同じ境遇の遺族の方々と話すことで、それはずっと“ふさがらない”ということを教えてもらったんです」
(撮影:高鍬真之)
仕事柄、警察署のイベントなどで、ほかの事故の遺族たちと話す機会があった。みんな自分の経験を淡々と語るだけだったが、それがいちばんの励ましになった、と言う。
「時間の経過に期待しても、ふさがらないよ、と。だけど、ふさがらなくても生きている人はたくさんいる。そうやって生きていけるんだと思えただけで、大きな希望になりました。それがわかったことが、自分にとって前に進む一つのきっかけになった」
13年前の悲劇
事故が起きたのは、2007年1月17日の朝。当時10歳だった長女のえみるちゃんは、学校に向かうため元気よく家を出た。
いつもと変わらない平日の朝。そのわずか数分後、一家に悲劇の報がもたらされる。「えみるちゃんが交通事故にあった」。風見さんが妻の尚子さんと現場に駆けつけたとき、エンジンがかかったままのトラックの下にえみるちゃんのスニーカーが見えた——。
病院に運ばれたとき、心肺停止の寸前だった。そして約1時間半後、えみるちゃんは静かに息を引き取った。

花火大会で空を見上げる風見さんとえみるちゃん(2006年夏、風見しんごさん提供)
「本当に突然だったので、最初はもう事実が受け入れられないんですよね。いろいろな感情が渦巻いて、怒りなのか、悲しみなのかわからない。悲しみのどん底なのに、ときどき、ふと長女が隣に帰ってきた錯覚で大笑いしたりする。子どもが亡くなったあの一瞬というのは、自分にとって、もう未来がないんですよ。これから生きていく希望とかが全部なくなったような感覚でした」
大俳優から投げかけられた言葉
それから、起きている間はずっと長女のことを探していた。テレビ番組の収録中でも、頭の片隅では常に、長女がどこかにいるんじゃないか、と考えていた。なにかの拍子に帰ってくるんじゃないか、いまなにをやっているんだろう、どこに行ったんだろう、どんな思いをしているんだろう……。
(撮影:高鍬真之)
自分を取り戻す過程は、本当に少しずつの歩みだった。えみるちゃんを亡くして2年ほどが経ったときのこと。風見さんは、ドラマの撮影現場で故・渡瀬恒彦さんからかけられた言葉をよく覚えている。
「おまえ、帰ってきたな」
愛する娘を亡くした悲しみにもがき苦しむ日々。仕事場ではそんなそぶりを見せないようにしていたが、風見さんのわずかな変化を感じ取っていたのが渡瀬さんだった。
「渡瀬さんは一緒に芝居をしながら、僕が長いこと、セリフをしゃべってはいるけれど、“ここにはいない”ということに気づいていたのでしょう。2年くらい経って初めて『帰ってきたな』と言って握手をしてくださった。あのときのことは、いまでも鮮明に覚えています」
(撮影:高鍬真之)
死産した長男がもたらした「光」
家族にとって大きな転機になったのが、死産した長男の存在だった。事故から1年後、風見さんと妻・尚子さんは、男の子を授かった。しかし、妊娠8カ月目、おなかの子どもの心臓が止まっていることが判明した。
再び家族を襲った悲劇。しかし、この長男の存在が、家族にとって大きな支えとなったという。
「いろんな感情と向き合って過ごしていたのですが、長男の妊娠がわかって、やっと先のことを考えられるようになりました。事故以来、初めて来年のことを話すようになっていた。光が差す小さな穴を長男が開けてくれたような。悲しい結果にはなりましたが、長男を授かったときから、未来へ向かって光が1本、それは本当に細い光かもしれないけど、スーッと目の前に走ったような気がしたのです」
遺族たちが深い悲しみから立ち直るきっかけは、さまざまだ。
大切な人と死別した直後から、真っ暗闇の世界に突き落とされ、どこを見れば光があるのか、それがいつ見つかるのかもわからない。「それが悲嘆状態の特徴です」と、前出の日本グリーフケア協会の宮林会長は言う。
「そして、この方向に進めば光に当たるかもしれないという希望をもてると、立ち上がるきっかけになるのです」
「欽ちゃん、私も出たい!」
事故のとき、3歳だった風見さんの次女ふみねさんは、いま16歳。3年前から妻の尚子さんとともに米ロサンゼルスに渡り、現地の学校で演劇の勉強をしている。風見さんが3カ月に1回程度、米国に会いに行くという単身生活を送っている。
家族バラバラの状態だが、風見さんは「長女のことがなければ、たぶん次女の留学はさせていなかった」と言い、こう続ける。
「物理的な距離は離れているけど、気持ちはまったく離れていませんので。それは、長女と長男が家族をつなげてくれているんだと思います」
「舞台女優になりたい」という夢に向かうふみねさんを、風見さんは応援している。その理由が、痛いほどわかっているからだ。

公園の滑り台で遊ぶえみるちゃんとふみねさん(2006年夏、風見しんごさん提供)
えみるちゃんの事故の直後から、風見さんはふみねさんが寂しがらないように、「欽ちゃん」こと萩本欽一さんとの舞台稽古に一緒に連れていった。いつしか、ふみねさんはこう言うようになった。「欽ちゃん、私も出たい!」
「いきなりお姉ちゃんがいなくなって、家族全員がつらい時間のなかで、あの舞台の上は唯一明るい世界、いわば魔法の国だったんですよ。あそこに行けば、笑顔になれる。そのときからですから、彼女があの舞台に立ちたいという夢を持ったのは」
「ここにいる」という感覚
事故から13年あまりたったいま、風見さんはこう感じている。
「こういうこと言うとおかしなヤツだって思われるかもしれませんが、僕のなかで、長女が“ここにいる”ということを確信しています。姿は見えないし、声は聞こえないけれど、僕たちにいろんなことを教えてくれているような気がするんです。そうして僕たちのなかで彼女の人生が続いている気がする。そう思えるようになりました」
(撮影:高鍬真之)
いまでも、無性に悲しくなって涙があふれてしまう時間があるという。ただ、かつてと違って自分のなかで感情が整理されているのがわかる。風見さんの家族はそれぞれの時間をかけながら、徐々に徐々に前へ進んでいる——。

(風見しんごさん提供)
鈴木毅(すずき・つよし)
1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て、株式会社POWER NEWSを設立。
高鍬真之(たかくわ・まさゆき)
1959年、石川県生まれ。講談社「月刊現代」記者を振り出しに週刊誌、ビジネス夕刊紙などで記事を執筆。その後、トラック専門誌「トラックボーイ」(日本文芸社)、「トラックキング」(英和出版社)編集長。現在、編集プロダクション「ル・ピック」代表