「ハイリー・センシティブ・チャイルド」(HSC)という気質を持った子どもたちがいる。「人一倍敏感な子ども」という意味だ。感受性が豊か。他人の気持ちによく気が付く。一方で、周囲の刺激に敏感で傷付きやすい――。そして親たちは、戸惑いや悩みも深いという。HSCについては、大人版の「ハイリー・センシティブ・パーソン」(HSP)もある。あまり知られていない、その現状を追った。(文・写真:当銘寿夫/Yahoo!ニュース 特集編集部)
突然の「学校に行きたくない」 やがて長期化
ある年の9月、2学期が始まる日だった。
埼玉県に住む斉藤和代さん(40代・仮名)の娘が朝、「行きたくない。給食食べて、吐いたらどうしよう」と言い出した。小学校1年生。今日は始業式だから給食はないよ、と言い聞かせて送り出すと、帰宅してからこう言った。
「お母さん、明日は行きたくない」

斉藤和代さん(仮名)。HSCの娘を育てている=埼玉県内で
予兆はあったという。夏休み中、熱中症のような症状が出て学童保育を休み、その後、学童保育に行けなくなった。斉藤さんは「学校に行ければいい」と考えたが、学校にも通えなくなる。
登校しようとすると、おなかが痛くなった。小児科を受診しても、医師は体に異常は見当たらないという。何度か受診した後、小児神経科を紹介された。小児神経科の医師は「不安障がいかもしれません」と言う。
並行して行政の教育相談室も訪れた。そのときのことである。
そこは、担当者が親子別々に話を聞く方式。1時間ほどの相談を終えて斉藤さんが外に出ると、泣き疲れた娘が立っている。母親と離されたことが不安で、ずっと泣き続けていたという。
「二度と教育相談室に行かない、と言いました。ほかの相談にも行けなくなって……。家でのお留守番もどんどんできなくなった。とにかく、私がいないとだめなんです」
娘から職場に「怖いよ」 5分おきに連絡
斉藤さんは、実母とも一緒に暮らしている。学校に行かなくなった娘を実母に頼み、斉藤さんは仕事に出た。娘には子ども向けの携帯電話を渡したが、今度は携帯に何度も連絡が来た。
「メールで何度も『怖いよ』って。5分おきだったこともあります。電話もしょっちゅうかかって。上司が『心配だったら帰っていいですよ』って言ってくれて早退したんですけれど、結局、その日を最後に職場に行けなくなった。娘は家の中どころか、私が一緒の部屋にいないと不安がるようになって」
斉藤さんと娘の離れられない日々が始まった。

イメージ
カウンセリングのために外出すると、建物の入り口で娘が強く嫌がり、入ることができない。電話相談をしようとすると、察した娘が携帯電話を持つ腕の裾を引っ張り、通話ができない。久しぶりの場所や初めての場所も極度に嫌うようになった。
斉藤さんの行きつけの美容室に一緒に付いてきても、店の前で泣き出す。だから、斉藤さんは自分で自分の髪を切るようになった。
「本当につらかったですね。くっついて離れなくて。どこにも行けない。誰とも会えない。誰かに相談さえできない。シングルマザーだったので、私が働かないと収入もない。フェイスブックとか、見られなくなっちゃいました。(友達は)みんな、『ここ行ってきたよ』と写真を載っけるじゃないですか。精神衛生上、すごくよくないんですよ。だから見なかったです。一切やめた」

イメージ
「自宅への訪問相談をやっていないか、あちこちに尋ねたんですけど、どこも(相談の際は)『来てくれ』って。それができないから困っているのに」
斉藤さんはこのころ、娘との日々をインターネットで発信していた。ある日、読者からのコメントが目に留まった。「娘さんのお話を読んでHSCが思い浮かびました」と記されている。HSC? 初めて聞く言葉だった。
調べてみると、「集団の中で疲れやすい」「周囲の人の負の感情が入ってきて、疲れる」といった気質らしい。どれも娘に当てはまる。発達障がいの可能性も考えていた斉藤さんは、ようやく、「これかもしれない」と得心したという。

斉藤さん
5人に1人が該当という研究も
HSCやHSPは病気や障がいではなく、持って生まれた「気質」の一つだ。米国のエレイン・アーロン博士(心理学)が1996年に提唱し、次第に研究が進んだ。
同博士によると、「深く考え、深く処理する」「過剰に刺激を受けやすい」「感情の反応が強く、特に共感力が高い」「ささいな刺激を察知する」という4条件を満たすと、HSCやHSPに該当する。該当者の割合は15〜20%、およそ5人に1人になるという。
感性が豊かで空想にふけりがちだったり、慎重すぎたり。周囲の微妙な変化も強く感じ取って自分の中に取り込んでしまうため、物事に圧倒されがちなところもある。そうした結果、思ったような行動を取れなくなり、周囲には「内向的」と映るケースも少なくないとされる。

米国では、アーロン博士の研究をもとに記録映画も制作された。その『Sensitive-The Untold Story』の一場面(documentary,2015, Foundation for the Study of Highly Sensitive Persons)
子どもが「ハイリー・センシティブ」だったらどうしたらいいか。
お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所の研究協力員・岐部智恵子さんによると、HSPやHSCの気質特性自体に「良い」「悪い」はない。
「子どもは一人ひとり違います。子どもをよく観察して、どんなときに心地よいと感じ、喜ぶか。探偵になった気持ちで接してみてください。集団になじめなかったり、細かなことにこだわったりするのは『わがまま』ではなく、感覚特性によるつらさかもしれません。困ったときには周囲や専門家の助けも借りながら、その子らしさが開花するよう子育てを楽しんでほしいと思います」
富山県にある真生会富山病院の心療内科部長・明橋大二医師は『HSCの子育てハッピーアドバイス HSC=ひといちばい敏感な子』など多くの関連著書を持つ。
「HSCが学校に行きづらくなる原因には『先生の叱り声が怖い』が実に多い。やんちゃな子を先生が叱る際、教室に響き渡るような怒鳴り声だと怖くなって教室に行けなくなる。先生の怒鳴りは、子ども全員が嫌なんです。個別に叱ればいい。敏感な子のサインを大事にすれば、みんなが過ごしやすい学校になるはずです」
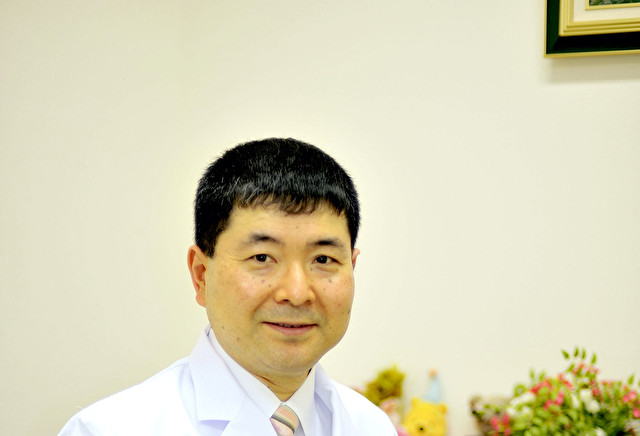
明橋大二医師(本人提供)
「この気質のことが広がれば、本当はHSCなのに発達障がいと誤解されていた人が救われたり、楽になったりするケースが増えていくでしょう。一方で、実際は病気や発達障がいなのに、『HSCだ』として治療や療育の機会が遅れるリスクもないとは言えない。発達障がいなどの診断に関わる全ての医師やカウンセラーがちゃんとHSCを知って鑑別できるようになれば、リスクも減らせます」
「とことん娘と付き合う」と決めて
斉藤さんの娘は3学期になると、母親と一緒なら教室で授業を受けられるようになった。それもつかの間、2年生になると、担任やクラスメートが替わったことで母親が一緒でも教室に入れなくなり、2人で図書室で自習するようになった。
このころ、斉藤さんは「貯金を取り崩しながらでも、とことん娘と付き合おう」と決めていたという。

斉藤さんの娘。ノートで分数の計算
2年生の1年間は毎日、娘に付き添った。娘が教室に入れるようになると、後ろで一緒に授業を受けた。給食の時間には弁当を一緒に食べる。校外見学では別料金を払って一緒のバスに乗った。
「2年生のときは学校のイベント、(私も一緒に)全部出た。許してくれた学校の対応も本当にありがたかったです」
娘が3年生になった秋、斉藤さんに乳がんが見つかった。
「毎年マンモグラフィーを受けていたんですけど、娘が一人でいられなくなってからは3年ぐらい受けてなかった。私が一人でレントゲン室に入るのも嫌がったので。抗がん剤治療のときは細菌感染しちゃいけないから、本当は(子どもは)部屋に入れてもらえないんです。でも、病院は配慮してくれた。そばにいさせてくれ、ありがたかった」

イメージ
「その日」は4年生に上がった瞬間に訪れたという。
新学期の初日。登校前に娘が言った。「お母さん、来なくていいよ。今日は教室にちょっとだけ入るだけだもんね。たぶん、大丈夫」。1年生の2学期以来、初めて娘が一人で学校に行った。夏休みになると、留守番ができるようになった。
そうやって、一人で大丈夫な時間が増えていく。
「娘の場合、『慣れない場所』と『目立つこと』が異常に苦手。今も週2回、出られない授業がある。その時間だけは一緒に空き教室で本を読んでいます。授業が終わると、教室にすーっと戻るんです」
今の社会に、安定したレールはない。斉藤さんはそれも実感したという。
「勤務先だった企業は安定していたので、食うには困らないと思っていたけど、働けなくなっちゃった。将来どうなるか、ほんとに分からない。娘? 中学は科目ごとに先生が違うからそんなに心配してないです。好きなことやってくれればいいです」

イメージ
気付かないまま当事者として生きた
子どもではなく、大人の「ハイリー・センシティブ」はどんな状態なのだろうか。
この11月、横浜市で開かれた当事者同士の交流会に足を運んだ。名称は「HSPカフェメリッサ」。同じ神奈川県内の相模原市などでも「お茶会」と呼ぶ交流会を定期的に開いているという。
月曜日の午後、横浜市の男女共同参画センター横浜に20〜40代の女性5人が集まった。ホームページの情報などで開催を知ったらしく、互いに初対面だという。参加者は「職場で一気に多くのことを言われると、パニックになってしまって」とか、「職場の人間関係がうまくいかなくて仕事を辞めたんです」とか、それぞれの経験を話していく。
「メリッサ」を主宰する秋池葉子さん(63)は「自分はHSP」と認識している。ただ、それを知ったのは40歳を過ぎてからだ。

「HSPカフェメリッサ」の「お茶会」。中央が秋池葉子さん
参加者の硬さがほぐれてきたころ、秋池さんは自身の体験を語り始めた。
「私は仕事を辞め続けて(自分の気質に)向き合うことをしないできた。年を取ればなんとかなるかなと思っていたら、少しもならなかった。(一歩間違えたら)今でも(逃げるような暮らしを)繰り返していたと思います」
終身雇用が当たり前の時代を生き抜いたにしては珍しく、秋池さんには20回以上も転職の経験がある。
最初の銀行で約10年。ほかに家電メーカー、問屋、印刷会社、金属部品メーカー、リゾートホテル……。正社員や派遣社員、パートタイマーなど雇用形態もさまざまだった。「スキルアップの転職ではないので、転職するたびにお給料も下がっていきました」と言う。

秋池さん
なぜ、そんなに転職したのか。
「(行く先々の)職場で、フラストレーションをぶつけられることが多かったんです。あるとき、親分的な立場の女性が私に厳しいことを言った直後、自分の傍らにいる人にニコッてした。私にはっきり分かるような形で、です。私はどの職場でもターゲットになりやすかった。そして人間関係が悪くなると、仕事も落ち着いてできなくなる。頑張ってみても改善できず、つらくなって……。辞めるというより、逃げたんです。そんなことをたくさんしてきました」
40代半ばのある日。仕事帰りに書店へ立ち寄り、偶然、HSPを紹介する青い本を手に取った。そこに出てくるチェックリストをその場で試した。「他人の気分に左右される」「明るい光や強い匂い、ざらざらした布地、サイレンの音などに圧倒されやすい」といった23項目。それらのほぼ全てに該当した。
「腑に落ちた、って言葉がぴったり。今まで自分に起きたことは、この気質のせいなんだって分かった気がした」
時代は2000年ごろ。インターネットもそれほど広がっておらず、このときはそれ以上の情報に接することはできなかった。
「人一倍敏感な人」の交流会を主宰して
転機は50代半ばになってからだ。大きな病院で患者の案内や書類回覧などの仕事に就いた。覚えることはたくさんある。最初は周りともうまくやっていたという。

イメージ(写真:アフロ)
仕事を始めておよそ1カ月後、ささいなことがきっかけで、「あの人、いったい何?」などと言われるようになった。職員から名指しでクレームも届くようになったという。
「すごく追い詰められた。もう一日だって(退職を)待てない状況でした」
数日後、家で出勤の準備をしていたとき、忘れ物がないか不安になり、かばんから物を引っ張り出しては入れ直すということを30分近く繰り返した。その様子を見た夫は「もう行かなくていいよ」と言う。そして、そのまま職場に行かず、退職した。
「極度のうつ状態になっていたと思います」と秋池さんは言う。
それから1年間、外出できなかった。家にこもり、ネットでHSPを調べていく。青い本に出合った2000年ごろにも浸透し始めたばかりのネットでHSPを調べた。あれから10年余り。それでも、HSPに関する情報は少なかったという。

イメージ
しばらくして、秋池さんはやっと交流会の開催情報を見つけた。
「行ってみたらすごく落ち着いたんですよ、心が解けて。自分でもそういった場を開きたいな、って。それがきっかけでした」
2013年からは「お茶会」を主宰するようになった。「1回目のお茶会では、参加者の一人が、始まると泣き出しちゃったんです」。当時はこの気質を持った人の集まりや拠点がほとんどなく、その女性は「同じような悩みを持つ誰かに会いたい」という思いが募っていたのだという。
お茶会は既に100回を超す。秋池さんはこれまでに600人ほどのHSPに会った。
「人が困っていたら(鶴の恩返しのように)背中の羽根を抜いてでも何かしてあげたくなってしまったり、人の顔色を読んで自分の思ったことをのみ込んだり、みんな、苦しんでいる。『自分にはこういう気質がある』と気付く必要がありますよね。そして、自分のトリセツをつくらないと」
当銘寿夫(とうめ・ひさお)
記者。琉球新報記者を経て、2019年に独立。Frontline Press(フロントラインプレス)所属。


















