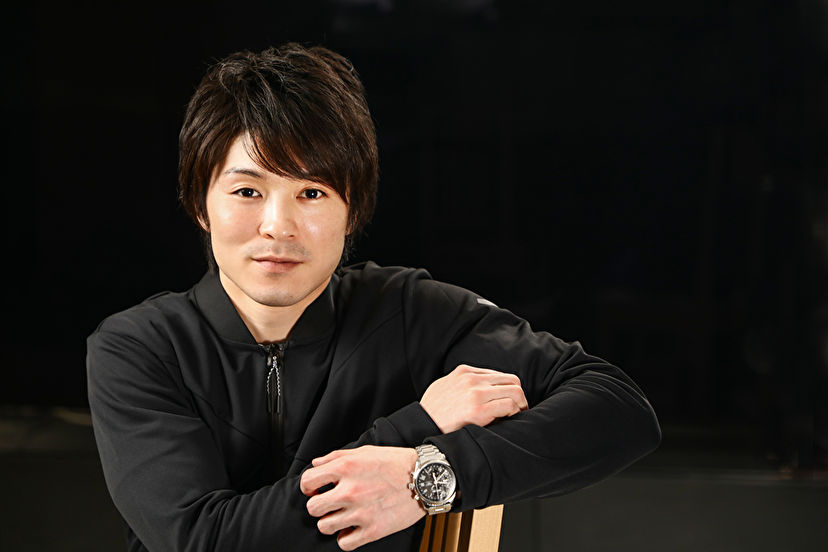「1964年の東京は素晴らしかった」――元サッカー日本代表監督のイビツァ・オシム(78)は、前回の東京五輪にユーゴスラビア代表として参加した。ヨーロッパの選手にとって日本は「文化衝突を怖れていた」というほど遠い国だった。終戦から19年、東西冷戦下の五輪はどのようなものだったのか。2度目の東京五輪を来年に控えて、当時の思い出と未来に向けての提言を聞いた。(ジャーナリスト・木村元彦/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)
「欧州の選手たちは文化衝突を怖れていた」
言葉は少しも分からなかったが、気持ちは伝わってきた。代々木の選手村で各国代表のために無料で貸してくれた自転車の乗り心地は最高で、毎日乗りまわしていた。ある日、気がつけば千葉県まで来ていた。田園地帯で休んでいると、農家の女性がやってきて梨をくれた。身振り手振りで、ノドが渇いているでしょう?食べなさい、と。その梨は、甘くて、柔らかくて、今まで食べたことのないおいしさだった。お土産にした日本の振袖は婚約者であった現在の妻アシマのウエディングの晴れ着になった。
イビツァ・オシムにとって1964年の東京五輪は特別な大会だった。23歳にしてのはじめてのアジア遠征。まったく未知の国であった“ヤパン”であったが、東京で予想もしなかったホスピタリティーに触れたことから、一気に親日家になったのは、知る人ぞ知る話だ。
ユーゴスラビアの長身FWは、やがて世界的な名将となって再来日した。指導者として日本サッカーに多大な貢献をした背景には、東京五輪での経験があった。あれから、55年が経過し、今のオシムの目にオリンピックはどう映っているのか。

東京五輪、開会式。1964年10月10日、国立競技場で(写真:読売新聞/アフロ)
――シュワーボ(オシムの愛称)は、ことあるごとに前回の東京五輪の好印象を語ってくれます。いつもは皮肉屋なのに(笑)。あらためて1964年を振り返ってもらえますか。今でも記憶は鮮明ですか。
あの東京大会のすべてのことは覚えていると言える。ボスニア、セルビア、クロアチア、モンテネグロ――今では分かれてしまった国と民族で構成されたユーゴスラビア代表は、首都のベオグラードをダグラスDC8で飛び立って、アムステルダム、アンカレッジを乗り継いで東京に降り立った。何て遠い国だろうという印象だった。
長い時間、移動に費やしたので疲れてしまい、迎えのバスの中で眠ってしまっていた。ホテルのベッドに入ってまどろんでいたら、そこに地震が来てまた驚いた。地震を経験したのも初めてだったから。とにかく最初は異なる文化の遠い国に来たという印象だった。

(撮影:ドラガナ・シュピッツァ)
――今では海外渡航も手軽になり、インターネットで外国の情報や映像も即座に入手できます。55年前のユーゴのスポーツ選手たちの世界観というのはどのようなものだったのでしょうか。
大きな冒険だった。実はヨーロッパの選手たちはアジアに行くということで、そこで文化衝突があるのではないかという恐れがあった。距離的にも遠いし、今ほどスポーツイベントが盛んでもなかった。決して豊かでもない中で、我々が日本に行くのは大きなリスクがあった。
――アジアで初めて開催されたオリンピックですが、アジアに行ったのも初めてだったのですね?
私は厳密には試合でイスラエル(当時アジアサッカー連盟に所属)に行ったことがあったが、あそこは今ではUEFA(欧州サッカー連盟)所属だ。
――イメージしていたものと大きなギャップはありましたか。
日本に対しては漠然としたオリエンタルなイメージしかなった。しかし、想像以上に東京はとても大きな都市で、それがまた整然としていた。日本人は規律を重んじて、自分が何をするべきかいつも考えて行動していた。感じたのは、戦争(第2次大戦)が終わってからまだ19年ではあったが、東京オリンピックのオーガナイズがとてもうまくいっていたということ。私は外国で暮らすことなど思いもしなかった若い頃だったけれど、ここなら生活しやすいと思ったものだ。結局、何十年か後にそうなるのだが(笑)。

オシムは、2003年にジェフユナイテッド市原(現ジェフユナイテッド市原・千葉)の監督に招聘されると、2005年ナビスコ杯初優勝へ導いた。写真は、選手に胴上げをうながされるも笑顔で辞退するところ。2005年11月5日、国立競技場で(写真:日刊スポーツ/アフロ)
東西冷戦のただなかで
ユーゴスラビアは当時、東側(社会主義陣営)にも西側(資本主義陣営)にも属さない非同盟中立国であった。それゆえにアメリカ、ソ連を筆頭にどの国とも対等な親交があった。オシムはそんな国の代表だった。
1964年は政治的に大変な時代ではあったが、事故や事件もなく、日本はオリンピックを平和的に開催できた。それが何より成功だった。そこに政治が入りかけてもいたのだが、幸いにしてスポーツ選手たちはそれを許さなかった。スポーツの記録的にもたくさん良い結果が出た。日本の東京五輪が大きな一歩になって、それから他の国際大会も開かれるようになったと言えるだろう。日本で知り合った人々とは国を超えて今でも強い絆でつながっている。
――日本戦で決めた2ゴールは記憶にありますか。亡くなった岡野俊一郎さん(元日本サッカー協会会長、当時日本代表コーチ)は、「オシムの名前を覚えたのは、このときにやられてからだ」と言っていました。
東京ではなく長居(大阪)でやった5位決定戦。ヘディングでのゴールだった。開催国である日本に勝てたのも良い思い出だ。いま思えば、新幹線に乗ったのはあれが初めてか。カラーテレビを見たのもこのときだな。敗戦国であった日本が急激な経済成長を遂げているのを感じていた。

サッカー予選リーグB組、ユーゴスラビアとハンガリーの試合。25分、ハンガリーのベネがシュートを決める。試合はハンガリーが勝利したが、オシムは2ゴールを挙げた。1964年10月15日、東京都世田谷区の駒沢陸上競技場で(写真:毎日新聞社/アフロ)
――本来、サッカーの世界では最大の大会はW杯です。五輪とW杯の両方を体験した立場から、どう比較しますか。
オリンピックの方がW杯よりも国際的で友好的な大会だと言えるだろう。そしてより人間臭い交流の場所だ。
W杯の出場枠は膨張しつつあるが、それでも32カ国しか出場できない。中心はやはりヨーロッパや南米の列強だ。そして勝敗が大きく問われる。キャンプ地でも別々だから、なかなかチーム同士で交わることもない。
しかし、オリンピックは、例えば、国が内戦状態であっても個人参加ができる。成績が良ければ、どんな小さな国からでも、一人ででも出場できる。選手村では、あらゆる国々の多様な民族が一堂に会した。そこでの出会いは新しい世界として広がるのだ。私にとっての東京五輪がそうだった。毎晩、いろんな国の文化を紹介するイベントがあった。特にアフリカの国々は、ガーナを筆頭に次々と舞踊をやったりした。
――東京五輪の最中には、ザンビアがイギリスから独立して閉会式のときには出場国がひとつ増えていたというエピソードがありました。
選手村やスタジアムでそれまで全然知らなかった国を知ることができた。オリンピックは最大の地理学や社会学をも学べる機会だった。世界の文化、民族、言語が1カ所に集まったわけだから、勉強をしたい人間はいっぱい学ぶことができた。もちろん勉強したくないやつもいたけど、そういうやつは永遠に学ばないだろう(笑)。

閉会式の選手入場。大会期間中に北ローデシアはザンビアとして独立、開会式とは別の新しい国旗を掲げて行進した。奥に日本選手団、右手前にユーゴスラビア選手団の姿も(写真:日刊スポーツ/アフロ)
選手村での交流は盛んだった。オシムは柔道の無差別級で日本の神永昭夫を破って金メダルを取ったアントン・ヘーシンク(オランダ代表)をよく見かけたと語っている。
ユーゴスラビアとオランダの宿舎が隣だったのだ。イメージとしてヘーシンクは3メートルほどの身長の持ち主だと感じていた。同じアスリートとして、彼が強いというのは、近くにいるだけで伝わって来た。試合も見ていたが、圧倒的な強さだった。ヘーシンクの戦い方は余裕すら感じさせるほどで、おそらく地球上で誰がやっても勝てなかっただろう。そう思わせるだけのものがあった。
――他の競技種目も観察することはできていたのでしょうか?
東西冷戦の壁はあったが、今以上に緩やかで親密な交流ができていた。体操のチェコスロバキア(当時)のヴェラ・チャスラフスカの演技は素晴らしかった。
トレーニングに関しても、他の種目の選手の練習も見ることができた。これも新鮮でいろいろと勉強になった。私は走り高跳びのアメリカ人選手(ジョン・トーマス)の練習を見て感動した。人間が2メートル18センチの高さを跳ぶために何を鍛えるのか。それが日本戦のヘディングゴールにつながったのかもしれない(笑)。

撮影のリクエストに応えるアントン・ヘーシンク。1964年9月28日、代々木選手村で(写真:TopFoto/アフロ)
平和のためにスポーツができること
日本の組織運営側のホスピタリティーも好評だった。交通量が多い今では考えられないが、冒頭に記した通り、すべての選手に自転車を無償で貸し出した。
1人に1台自転車を持たせてくれたと思う。それで自転車同士がお互いにぶつかりあったりしたものだ。なぜか。選手の出自から右側通行か左側通行かも分からなかったのだ。それが平和な選手村であった唯一の文化の衝突かもしれない(笑)。

自転車の貸し出しは選手たちに好評だった。選手村内を移動するイタリアの選手たち。1964年10月1日、代々木選手村で(写真:Mondadori/アフロ)
――日本は来年、いよいよ2度目のオリンピックを開催します。この56年で世界は変わり、科学も大きく発展しました。現在のオリンピックは、大きな商業主義に飲み込まれているという指摘があります。ちょうどシュワーボがユーゴスラビア代表のコーチとして戦った1984年のロサンゼルス五輪が商業五輪に向かった転機だったと言われています。
商業主義はもうあの前から始まっていた。お金がないと何もできないのは厳しい現実だ。しかし、今はビジネスがスポーツに勝ってしまっている。オリンピックにせよ、W杯にせよ、残念ながらお金があり過ぎることで、それが問題になっている。開催招致のために賄賂が流通する事態は悲しいことだ。そしてスポーツを愛する一般の人たちがその犠牲になっている。結果的にお金を一般の人から収奪して賄っているという構造がある。それに開催にあたって莫大な予算をあて過ぎている。巨額なお金が動けば、本来スポーツとは関係のないひずみがそこに必ず生まれる。一方でボランティアの人たちは報われているだろうか。

(撮影:ドラガナ・シュピッツァ)
――2017年にはリオ五輪の大会委員長だったヌズマン氏が買収容疑でブラジル連邦検察に起訴されるなど、招致に向けての汚職の疑惑はたびたび報じられます。チケットも2020年東京大会の開会式のA席が30万円です。そして放映権の高騰。1964年の東京大会はスポーツに適した10月開催でしたが、今回7月下旬という最も暑い時期に行われるのはアメリカのネットワークのためだとも言われます。
主催者やメディアはプレイヤーズファーストで考えているのだろうか。メッシやネイマールなど一流の選手たちはヨーロッパのリーグ戦を散々戦ってとても疲労しているが、テレビはそういう選手を視聴者にオリンピックで見せたい。お金が関わっているからだ。しかし、彼らは(所属する)バルセロナやパリ・サンジェルマンでの仕事でヘトヘトになっている。猛暑の夏はシーズンオフにあてたいだろうが、テレビと契約した視聴者は待ち望んでいるし、それは許されない。
結果、サッカーや選手が消費されてしまう。お金を稼ぐことは重要です。オリンピックを運営する職員や携わる人たちに対する雇用の責任がある。しかし、今は度を越しています。
――一方で五輪憲章そのものは素晴らしく平和の祭典とも言われています。来年の東京五輪に何を期待しますか。
すべての人はオリンピックが平和をもたらすことを願っている。そして人がオリンピックに平和を期待すればそれ自体が力になる。オリンピック休戦もそうだ。当然のことだが、選手は生まれ故郷が戦争だとプレーに集中できない。スポーツの力を信じるならば、外交的には仲の良くない国同士で合同主催させることによって、解決の方向に向かわせることだってできる。オリンピックを通じて複数の問題が解決されてほしい。しかし、残念ながら、スポーツの成績を勝った負けたという国ごとの軍事作戦とシンクロさせている人さえいます。それはとても危険なことです。

ドイツは当時、東ドイツと西ドイツに分かれていたが、統一チームをつくって出場した。1964年10月10日、国立競技場で(写真:picture alliance/アフロ)
――リオ大会では難民選手団が初めて結成されました。これはシリア、コンゴ民主共和国、南スーダンなど紛争で国を追われたアスリートによって結成されたチームでした。
アイデンティティーの問題もあるが、難民の人々が再びスポーツをする場が与えられたのは素晴らしいことだ。私たちボスニアや旧ユーゴの出身者でもそのようなチームを作ることができる。戦争で憎しみあったセルビア人とクロアチア人も、国外に移民して、そこで同じチームになればまた仲良くなれるのだ。
そしてそういうチームを作ったならば、スポーツである以上、競技力を高めて結果を出すようにしないといけない。重要なことは徹底的にコミュニケーションを取ること。相手を知っていれば、一緒に戦いやすい。食事や言語の交流もある。友情も成果としてある。難民チームもそうだが、オリンピック会場自体がそういう場所になってほしい。少なくとも1964年の東京は素晴らしかった。

(撮影:ドラガナ・シュピッツァ)
――来年は、東京に来られますか?
東京でオリンピックなのだから、行きたい気持ちはあるが、健康次第だな。でも知っているか? オリンピックはときに奇跡を起こす。サラエボ冬季五輪(1984年)のときは暖冬で雪がまったく降らなくて開催中止かと心配されていた。それが開会式前夜にいきなり豪雪にみまわれたのだ。サラエボ市民は踊りあがって喜んだ。
オシムの健康状態が良好に回復し、再び東京に降り立つことを切に願う。そのとき、落胆させないオリンピックを我々は見せることができるだろうか。
イビツァ・オシム
1941年サラエボ生まれ。1962年プロデビュー。旧ユーゴスラビア代表のフォワードとして、1964年の東京五輪に出場、1968年の欧州選手権で準優勝。1978年現役を引退。クラブチームの監督を経て、1986年、旧ユーゴスラビア代表監督に就任。2003年、ジェフユナイテッド市原(当時)の監督に就任。2006年、日本代表監督に就任するが、翌年脳梗塞で倒れやむなく退任。2009年ボスニアに帰国。2011年、民族別に3つに分かれているボスニア・ヘルツェゴビナのサッカー協会が統合を拒否したために、FIFA、UEFAから資格を停止されると、「正常化委員会」の委員長に就任。会長を一本化させ、資格停止が解除された。
木村元彦(きむら・ゆきひこ)
ジャーナリスト、ノンフィクションライター。中央大学卒。代表作にサッカーと民族問題を巧みに織り交ぜたユーゴサッカー三部作。『誇り』、『悪者見参』、『オシムの言葉』。『オシムの言葉』は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞、40万部のベストセラーとなった。他に『蹴る群れ』、『争うは本意ならねど』『徳は孤ならず』『橋を架ける者たち』など。
通訳:ドラガナ・シュピッツァ