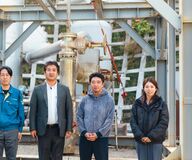食べる人と農家が地域内で支え合う、夕張の自立型農業とは? 【地域の経済】

日本各地で人口が減り、行政サービスも縮小する。地域での生活の維持が難しくなる中、どう豊かな暮らしを成り立たせていくのか。地域から始まる、これからの時代を生き抜く知恵とノウハウを学ぶ。第2回目は、北海道夕張郡の「メノビレッジ長沼」。

日本で初めての会員制農業。CSAとは?
農業を始めて以来ずっと、一般の市場や流通を通さず、会員の注文のみでやってきた農家がある。北海道夕張郡にある「メノビレッジ長沼」。米国人のエップ・レイモンドさんと奥さんの荒谷明子さんが営む、いわゆるCSA(Community Supported Agiculture)型の農業だ。夕張郡は経済破綻した夕張市の隣に位置している。
CSAとは「消費者が農家のパートナーとなり費用を先払いして定期的に作物を受け取るしくみ」のこと。日本ではまだあまり馴染みのない産直提携の一つだが、欧米では広まりつつある(*1)。
札幌駅から車で約30分。メノビレッジの広大な畑の中に鶏小屋や貯蔵室などに並んでレイモンドさん(以下、レイさん)たちの暮らす母屋も建つ。
会員は春に一年間の費用を前払いし、5〜11月に毎月2回、食材を受け取る。ナスやキャベツ、大根など何十種類もの野菜に米、大豆、麦、トウモロコシなどの穀物も。農場では鶏も飼っていて新鮮な卵も届く。会員は札幌市内に多く、各戸に直接配達される。会費は年3万7800円。別途明子さんの焼くパンも注文できる。宣伝は一切したことがないが、味が評判で2013年までに会員は100軒近くに増えた。
だが2年ほど前、研修生の卒業時期が重なり人手不足に陥ったことで今は前払い制を一時やめて、都度注文を取る方法に切り替えている。人数は減ったもののお客さんのほとんどは当初の会員で会員に買い支えられていることに変わりない。人手が戻れば以前のしくみに戻したいと明子さんは話す。
「年間契約のほうが経済的には安定するので、安心して栽培に専念できます。でも100軒分の野菜をつくるのには手がかかる。土地の改良にも力を注がなければならかったのと、人が減ったのが重なって、今は仕方なく前払い制はお休みしているんです」

大規模経済は暴力にもなる
レイさんが畑から戻ってきた。米国人らしく大きな体躯の持ち主で、難しい話もユーモアたっぷりに話すチャーミングな方だ。
それにしてもなぜ、CSAなのか。経済的な安定を考えるなら、大手の取引先が決まるほうがいいのでは?と尋ねると「その質問に答えるには、少し時代を遡らなくてはなりません」と話し始めた。
1970年代末、レイさんがネブラスカの大学で農業経済学を学んでいた当時、アメリカはカーター政権下で好景気。研究者たちは「今こそ農家は借金してでも規模拡大に投資すべき」と主張し、話にのった農家も少なくなかったという。ところがわずか数年後、レーガン政権になるとインフレ収束に向けた政策が打たれ始める(*2)。金利は4倍に跳ね上がり、農家の借金額は3年間で倍になった。
「多くの農家が倒産し、自殺する人も出ました。なのに学者たちは間違えたというだけ。そのとき、経済学の無意味さを思い知ったんです」
失望したレイさんは学校を辞めた。1980年、アメリカで再び徴兵制度が制定されたのを機にカナダのウィニペグへ渡り、改めて平和主義と農業について勉強し始める。
当時のカナダはNAFTA(*3)への加盟が決まり、やはりグローバル企業が進出し始めていた。1991年にはアメリカが備蓄していた小麦を放出し、穀物の値段が暴落。カナダの穀物農家は大打撃を受け、このときも何人も亡くなったという。
「経済システムも戦争と同じ、暴力になりうると思いました。文化も駄目になる、まちも駄目になる。人も亡くなりました。ベトナム戦争のときに枯れ葉剤が撒かれましたが、大規模農業では、当たり前のように大量の農薬を使っている。戦争と同じことが行われていると思ったんです」
経済の暴力に振り回されずに、人と人が支え合うことで成立する農業のしくみはないものか。そう考え模索した先で行き着いたのが、当時アメリカで始まりつつあったCSAだったのだ。(*4)
レイさんはカナダで仲間と共に、小麦の生産とその麦を使った小さなパン屋を始める。ちょうど同じ時期に帯広畜産大学の学生だった明子さんも教会の交換プログラムでカナダに来ていて、このパン屋を手伝うことになりレイさんと知り合った。明子さんは話す。
「当時カナダの製粉工場の多くがアメリカの企業に買収されて、そのパン屋にあった小さな製粉機が州で唯一の製粉機だったんです。ガンジーのチャルカ(糸車)のように、これをシンボルに多くの人に状況を知ってもらいたい。パンを買ってもうことで地域の消費者と直接つながり、農業を維持していこうというトライでした」
パン屋を始めたのと同時期にCSAの会員を募ったところ反響は大きく、ラジオなどでも取り上げられ、200名がすぐに集まったのだという。
「みんな、農家の状況を知って自分にできることはしたいと思っていたんですね。手段が必要だったんです」
その後、二人は明子さんの故郷である札幌に移りメノビレッジを立ち上げるが、ウィニペグのパン屋は今も仲間たちの手で続けられている。

会員との信頼関係に支えられて
グローバル化によって小さな農家が苦しむ状況を見てきたレイさんたちが行き着いた答えが「地域のコミュニティで地元の農家を支える」CSAだった。グローバル化とは対極にある。
日本でも昭和40年代に「提携」といわれる産地直送のしくみが生まれたが、CSAとは根本的な目的が違うとレイさんは話す。
「生産する人と食べる人の信頼関係という点では同じですが、CSAではそれに加えて食べる人同志の関係、コミュニティの部分を大切にします。生産者と近郊の都市の人たちが食べものを分かち合うこと。CSAのSにはsupported(支援)だけでなく、shared(共有)の意味も含まれていると私は考えています。ただ安全でおいしいものを提供するサービスではないのです」
つまりメノビレッジは生産者というだけでなくコミュニティのオーガナイザーでもあるということだ。会員と一対一の関係をつくるだけでなく、自分たちが農業を通してどんな世の中を志しているのかを発信し続けること。それに共感する地域の人たちに、買い支えられてきた。
生まれたばかりの長男を抱えて、明子さんは配達先でよくお客さんと話し込んだ。毎回宅配に入れる「野菜だより」は手書きのイラストや文字でびっしり埋まっている。
会員が田植えや稲刈りを体験できる田んぼをつくり、食のイベントや月1回の勉強会も開いていた。そうした交流の場があってこそ、食べる側も食や農業のあり方に関心をもつようになり、理解と信頼が生まれる。
コミュニティになればものごとを動かす大きな力になる。それを裏付けるエピソードがある。メノビレッジの畑近くに砂利プラントが建つ計画が持ち上がった。周囲の住民は皆諦める中、明子さんたちだけが反対し続ける状況を「野菜だより」に綴ったところ、みな気にかけてくれるようになり「野菜はいいけど、プラントは?」と言う人まで現れた。そして建設予定地の森を買い取りたいと寄付を募ると、なんと1週間で1200万円ものお金が集まったのだ。


大規模経済にNOを言うべき
「有機かどうか、肥料は何を使っているか、みなオーガニックかどうかにはすごく関心が高い。うちも有機栽培ですが、現代の農業にはそれよりもっと構造的で本質的な問題がある」とレイさんは言う。
スーパーへ行くと、多少は有機野菜も置いてあるが、多くの棚には安い輸入作物が並ぶ。地元の野菜は見つける方が難しい。
「私たち消費者には選択肢があると思っているかもしれませんが、すでに農業は大きな経済システムに組み込まれていて、実際は選択することさえできなくなっています」
国はますます大規模農業やグローバル化を推進する方向にある。その実現のために私たちの”税金”が使われていることにもっと自覚的になったほうがいいとレイさんは説く。
米の転作対象である大豆や小麦などには補助金が支払われ、栽培面積が大きいほど金額も上がる。
「私の知っている農家には、年間の売上が3300万円なのに補助金を6700万円もらっている人もいます。彼はどうやっていい作物をつくるかではなく、助成額を増やす方法を考え続けています。うちも助成は受けていますが、人の食べるものを誠心誠意つくっている農家と、補助金目当てで飼料をつくっている農家は全然違う」
その農業のあり方そのものに目を向けるべきだとレイさんは言う。
さらにもう一つ。日本の政府が税金を投入して、海外の大規模農場開発に加担している事例を教えてくれた。「プロサバンナ計画」と呼ばれるアフリカのモザンビークで起きている開発で、日本の国際協力機構(JICA)と企業がブラジル政府と手を組み、1400万ヘクタールもの世界大規模の農場をつくろうとしているという。
地元の農民組織UNACからは、彼らの主権を無視して土地が奪取され、安価な労働力にされようとしていることに抗議の声があがっている。森林破壊、遺伝子組換え導入の危険性もある。ここで土地を借りるお金は1反あたりたったの10円。「開発国への農業支援」と言えば聞こえはいいが、誰が得するのかは考えればわかる。ここでも地元の農家がグローバル経済の波に襲われようとしている。それを推進しているお金も、私たちのお金だ。


小規模のコミュニティを大きなつながりに
お金をもつ企業が、貧しい国に農業投資をする事例は他にもたくさんある。工業製品と同じように食べものが投資の対象になり、安く大量に売り買いされる世の中になって本当にいいのか。
そうでないとしたら、今必要なことは何か?
「まず地域で、農家と都市の人たちによる小規模のしっかりしたコミュニティをつくること。そしてもう一つは、そうしたコミュニティ同士がつながって、農政や国政に対してNOを言えるネットワークをつくることです。これは大きな組織でなければなりません」とレイさんは話す。
日本ではCSAモデルがなかなか広まらない。その理由を、明子さんは「既存の経済システムの中で、各農家も生き残るのに必死で余裕がない」ことを挙げる。「それに今はなんでも個人主義で、たとえ消費者の側がCSAの考え方に賛同しても、農家が甘えられない。支え合っていこうという関係ではなくて、迷惑をかけてはいけないという意識が強すぎてハードルになっているように思います」
だがCSAに限らずとも、地域で地元の農家を支援する方法はいろいろ考えられる。地域団体やNPO、流通者が中心となって会員を募ることもできるだろう。前払いでなく注文制から始めたり、作物の種類を絞ったり。一消費者としては地元の野菜を買うことから始めてもいい。
見えない経済に振り回されることなく、顔の見える農家や信頼できる仲間と食や地域の未来について考えることができたら。それほど心強いことはないだろう。

(*1)CSA…Community Supported Agriculture(地域支援型農業)の略。
米国農務省2012 年の発表によれば米国のCSA農場の数は1万2617軒(農業統計局「2012 Census of Agriculture- State Data」)
(*2) 1980年代にアメリカ合衆国大統領のロナルド・レーガンがとった、一連の自由主義経済政策、レーガノミクス。
(*3)NAFTA…North American Free Trade Agreement(北米自由貿易協定)の略。
(*4)「アメリカ合衆国におけるCSA運動の展開と意義」桝潟俊子、淑徳大学総合福祉学部研究紀要402006
---
ソース:『自然栽培』(東邦出版)
この記事は『自然栽培Vol.10』(2017年3月刊行)掲載された同著者による記事を改修したものです。