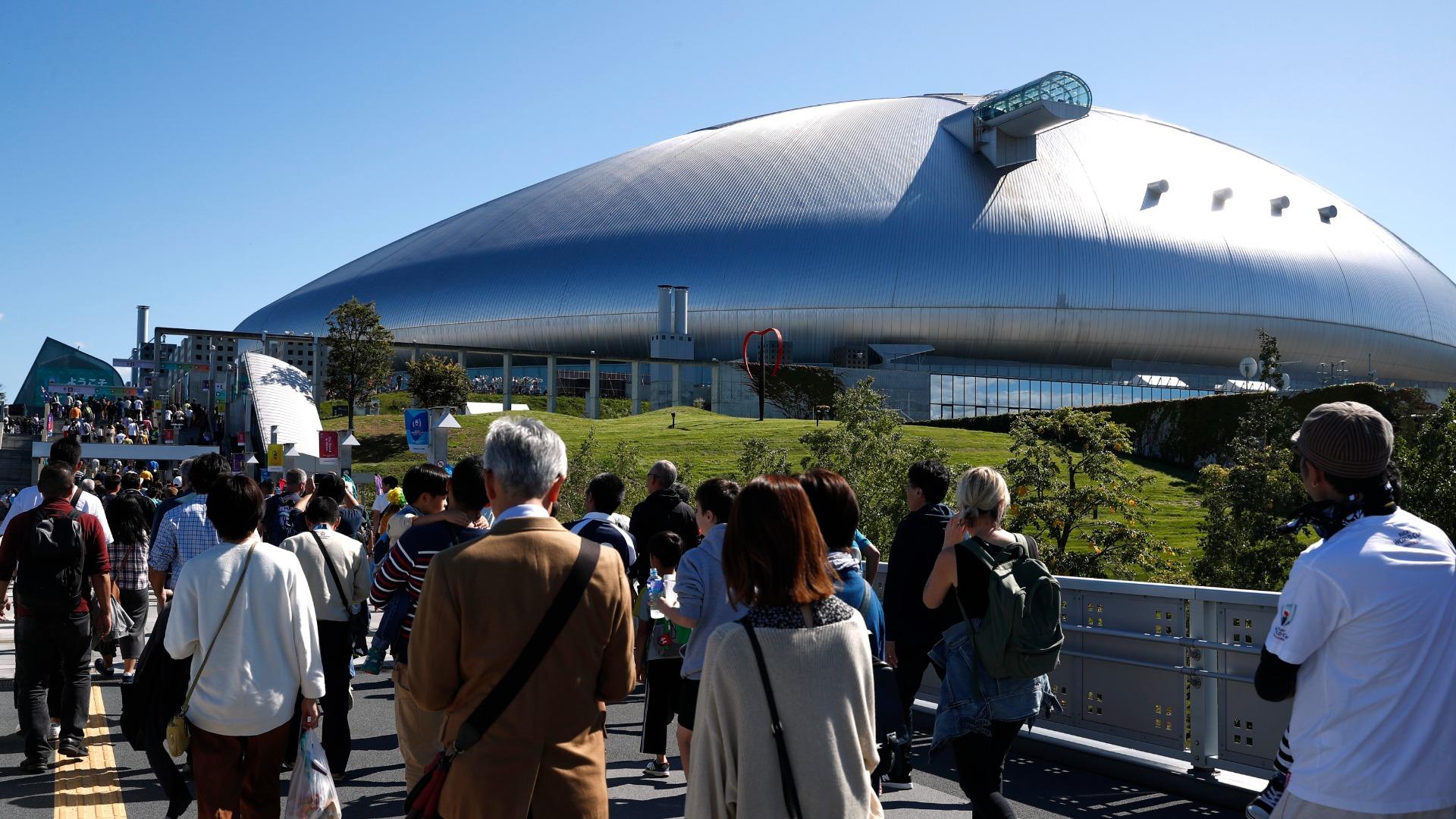小中高校生のパソコン利用の実態を探る
小中高校生におけるパソコン利用は学校の授業などで機会がある一方、個人、家庭などのプライベートではスマートフォンやタブレット型端末がインターネット利用の機器として多用されるこから、昨今では距離が離れつつあるとの指摘もなされている。その実態を、内閣府が2015年3月に確定報を発表した「平成26年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果」から探る。
次に示すのは中高校生別の、パソコンの利用率。単純に「利用しているか否か」のみを尋ねており、パソコンの種類(デスクトップ・ノート)や利用頻度、所有の是非は問われていない。さらに「利用」の明確な定義も行われていないため、回答者の判断で「利用」とした場合のみ回答したことになる。往々にして「日常茶飯事的に、普段から使っている」と解釈できるため、冒頭の「授業でのみ使っている」ようなパターンの場合、「利用している」とは回答しない場合も多分に考えられる。
昨今ではインターネットに初めてアクセスする端末が、パソコンからスマートフォンやタブレット型端末へとシフトし、その便利さからその環境に慣れ親しみ、パソコンを敬遠する動きが若年層の間に広まり、いわゆる「パソコン離れ」「キーボード離れ」が起きているとの話もある。元々2010年から2013年にかけてパソコンの利用率は逓減していたものの、直近2014年では急激に加速化したように見える。
しかしこれは一連の調査において、2014年から調査様式を(昨今のインターネット界隈の急激な変化に対応すべく)変更しているのが原因。2013年までは具体的に「自分専用のパソコンを使っている」「家族と一緒に使っているパソコンを使っている」など使用例を挙げた上で使っているか否かを尋ねており、その中には漫画喫茶や学校での利用も明記されている。ところが2014年では単に「下記の機器を利用していますか」とだけ尋ねており、その中にパソコンが含まれているのみとなっている。
回答者が「使っている」との言葉の解釈を、2013年までは多分に「その場所で使ったことがある」と経験則的な意味でしていたのに対し、2014年分では「日常茶飯事的に利用している」と読み解く事例が増え、結果として回答率が減った可能性はある。そのため、単純比較をして「1年間で半減、それ以下になった」とし、急激な減少傾向が生じたと断じるのは早計に過ぎる。
他方、「小中高校生のパソコンや携帯電話の利用率の変化をグラフ化してみる」などでも触れているが、インターネットの窓口として小中高校生の間にスマートフォンなどが急速に浸透しているのも事実。減退傾向が生じていることに違いはあるまい。
また回答者の「利用している」との認識の範ちゅうにおいて、高校生ですら4割強しかパソコンは利用されていない。つまり6割近くはパソコンとはほぼ無縁の状態にある…現実には授業などで使うことがある位…実情は認識しておく必要がある。
昨今では大学生、あるいは新社会人において、パソコンが使えない、キーボードの利用経験がほとんどない生徒が少なからず見受けられるとの報告を少なからず耳にするようになった。インターネットへのアクセスツールとしては、携帯電話、特にスマートフォンは性能面でパソコンにそん色ない機能を実装し、しかも利用ハードルも低い(操作、コストの両面で)。スマートフォンの普及、幼少時からの利用は同時に、少なくとも子供時代におけるパソコンの必要性を減らしている。その結果としてパソコンやキーボードへの経験が浅い大学生や社会人が登場するパターンが増えつつあるのかもしれない。
あるいはこれらの人たちを「タッチパネル世代」とでも呼ぶようになるのだろうか。
■関連記事: