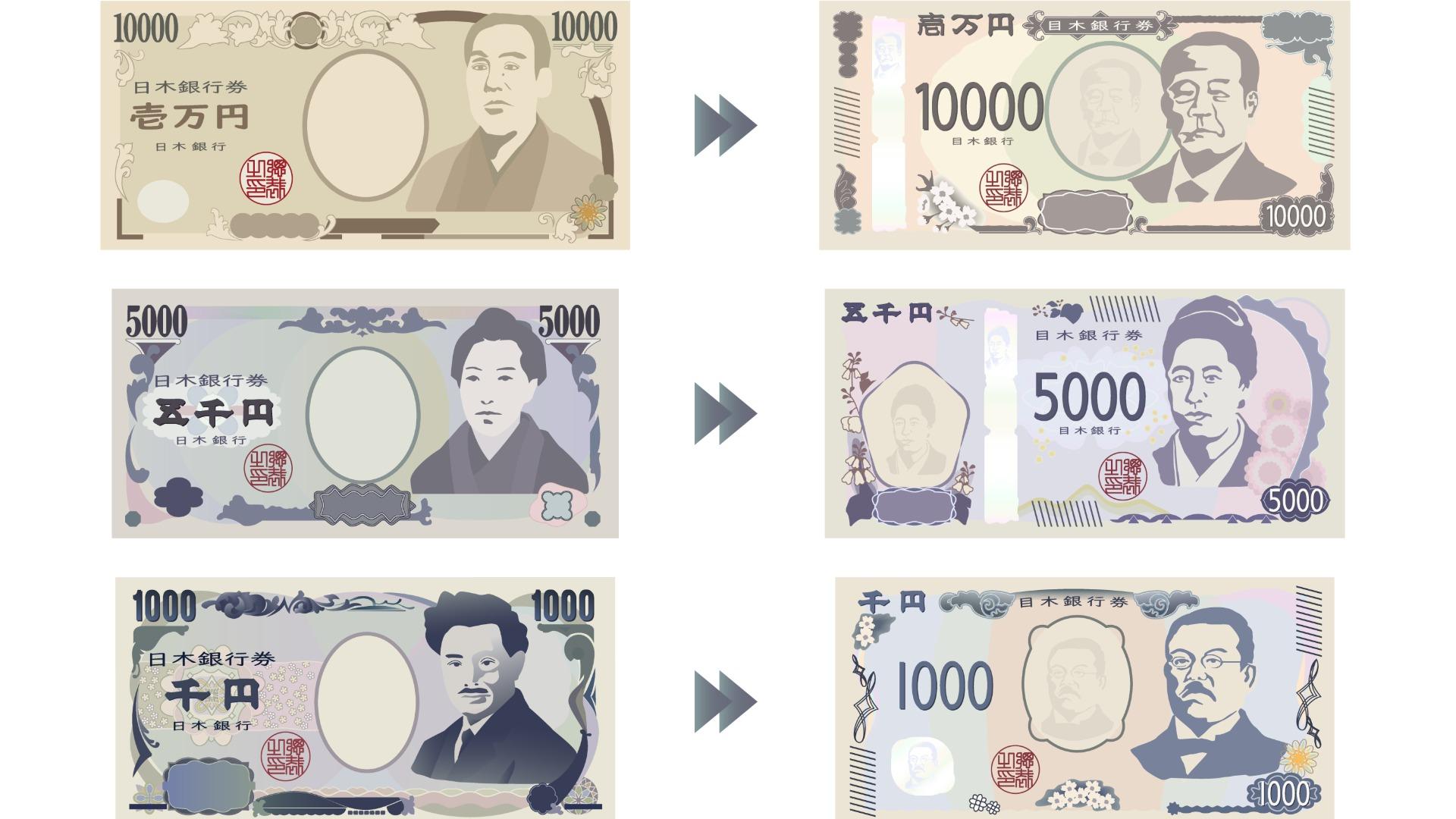国内企業物価指数と消費者物価指数の乖離

日銀が17日に発表した4月の国内企業物価指数は前年同月比で3.6%の上昇となった。前月比で0.7%上昇した。2か月連続の上昇で、2014年9月以来、およそ6年半ぶりの高い水準となった。
昨年4月はコロナ禍のなかで、景気の落ち込みとともに物価も下落した。物価に影響を与えやすい原油価格も、先物が一時マイナスになるなど大きく下落していた。
昨年4月の国内企業物価指数は前年同月比で2.5%の低下、5月は同2.7%の下落となっていた、その反動も大きかったといえる。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は続いているが、一部の国ではワクチン接種も進み、正常化への期待も強まっている。このため原油価格は上昇し、自動車などの生産も伸びてきている。これらが反映されて前年比で大きなプラスとなった。
さらに木材や銀や銅、アルミニウムなどの金属の価格が上昇してきており、食料品の原材料などの価格上昇なども反映されているとみられる。
これに対して日本の消費者物価指数の伸びは限られている。21日に発表された4月の全国消費者物価指数は、総合で前年同月比マイナス0.4%、生鮮食品を除く総合で同マイナス0.1%、生鮮食品及びエネルギーを除く総合で同マイナス0.2%となった
これは個人消費の低迷もあり、企業もなかなか原材料の価格上昇分を製品の価格に転嫁できず、いわゆる企業努力によって製品価格が抑えられている面もある。
また、携帯電話料金の引き下げといった特殊な要因もあって消費者物価指数は大きく上昇できずにいる。
これに対して、米国では4月の消費者物価指数が前年比で4.2%もの上昇となって市場参加者を驚かせた。これについてFRB関係者は一時的な動きに過ぎないとしている。さすがに4%以上がそうそう続くことは考えづらいものの、2%を超えて推移してくる可能性はあろう。
ちなみに米国労働省が発表した4月生産者物価指数(PPI)は前年比では6.2%の上昇となっていた。少なくとも2010年来で最大となった。
日本でも消費者物価はさておき、企業物価指数で見る限り、2%を大きく超えてきている。
日銀の物価目標は日銀が集計している国内企業物価指数ではなく、総務省が集計している消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)である。現状はこの消費者物価指数が日銀が目標と掲げる2%までは距離がある。
現在のように前年比で物価が上がりやすい環境にあっても消費者物価指数が低迷しているというのは、本当にデフレ圧力が強いためという単純な理解で良いのだろうか。
視点を消費者物価指数ではなく国内企業物価指数に移せば、2%など軽くクリアしているのだが。
消費者物価指数が低迷しているのはどうしてなのか。これは日銀の金融緩和が足りなかったためなのか。それよりも別な要因が反映されていないのか。このあたりを突き詰めないと、日銀の物価目標が消費者物価指数の2%で果たして適切なものであるのか、という疑問も当然出てこよう。