HSPと不安障害は似ている?チェックリストや不安障害にならないための対処法を紹介
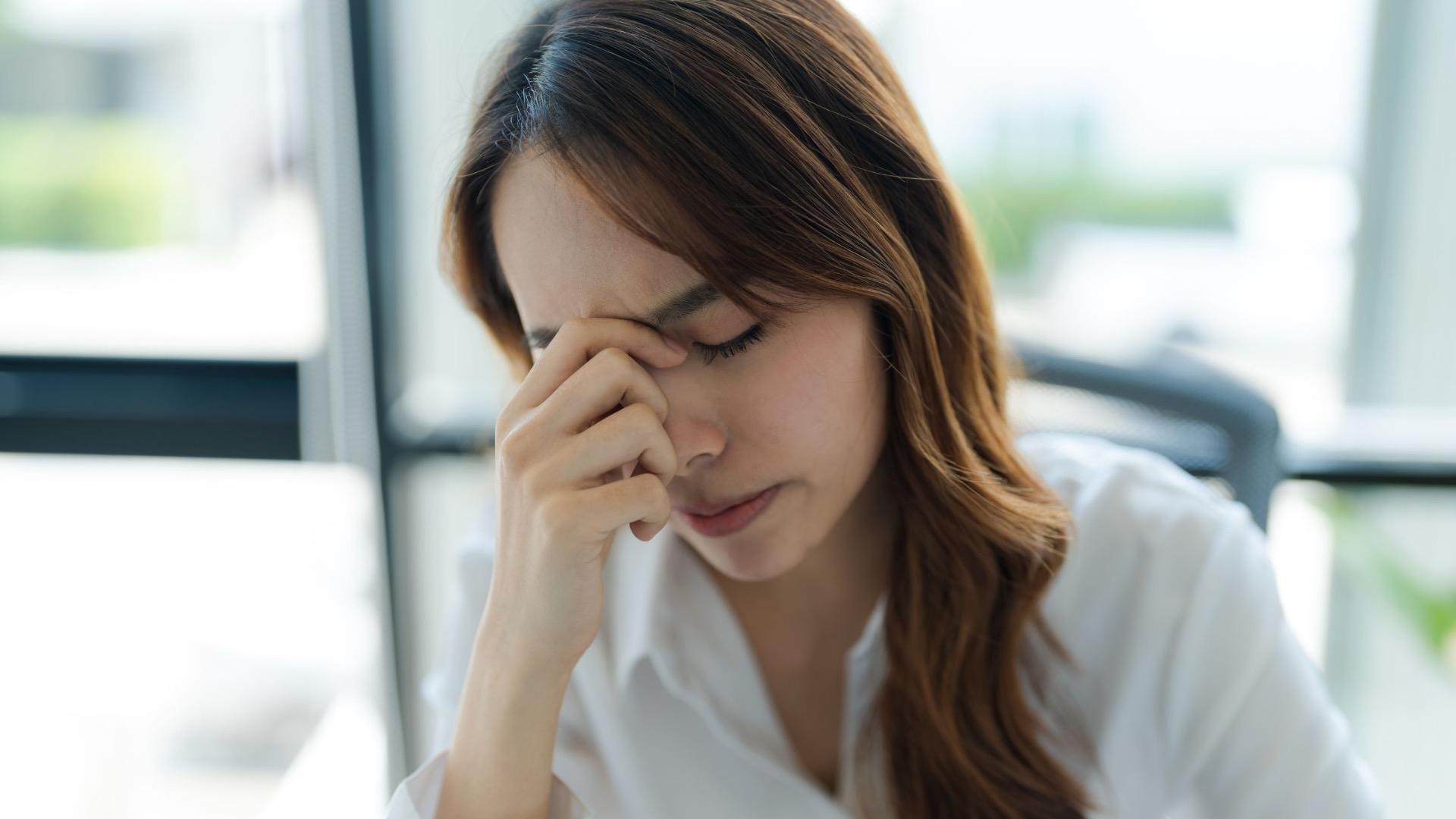
こんにちは、精神科医しょうです。
「些細なことで不安になってしまう」「心配事が頭から離れない」「心身が疲れやすい」というような不調に悩んでいませんか?
外部からの刺激に疲れやすく、生きづらさを感じているのなら、それはHSPが原因である可能性があります。
一方、HSPに似ている不安障害というこころの病気もあります。
不安障害は不安を過剰に感じやすく、特定の場面で恐怖を感じて動悸やパニックを起こしてしまうため、HSPと同じように生きづらさを感じている人もたくさんいます。
今回の記事では、HSPと不安障害のチェックリスト、HSPと不安障害の関係、HSPが不安障害にならないための対処法を紹介します。
HSPのチェックリスト

HSPとは敏感な気質を持つ人のことを指す言葉であり、音や光などの外部からの刺激のほか、目に見えない感情やエネルギーなどにも敏感に反応を示します。
下記でHSPの気質の主な特徴について紹介します。
・音や光、におい、肌触り、味覚など五感が鋭い
・外部からの刺激にストレスを感じやすい
・他人の些細な言動にも反応してしまう
・他人と数時間一緒に過ごすと疲れてしまう
・SNSやテレビなどで強い言葉を目にすると影響されてしまう
・涙もろく、感情移入しやすい
・他の人が怒っていると自分のことでなくてもストレスを感じる
・相手の表情や言葉などから感情を察して不安になることが多い
不安障害のチェックリスト
不安障害とは不安の感情が強くなりすぎてしまった結果、心身に症状が現れて日常生活に支障をきたしてしまう病気です。
下記で不安障害の特徴について紹介します。
当てはまるものがあるかチェックしてみましょう。
・いつも漠然とした不安感がある
・人と一緒に飲食すると緊張する
・人前で発言や行動することに不安を感じる
・注目を浴びることに不安を感じる
・些細なことでも過剰に心配してしまう
・恥をかいたり失敗してしまうのではないかと不安になる
・不安に押し潰されそうになる
・緊張やパニックになって目眩や動悸、息切れを起こすことがある
HSPと不安障害は似てる?

HSPと不安障害は似ている部分もありますが、根本的に異なるものです。
HSPとは過敏性と感受性の高さを持った人のことであり、先天的な気質や性格といったものに分類されます。
一方で不安障害は、何らかの原因で不安が強く出てしまうことにより、動悸や震え、パニックなどの症状が現れるこころの病気です。
HSPは常に刺激に敏感に反応してしまうのでストレスを溜め込みやすく、他人からの些細な言動にも不安になりやすいという傾向があります。
このように、HSPは他の人よりも過剰に不安を感じやすいため、不安障害と混同されることも多いです。
HSPは不安障害になりやすい?
HSPは刺激に対して反応する脳の部位「扁桃体」の機能が他の人よりも過剰になりやすく、不安や恐怖を感じやすいと言われています。
扁桃体が過剰に働いてしまうと些細なことに対しても過敏に反応してしまったり、ストレスを感じやすくなってしまいます。
そのため、HSPは不安障害やうつ病、パニック障害になる可能性が他の人よりも高いと考えられています。
HSPが不安障害にならないための対処法

規則正しい生活習慣を意識する
生活習慣を正して自律神経を整えることによって、不安障害の発症を予防することができます。
起床と就寝時間をなるべく毎日同じにして、栄養バランスの取れた食事を適量食べるようにしてください。
また、十分な睡眠時間の確保と適度な運動も大切です。
規則正しい生活を続けると体内リズムが正常になり、心も体も安定していきます。
不安になりやすい、ストレスが溜まりやすいHSPの人は、正しい生活習慣を送ることを意識しましょう。
ひとりの時間を大切にする
HSPは常に外部からの刺激に敏感に反応してしまうため、ストレスを溜め込みやすいと言われています。
人混みや集会、混雑した電車の中、騒がしい場所において大きな不安を感じる人もいるかもしれません。
なるべく誘われたとしても、大勢が集まる場所に行かないようにする、混雑する時間帯を避けるなど自分の気質に合わせた行動を取ることが大切です。
また、HSPは感受性が豊かなため他人の言動や感情にも敏感に反応します。
そのため人間関係に疲れやすく、ひとりの時間の方が落ち着くという人もいるでしょう。
HSPはひとりの時間を意識的に設けて、ゆっくりと心身を休めることが大切です。
日記をつける
HSPは繊細で内向的な人が多く、不安を抱え込みやすい傾向があります。
自分の心の内を誰かに打ち明けたり、悩みを相談したりすることがあまり得意ではなく、どちらかというと悩みを聞く側に回ってしまうことも多いのではないでしょうか。
そのようなことから不安を溜め込みやすく、大きなストレスがきっかけとなり、不安障害を発症する方も少なくありません。
繊細なHSPにおすすめなのは、自分の感情や体調を記録するために日記を書くことです。
もやもやした感情を言語化して整理することで頭の中がスッキリして、精神を安定させることができます。
まとめ

今回はHSPと不安障害のチェックリスト、HSPと不安障害の関係、不安障害にならないための対処法について紹介しました。
不安障害はどんな人にでも起こりうる心の病気ですが、繊細な感受性を持っているHSPの人は他の人よりも発症するリスクが高いので注意が必要です。
不安障害を発症しないためには、自分の時間を大切にすること、不安やストレスを軽減する方法やリラックス方法を持っておくことが大切です。
もしも不安障害に当てはまるような症状が続いている場合は、無理をせずにお近くの医療機関を受診しましょう。
私のブログのテーマは、「他人軸でなく自分軸で気楽に生きる」です。
あなたはこんな悩みをお持ちではありませんか?
「他人の顔色ばかりみてクタクタ」
「自分の意思で生きられない」
「いつも後悔ばかりでグルグル一人反省会」
そんな他人軸に悩むあなたは私のブログ(外部リンク)をチェックしてくださいね。
あなたが「自分軸で気楽に生きられるようになる」ことを応援しています♪










