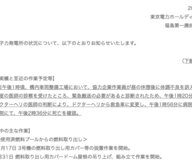トリチウム水は海に流すのが“簡単”という結論〜ALPS小委報告書を読み解く

事故収束の条件をすり替えた収束宣言
福島第一原子力発電所に林立する汚染水タンクの貯蔵水を処理して海に流すという話が、いよいよ現実味を帯びてきた。海洋放出の前提のひとつは、「廃炉作業」と国やマスメディアが呼ぶ福島第一原発の事故収束作業が40年で終わるという夢物語だ。
経済産業省資源エネルギー庁の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」(委員長・山本一良名古屋学芸大学副学長)、通称ALPS小委員会は2020年1月31日、17回目の会合を行い、提言案をとりまとめた。この案はその後、各委員とエネ庁の事務局の間でメールで意見交換を行った後、2月10日に最終の報告書として公表された。
《参考資料》多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書
結論は、トリチウム水の「海洋放出が現実的な選択肢」というものだった。
福島第一原発には2020年3月5日の時点で約123万トンの汚染水が貯蔵されている。汚染水は、2011年3月11日の東日本大震災で壊れた原子炉建屋やタービン建屋に地下水が流入し、メルトダウンした燃料デブリに触れて高濃度に汚染された冷却水と混じり合うことで、1日に約170トンずつ増えている。
本来、汚染水は2011年中に増加を抑える計画だったが、荒唐無稽な寝物語が実現できるわけもなかった。汚染水が増え続ける中、政府は目標を「汚染水全体量の抑制」から「建屋内の汚染水」が増えないことにすり替え、「事故収束宣言」を出した。この時点で汚染水問題は、福島第一原発の事故処理で最大の壁になっていた。
ALPS小委の報告書は、福島第一最大の問題に一気にケリをつけるものになっている。
報告書では、今後の処分方法について「地層注入・地下埋設」「海洋放出」「大気への水蒸気/水素放出」の3つの選択肢を示している。その上で、現実的な選択肢は「前例のある水蒸気放出及び海洋放出」だと結論づけている。地元住民からの要望が最も強かったタンクでの貯蔵継続は、そもそもの選択肢から排除された。
なぜこうなるのか。報告書の記載を順番に見ていくと、不条理が多々あることがわかる。
2013年とは大きく変わった汚染水の状況
まず第一に、ALPS小委が前提にしていた「トリチウム水タスクフォース」の結論が、実態に合っていないのではないかという点だ。
2016年6月3日にまとまったタスクフォースの報告書では、汚染水の処分方法について、地層注入、海洋放出、水蒸気放出、水素放出、地下埋設の5つを提案していた。ここに貯蔵継続が含まれていないのは、タスクフォースが始まった2013年は、タンクから300トンの高濃度汚染水が漏れたり、東電が海に汚染水が出ていることを隠ぺいしていたことが発覚するなどしたために、タンクにためておくのは高リスクという認識が生まれたからだった。
しかし当時と今では状況が大きく異なる。
2013年当時のタンクは組み立て式で、設置当初から漏えいの危険があると指摘されていたものだった。今はタンクは溶接型に置き換わり、漏えいリスクは大きく減った。タンクは周辺に堰もできていて、事故直後のように漏えいが即、海への流出にはならない。このことはALPS小委の報告書にも記載がある。
またタンクに貯蔵されている水は、2013年の頃は放射性ストロンチウムが高濃度に含まれた汚染水だったが、多核種除去設備(通称、ALPS)での処理が進み、現在はトリチウム以外はとても低レベルになった。政府と東電は「ALPS処理水」と呼んで、低リスクをアピールしている。
つまり、タスクフォースで議論を始めた頃とは前提条件が大きく変わっている。だからALPS小委の住民説明会では、貯蔵継続を望む地元住民の声が大きくなったと言える。
それでもALPS小委の報告書では、貯蔵継続を否定し、選択肢から除外した。理由のひとつは、「タンク貯蔵には、自然災害、腐食や操作ミスによる漏えいのリスクを排除できず、万が一漏えいした場合には、報道等により新たな風評への影響が発生する可能性がある」からだ。
でも考えてみてほしい。タンクからの漏えいで風評被害が発生するのなら、海に出すのはどうなのか。報告書では、「社会的な影響の観点で処分方法の優劣を比較することは難しい」としつつ、「海洋放出について、社会的影響は特に大きくなる」と懸念を示している。
それにもかかわらず、海洋放出だけが選択肢として残り、貯蔵はできないという結論の根拠は、報告書からは読みとれない。
明確な理由なしにタンク貯蔵より海洋放出が簡単と結論
おかしな点はまだある。東電はタンク貯蔵容量について、2022年夏頃に満杯になると説明している。貯蔵を続けるなら追加対策が必要になる。ALPS小委の報告書は、こうした追加措置が困難として、選択肢から除外した。
たとえば報告書では、トリチウム水を敷地外に搬送して保管することについて、「法令に準拠した移送設備」や「移送ルートとなる自治体の理解」が必要だと説明している。さらには、配管で搬送する場合にはフェンスの設置が必要、車両や船舶で搬出する場合には搬送手続きが必要、法定に準拠した移送設備が必要になるので、「大量の処理水を移送する手段の検討・準備に相当な時間を要するとともに、多岐にわたる関係者との事前調整が必要」と、必要な項目を並べている。
また敷地外にタンクのための土地を確保することについても、「自治体の理解」が必要で、「放射線による障害の防止措置を講じ、同法に基づく保安検査や核物質防護検査等を受ける必要」があると、理由を並べ、「相応の設備や多岐にわたる事前調整、認可手続きが必要であり、相当な時間を要する」から、難しいとしている。
福島第一原発を取り囲む中間貯蔵施設の予定地にタンクを建設することについては、土地は中貯のために地元に受け入れてもらったので福島第一の土地拡大は難しいと、切って捨てている。しかしエネ庁は、周辺住民から報告書に引用できるようなヒアリングをしたことはない。
とにかくタンク貯蔵を続けることについては、できない理由を並べ立てているという印象を受ける。しかしそのほとんどは法的な手続きなので、粛々と進めればいいだけだ。法的手続きを除くと、必要なのは周辺住民や関係自治体との事前協議だけになる。
以上のような理由で、タンク貯蔵の継続を否定している。
では海洋放出はどうなのか。ALPS小委の報告書では、「処分開始の時期や処分期間については(中略)関係者の意見を聴取し、政府が責任を持って決定すべき」と書いているだけだ。
つまり海に流すためには、タンク貯蔵を続ける場合のような関係者の事前協議や自治体の理解は不要ということだ。なぜこんな認識の違いが生まれるのか、理由の明示はない。
結局、タンク貯蔵に比べると海洋放出の方が簡単だと言っているにすぎない。しかも「政府が決定」すればいいので、誰の理解も必要ないと読める。
このことを、ALPS小委の終了後に、福島大学食農学類の小山良太教授に聞くと、次のように話した。
「実際、そう。東電や環境省や復興庁と調整をするよりも、あるいは今の政府の大臣を説得しないといけないので、それをやるくらいなら、弱い漁業者を納得させた方が早いという結論ですよ。簡単だって言うことなんですよ。(もし漁業者と)決裂しても(放出は)やれるから。でも環境省等とは決裂したらやれない。そういうことだと思います」
福島県漁連をはじめ、漁業関係者は海洋放出に強く反対している。2020年2月19日にいわき市で開催された経産省の廃炉・汚染水対策福島評議会で、福島県漁連の野崎哲会長は「報告書は具体的な施策を盛り込んでいない。これでは漁業者は納得できない」などと話して明確に反対をした(2020年2月20日付河北新報)。
政府は、こうした漁業者の意見を踏みつぶして海洋放出するのだろうか。
合理性のない40年廃炉を前提に海に流そうとするエネ庁
ここまできたら、廃炉の欺瞞性についても触れておきたい。ALPS小委の報告書が大前提にしている条件がひとつある。次の一文だ。
「大原則として、福島の復興と廃炉を両輪として進めていくことが重要であり、廃止措置が終了する際には、ALPS 処理水についても、廃炉作業の一環として処分を終えていることが必要である。したがって、貯蔵継続は廃止措置終了までの期間内で検討することが適当である。」
もちろん、そうなれば言うことはないが、現実には、中長期ロードマップの計画は年々、後ろ倒しになっている。ちなみに東電は2019年1月に、2号機の原子炉建屋の地下から汚染水を採取し、α核種等の分析をすると説明していたが、1年以上経ってもできていない。分析すべき汚染水は今でも福島第一の敷地にあると、会見で説明があった。数グラムの水の分析に1年かかるのに、どうやって燃料デブリを取り出すための性状分析をするのだろうか。
ALPS小委報告書では、タンクのトリチウム水の処分を廃止措置終了までに終えるとしているが、廃止措置計画はまだ影も形も見えない。そもそも廃止措置計画が策定できるのかどうかもわからない。計画策定のためには核物質の処分場所を明記する必要があるが、燃料デブリをどこに持っていくというのだろう。
廃止措置計画も策定できず、廃止措置の終了形を描くことができないのなら、汚染水の処分を急いで決めることはないのではないか。報告書にも「処分の開始時期が遅ければ遅い方が世の中の関心が小さくなり報道量も減り、風評への影響は少なくなる」と書かれているのだ。
それにもかかわらず、タンクの汚染水の処分だけを先に進めようとしているのはなぜなのか。
ALPS小委終了後、事務方の責任者である経産省の福島第一原発事故廃炉・汚染水対策官の奥田修司氏は記者レクの中で以下のように答えた。
──廃止措置は30~40年というが、委員の中には更地にするという共通認識があった。一方で政府は更地にするか決めていない。なぜトリチウム水だけを先に処分しなければいけないのか、報告書には書かれていない。
奥田対策官
廃止措置終了時にはすべてが処分されていないといけないが、処分されている状態がどういうものかはこれから検討しなければいけない。処分しなければいけないのはすべて同じだが、処分のやり方や処分の方法を見定めるコトができるものは検討を進めるべきと思う。とくに処理水の問題は、廃炉が終わるまでに全部を片付けるということかもしれないが、今後廃炉作業の進捗に影響してくる可能性もあるので、早く検討していると認識している。
──それなら、廃止措置計画が出てからやっても遅くないのではないか。廃止措置計画の中でこれも決めることは考えられないのか。
奥田対策官
先送りして廃止措置計画が出てからということもあるかもしれないが、問題を先送りする必要は無いし、早く検討できるものは検討していく方がいいと言うことだと思う。
福島県浜通りの将来像に大きな影響を及ぼす廃止措置計画や廃炉の定義の明確化を先送りにしながら、なぜトリチウム水の処分を急ぐのかについて、説明はなかった。
3年間のALPS小委の議論は、エネ庁の責任回避か?
そして報告書の結論から感じたのは、これならALPS小委をやらなくてもよかったのではないか、ということだ。この内容なら、ALPS小委が始まった2016年11月にエネ庁の官僚が書けたのではないかと思う。実のところ、ALPS小委が終わった後、何人かの委員も同じ感想を口にしていた。
ではエネ庁が単独で方針を出す場合と、審議会を経る場合で何が違うのか。
最大の違いは、見かけ上の責任所在だろう。この3年間のALPS小委は、処分方針を決めたのはエネ庁ではありませんよという様式を形作るためだったのではないかと考えると腑に落ちる。
こうした審議会の報告書は基本的に事務局が作文をして、委員会の了承を得る。だから全体構成を委員会で作り上げることはほぼ、ない。委員会は、上がってきた報告書の文言を少し修正するくらいが限度で、構成をひっくり返すことはほぼないと言っていい。
今回の場合も、エネ庁が昨年12月の会合で提示したとりまとめ案に対して委員から批判が相次いだ際、事務局を担うエネ庁電力・ガス事業部原子力発電所事故収束対応室の奥田修司廃炉・汚染水対策官は記者レクの際に、「ゼロベースで(委員会で)相談していきたい」と発言していた。しかし、その後の会合で出てきた構成にほとんど変化はなかった。
審議会の結論が、委員より官僚の意思を反映しているところに、日本の審議会制度の問題があると改めて感じる。
梶山弘志経産相は3月17日の大臣会見で、4月6日から方針を決めるための意見聴取を始めることを発表した。梶山大臣は記者の質問に、「スケジュールありきではない」と回答している。
しかしタンクは2022年に満杯になるので、スケジュールありきではないといっても時間は限られている。東電は、何か突発的な緊急事態が起きない限り、今以上にタンクを増設する意思はない。
こうなると最大の懸念は、時間切れを理由に海洋放出を強行することだ。なにしろALPS小委の報告書は、政府が独善的に海洋放出を決定することを否定していないのだ。
残された時間の中で、政府はどこまで合理性のある説明をするのか。報告書に残されている疑問にはどう答えるのか。意思決定の経緯は公開されるのか。そもそもなぜタンク保管より海洋放出の方が合理的なのか。注意深く政府のふるまいを見ていく必要がある。