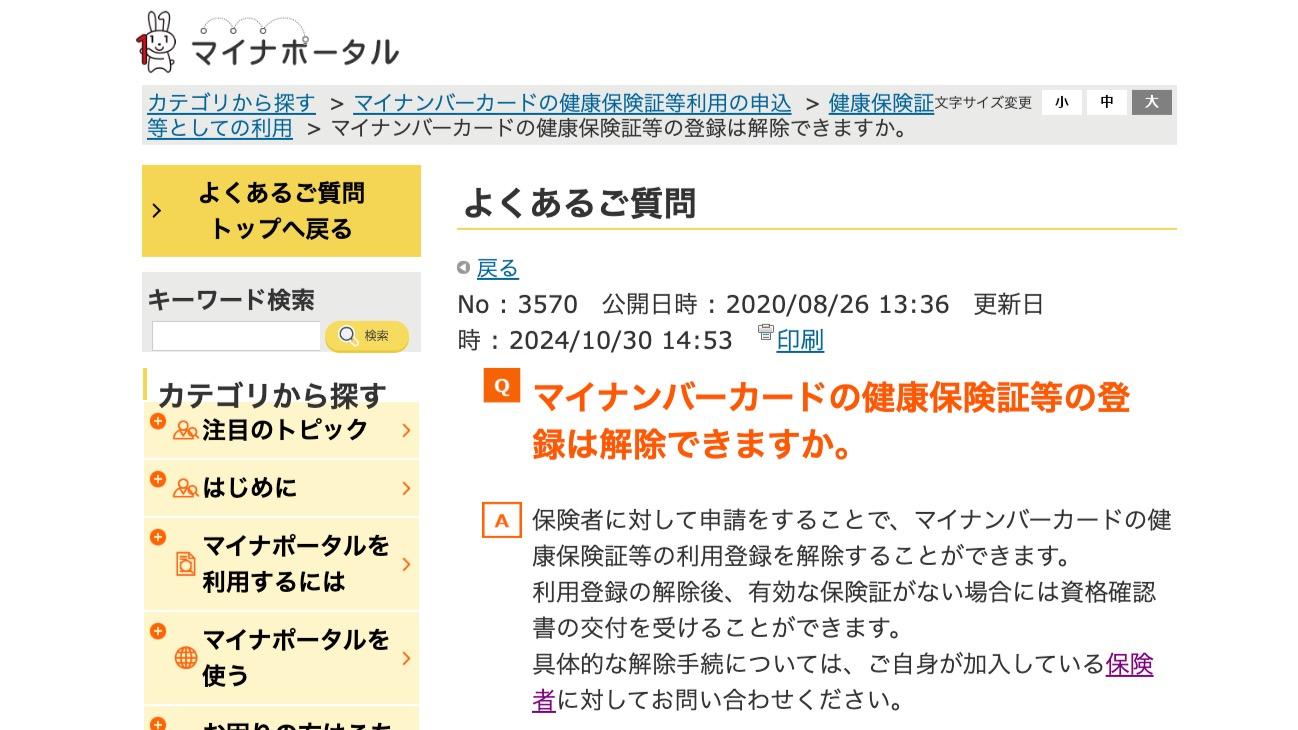【富田林市】銀座・京都の高級料亭にお届け。富田林産は最高品と評判の海老芋。西板持の畑に行ってきました

大阪府の「大阪」というキーワードの影響で、どうしても都会のイメージが強いのですが、富田林市の場合、石川から東に行けば、農園地帯が広がっています。キュウリとナスビについては、府内でもトップの生産量を誇るほどなのだとか。
そんな「大阪産(もん)」の農作物の中でも、別格なのが海老芋です。生産量こそ静岡の磐田に劣るものの、富田林の海老芋はとにかく質が良いと全国的に大評判。その結果、東京銀座や京都の高級料亭でも、富田林の海老芋が使われています。

それではまず、海老芋についておさらいしましょう。海老芋は里芋の一種ですが、大阪府農業史の資料では唐芋に分類されています。
海老芋と呼ばれているのは、歪曲した形状と縞模様が海老のように見えるからで、江戸安永年間(1772年から81年)に、京都市東山区円山公園にある「いもぼう平野屋」の初代当主・平野権太夫(ひらのごんだゆう)が名付けたと伝わります。

海老芋の特徴として、粘り気と優れた風味、ほのかな甘みがあるところがあげられます。そして煮崩れしにくいので、煮物に最適。
そのため、海老芋の代表的な料理法が「いもぼう平野屋」の名物料理でもある「芋棒」で、棒ダラといっしょに煮たものを指しています。富田林では、コロッケに使われたりしていますね。

さて、海老芋はスーパーや直売所などで知っているものの、実際に富田林でどんなふうに栽培されているのか、とても興味がわきました。
そこで、富田林市役所産業まちづくり部農とみどり推進課にお願いし、課長代理の花岡美保さんのご案内で、海老芋畑を見学する機会に恵まれました。

取材当日、市役所で花岡さんと農業振興係長の中辻裕一さんと待ち合わせて、市の車で畑に移動しました。
場所は、市役所から見て石川を越えた西板持町。石川の氾濫の影響で、東側に形成された土壌が海老芋の生産にとても適しているのだそうです。正直言って、トライアル(TRIAL)の近くに海老芋畑があるなんて想像もできなかったので、かなり驚きました。

こうして訪れたのは、辻農園の辻晃司(つじ こうじ)さんの畑です。30歳代後半の辻さんは、海老芋生産暦5・6年。現在は、海老芋生産部会の会長を務めています。
辻農園さんは、海老芋畑が全部で218アール(1アール=100平方メートル)あるそうで、ちょうど掘り起し作業の最中でした。

このあたりは、海老芋栽培に適した土壌とのことで、ポイントが補水がよく乾きやすい土壌であるとのことなのだそうです。
畑は、土手が列になって並んでいて、その土手の両横に溝があります。ここで驚きの事実がわかりました!あの海老芋の特徴的な形を作るために、土を何回にも分けて盛り上げる作業をして、人工的に栽培しているのだそうです。

具体的な栽培方法ですが、まず4月に親芋を植えた後、肥料を与え、土のうえ藁を敷いて行きます。そして6月から7月にかけて、畝に土を盛り上げて行き、あの海老の形を作っていきます。
この時期は炎天下の作業になることが多いので、「海老芋の形を決めるのは、体力勝負だ」と辻さんは語っていました。

水をあげるときには直接葉にかけるのではなく、溝に水を満たせることにより育てるとのこと。
海老芋を育てるにはさらにひと工夫があって、葉が大きく広がってしまうのですが、このままだと日光が下の方に行かないので、先端の大きな葉を手でちぎり、茎全体に日光を照らせます。そうすることで、芋が大きく育つのだそうです。これは7月から10月の作業になります。

さて、いよいよ中の海老芋を取り出します。この作業は、10月中旬から11月にかけて行われます。掘り出し作業ですが、最初に茎と葉を手とナイフを使ってカットします。その後の掘り出しには手を使いません。辻農園では、パワーショベルを使います。
パワーショベルについても一工夫。先端部分を特別に地元の業者に依頼して、海老芋を掘り出すのに最適な仕様にしています。ここで、芋を掘り出す模様を動画に撮りました。
こうしてパワーショベルを動かして、地中からひとつの芋の塊を掘り出しました。掘り出すと、巨大な塊とそれに寄生するような小さな塊が多くついていて、それを手で振り分けていきます。

辻さんによれば、海老芋には3種類あることを教えてくれました。いちばん大きなのが親(親芋)、つぎに荒子(子芋)、最後に小さな孫(孫芋)です。
この中で、もっとも高級なのが荒子で、一般の市場に出回らず、東京の豊洲市場や京都の京果(京都青果)市場に送られるとのこと。そして1席数万円単位の高級料亭のコースの中に登場します。

そして孫芋は、一般に出回っています。サバーファームのにこにこ市場や道の駅などでも販売しているとのこと。そして意外なのは親芋の使い方でした。
親芋は、育つ過程で荒子や孫に栄養を取られるらしく、筋が多くなり、芋としての価値が劣るとのこと。主に畑の栄養にしたり、場合によってはコロッケなどの加工品に使うそうです。

最後に聞いたのですが、1年間生産した畑は翌年には海老芋用に使えない(連作ができない)そうです。これは海老芋だけでなく、里芋系統の植物共通とのこと。理由は嫌地物質(いやちぶっしつ)と呼ばれている他の植物(芋類)の生育を妨害する物質を出すからだそうです。
このように連作障害を起こすことから、翌年は水田など別の用途に使い、3~5年後にようやく海老芋用に利用できるとのこと。だから毎年、海老芋畑の場所が変わるというわけです。

もし春から秋にかけて石川を渡って東に行くときに、海老芋の畑をじっくり見てみてください。土の中に隠れて外からは見えませんが、地中には、全国の料亭に出回って美食家の舌を唸らせる、富田林自慢の海老芋たちがすくすくと育っているはずです。