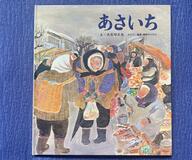【能登半島地震】漆玉アクセサリー作る姉妹、2度目の被災「輪島が前よりも素敵な場所になると信じる」

その玉の材料が何か、すぐには分からなかった。陶器かガラスだと思って持ち上げると軽い。木製の玉に漆を塗ったカラフルな「漆(うるし)玉」である。ピカピカ、つやつや、うるうる、トゥルントゥルンの質感だ。
木嶋里美さん(67)は「能登ロマン」の屋号で石川県の「輪島朝市」に25年間以上出店し、この漆玉を使ったアクセサリーを販売してきた。昨年までの作品は、2024年元日の能登半島地震後に起こった火災で全て焼失した。2月に再び作り始め、完成した作品を持って4月下旬に富山市内で開かれた復興支援バザーへ出店した。地震後、初めて姪と再会した叔母たちの目には涙が浮かんでいた。

手頃な価格の作品を手に取ってもらいたい
木嶋さんは息子2人の子育てが、ひと区切りついた32、33歳ごろから漆のアクセサリーを作り始めた。七尾市に生まれ、輪島市で暮らすようになって伝統工芸の「輪島塗」は、ぐっと身近になっていた。当初、輪島塗の特徴である沈金や蒔絵を施したものを作っていたが、きらびやかな装飾を施すと高額になる。「軽くて丈夫、変色しにくいという漆の利点を生かしながらも手頃な価格の作品を手に取ってもらいたい」と考えるうち、多様な漆玉を作って、それらをつないでアクセサリーにするアイデアが浮かんだ。
漆玉はハナミズキの木板をくり抜いて作った丸い玉に下地漆を塗った後、色漆を重ね塗りする。回数は、色やその時の湿度、温度によって変わるが、大体5回から6回程度。色漆を塗り重ねることで独特のつやが増していく。5つの原色を絵の具のようにブレンドした漆を用いる。表面に花を描いたものもある。

「漆は100年たっても色が変わりません。また、美しさや耐久性だけが輪島塗の特徴ではありません。漆塗りの重箱におせち料理などを詰めるのは食べ物が長持ちするからとされ、科学的にも抗菌作用が立証されています。また、漆は身につけると魔除けになると言われています」(木嶋さん)
木嶋さんは25年ほど前から自作のアクセサリーを屋台に積んで「輪島朝市」に出店するようになった。輪島朝市は、岐阜県の「飛騨高山宮川朝市」、千葉県の「勝浦朝市」とともに、日本三大朝市の一つに数えられる。定休日は第2、第4水曜日と正月三が日のみで、午前8時から昼ごろまで輪島市中心部の「朝市通り」に新鮮な海産物や干物、野菜、民芸品などを売る露店が並ぶ。同じ時期、朝市通りに店舗を借りて常設のギャラリー「能登ロマン」での販売も始めた。
ブドウをモチーフとしたペンダントが人気
2004年には妹の高木明美さん(65)が漆玉アクセサリーの製作に加わった。高木さんは高校卒業と同時に石川県を離れ、京都市にある染色の専門学校で3年間学んだ後、職人に師事し1年間修業してからUターンし、金沢市で加賀友禅の職人に弟子入りして5年間働いた。その後、化粧品販売業に転じて20年間、事業は順調だったが「もっと別の仕事があるかもしれない」と思うようになった。輪島市に転居して姉の仕事を手伝うようになったのは40代半ばのころである。

大きさの異なる漆玉を組み合わせてブドウをモチーフとしたペンダントを考案したのは高木さんだった。同系色の濃淡の違う玉を集めたものと、同一色でまとめたものがあり、葉の形をした金属を飾るとブドウの房に見える。ストラップを取り付けてネックレスとして販売しており、房の部分を取り外してピンをつければブローチとしても使うことができる。

「ブドウをモチーフにするようになった理由は、縁起がいいから。そしてワインが好きだから」と高木さん。色彩感覚や美的センスは、染色を学ぶ過程で培われてきた。高木さんのブドウのペンダントは「能登ロマン」の人気商品となっている。
2024年4月28日、木嶋さん・高木さん姉妹は富山市岩瀬地区にある喫茶店「にしのみや」で開かれた「能登半島地震復興支援バザー」に出店した。同店を営む西宮外喜子さん(74)は叔母にあたる。「女性が頑張って立ち上がってこそ復興になる。こんな時こそ底力を出して立ち上がって」と姉妹に参加を呼び掛けた。富山県小矢部市に住むもう1人の叔母・金山君子さん(78)もやって来た。コロナ禍や能登半島地震を経て数年ぶりに再会した4人は喜びもひとしお。金山さんは涙ぐんで姉妹の肩を抱き「顔を見てホッとした」と話し、ブドウのペンダントを購入した。

2024年元日は震えながら一晩過ごした
筆者も木嶋さんのアクセサリーが欲しくなり、ピアスを選びながら輪島朝市と、これまでの活動について聞いた。
「輪島朝市やギャラリーで対面販売をしながら、出店者や観光客と語り合う時間は貴重でした。好きなものを作って並べ、買ってもらえたことは何にも代えがたい喜びです。毎日顔を合わせる出店者に、悩みや愚痴を聞いてもらうこともよくありました。何度も足を運んでくれるお客さんが徐々に増え、観光客も増えて賑やかになっていきました」(木嶋さん)
2024年元日に能登半島地震が起こった時、木嶋さんは自宅にいた。海岸から100メートルほどしか離れていないため、「大津波が来る」との警報を聞いて高台へ避難し、津波の危機が去った後は輪島中学校へ向かった。体育館はガラスが全て割れ、「低体温症になりそう」とガタガタ震えながら一晩過ごした。
1月2日、家へ戻ると食器が割れ、いろいろなものが散らばって足の踏み場もない状態だった。築35年の家屋は倒壊を免れたが、水道管が破裂するなどライフラインはストップ。寒さを凌ぐために数日間、車中泊を続けた。飼っていた2匹の猫は行方不明になり、数日後に戻ってきた。今でも大きな音がすると、どこかに逃げ隠れてしまうそうだ。
「わが家は朝市通りから直線距離で50メートルほどです。風が強かったら延焼していたかもしれません。輪島朝市で世話になった方が何人も亡くなりました。1月中は余震で睡眠が妨げられ、いつもびくびくしていました。いまだに雨風などで家が揺れると怖くなります。台湾や国内で頻発する地震の報道からは目を背けてしまいました」(木嶋さん)
2007年の地震ではギャラリーが損壊
木嶋さんらが被災したのは今回で2度目である。2007年3月の能登半島地震ではギャラリー「能登ロマン」の建物が損壊し、店頭販売から撤退した。アクセサリー販売を屋台だけで続けていたところ、2024年元日の能登半島地震でアクセサリー数百点を積んだまま保管してあった屋台が焼失。その後、漆玉アクセサリーは全て灰になった。

被災した直後の1月中は落ち着かず、倒壊を免れた自宅兼作業場に残された漆玉を集めてアクセサリー作りを始めたのは2月に入ってからである。漆玉は身につけてもかぶれないように時間をかけて乾燥させるので、完成までは3カ月以上かかる。能登半島地震発生後に作った漆玉アクセサリーを初めてお披露目できたタイミングが、叔母が営む「にしのみや」で開かれた復興支援バザーだった。
高木さんは「いまだに寝ていると地の底から、何か地響きのようなものを感じる気がする」と話す。ライフラインが復旧して自宅で生活し、仕事を再開できたのならば客観的には「日常を取り戻した」と思ってしまうが、そうではないようだ。
「2007年の地震の後は復興が早かったと思います。支援の手がいろいろとあり、1、2カ月で元に戻りました。今回、輪島市内を見渡して復興が進んでいるとはとても思えません。私たちは、やっと仕事を始め、先のことを考えられるようになったところです」(高木さん)
現在は出張販売とオンラインショッピングのみである。過去に漆玉アクセサリーを買ってくれた人が会いに来てくれたり、注文とともにメールや電話でエールを送ってくれたりしている。それでも、ホームである輪島朝市で対面販売する日が戻ることを願ってやまない。
なぜなら木嶋さんと高木さんは輪島朝市を特別な場所と思っているからだ。本来、朝市は水揚げした魚を一夜干しにして持ってきたり、畑で収穫した野菜を売ったりするなど、輪島で農業・漁業を営む人が地産地消を目的に「おいしいものを皆に食べてもらいたい」と集う場だった。生産者の生活が元に戻ってこそ朝市の復興だといえる。
「富山の方に励まされました」
「復興支援バザーでは叔母をはじめ、富山の方に励まされました。輪島の街と輪島朝市が前よりも素敵に、良い場所になると信じて今、いろんな場所で(漆玉アクセサリーを)販売しています」(木嶋さん)
「漆玉アクセサリーの金具が壊れたら修繕しますので持ってきてください」と木嶋さんと高木さんは声をそろえる。色褪せぬ漆だからこそ、買ってくれた人との縁は続いていく。地震発生から4カ月。姉妹は輪島朝市で屋台を並べた仲間や常連客との再会を切に願い、出張販売に忙しい日々を送る。



※2024年3月24日から金沢市内に避難している輪島朝市の出店者らが同市金石港で「出張輪島朝市 in 金石」を始め、「能登ロマン」も参加している。公式ホームページは次の通り。
※クレジットに撮影・提供の記載がない写真は筆者撮影。
※輪島朝市については次のような記事も書いています。
【能登半島地震】「こうてくだー。ぶりと かにと たこと いか」 絵本『あさいち』でよみがえる輪島朝市
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/318d0ab7afc6314d35fa521ce496532e1e6ea347