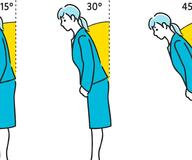新聞はHPVワクチンをどう報じたか
いま「ワクチン」というと新型コロナウィルス感染症のワクチンがまず頭に浮かぶが、もう1つ、今話題になっているワクチンが、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウィルス(HPV)への感染を防ぐHPVワクチンだ。2008年のWHOの報告によると、子宮頸がんは全世界で年間約50万人に発生し、約27万人が死亡しているとされる。
WHO (2008) “Cervical cancer, human papillomavirus (HPV), and HPV vaccines: Key points for policy-makers and health professionals.”
その主な原因はHPVの感染であり、有効な予防方法としてHPVワクチンの接種がある。世界の多くの国で接種が行われており、日本でも行っていないわけではないが、政府が積極的勧奨を行っていないこともあり、接種率はきわめて低い。
そのきっかけとなったのが副反応問題だ。HPVワクチンは2010年度から接種の公費助成が行われ、2013年4月に定期接種が始まったが、副反応を訴える人々の声を受け、同年6月には積極的勧奨が中止された。公費助成時点の対象だった1994~1999年度生まれの女子のHPVワクチン接種率が70%程度ほどであったのに対し、2000年度以降生まれの女子では接種率が激減し、2002年度以降生まれの女子では1%未満へと激減した。
公益社団法人日本産婦人科学会「研修ノート No106 思春期のケア 3. 思春期に接種するべきワクチン(5)HPV ワクチン」
接種激減の影響は大きい。自民党の「HPVワクチンの積極的勧奨再開を目指す議員連盟」が田村厚生労働大臣と加藤内閣官房長官に「年間1万人以上の女性が子宮頸がんに罹患し、3000人近くの命が失われている現状は看過できず、1日も早いHPVワクチンの積極的接種勧奨再開が望まれる」との要望書を提出した。加えて今年10月までに再開しなければ定期接種の最終学年である高校1年生分に確保したワクチンを使い切れず廃棄せざるを得なくなる。今後のワクチン入手への影響も懸念される。
「「年間3千人近くの命が失われている現状、看過できない」HPVワクチンの積極的勧奨の再開、厚労相らに申し入れ」
Yahoo!ニュース2021年8月30日
こうした一連の流れは副反応の被害を訴えた女性たちの声が大きなうねりとなった結果であるわけだが、併せてマスメディアが「反ワクチンキャンペーン」を行ったからだ、とする批判がある。この問題について下の2019年の記事では、厚労省の担当官だった官僚が「なぜ積極的勧奨を中止したまま6年以上も引っ張っているんですか?」とのバズフィード岩永直子記者の問いに対して「今となっては、マスコミの方からそのように言われてしまうのですね」という皮肉たっぷりの回答をしている。このような状況を作ったのはマスメディアではないか、というわけだ。
「HPVワクチン 厚労省はいつ積極的勧奨を再開するのですか?」
Buzzfeed News 2019年7月26日
しかし、マスメディア側にはあまりそうした「自覚」はないようだ。2021年8月に一部で話題となり批判を浴びた中日新聞記者のツイート(現在は削除)も、ワクチンへの不信を解消するのはマスメディアの責任ではないという趣旨の発言をしている(元ツイートは削除されたがご本人がスクリーンショットを別途ツイートしている)。
こうした見方は適切なのか。マスメディアの報道が万能でないことはもとより当然だが、そもそもマスメディアはこの問題をどのくらい、どのように報じてきたのか。というわけで例によって大学で契約している新聞の記事データベースをざっと見てみることにした。いつもの朝日新聞に加えて、せっかくなので今回は今井記者が所属する中日新聞と、バズフィード岩永記者の出身である読売新聞もやってみる。
まずは朝日新聞。記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」で「子宮頸がんワクチン」に関する記事を検索した結果、2013年1月から2021年8月までの間に235件の記事が記録されている。年ごとの記事件数は以下の通りだ。
2013年 60件
2014年 34件
2015年 72件
2016年 45件
2017年 14件
2018年 2件
2019年 4件
2020年 0件
2021年(8月まで)4件
これらのうち2017年までの記事のほとんどはワクチン接種に伴う副反応やそれに対する不安の声、その後被害者らが起こした訴訟に関するものだった。また、2015年12月に名古屋市が「接種と副反応の関連は確認できなかった」と発表して批判を浴び、2016年6月にこれを撤回し「統計学的な分析は困難」として因果関係に関する判断を避けた件では、データベースでみる限り当初の発表を報じていないようで、翌年の撤回のみを報じている。
しかし2014年にWHOが「安全性を再確認」したと報告、2015年には欧州医薬品庁がHPVワクチンは複合性局所疼痛症候群(CRPS)及び体位性頻脈症候群(POTS)を引き起こすことはないと発表、2017年にはHPVワクチンの安全性を発信してきた医師でジャーナリストの村中璃子氏が英科学誌「Nature」などが主催する「John Maddox賞」を受賞、2018年には英科学誌Scientific ReportsがHPVワクチン接種後に脳の異常などを確認したとする東京医科大などのチームの論文を「研究方法が不適切」として撤回するなど、ワクチンの効果などに関する肯定的な評価が出てくるにつれ、記事数が激減していく。海外でのこうした流れを朝日新聞は報じていない。
The European Medicines Agency (2015). “Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS.” European Medicines Agency Press release.
Springer Nature Group (2017). “Women’s health champion, Dr Riko Muranaka, awarded the 2017 John Maddox Prize for Standing up for Science.”
The Publisher (2018). “Retraction Note: Murine hypothalamic destruction with vascular cell apoptosis subsequent to combined administration of human papilloma virus vaccine and pertussis toxin.” Scientific Reports 8, 46971.
その後記事数はさらに減って2020年にはとうとうゼロとなったが、2021年に入って、ワクチンの効果や接種が進まないことの問題などを取り上げるなど、論調が変わってきているようにみえる。新型コロナウィルス感染症のワクチンが関心事となった世論を受けて「仕切り直し」をしたのだろうか。しかしそれまでの報道に関する検証やふりかえりの姿勢はあまりみられなかった。
次いで中日新聞。同じく2013年1月から2021年8月までで計93件。「中日新聞・東京新聞記事データベース」となっているが、中日新聞の記事のみで検索した。記事数自体は朝日より少なく、2016年以降記事数が減っている点は同様だが、さすが地元というべきか、名古屋市の調査に関しては当初の「接種と副反応の関連は確認できなかった」との発表も報じている。また朝日新聞より早く、少なくとも2018年以降は記事数もやや増加し、内容もワクチンの効果や接種が進まないことの問題などを取り上げるなど、論調が変わっている。
2013 13件
2014 11件
2015 33件
2016 14件
2017 3件
2018 3件
2019 8件
2020 7件
2021(8月まで)1件
最後に読売新聞「ヨミダス歴史館」。これも2013年1月から2021年8月までで計212件。2013年当時は朝日新聞に匹敵する記事件数で、内容も副反応やその後の勧奨中止の影響などを報じたものがほとんどを占める。とはいえその中に副反応を「痛み」と表現し、「継続治療で「改善」62%」といった記事(2013年12月18日)がみられ、その後も「再開要望」を報じるなど、ワクチン接種に前向きな論調の記事が散見される。2018年以降は前向きな記事がほとんどを占めるようになった。
2013 60件
2014 25件
2015 52件
2016 41件
2017 9件
2018 14件
2019 3件
2020 4件
2021(8月まで)4件
ざっくりまとめるとこうなる。
- 2013年に副反応問題が注目を集めた際は3紙ともこれを数多く報じており、全体としてワクチン接種に対する否定的な印象を読者に抱かせるものだった。
- しかし2010年代半ば以降、3紙とも記事数が激減している。
- 2018年以降、中日、読売両紙においてワクチン接種に前向きな論調の記事が増えているのに対し、朝日は2020年に0件となるなど記事数がさらに減少しており、接種に前向きな姿勢は弱めとなっている。
- 2013~2021年全体を通してみると、3紙とも接種に前向きな論調の記事の数は否定的な論調の記事の数を大きく下回っている。
もちろんこれはほんの片手間のなんちゃって調査なので、これだけで新聞各社の報道姿勢を論じるのは乱暴だが、現在の状況に至るおおまかな流れをかいまみることはできるだろう。いわゆるマスメディアのアジェンダ設定機能を考えれば、少なくとも2013年の定期接種開始直後に積極勧奨中止になった経緯は、これら3紙を含むマスメディアの報道が世論形成に少なからぬ影響を及ぼしたものと考えてよさそうだ。
またその後さまざまな検証などによって、ワクチンのメリットがリスクを上回ることが改めて示されるようになった後、各紙の論調は変わっていくが、それ以前の記事に対する検証やふりかえりなどはみられない。こうした一連の流れを「反ワクチンキャンペーン」とまで呼ぶのはやや乱暴かとは思うが、記事数などからみても、子宮頸がん予防のためのワクチン啓発の姿勢がもっとあっても罰は当たらないだろう。
むろん報道姿勢がいずれも同じというわけではなく、3紙の中では朝日新聞が最も否定的な論調が強いという印象を受けた。被害者や弱者に寄り添う姿勢はマスメディアとして何の不思議もないが、一方で報道内容を検証していく姿勢や、報道の影響やそれによる別の健康被害に対する視点が欠けていたのではないかという批判は甘受すべきではないかと思う。
厚生労働省研究班による全国疫学調査では、HPVワクチンを接種していない者の中にも接種後の症状として報告されたのと同様の多様な症状を訴える者が一定数存在すると報告されており、これまで副反応とワクチン接種との因果関係を科学的・疫学的に証明した報告はない。いうまでもないがこのことは被害を訴える人々の「経験」や「尊厳」を否定するものではない。しかし、接種者が少ないことにより現実に生じつつある健康被害を座視しているわけにもいかないだろう。接種の積極勧奨を早期に再開すべきだと思う。
新型コロナウィルスワクチンに対しても、不信感を持つ人は少なからずいるように見受けられる。マスメディアの力だけで信頼回復は無理、という見方自体はおそらくまちがってはいない。医療関係者、及び(特に)政府がこれまでの姿勢を改め、さらなる努力をすべきであるというのも当然だ。ならばマスメディアもまた、その社会的責務を果たすべく、力を合わせていくべきときではないだろうか。