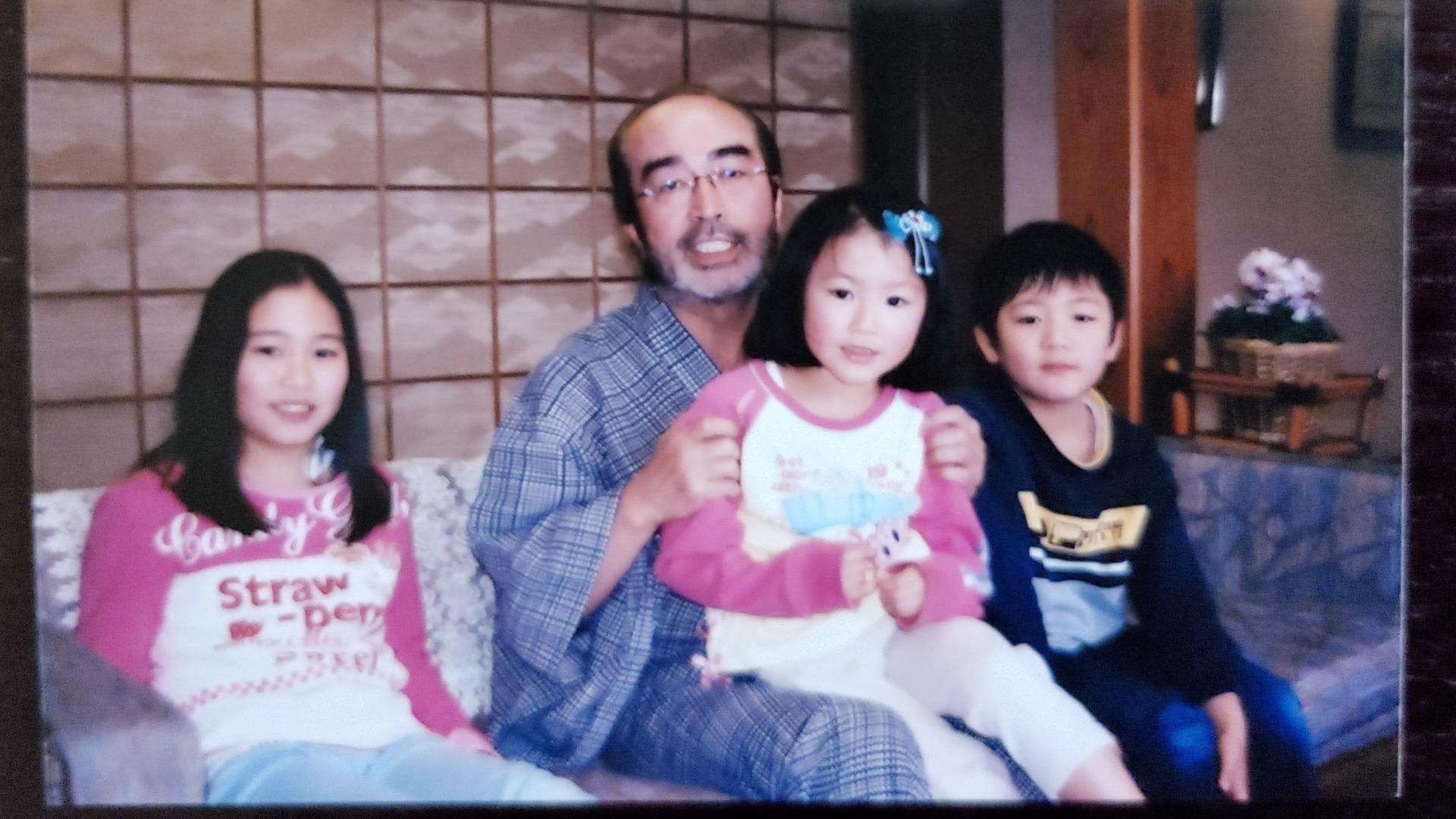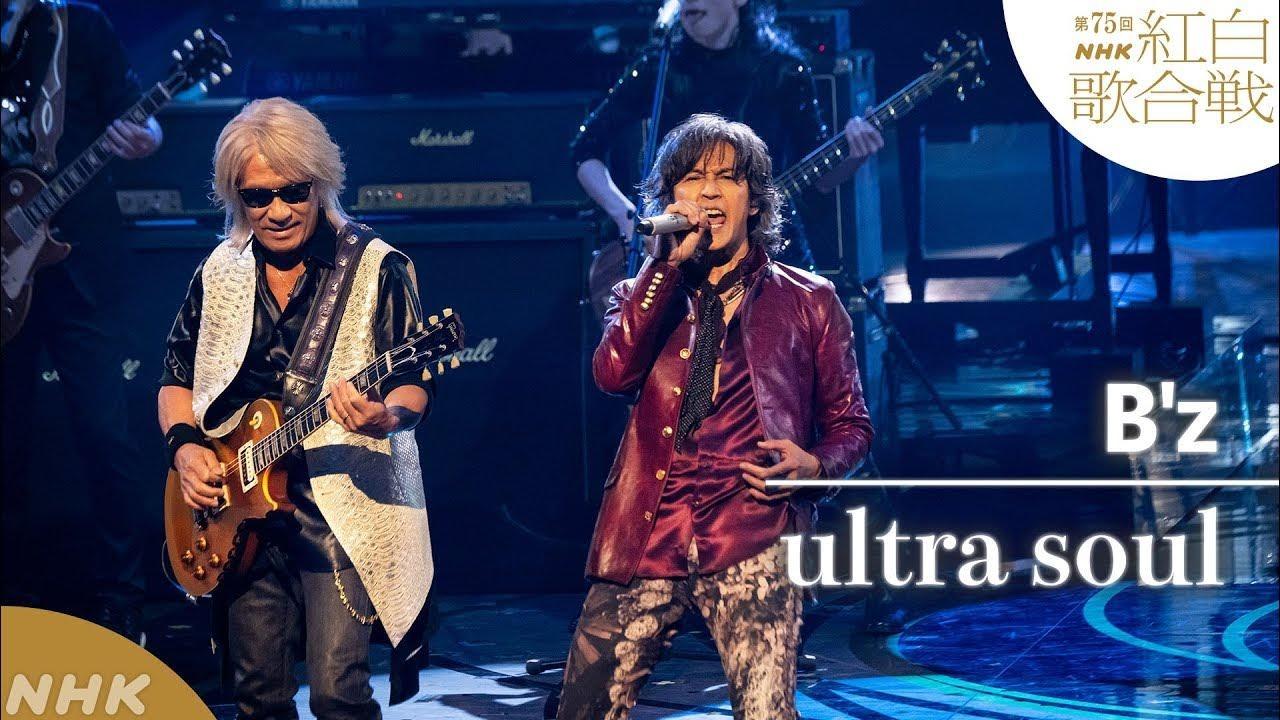【京都市】中京区 『本能寺大寶殿宝物館』にて幻の名刀「薬研藤四郎」復元刀などの特別展で歴史を学ぶ

『本能寺(ほんのうじ)』というお寺さんが京都の繁華街にあることをご存知でしょうか?幼い頃から習い物などで『本能寺』さんの庭を通らせていただいてました。

京都人だけでなく日本人にとって『本能寺の変』は有名ですね。『本能寺の変』とは、天正10年6月2日(1582年6月21日)早朝、京都本能寺に滞在中の織田信長を家臣明智光秀が突如謀反を起こして襲撃した事件を言います。

『本能寺の変』は有名な話ですが、それ以外でこの場所が、歴史的にどういった役割を果たしてきたのかを学べるイベントが開催されています。

『本能寺』とは、「日蓮」(にちれん)大聖人の教えを広める「法華宗本門流」(ほっけしゅの大本山のひとつです。山号はなく、本尊は本門八品上行所伝の南無妙法蓮華経です。

『本能寺』は、2020年大河ドラマで脚光を浴び、人気を博した明智光秀が起こした日本史上で最も有名な謀反劇の舞台となった場所と言われています。

「本能寺大寶殿宝物館」では、2022年4月16日から9月25日まで、特別展『幻の名刀「薬研藤四郎」復元刀と大寶殿宝物館』が行われています。
先日行われた『高津商会』のTV収録でご縁をいただいたのをキッカケに「本能寺」さんをご案内頂きました。
『本能寺の変』で命を落とした織田信長は、焼け落ちる御殿の中で、2振の日本刀と運命を共にしたそうです。1振は「実休光忠」(じっきゅうみつただ)、もう1振が「薬研藤四郎」(やげんとうしろう)。

三脚の蛙で知られている「三足の蛙」や織田信長ゆかりの宝物、信長所有の刀などが所狭しと展示されています。

展示室前には、甲冑と写真撮影できるパネルが出迎えてくれました。

注意書きがあるほど、大人気だということがわかりますね!

「御本尊御曼荼羅」をはじめとする宗教的遺物や檀信徒の豪商・茶屋家寄進の「大明万暦年製景徳鎮窯大瓶」、狩野直信による「六曲一双 唐人物図扇面貼交屏風」、「建盞天目茶碗」など織田信長所蔵の茶道具類や書状など歴史を再確認するものが多く、見所満載!

展示品は写真撮影不可ですが、レプリカは入り口に飾られており写真撮影可能でした!
織田信長に危険を知らせたという唐銅香炉「三足の蛙」の名品は、果たしてどうやって鳴いて知らせたのか…実際のものを見ると納得です。蛙が鳴く→ゲロゲロ→2ゲロ→逃げろ!ということだそうです。

実際の展示物を見せてもらいながら、説明を聞くとより理解が深まります。

『本能寺』は、1415年(応永22年)に日隆聖人が油小路高辻(現・仏光寺付近)に建立した本応寺が前身です。本来の『本能寺の変』が起こったのは、今ある『本能寺』ではありません。ただ、数々の出来事を経て残ったものが実際に目の前で見れるのがこの展示会です。
復元薬研藤四郎を作った刀匠の河内一平さんらの魂も感じられます。
宝物館以外にも『本能寺』には多くの見所があります。①「総門と日蓮聖人(にちれんしょうにん)の像」②「登録有形文化財の本堂」③「塔頭寺院」④「織田信長公の供養塔」⑤「おおいちょう」などなど…
この辺りは日本三大祭りの一つである『祇園祭』が行われる場所の一つでもあります。地下鉄「京都市役所前」駅から降りて1分の場所にある『本能寺』さんで歴史を再認識するのも楽しいですね!
本能寺
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町522
電話 075-231-5335