折り紙で作った三越伊勢丹ショッピングバッグが凄い ー『シン・ゴジラ』にも関わった大学教授とのコラボ

三越伊勢丹グループでは、クリスマスキャンペーンとして、折り紙とショッピングバッグのコラボレーションが展開されています。
「MAKE it HAPPY!」
ひと手間加えることで、想いを伝える。
をキーワードに、折り紙のように折ることで形を変えるショッピングバッグが話題を集めています。

そこで、このキャンペーンの企画・制作を担当した、株式会社日本デザインセンター(以下NDC)に取材しました。
なぜ折り紙をショッピングバッグに?
企画をスタートした経緯は、2017年のディレクションテーマ「MAKE」(つくることで人とつながる)をベースに、三越伊勢丹ならではのクリスマスキャンペーンができないか、と考えたことが発端だそうです。そしてキャンペーンの主役として取り上げることになったのが、ショッピングバッグでした。
「お客さまに直接手渡すことができるショッピングバッグは、百貨店ならではの『コミュニケーションツール』であり、三越伊勢丹独自の『ファッションアイテム』でもあります。特に三越と伊勢丹はともに呉服業から始まったという歴史があり、ショッピングバッグをファッションとしても大切にしています。通常のショッピングバッグも、伊勢丹はスコットランド・タータン協会にも正式登録されているオリジナルのタータン柄、三越は人間国宝の森口邦彦氏が友禅の表現技法を用いてデザインした柄を使用しています」(NDC)
この2017年のテーマを軸に、ショッピングバッグにどんな新しい魅力を付加するか? というところがなかなか難しい課題だったそうです。
ただでさえ、三越伊勢丹が普段からこだわり抜いているショッピングバッグ。これまでのクリスマスキャンペーンでも、アーティスト(クラウス・ハーパニエミ氏、ミロコマチコ氏)とコラボレーションをしたり、ドキュメンタリー写真(北欧のサーミ民族や動物)を起用したりと、いろいろな手法で展開しています。
「そんな中、行き着いたのが、『構造物としてショッピングバッグを捉える』という考え方。折ることで変容し、新たな構造物としての表情を見せるバッグがあったら面白いのでは? という発想です。折るという行為は、日本の『折り紙』(遊び心)や、『折形』(礼の心)の文化にも通じるものです。そこで今回は、『折る=楽しみながら手を動かし、相手への想いを込める行為の象徴』と捉え、お客さま自身がひと手間を加えることで完成する『折るショッピングバッグ』をメインに展開することになりました」(NDC)
折り紙研究者、筑波大学三谷教授とのコラボ
そこで、折り紙の研究者でもある、筑波大学の三谷純教授とコラボすることになります。
日本デザインセンターによると、「三谷先生の作品は、切ったり貼ったりすることなく『折る』という行為だけで紙の未知の可能性を感じることができて、(先生の本などを見ると)『折っただけで、これができるの!?』という驚きがありました」 といいます。
もしも先生と一緒に紙袋を折ったら、どんなものができるのだろう? と思ったのがきっかけだったそう。
「紙袋を折るというのは先生も初めてで、いろいろな規制がある中で試行錯誤してくださいました。先生と制作スタッフ、クライアントが集まって『ショッピングバッグを折ってみる会』を開いたりもしました。私たちは手で折って考えることしかできないのですが、先生はコンピューターグラフィックスを使い、想像もできない折り方をいくつか作成していただきました。先生の作品に、『ULTIMATE(究極の)』と名前をつけたのはそのためです」(NDC)

また、一般のお客さまが楽しんで折ることができるように、簡単な折り方にしなければいけないところが大変だったそうです。また、素材が平面の紙ではなく、立体物のショッピングバッグという点も難しいところだったとのこと。
現在公開されている4つの折り方は、このキャンペーンを担当したアートディレクター2名が試行錯誤しながら考案したものだそうです。「デザイン性は損なわないよう気をつけながら折り線を付けたり、底面には折り方解説を載せたり、誰もが楽しんで折れるように工夫しています」(NDC)。
このショッピングバッグの魅力はハッシュタグ「#oruorubag」で検索すると一目瞭然。日本デザインセンターによると、例年以上に、Instagramでの拡散を意識し、#(ハッシュタグ)をつけて投稿してもらいやすいように、語感や覚えやすさも考慮してこのネーミングになった、とのこと。「oruoru」(折る折る)と2回繰り返すことで、折る行為を感じることができるように、という狙いもあるのだといいます。
これまでに届いた声には、「バッグがかわいいからまた買い物に行きたい」「これ、商品を買ったら無料でもらえるの!? びっくり!」「全部集めたい」など、魅力が幅広い客層に伝わっている様子がうかがえます。また、「バッグの柄には、カラフルでインパクトのあるアフリカのテキスタイルを採用したのですが、意外に60〜70代の方々にも好評なようでした」(NDC)とのコメントも。
三谷教授が通常の「折り紙」とは違った形状に取り組んだきっかけ
筑波大学の三谷純教授は、コンピューターグラフィックスの研究者ですが、世界を代表する折り紙の研究者でもあります。三谷教授の、通常の折り鶴などに代表される「折り紙」とは違った形状の作品に、インパクトを受ける者も少なくないのだそう。
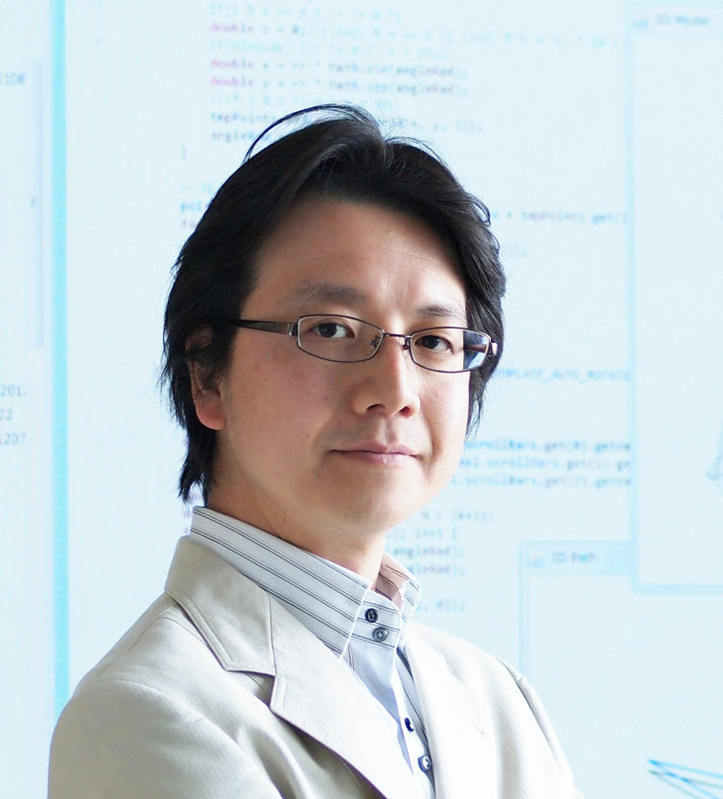
三谷教授に、このような形状を対象として取り組み始めたきっかけについて聞いてみたところ、
「折り紙で作れる形は、どれも簡単な形だという認識があったのですが、 折り紙愛好家の方々の作品を目にして、そのような考えが間違っていたと気づきました。 実に見事な作品が多く、紙の可能性の広さを感じました。 そこで、私が得意とするコンピュータによる設計で、今までの折り紙の概念とは違うような作品を作れるのではないかと思い、今の研究に取り組むことにしました」と答えてもらいました。
三谷教授の設計は、折り紙と数学(幾何学)の融合。「視覚的に分かりやすい、というのが幾何学の面白さである」と三谷教授は言います。それに加えて、理論的に導き出された形を実際に作ることができる、という点が折り紙の大きな魅力でもあるそうです。実際に作ることで、手に触れることができ、光に当たった時の綺麗な陰影を楽しむことができます(写真1)。

「1枚の紙という単純なものから、ちょっとした工夫で興味深い形ができます。 誰でも簡単に取り組めるものですから、ぜひ、子どものころに戻った気持ちで、紙を折って遊んでみてください。今、世の中に役立つ研究が求められがちですが、私が行っている研究は、すぐに役立つものではありません。それでも、数学を通して折り紙の世界を覗いて見る面白さを多くの方と共有できたらありがたいです」と話す三谷教授。
最近作った作品(写真2)を見せてもらいました。このように陰影が綺麗な作品ができると、ワクワクするのだそう。「このような楽しみを多くの人と共有できるように、設計の方法なども広く発信していきたいと思っています」(三谷教授)

先の日本デザインセンターも「世の中全体のスピードが速くなり、デジタル化が加速する時代だからこそ、三越伊勢丹は、人が生みだすぬくもりや、“リアル”が持つパワー、手ざわりのある時間を大切にしたいと考えました」と今回の取り組みについて話していました。
これまでのクリスマスキャンペーンでも三越伊勢丹グループが意識してきた「先進性」や「ファッション性」。これらに加え、今年は特に、人のあたたかさも感じることができるクリスマスキャンペーンを展開しているのだとのこと。
クリスマスシーズンということで、手作業でひと手間加えてプレゼントを贈る、というのにまさに最適な時期。こういったショッピングバッグをきっかけに、ぜひ幾何学の面白さを体験してみてはいかがでしょうか。
(この記事は、JBPressからの転載です。)










