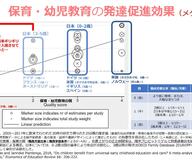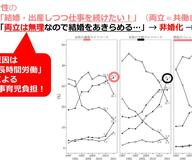コロナ後の社会――長期的にどう変わっていくのか(2)「リスク社会論」(前編)

前回では、新型コロナウイルスについて、「感染を自他ともに知覚できない場合が(近年の他の新型ウイルスに比べて)多い」ことが、世界的非常事態の一因だったのではないか、と論じた。
そして、今後「コロナ収束後の社会」で世界的非常事態を引き起こす未知の新型ウイルスもまた、(当然ながら「命にかかわる症状をもたらしうる」ことに加えて)「自他ともに感染をなかなか知覚できない」つまり「不可知性が高い」という特徴があるのではないか、と予測した。
つまり「コロナ後の社会」の行方を考えるとき、この「不可知性」という概念が鍵になるのではないかと私は考えている。
「リスク」
ここで、新型コロナウイルス(やおそらく今後脅威となる未知の新型ウイルスも)の「知覚できない」危険は、理論社会学者ウルリッヒ・ベックが提唱した「リスク」という概念と、通じるものがある。
さらに、「知覚できない」という点だけでなく、「その危険が、近代化がもたらしたグローバル化した社会環境のもとで、国境を越えてグローバルに広がりやすい」という点でも、「リスク」と(新型ウイルスの)「不可知性」は、共通している。
そこで今回からしばらくは、ベックの「リスク」概念を確認し、新型ウイルスの「不可知性」との共通点と相違点を検討することで、「不可知性」の特徴を考えてみたい[※1]。
※1:以降の記述の多くは、拙稿「リスク社会と福島原発事故後の希望」(大澤真幸編『3・11後の思想家25』左右社、2012年)に負っている。
ウルリッヒ・ベックとは
ウルリッヒ・ベック(Ulrich Beck、1944-2015年)は、「リスク社会論」や「再帰的近代化論」を提唱した、ドイツの理論社会学者である。
「社会の近代化の必然的帰結として、放射能などの空間的・時間的に無限界なリスクが社会的に生産され、近代社会への脅威となる」と警告した著書『リスク社会』を、チェルノブイリ原発事故の同年に出版した。
同書はその後20ヵ国語以上に翻訳され、これにより彼は「リスク社会論」の第一人者となった。
2011年には、福島第一原発事故を受けて設置されたドイツ連邦政府の「安全なエネルギー供給のための倫理委員会」の委員も務めた。
「リスク社会論」の誕生
ベックにとって、自らの社会的役割は、社会を理解するための鍵となる概念を発明し、社会学への関心を呼びおこすことだという。
Q 私たちはそもそもどのような社会に生きているのでしょうか?
ベック 私たちは概念を喪失した社会に生きています。そのキー概念を新しく取りださなければなりません。ですから「世界リスク社会」の概念は理解しやすいキーワードだと思っています。「個人化」や「グローバル化」……「再帰的近代化」などはそのようなものだと思います。
Q 社会のなかであなたはどのような役割を果たしているのでしょうか?
ベック 私は、世間一般を意識しようとしている社会学者です。それは、社会学にたいする関心を呼びおこすためです。
出典:Armin Pongs, In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Dilemma, 1999. 木前利秋・中村健吾監訳『グローバル化の社会学』国文社、2005年、307頁
しかし、ベックが発明した「(世界)リスク社会」という概念が、実際に人々の関心を集めたのは、皮肉にも、その概念の提唱によってベックが防ごうとしていた悲劇が、実際に起こってしまったことによってであった。
1986年4月26日、チェルノブイリ原発事故が起こったとき、ベックは実質的に初となる単著『リスク社会』の校正作業をしていた 。事故を受けて、彼は、「この機会に」と題した5ページほどの短い前書きを――すでに書き上げていた長い「序論」の前に――追加する。その前書きで、彼はつぎのような苦々しい思いを吐露している。
リスク社会について語る場合、1年以上前には内外の多くの批判を甘受しなければならなかった。しかし、今では真実の苦みが混じっている。本書の多くの認識は、書物の中で論証を重ねてようやく獲得された。例えば、危険が知覚されないこと、危険が知識に依存していること、危険の超国家性、「生態学的収用」〔原発事故などによって周囲の土地の生態系が破壊され、その土地の所有価値が、たとえそれが高価であったとしても、完全に無化されてしまうこと〕、正常性から不条理への転換〔科学的な合理性に固執すると、放射性物質などの有害物質と病気との因果関係を厳密に証明できないため、有害物質への対策が遅れて、人々の健康がますます害されるという非合理な結果が生じてしまうこと〕、など。これらはチェルノブイリ事故以降、現代の状況の月並みな記述と同様に、抵抗なく受け入れられるようになってしまった。
ああ、このような議論によって、ある種の未来の到来を防ぐことができればよいのだが!
出典:Ulrich Beck, Risikogesellschaft, Suhrkamp, 1986. 東廉・伊藤美登里訳『危険社会』法政大学出版局、1998年、6頁(〔 〕は引用者による注。一部改訳あり。以下の引用でも同様。)
このようにして、「リスク社会」という概念は、チェルノブイリ事故を転機として、社会的に承認され、一般に普及することとなる。ただし、ここで注意すべき点が2つある。
第1に、事故を受けて追加した前書きのなかで「チェルノブイリ」は5回言及されるものの、その前書きを除くと、『リスク社会』のなかで「チェルノブイリ」という語は1回も現れない。それは、チェルノブイリ原発事故が起こる前にすでに、『リスク社会』が実質的に書き上げられていたからである 。つまり、「リスク社会」という概念は、チェルノブイリ事故という一つの具体的事例に依拠した概念ではなく、もっと多くのさまざまな諸事例を抽象化するなかで見いだされた、高度に理論的な概念だった。だとすれば、時空を越えた「コロナ後の社会」においても、それは十分参照に値する概念である可能性がある。
第2に、『リスク社会』のなかで常に念頭におかれた「リスク」は、それでもなお第一に、原発や核兵器から拡散しうる「放射性物質(のもつ放射能)」であった。
リスクという言葉で私が念頭においているのは、何よりもまず、人間によって全く知覚されない放射能である。
出典:前掲『危険社会』28頁
たしかに彼は、これまで「リスクと社会の関係」の考察(リスク社会論)のために誰よりも多くの時間を費やし、それが大きな反響を呼んで「リスク社会論」の第一人者となった。
しかし、彼の考察が「放射性物質のもたらすリスク」についての考察を基軸にしている、という点については、私たちには留意が必要だ。つまり、「放射性物質」と「新型ウイルス」の違いに慎重に注意を払いながら、彼の議論を参照する必要がある。
そのうえで次回は、彼の「リスク社会論」の内実に迫っていこう。(つづく)