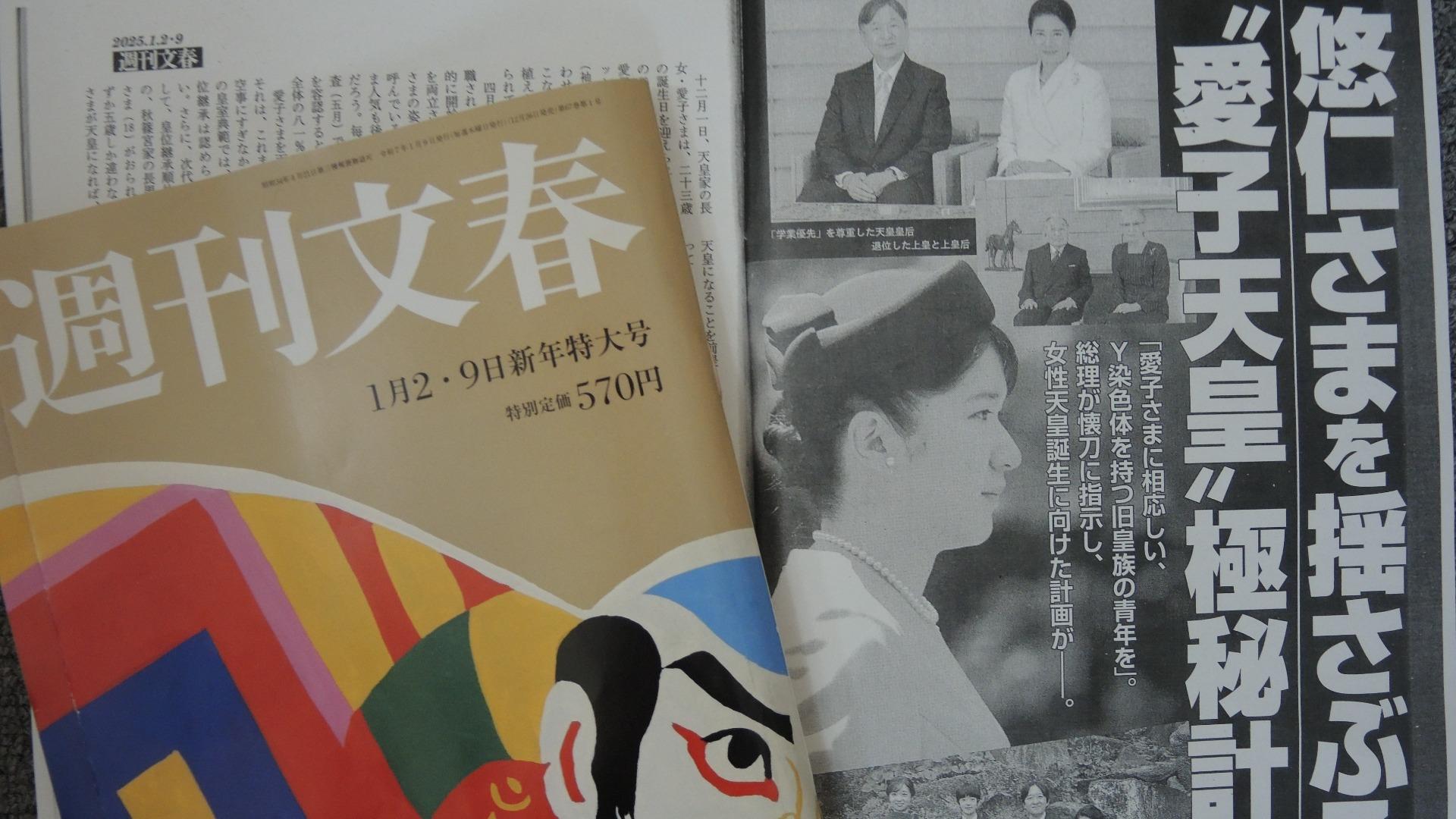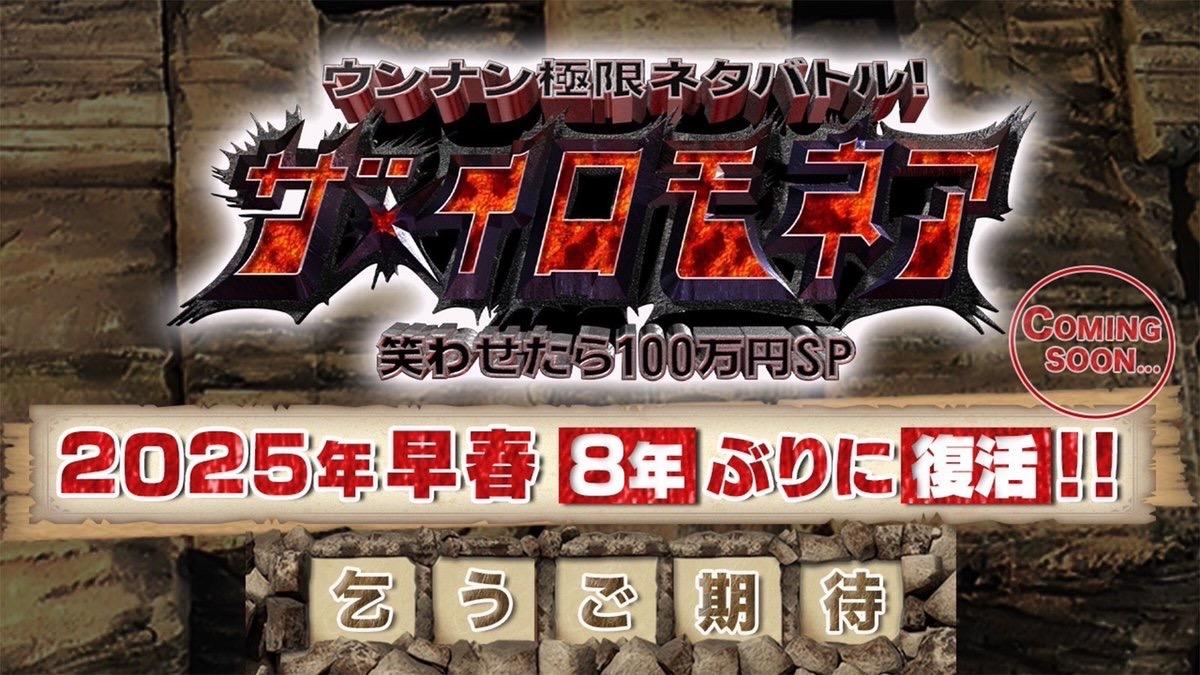コミュニケーション能力偏重はそろそろ終わりにしましょう〜伝え方よりも中身が重要〜

■企業の最重要能力「コミュニケーション能力」
経団連の調査などでも何年にもわたって「コミュニケーション能力」を企業が採用において最重要視しているとのことです。
ところが、「コミュニケーション能力」という言葉ほど空虚な言葉はない、というぐらい、この言葉は各企業、各発言者においてバラバラな意味で使用されています。
元々は言語学の用語のようで、ただ文法的に正しい言葉遣いができるだけでなく、ある特定の文脈においてメッセージの伝達や解釈などができるという能力を指していました。
■そのくせ、意味はバラバラ
しかし、現在の日本の企業社会においては、さらにたくさんの意味を付与されています。以下にその例を挙げます。
・相手の気持ちや感情を推察する力(感情把握)
・相手の伝えたいメッセージを推察する力(趣旨理解)
・相手に心地よい表現方法で物事を伝える力(配慮表現)
・相手の感情を高ぶらせるような表現をする力(人心高揚)
・論理的に筋道を立てて、伝えたいことを述べる力(論理表現)
・様々な話題を提供し、場を盛り上げる力(話題提供)
・一つの雰囲気(空気)を作り上げる力(空気醸成)
・複数の人々の間において合意を形成する力(合意形成)
・ある案件について相手と交渉して、説得する力(交渉説得)
・個人や集団との間で信頼関係を作る力(信頼構築)
などです。もちろん他にもたくさんあります。これらに共通することは、すべて「いかに伝えるか」「いかに感じ取るか」ということであり、中身についてはあまり述べられていないということです。
■中身の方をきちんとみてもらえる時代に
しかし、最近、とみに思うのは、「いかに伝えるか」の時代から、そもそも「伝える内容がどれだけ素晴らしいか」の時代に徐々に少しずつ移ってきているのではないかということです。
もちろん、口達者な人間が中身のないことをそれっぽく言って人々を弄することはしばらく無くならないでしょう(絶対無くならないでしょう笑)。
ですが、一昔前なら通用しなかった「コミュニケーションレベル」(いわゆる上記のような意味での)の人がスター社員になっている時代です。
例えば、エンジニア中心の会社などはわかりやすい例です。言葉は達者ではなく、ぼそぼそとしか話さない人でも、中身が素晴らしければ人は一生懸命聞きますし、理解しようとします。ビル・ゲイツも以前「ギーク(オタク)には優しくしろ。将来、彼らの下で働く可能性は高い」と言ったようですが、一つのことをとことん突き詰めて、深いコンテンツを作れる人の方が重用されるということのようにも思えます。
■ただ話すことだけがコミュニケーションではない
また、以前、所属した会社で自社専属クリエイターの採用をしたことがあります。最初にいろいろな作品を送ってもらいました。中には食べ物をオブジェにつけて送ってきた人もいて、腐って異臭を放ち、難儀したことを覚えています。
それはさておき、彼らと面接してみてわかったのが、普通に話すと全然しゃべれない人が、作品を間に置いて話すと饒舌にいろいろと話してくれるということでした。「能力は領域固有」と言いますが、まさにそうで、彼らのいわゆる「コミュニケーション能力」は特定の「モノ」を挟むことで発揮されるものだったということです。
■「コミュニケーション能力」を純粋に信奉するのは危険
以上のようなことを考えると「コミュニケーション能力」とは、意味もバラバラであることや、そしてそもそも面接などの「特異な場」(初めて会った得体の知れぬ面接担当者に自分の人生やパーソナリティを語るという異常な場)で発揮されるかどうかがそんなに大事なことなのか(その場で発揮できたからと言って他の場面で発揮できるとは限らないし、逆に面接で発揮できないからと言って、他の場でも発揮できないとも言えない)ということを考えると、そこまで多くの企業が素朴に重視するというのはやや危険性が高く、落とし穴があるような気がしてなりません。
■緊張がダメなのではなく、緊張させないことが重要
面接担当者は、面接の場での話しぶりなどで「コミュニケーション能力」を測りがちですが、評価は慎重にすべきではないかと思います。緊張=コミュニケーション能力が低い、のように判断することなどが典型例です。
そうではなくて、彼/彼女が自在にコミュニケーション能力を発揮できるようなもっとリラックスできる場を用意し、そこでいろいろな話を通じて評価をすべきではないかと思います(ここに、通常の採用面接だけではなく、インターンシップなどのできるだけ「素」を見ることができるような場を用意する採用的な意味があると思います)。
さて、本稿では、「コミュニケーション能力」という言葉の曖昧さと、評価のしづらさについて少し書いてみました。自社でこの言葉をあまり明確化することなくお使いになっているところがありましたら、ぜひ一度「そもそもそれはなんなのか」「それは本当に面接という場で評価できるものなのか」をご検討いただければと思います。