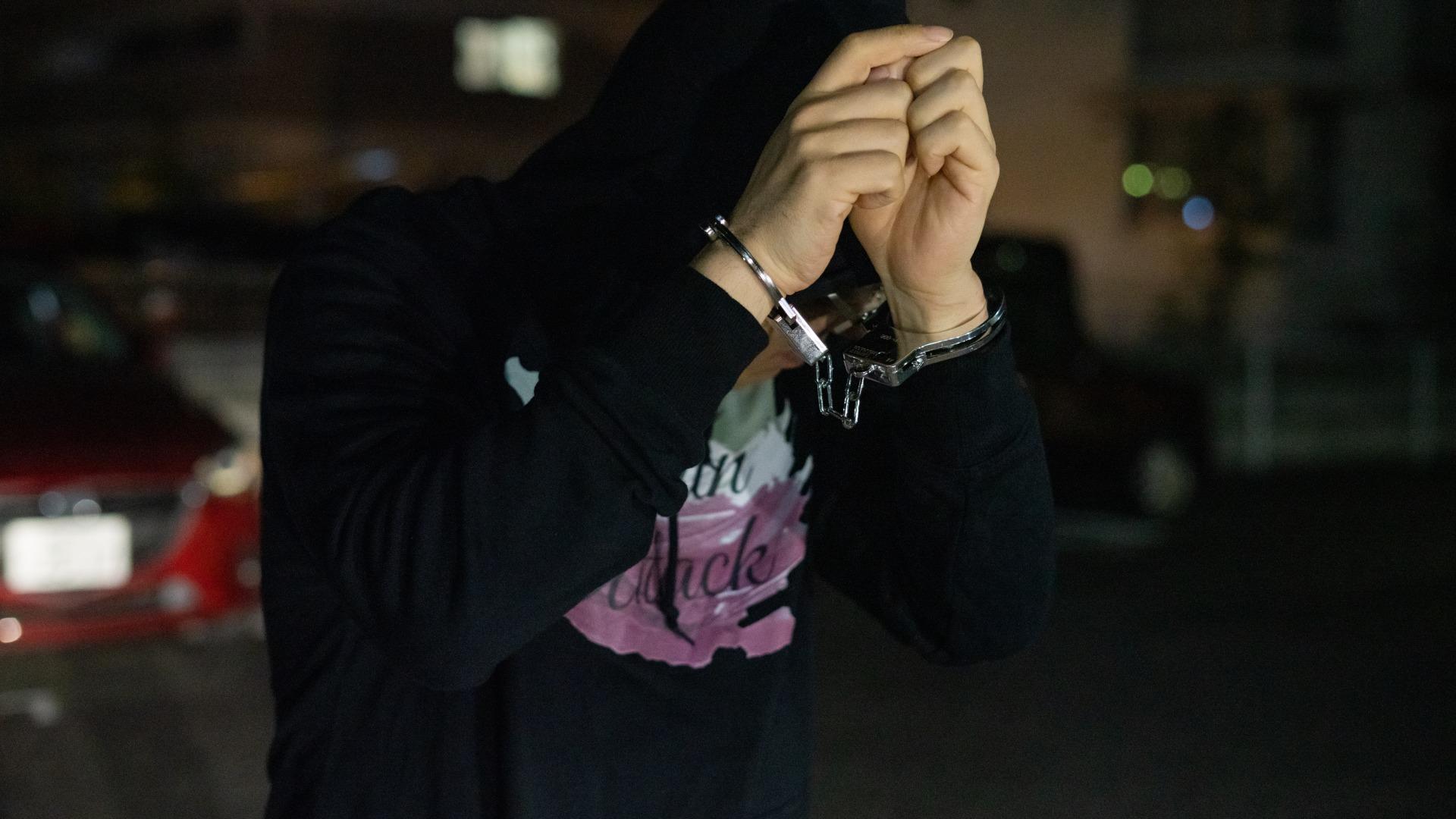海外進出の夢を果たした西野亮廣。今の心境をL.A.で聞く

西野亮廣の絵本をアニメ映画化した「映画 えんとつ町のプペル」が、アメリカで公開される。英語のタイトルは、「Poupelle of Chimney Town」。今月30日にニューヨークとL.A.でスタートし、年明けに拡大して、500スクリーン規模で上映される予定だ。
公開に先立ち、西野はニューヨークとL.A.を訪れ、現地の記者のインタビューを受けた。現場を仕切っているパブリシストに聞いたところ、L.A.での取材日には、筆者のほかに10人の記者が彼にインタビューをしたようである。
海外進出は、25歳の時からもっていた計画とのこと。ついにその夢を果たした彼に、今の心境を聞いた。
アメリカの記者から取材を受けた感想は
彼らはすごく解像力が高いと思いましたね。インタビュー(での質問)もですけど、作品への感想にしてもそうです。「面白かった」だけじゃないんですよ。この間も試写会があり、その後にレセプションがあったんですが、「あそこにはこんなメッセージがあるんですよね?」とか、「あのシーンではどうして背景にあの色を使ったんですか?」とか、解像度が高いと感じることを聞いてくる。感想にしても、たっぷりあります。5分や10分、ずっと感想を言ってくる感じ。
本当に目が肥えているんだなと思います。(映画を)観ることに慣れているし、思ったことを伝えるのに慣れているんだなと。作り手としては非常に気持ちが良いですね。そこまで見てくれていたんだ、って。なんか、作り手としゃべっているみたいなんですよ。全員がクリエーターみたいな感じ。むちゃくちゃ楽しかったです。
今、自分の作品がアメリカに進出したことへの思い
スタートは絵本なんですけど、絵本を書き始めたきっかけは何かというと、僕はもともと5年ほどテレビでお笑い芸人をやっていたんですね。でも、漫才とかそういうのは、日本語に依存した活動なので、海を越えないじゃないですか。最大楽しませることができたとしても、1億2,000万人。いや、自分はこれをずっとやるのか、って。それで25歳の時、もうちょっとスケールの大きいことをしたいなと、テレビをやめたんです。非言語の、あるいは翻訳のできる活動をしようと。で、絵本をスタートしたんですよ。絵だったら1秒で伝わるじゃないですか。そんなふうに、世界を狙うというつもりで始めたんです。
ただ、誰も信じてくれませんでしたよ。日本のイメージでは、テレビで売れて、その後絵本を書くというのは、ちょっとスケールダウンなんですよね。テレビの方がマス(大衆)に向けてやっている活動なので、絵本を書くと言った瞬間に、「いったいどうしたんだ?」みたいな。「世界でやりたいから」と理由を言うと、「ばかじゃないの」って感じで(笑)。当時はすごくバッシングされました。酷かったですよ。でも、僕は欲が強かったんでしょうね。もっと、もっと、っていうのがあったんです。
別に遠回りしたつもりはないですが、すごく時間がかかりました。だけど結局、1冊の絵本が映画になり、海を越えて、今こうなったわけですから。あの時挑戦して良かったなと、あらためて思いますね。
「絵本」を選んだのは、日本人として世界に通用する戦略を考えた結果
最初から、「絵」というより「絵本」だったんです。明確な理由があって。まず、日本人が強いこと、もともと日本人が向いているジャンルって何なのかなと考えたんです。世界に通用しているジャンルって何があるのかなと考えてみると、規格を合わせて、その規格内で戦ってください、というゲームに関しては、日本人は結構善戦している。たとえばスポーツにしても、体重別のボクシングとか、柔道とかだと、わりと世界でも戦えているなと。これが無制限になってしまうと、体格の差とかが出てくる。お料理もそうで、この素材を使って誰が美味しい料理を作れるかとなると、頑張れている。無制限のところに挑んでしまうと、分が悪い。
エンタメ界でも、めちゃくちゃ予算をかけられてしまう勝負に単体で乗り込んでしまうと、予算でマウントを取られて負けてしまう。僕はディズニーとかハリウッド映画が大好きなんですけど、絵本だと、彼らでも100億円かけることはできないじゃないですか。ディズニーが絵本作るとしても、かける予算は僕と一緒ぐらいなんですよ。それだと、シンプルに才能勝負になって、かなりフェアな戦いができる。茶室とか盆栽とか、ああいうところに持ち込んでしまえば、第1歩目は行けるかなということで、絵本だったんです。
いや、絵は、全然得意じゃなかったですよ(笑)。25歳でテレビタレントやめようと思った時、タモリさんと夜飲んでいて、「僕、テレビやめると思うんですよね」って言ったら、「お前、絵でも描けば」って言われて。「ああ、絵、いいっすね」って答えて、その翌朝に絵本作家になるって決めて。そっからのスタートなんで、絵なんて描いたこともなかったです。でも、頑張り屋さんなんですよ、すごく。努力とかがすごく好きなんです。練習とか、すごく好き。もともと運動部なんで。

映画の舞台のインスピレーションは大阪の新世界。これは「僕の話」
僕は兵庫県の川西市っていう田舎の街で育って、最初に出たところが大阪。新世界に住んでいて、その風景がすごく心に残っているんです。新世界にはいろんな人がいるんですよ。いろんな国の人がいるし、マフィアみたいな人もいるし、ジェンダーもいろいろ。韓国の人もいるし、ごちゃ混ぜだったんですね。ホームレスもいるし、僕みたいな田舎から出てきた奴も、ずっと住んでいる人もいる。あれが僕にはすごく魅力的に見えたんです。
それに、工場がむちゃくちゃかっこよく見えたんですよね。田舎にはなかったんで。どこかに行って初めてコンビナートを見た時は、「これは何なんだ!」みたいな感じでした。そんなふうに、自分が好きでたまらないものを入れて、そこにニーズがあるか、見てみようと思ったんです。ニーズがあるかどうかなんて、わからない。たとえば、日本だと、イケメンと美女の高校生が恋愛してとかいうのだと、ある程度ニーズがあるのはなんとなくわかる。でも、「えんとつ町〜」みたいなものだとわからない。少なくとも、僕の身の回りには、こういうのに興味がありそうな人は、あまりいない。ただ、考えてみたら、自分も普通に兵庫県川西市で育って、みんなと同じようなテレビを見て、音楽を聴いて育ったんですよね。つまり自分はそんなに特別な人間ではないのだと。周りに自分みたいな奴がいないだけの話で、同じようなものを好きと言ってくれる人は、世界を探せばどこかにいるかもしれない。その人が見つかるまで発信を頑張ろう、と思ったんです。

つまり、ニーズに合わせて投げるんじゃなく、とにかく自分が好きなものをやってみようと。そしていろんなものに挑戦してみる。でも、日本は村社会ですから、挑戦すると、みんなに叩き潰されるんですよ。僕は芸人から絵本、絵本から映画、今はミュージカルや歌舞伎とか、いろいろ挑戦してきましたけど、むちゃくちゃ叩かれます。うまくいったら、余計。成功すると、妬み、やっかみがひどい。それで、その時の気持ちもちゃんと書こうと思いました。これはもう、僕自身の話ですから(笑)。好きな街もそうだし、主人公たちの思いとかも、全部、僕。
政治的発言をする、あるいはチャリティに熱心な芸能人を批判する日本の文化には、「納得がいかない」
その部分の日本の文化には、納得がいっていないですね。あと、お金の問題も。日本はお金の教育をしないんで、そのまま大人になっちゃって。税金のこともだし、当然、投資のこともよくわかんない。みんなお金音痴なまま社会に出て、「お金ない」「お金ない」って言って、お金を持っている人を妬んで、叩いて。これはよろしくないなと思って。いつまでやっているんだ、って。政治的なメッセージを伝えるインフルエンサーを叩いて。非常に重要なことを喋る人をも叩いて。いつまでやっているんだ、もうこれ終わらしたいなと思ったから、子供が見るファミリーエンタテインメントの中に(そのメッセージを)堂々と入れたんです。非常に大事な問題だと思うんですよね。そこが土台ですから。そこしっかりしていないと、どんだけ頑張っても報われなくて、貧乏から抜け出せない。
僕、被災地支援と途上国支援をずっとやっているんですよ。それに関しても、むっちゃ言われますよ。ずっと叩かれてます。本当に病んでいると思う。すごく病んだ国。
来年はニューヨークに移住する。「現地に出て行って、膝を突き合わせて話し合うために」
たぶん来年はニューヨークに住むと思います。この間、日本でミュージカルをやったんですが、それをブロードウェイでやる話を進めるために。
ひとつ気づいたことがあるんですよね。たとえば小学校で野球少年だったとしたら、そこで結果を出せば中学からスカウトが来て、中学で結果を出したら高校からスカウトが来て、そこでまた結果を出したらプロからスカウトが、となるじゃないですか。勉強もそうかもしれないですけど、今いるところで頑張ったら報われる。
でも、そのルールって本当に日本の国内だけなんですよ。日本でミュージカルをすごく頑張ったところで、ブロードウェイの人は日本のミュージカルを持って来ようとはしない。その必要がないから。世界中からニューヨークに集まるんだから。そこを痛感しました。だから、こちらから出て行かないといけないんです。ミュージカルとか、まあ映画もそうかもしれないですけど、ちゃんとコミュニティに入ってコネクションを作らないと。誰と組むとか、そういうことがむちゃくちゃ重要。
今回はこれ(『えんとつ町〜』のプロモーション活動)に合わせて日本のミュージカルチームもみんなこっちに来て、ブロードウェイのミュージカルのスタッフと交流をとって、話をしたんですけど、これ、めちゃくちゃ大事なんだなと思いましたよ。コミュニケーションを取るということ。出て行って、膝突き合わせてしゃべること。飲みに行こうと言われたら「行きます!」、ランチしようと誘われたら「行く、行く!」と言うこと。そこでコミュニケーションをとっていく。だから、よし、もう住んでしまおうと思ったんですよね。
彼の新たな挑戦を、ニューヨークはどう受け止めるだろうか。
「映画 えんとつ町のプペル」(『Poupelle of Chimney Town』)は12月30日からニューヨークとL.A.、1月7日から全米主要都市で公開。
場面写真クレジット: Akihiro Nishino / Poupelle of Chimney Town Production Committee