気になる体臭は病気のサイン?ワキガの科学的知識を皮膚科の視点から解説
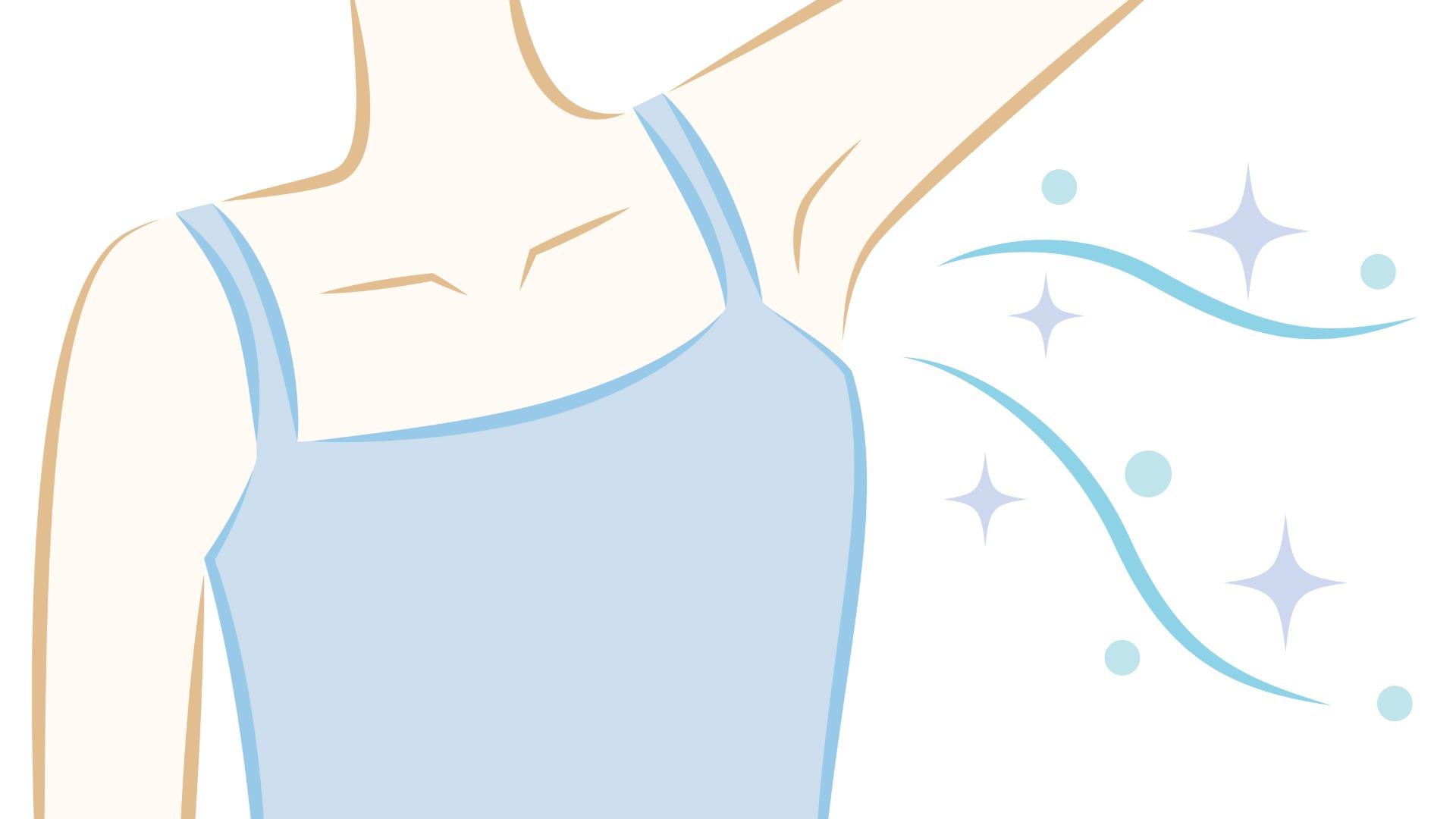
【体臭の原因は皮膚にあり?発生メカニズムに迫る】
私たち人間の体臭は、皮膚にある「アポクリン腺」と「エクリン腺」という2種類の汗腺から分泌される汗が原因です。特に、ワキの下にあるアポクリン腺から出る汗は、体臭の主な原因物質となっています。

アポクリン腺は思春期から活動を始める汗腺で、無色で粘り気のある汗を分泌します。一方、エクリン腺は体温調節に関わる汗腺で、水っぽい汗を出します。実は、どちらの汗腺から出る汗も、そのままでは臭いません。皮膚に存在する常在菌が汗に含まれるタンパク質や脂質を分解することで、イソ吉草酸などの臭いの元となる物質ができるのです。特に、ワキなどの湿った環境を好む菌が臭いの発生に関与していると考えられています。
ワキの臭いの強さには個人差があり、この個人差を生む要因の1つが、ABCC11という遺伝子の型です。日本人を含むアジア人に多い、このABCC11遺伝子のAA型の人は、ワキの臭いが少ない傾向にあるのです。面白いことに、このABCC11遺伝子の型は、耳垢の質とも関連しています。AA型の人は、乾いた耳垢を持つ傾向があり、ワキガになりにくいのです。一方、GA型やGG型の人は、湿った耳垢を持ち、ワキガになりやすい傾向があります。
【体臭を左右する意外な要因とは?】
性別や年齢、人種、ストレス、食事、生活習慣など、体臭に影響を及ぼす要因は様々です。
男女差についていえば、一般的に男性の方が体臭が強いとされていますが、実際には汗の量や臭いの強さには個人差が大きく、一概に性別だけでは判断できません。ただ、男性ホルモンの影響でアポクリン腺が発達しているため、男性の方が強い体臭を発することが多いようです。
年齢も体臭に大きく関わります。思春期になるとアポクリン腺が発達し、体臭が目立つようになります。一方、加齢とともに皮脂腺の機能が低下し、特有の加齢臭が発生します。ワキの臭いとは違った不快臭で、加齢による皮膚の変化が原因と考えられています。
ストレスによっても体臭は変化します。精神的なストレスを感じると、アポクリン腺の働きが活発になり、汗の量が増えるため体臭が強くなるのです。
食生活の影響も無視できません。ニンニクやネギ、お酒の摂取後は、汗からそれらの臭いが感じられることがあります。逆に、緑黄色野菜など抗酸化作用のある食品を積極的に摂ると、体臭が軽減される可能性も指摘されています。
生活習慣では、入浴やシャワーの頻度、下着の洗濯頻度なども体臭と関係があります。汗を長時間付着させたままだと、皮膚の常在菌が増殖しやすくなり臭いの原因に。こまめな清潔保持が体臭対策の基本と言えるでしょう。
【気になる体臭は病気のサイン?体臭から分かる皮膚疾患】
気になる体臭は、何らかの病気のサインかもしれません。体臭の変化から、皮膚疾患などの異変に気づくことができるのです。
ワキガは、アポクリン汗腺が過剰に反応することで発生する強いワキ臭のことを指します。単なる体質だと思われがちですが、立派な疾患の一つ。エクリン汗腺腫といった良性の汗腺腫瘍や、ある種の遺伝病が原因となることもあるため、皮膚科での診察が必要です。
また、ワキの臭いとは異なる不快な臭いがする場合は、皮膚疾患の可能性もあります。たとえば、細菌感染によって皮膚が化膿すると腐敗臭のようなニオイを発することがあります。糖尿病など全身の代謝異常が関係する疾患では、ケトン臭と呼ばれるアセトン様の臭いを伴います。いつもと違う臭いを感じたら、皮膚科専門医に相談するのがよいでしょう。
体臭の悩みは皮膚トラブルと密接に関わります。皮膚疾患が疑われる場合は、市販の制汗剤などに頼るのではなく、まずは専門医の診察を受けることが大切です。
参考文献:
Physiol Behav. 2023 Oct 15:270:114307. doi: 10.1016/j.physbeh.2023.114307.










