「あずみの里」逆転無罪・介護現場にゼロリスクを求めた一審判決を是正

長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」で、おやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し、その後死亡した件で、准看護師の山口けさえさんが業務上過失致死に問われた刑事裁判で、東京高裁(大熊一之裁判長、奥山豪裁判官、浅香竜太裁判官)は28日、一審の有罪判決は「予見可能性を適切に捉えていない」などとして破棄し、無罪とする判決を言い渡した。
ドーナツを食べた直後に崩れ落ちた

女性入所者Kさん(当時85)が倒れたのは、2013年12月12日午後3時15分頃。おやつでは、17人の入所者にドーナツ、もしくはゼリーが提供されていた。介護職員が行うおやつの配膳を手伝っていた山口さんは、嚥下障害のないKさんにはドーナツを提供し、近くで全介助が必要な別の入所者に、おやつを食べさせていた。その背後で、Kさんは声を挙げることもなく、もがくこともなく、静かに崩れ落ちた、という。
検察が途中で訴因変更、一審はそれを認めて有罪判決
検察は、Kさんがドーナツを喉に詰まらせたのが原因で死亡したとし、山口さんが注視義務を怠ったとして(訴因A)起訴した。ところが一審の途中で、2度にわたって訴因を変更。Kさんが慌てて食べて嘔吐することがあったため、1週間ほど前に介護職員の判断でおやつをゼリー系に変更していたことをとらえ、山口さんがそれを知らずにドーナツを配ったことは、おやつの形態変更確認の義務違反だと主張(訴因B)した。
一審の長野地裁松本支部(野澤晃一裁判長、高島由美子裁判官、岩下弘毅裁判官)は、当初の起訴事実(訴因A)については、Kさんには嚥下障害はなかったことなどから、山口さんが窒息事故を防ぐために食事中の動静を注視する義務を怠ったとはいえない、とした。
その一方で一審は、訴因Bについて、Kさんにドーナツを配膳すれば、誤嚥や窒息によって死亡させる結果を十分に予見できたと、訴因Aへの判断と矛盾するような認定を行った。そして、山口さんが介護職員の記録を遡っておやつの形態が変更になっていることを確認する義務を怠ったなどとして、検察の求刑通り罰金20万円の有罪とした。
「窒息や死の予見可能性は低かった」
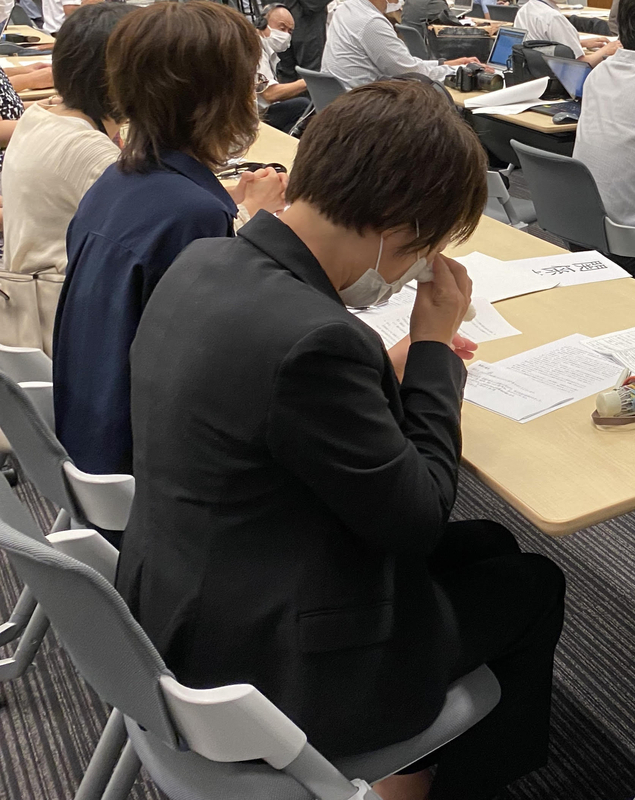
これに対し東京高裁は、一審は窒息の可能性を抽象的、包括的にとらえ、予見可能性を広げすぎているとし、Kさんがドーナツで窒息・死亡することへの「具体的な予見可能性を検討すべき」と指摘。「原判決はこの点を看過している」と一審判決を批判した。
そのうえで、おやつの形態変更は、看護職と介護職で共有される文書ではなく、介護職員の間で情報共有する資料のみに記載されており、山口さんが介護資料を遡っておやつの形態についてチェックする義務があったとはいえない、とした。
さらに、Kさんがドーナツを含む常菜系の間食(おやき、いももち、今川焼き、ロールケーキ、まんじゅう等)を食べていたが、窒息を招くような事態が起きたことはなかったなど、6点にわたって詳細に検討。「本件ドーナツでKさんが窒息する危険性ないしこれによる死亡の結果の予見可能性は相当に低かった」と結論づけた。
死因を検討するまでもなく無罪

控訴審で弁護側は、「Kさんの死因は窒息死ではなく脳梗塞によるもの」と主張。脳神経外科の専門医6人を含め7人の医師の意見書を証拠申請した。しかし高裁は、「(ドーナツ片による気道)閉塞に至る具体的機序を確定できない」として一審の判断に若干の疑問符は付けたものの、弁護側が請求する専門医の意見書を1通も採用せず、これを退けた。
その理由について判決要旨は、本件が起訴されてから既に5年以上が経過し、一審判決には明らかな事実誤認があることを指摘。医師の意見書を証拠採用するには、証人尋問などを行い、山口さんをさらに長く被告人の席にとどめることになる。高裁は、「(これ以上)時間を費やすのは相当でなく、速やかに原判決を破棄すべきである」とした。
要するに、Kさんの死因を検討するまでもなく、山口さんは無罪、という判断だ。
「一審による萎縮効果が払拭される」と
本件の一審有罪は、全国の介護施設に衝撃を与えた。入所者に急変があった場合に職員が刑事責任を問われることを懸念して、おやつの種類を限るなど、施設側の萎縮が見られた、という。
そうした介護の現場にとって、今回の判決は重要だ、と弁護人の1人上野格弁護士は、その意義を強調する。

「最近は過失が問われた事件で、『結果回避義務』を重視し、起きてしまった結果は回避できたはずだ、として責任を負わせる傾向がある。しかし今回の判決が、(結果だけに目を奪われず)『予見可能性』をきちんと判断してくれたことで、介護の現場にとってみれば、リスクや状況をきちんと判断して仕事をしていれば、(仮に残念な結果があっても)刑事責任に問われることはない、ということになる。高裁判決は、一審判決による萎縮効果を払拭してくれると思う」
木嶋日出夫・弁護団長も「最近は、何かと結果責任を問う社会になっている。悪い結果が出れば、(予見可能性など問わずに)誰かが責任を取るべきだ、と。その傾向に歯止めをかけた」と評価する。
食の楽しみの大切さを認めた判決
本件の支援者たちは、終の棲家である特養においては、おやつの提供は入所者たちの日々を彩る大切なものであると訴えてきた。今回の高裁判決は、その点についても、専門家が「あらゆる食品が窒息の原因になってもおかしくない」と指摘していることを挙げ、次のように判示している。
〈窒息の危険性を否定しきれる食品を想定するのは困難である。そして、窒息の危険性が否定しきれないからといって食品の提供が禁じられるものでないことは明らかである。他方で、間食を含めて食事は、人の健康や身体活動を維持するためだけではなく精神的な満足感や安らぎを得るために有用かつ重要であることから、その人の身体的リスク等に応じて幅広く様々な食物を摂取することは人にとって有用かつ必要である〉
この点でも、今回の判決は介護現場の現実をとらえたものと言える。
司法がゼロリスクを求めるとどうなるか
「安全」は大切だが、過剰に「安全」のみを求めれば、高齢者施設では提供できる食べ物は限られてしまう。それが高じて、安易に胃ろうを作れば食の楽しみは失われる。そういう施設に、人は入りたいと思うだろうか。そういう所で、幸せな老後を送れるだろうか。
さらに、「安全」が保障できない高齢者は入所を断る、という施設が続出して、受け入れ施設に困る、ということもありうる。高齢者の終の棲家である特養では、職員がベストを尽くしても、入所者が亡くなることはある。その場合、刑事責任を負わされる、となれば、そのような危うい職場で人は働きたいと思うだろうか。ただでさえ、人手不足の介護の現場は、ますますなり手が少なくなり、立ちゆかなくなるのではないか。
本件一審判決のように、司法が介護の現場に100%の安全、リスクゼロを求めれば、不幸なのは高齢者であり、困るのはその家族だ。その点で、今回の高裁判決は、「予見可能性」を厳格にとらえ、入所者の「安全」と「幸せ」、介護する人たちの「安全」と「責務」のバランスを考えた、現実的な判決と言える。
検察を追認した裁判所の過ちを正した判決
本来は、様々な証拠調べを行う一審で、この判断が出されるべきだった。ところが、一審の長野地裁松本支部は、弁護人が現場となった「あずみの里」の検証を行うよう求めても受け入れないなど、現場の状況を見ようともしなかった、と弁護人は言う。

弁護人の宮地理子弁護士は、一審の裁判所と検察の対応について、今なお憤慨している。
「検察は当初、現場に利用者が何人いたのかも調べていなかった。山口さんや介護職員が、その日どのように動いていたのかもつかんでいなかった。裁判で全容が明らかになって、(当初の訴因で)有罪判決が難しくなると、検察は訴因変更をし、裁判所は簡単にそれを認め、それに基づいて有罪判決を出した。山口さんにとって、訴因変更は(無罪になると思ったら)もう一度起訴されたのと同じ。こういうことを認めた裁判所は、本当に許せない」
一審の誤った判断を正すことで、言外に裁判所の役割は何なのかを問う高裁判決でもあった。










