検事長定年延長は指揮権発動よりひどい
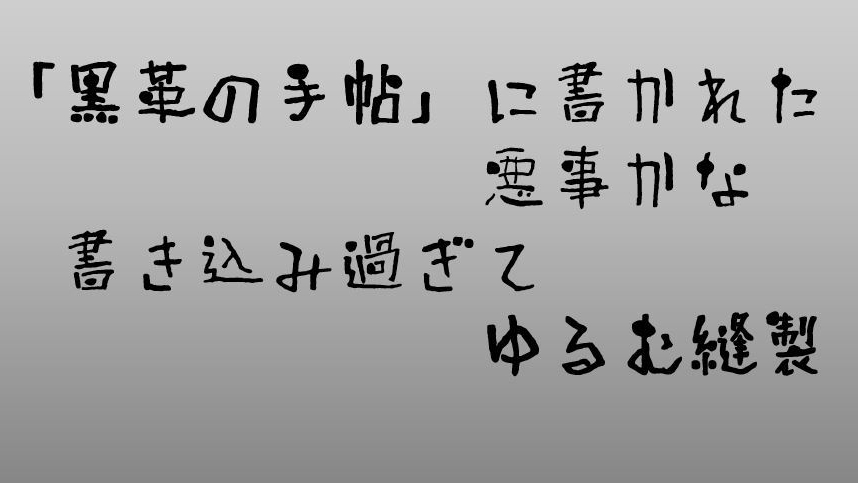
黒川弘務検事長の定年延長は、「第二の指揮権発動」だと言われることがありますが、指揮権発動よりもひどいものだと思います。
検察権は、立法・司法・行政の三権の中では、行政権に属しています。だから、検察官の任免権は法務大臣が持っていて、内閣が検察権の行使については国会に対して責任を負うことになっています。しかし、検察権は法の厳格、公平公正な執行という意味では司法権と密接な関係にあり、検察権の行使が時の政党の恣意的な判断によって左右されるようなことがあれば、法に対する国民の信頼が地に落ち、国家の土台が崩れることになりますから、検察庁は法務大臣からは独立した組織として位置づけられています。
法務省内の特別な機関としての検察庁と検察権の独立という2つの課題に配慮して、検察庁法には次のような規定が置かれています。これが、法務大臣の検事総長に対する指揮権と呼ばれるものです。
検察庁法14条 「法務大臣は、・・・検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」
つまり、法務大臣は検察庁のトップである検事総長に対する指揮権は持っていますが、具体的な事件を担当する個々の検察官に対する指揮権は持っていません。したがって、個々の検察官は、法務大臣とは無関係に、国を代表して捜査権を行使する権限を持っているということになります。
極端なはなし、かりに法務大臣がなにかの犯罪を犯して、捜査の手が自身に及びそうになったときに、みずから指揮権を発動して逮捕を免れようとしても、その指揮権はあくまでもトップの検事総長に対するもので、個々の検察官はその法務大臣を逮捕することは法的には可能です。もちろん、法務大臣の上に位置する内閣総理大臣を逮捕することも可能です。ただ、実際上は、法務大臣の指揮権が発動されれば、検察全体の動きにきわめて大きな影響を与えることは間違いありません。実はかつて一度だけ、この指揮権が発動されたことがあり、検察にとってそれはそれは苦い経験として残っています。
昭和28年のいわゆる「造船疑獄」と呼ばれる事件です。
海運会社からの収賄容疑が濃厚であった、当時の自由党幹事長佐藤栄作氏(後の総理大臣)の逮捕を、犬養健法務大臣が指揮権を発動して阻止したのでした。検事総長は結果的にその圧力に屈し、佐藤幹事長の逮捕を見送らせました。検察は、佐藤氏の逮捕を突破口として、さらに汚職の解明を進めることを狙っていただけに、その検事総長はマスコミからも、検察内部からも「腰抜け」と言われ、信頼を失ってしまい、結局は辞任に追い込まれました。
事件としての造船疑獄は、指揮権発動で本質的部分が吹き飛ばされ、わずかに東京地裁で(1)佐藤被告の政治資金規正法違反、(2)海運会社の特別背任罪が審理されましたが、(1)は、昭和31年12月の国連加盟恩赦で免訴(刑事手続き打ち切りの判決)となり、(2)は、無罪となりました(昭和29年4月23日に参議院が犬養法務大臣の指揮権発動に対して内閣に警告する決議が可決されています)。
このように指揮権発動は、事件の本質的部分を崩壊させてしまうような強烈な威力を持っているわけですが、しかしともかく形式的には検察庁法14条に則って行われるわけで、法的根拠を有してはいます。
ところが、今回の黒川検事長の定年延長は、指揮権発動と異なり、法的根拠が疑わしい措置だと言われています。
検察庁法は、検事総長は65歳、その他の検察官の定年は63歳と決めています(同法22条)。他方、昭和56年に改正された国家公務員法は、1年を超えない範囲での勤務延長を認めています(同法81条の3)。検察庁法と国公法は、特別法と一般法の関係に立ち、国公法改正の時の国会審議では、人事院が「検察官と大学教員には国公法の定年制は適用されない」と明言していました。
それが、1月31日、政府は突然、国公法の規定を使って、2月7日に定年退官する予定だった黒川検事長(2月8日が63歳の誕生日)の定年を8月7日まで延長することを閣議決定したのでした。
この異例の人事は、2月3日の衆議院予算委員会でも問題になり、定年延長の緊急性、必要性について質問された森雅子法務大臣は、「重大かつ複雑、困難な事件の捜査・公判に対応するため」という空虚な答弁を繰り返し、詳細は語られませんでした。
その後、2月12日の衆院予算委員会では、人事院の松尾恵美子給与局長が、従来の解釈を「現在まで」維持していると答弁しましたが、安倍晋三首相が13日の衆院本会議で、黒川検事長の定年延長について「国公法の規定が(検察官にも)適用されると解釈することにした」と答弁し、松尾局長は、19日の予算委員会で、法解釈の変更はすでに1月中に行っており、12日の答弁は「現在」という言葉の使い方が不正確であり、「言い間違えた」と修正を余儀なくされました。
そして、法務省は、21日、衆院予算委理事会に対して、法解釈変更の決裁を公文書ではなく口頭で行ったと報告しています。
法がその時々の社会的、経済的、政治的要請で作られる規範(ルール)である以上、状況が変われば法の解釈も変わるのは当然ですが、解釈を変更するには、変更するだけの合理的で説得的な根拠が語られなければなりません。現在まで、政府からは納得できるだけの説明はなされていないと思います。
検察内部からも、2月19日の「検察長官会同」で、静岡地検検事正から批判的な意見が述べられ、疑問の声が上がっていることがわかりました。
詳細な根拠は、すでに別稿で指摘しましたので、繰り返しませんが、今回の定年延長が指揮権発動よりもひどいものだというのは、圧倒的多数の国民が感じることではないかと思います。(了)










