40年読み継がれる「思考の整理学」大事なのはアイデアを寝かせること?【行き詰まった時ほど、忘れよ】
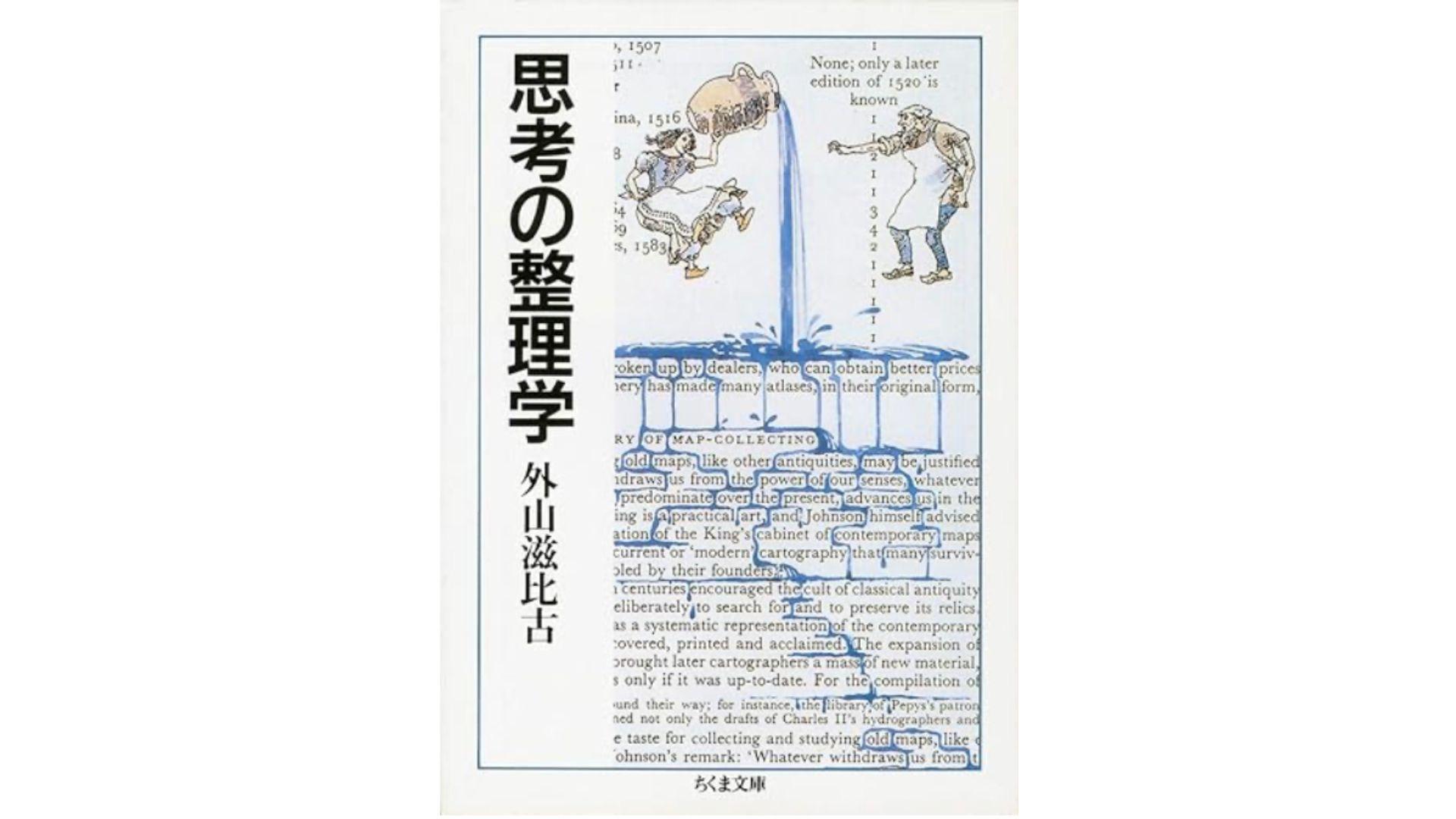
この本は、学校教育への問題提起から始まります。
学校教育で身につきやすいのが、「受動的に」知識を身につける力。一方で、学校では身につきにくいのが、「自分でものごとを発見、発明する力」です。新しい文化の創造には、「自分で創造する力」が不可欠となります。
『思考の整理学』ちくま文庫(1986、外山 滋比古著)。1986年に発売されて以降、40年近く読み継がれている本です。長く読み継がれているのは、普遍的で大切なことが述べられているからこそ。
自分で物事を発見し発明するために、現代でも通用する、大事な要素を3つご紹介しますね。
(1. 発酵させる )

思考の整理法としては、寝させるほど大切なことはない。
アインシュタインが、「なぜシャワーを浴びている時に限って、いいアイデアが閃くのか?」と言った。というエピソードはよく知られています。
行き詰まった時に、全く違うことをして忘れていたら、ふといいアイデアが閃いた。一晩寝てみたら、悩んでいたことに、突然解決策が思い浮かんだ。
誰しも、そのような経験をしたことがあるのではないでしょうか?この本でも、アイデアを時間をかけて寝かせることの重要性について述べられています。
「ちょっと、煮詰まっているな」そんな時ほど、いったん忘れてしまって、自分がリラックスできることに目を向けてみるのが良いのかもしれません。
努力してもできないことがある。それには、時間をかけるしか手がない。(〜中略〜)いずれにしても、こういう無意識の時間を使って、考えを生み出すということに、われわれはもっと関心をいだくべきである。
(2. セレンディピティ)

それが思いもかけない偶然から、まったく別の新しい発見が導かれることになった。
”セレンディピティ”とは、「思いもよらなかった偶然がもたらす幸運」のことです。どちらかというと、思いがけない幸運に「気づく力」と言い換えてもいいのかもしれません。
たとえば、お目当てのコーヒーを買いに来たのに売り切れだった。けど、ふと気がついたら隣のお店で、ずっと探していた理想の洋服を見つけた。
「〜を探しにきたのに」求めていたものが得られそうにないな。そんな、残念なシチュエーションにこそ、実は思いがけないチャンスや幸運が潜んでいるかも...!?しかし、心がオープンでないと、探していたものとは”別の良いチャンス”に気がつくことができません。
いま、一番関心を持っていること、探しているものよりも、その周辺にあることの方が活性化しやすい。だからこそ、自分のこだわりを手放して、あらゆる可能性を受け入れられる心の余裕が必要なのかもしれません。
これも、対象を正視しつづけることが思考の自由な働きをさまたげることを心得た人たちの思い付いた知恵であったに違いない
(3. ノート術)

寝させるのは、中心部においてはまずいことを、しばらくほとぼりをさまさせるた目に、周辺部へ移してやる意味をもっている。
では、どのようにして、思考を寝かせれば、アイデアを熟成させることができるのでしょうか?それが、ノートに書き留めることです。ふっと頭に浮かんだことや、閃いたことは消えてしまいやすいので、閃いたタイミングで必ず手帳に書き留めるようにします。
しかも、アイデアが閃きそうにない場所ほどアイデアが閃きやすいので、いつでもノートを持ち歩くようにしましょう。今であれば、スマホに書き留めても良いかもしれません。
本書の中には、思考をうまく寝かせるための、様々なノート術が紹介されています。
「思考の整理学」ちくま文庫(1986、外山 滋比古著)。「全国の大学生に一番読まれた本」というキャッチーな見出しが印象的で、本屋さんで一度は見たことがある、という方も多いのではないでしょうか?
読んでみれば、AIが発展している現代だからこそ、人間として「自分で飛ぶ」力を鍛えるヒントを得られるかもしれません。気になった方は、ぜひ書店やオンラインで見てみて下さいね。最後までお読みいただき、ありがとうございました。










