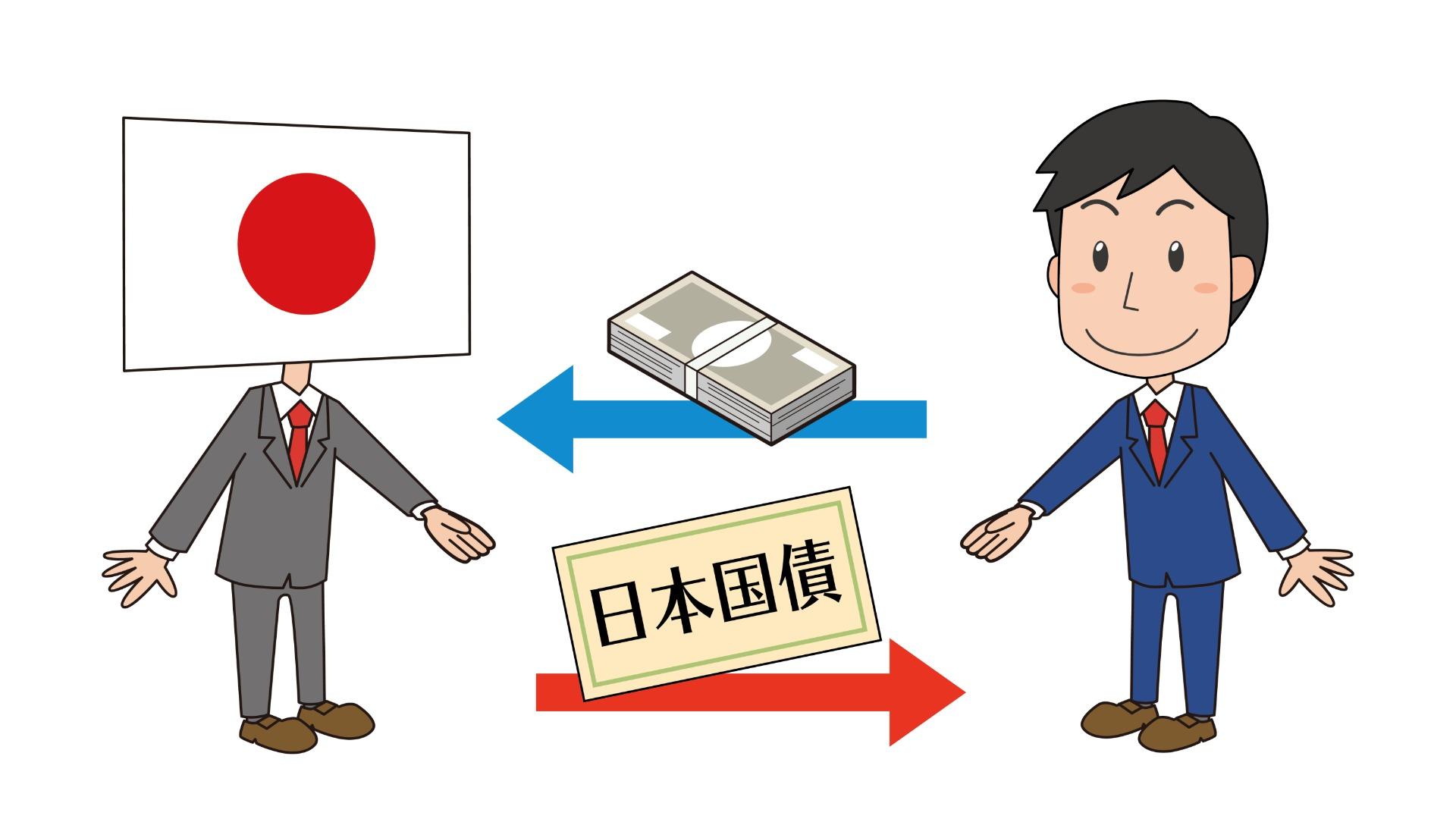いじめを苦にした死が後を絶たない社会を見つめて。生き地獄にいる少女二人の物語に込めた思い

韓国から届いた映画「地獄でも大丈夫」は、ナミとソヌという女子高生の物語だ。
ただ、二人を取り巻く状況はキラキラした青春とはほど遠い。
スクールカーストで底辺に位置する二人は常にいじめの対象。
もはや学校生活は地獄でしかない二人は、自死を心に決めている。
地獄の日々になることが目に見えている修学旅行をパスした二人は、その期間を使ってソウルへ。
死ぬ前に、かつて自分たちをいじめて地獄行きへと主導したチェリンへの復讐を果たそうとする。
その物語は、競争社会、学校でのいじめ、自殺率の高さといった現在の韓国社会の問題に言及。学校の隅に追いやられ、居場所を失い、この先いいことがあるなんて到底思えない少女たちの切実な声が伝わってくる。
ただ、だからといってダークでシビアな物語というわけではない。
この世に絶望した少女二人の物語は、ソウルに向かうあたりから凸凹コンビのバディ・ムービーへ。
それが、宗教や虐待の問題に言及した社会派ドラマから、アクションへと転じ、最後は10代のすべての子たちに贈るような青春劇へと顔を変えていく。
当事者の切実な声を拾い、社会を鋭く見据えながらも、変に硬派ぶらない、エンターテイメント性がしっかりと宿る一作となっている。
手掛けたのは、ポン・ジュノ、チェ・ドンフン、ユン・ソンヒョン、チョ・ソンヒ、キム・セインなど韓国映画をリードする新しい才能を輩出し続けている「韓国映画アカデミー(KAFA)」が2022年に「今年の顔」に選出したイム·オジョン監督。
長編デビュー作である本作に彼女が込めた思いとは?
韓国からまた現れた女性監督のニューフェイスに訊く。全七回/第二回

韓国の社会にある支配構造と一向に変わらない負の連鎖の問題の本質
前回(第一回はこちら)は、少女たちの切実な声と願いが聴こえてくる本作の物語がいかにして生まれたのかを語ってくれたイム・オジョン監督。
その中で、自分も「死にたい」という感情に陥った時期があったことを明かしてくれた。
そのような自身のネガティブなことを打ち明けるのは勇気がいることだと思う。
また、心にとめておくことはあっても、わざわざ改めて向き合いたいと思うことではない。
それでもなおこの負の感情と向き合おうと思ったのはなぜだろうか?
「やはりいま描いておきたい、いま向き合っておきたい。そう思ったんです。
なぜ、そのような強い意思をもったかというと、わたしが同時代の人たちと同じように息をして生きてきて痛切に感じるのは、自分と同世代、その下の世代にある意味、全員が『自分はひとりぼっちで孤独』というアイデンティティを多かれ少なかれ持っているのではないかということでした。
つまり、長らく社会において『孤独』や『孤立』は解消されていない。きつい言い方になるかもしれませんが、社会で問題化されているのに放置され続けているような気が個人的にはしていました。
たとえば、学校での暴力、要は校内でのいじめをテーマにした映画やドラマは数多く存在します。
でも、依然としていじめ問題は解消されていません。残念ながら少しも解決策ができていないし、少しも良い方向に動いていない。
なぜ、変わらないのか?
わたしが考えるに、同じことが繰り返されているような気がします。
それはどういうことかと言うと、たとえばいじめを苦にある女の子が自殺してしまうことが起きたとします。
すると、いじめの問題を、その人個人の問題にしてしまう。
いじめに遭ったのは、彼女に問題があった、彼女が毅然とした態度をとればそうならなかったといったように問題がすり替えられてしまう。
そのような状態になってしまったときにどのように改善していくのか、もしくはそのようにならぬように、どうすれば未然に防げるのかを考えなければいけないはずなのに、個人の問題になってしまう。
このままでは何も変わらないと思いました。
それから、韓国では依然として競争システム、競争の構図が成り立っています。
その競争に敗れると、社会から取り残され隅へ追いやられるような構図がある。
そのような中で、社会からこぼれおちたような感情を幼いときから味わう子どもたちがいます。
そのような苦境に立たされる子どもがいる一方で、うまく力を手に入れる子どもがいます。
その中で、自分の手にした力に味をしめて、暴力によってあらゆることを支配しようという者がいる。
弱者に不条理を強いて、権力を振りかざして誤った目的を達成しようとする者が出てきてしまう社会構造のようなものがあるような気がしました。
個人がないがしろにされて集団の論理が優先される。
その集団の象徴のような存在として、学校や宗教団体があり、その内部での論理が一個人に大きな影響を及ぼしているのではないか、その影響が個人のストレスとなって孤立や疎外といったっことにつながっているのではないか。
その韓国の社会にある支配構造と一向に変わらない負の連鎖の問題の本質がどこにあるのか、をつまびらかにして描きたいと思いました。
いますぐ変えられなくても、もしかしたら変わるかもしれない。それを打破する鍵はどこかにあるかもしれない。
そういう思いも込め、問題提起をする意味でもこの現実を描きたいと思いました。
そして、一個人と一個人の連帯の大切さも伝えたいと思いました。
ですから、負の感情と向き合うのは苦しいことですけど、それよりもいまきちんと向き合って描きたいという自分の気持ちが上回りました」

世の中に怒りをぶつけ叫んでいるナミに近かったです
ここまでの話から、あまり明るいとは言い難いことが想定されるが、監督自身は、本作の主人公ナミとソヌと同じぐらい、高校生ぐらいのときはどんな時間を過ごしていたのだろう?
「わたし自身は二人のように高校時代にいじめを受けたことはありませんでした。
ただ、決してキラキラした青春ではなかったです。
かなり暗かったといいますか。学校にも、先生にも、両親にも不満を抱いていました。世の中にも怒っていました。
なにか嫌なことがあると怒りを露わにして怒鳴ったり、かと思うと、大泣きしてしまったり、いいことがあると大笑いしたりと、今振り返ってみるとかなり情緒不安定だったと思います。
学校の先生も両親もかなり困ったんじゃないかと(苦笑)。
何に対して、一番怒っていたかとう言うと、学校と両親です。
当時、わたしはもう映画が撮りたくて撮りたくてたまらなかった。
いますぐ学校を辞めて、そちらの道に進みたいと、少しでも早く映画の世界に入りたかったんです。
そのような衝動に駆られていた。
でも、両親も学校もそれを許してくれなかった。
ですから、わたしの高校時代というのは、学校と家庭と対立して闘っている真っただ中でした。
両親と学校にファイティングポーズをずっと向けていました。
世の中に怒りをぶつけ叫んでいるナミに近かったと思います」
(※第三回に続く)

「地獄でも大丈夫」
監督・脚本:イム・オジョン
出演:オ・ウリ、パン・ヒョリン、チョン・イジュ、パク・ソンフンほか
公式サイト https://www.sumomo-inc.com/okiokioki
ユーロスペースにて公開中、以後全国順次公開
筆者撮影以外の写真はすべて(C)2022 KOREAN FILM COUNCIL. ALL RIGHTS RESERVED