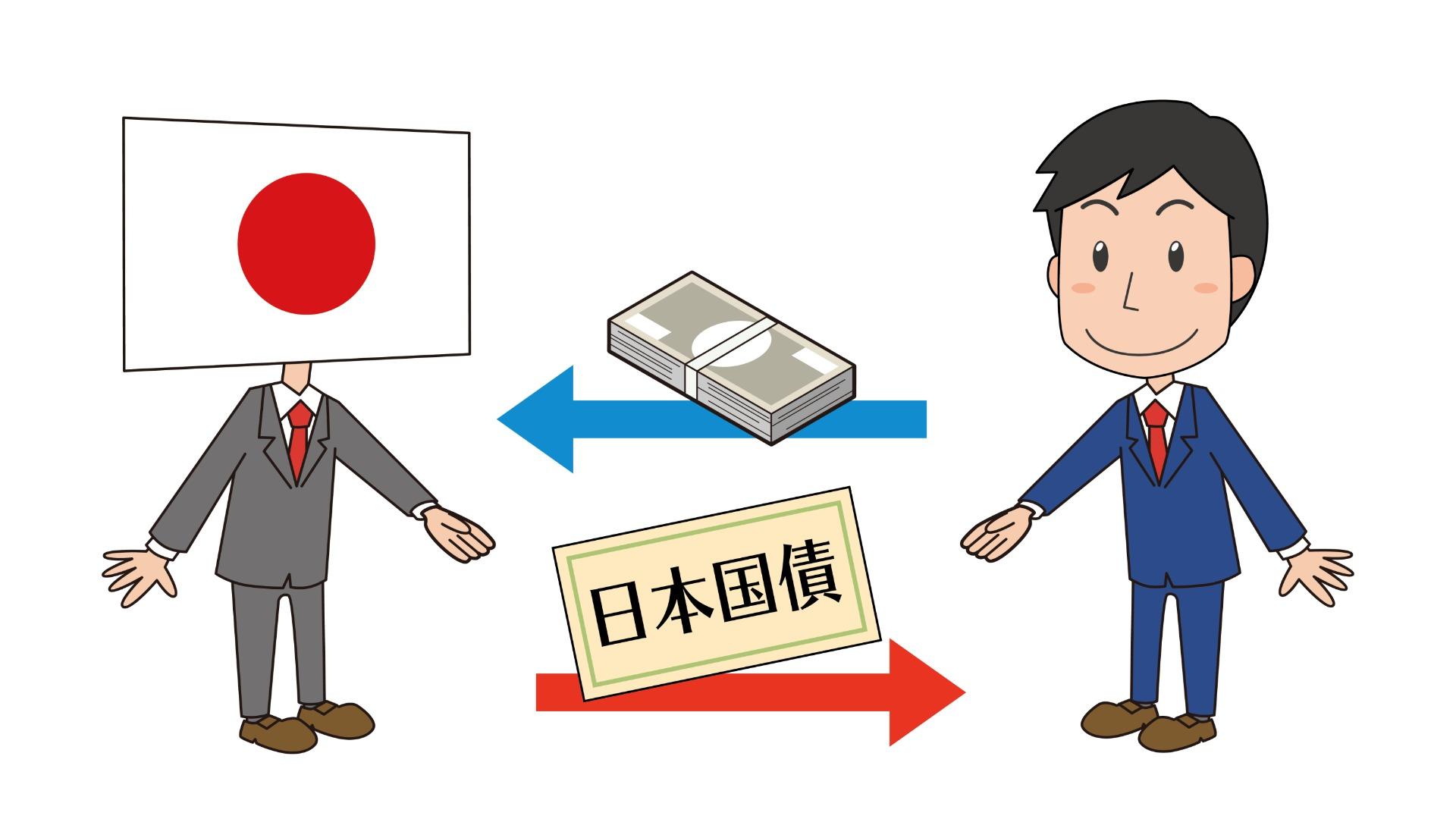原作ものの映像化と改変、最近のハリウッドの例を見る

小学館が編集者一同の名前で声明を発表してもなお、「セクシー田中さん」ドラマ化をめぐる悲劇が波紋を呼び続けている。連載進行中のドラマ化であったこと、最後の2話を原作者本人が脚色したいと主張して実際にそうしたこと、それについて脚本家がSNSで発言したことなど、今回のケースにはいろいろな事情がからんでいて、かなり複雑だ。
単に原作に忠実でない形で映像化されようとしたという話だけでないのは理解しているが、今回のことでそこにも焦点が当たったのはたしか。小説やノンフィクション本、コミックが映像化されることは過去にも今にも数えきれないほどあるハリウッドでは、傑作の中にも、駄作の中にも、原作に沿ったものもあれば、大きく改変されたものもある。実際のところ、ある程度改変されることのほうが多い。オスカー授賞式がちょうど1ヶ月先に迫ったタイミングでもあるので、この機会に、候補入りした作品の脚色について見てみたいと思う。
まずは、脚色部門は逃したが、作品、監督など10部門で候補入りしたレオナルド・ディカプリオ主演、マーティン・スコセッシ監督作「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」。原作は、2017年に出版されたノンフィクション本「花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生」。映像化権は、出版前の2016年、インペラティブ・エンタテインメント社が500万ドル(今日の換算レートで7億4,600万円)で競り落とした。2017年にスコセッシ、ディカプリオ、ロバート・デ・ニーロが興味を示し、オスカー受賞歴のある大ベテラン、エリック・ロスが脚色を開始。最初のバージョンは原作本に近く、ディカプリオが演じる予定だった主人公は、完成版ではジェシー・プレモンスが演じているFBI捜査官トーマス・ホワイトだった。

しかし、スコセッシがオクラホマ州のオセージ族の人々にたっぷりと話を聞いていく中で、アーネスト・バークハートという白人男性とモリー・カイルというオセージ族のカップルの名前がたびたび挙がるようになる。映画のハートはそこにあると感じたスコセッシは脚本の大幅改変を決め、ディカプリオは新たな主人公バークハートを演じることになった。このバージョンで重要なキャラクターとなったモリーを演じたリリー・グラッドストーンは、ネイティブ・アメリカンの女性として、史上初めてオスカー助演女優部門に候補入りをしている。
ランティモスは原作者に「映画化にあたっては変更もある」と話した
一方、作品、監督、主演女優、脚色など11部門で候補入りした「哀れなるものたち」の原作は、1992年に出版された、アラスター・グレイによる小説。これからは英語の映画を監督したいと思っていたギリシャ人監督ヨルゴス・ランティモスは、この小説に魅了され、2011年、映画化権を売ってもらうため、スコットランドまで直接グレイを訪ねていった。
グレイはランティモスをグラスゴーのお気に入りの場所に連れて行ってくれ、その間さまざまな会話をしたが、映画化についての細かいことは何も話さなかったと、ランティモスは語っている。それでも、ランティモスのギリシャ語作品「籠の中の乙女」(2009)を見ていたグレイは、「あなたは才能のある人だ」と、彼が映画化することを承諾してくれた。ランティモスは、「映画化する上ではそのままにはできません。変更もあります」と言い、それについても理解を示してくれたという。ランティモスはすぐにでも映画化したかったが、今ほど業界内での尊敬を集めていなかった当時は資金が集まらず、実際に動き出したのは「女王陛下のお気に入り」(2018)の製作が始まってから。グレイは完成作を見る前に亡くなってしまった。脚色を担当したのは、「女王陛下のお気に入り」でもランティモスと組んだトニー・マクナマラだ。

脚色以外に作品、監督、国際長編部門に候補入りした「関心領域」は、マーティン・エイミスの小説を映画化したものだが、原作とはまったく違う。ジョナサン・グレイザー監督は、出版前に入手した原作小説の抜粋を読んで強く心を惹かれ、次の作品にすると決意。ホロコーストをナチ将校の家族の視点で語る映画を作るためにたっぷりとリサーチをしていく中で発見したことを取り入れ、原作にあった筋書きの重要な部分を削除して、意図的にストーリーがほとんどない、観客が彼らを観察するような映画に仕上げた。
しかし、その過程では「何度も原作を読み直した」とも、グレイザーは語っている。エイミスは、完成した映画がカンヌ映画祭でお披露目されたのと同じ日に亡くなったが、グレイザーはこの映画の製作に10年近くを費やしており、その間なんらかの、またどれほどの会話があったのかはわからない。
”原作者”に一番近いマテル社は、事実の変更をサポート
おもちゃの人形をベースにした「バービー」が脚色部門に入ったことには、数々の疑問の声が聞かれる。実際、英国アカデミー賞や放送映画批評家協会賞(Critics Choice Awards)では脚本賞に入っているのだ。存在するIPがあることから、アカデミーは脚色部門に指定したとのことである。
原作がないので原作者もいないが、それに最も近いマテル社は、何度もフィルムメーカーやスタジオが変わった末に行き着いたプロデューサー、マーゴット・ロビーと、彼女が選んだ脚本家グレタ・ガーウィグとノア・バームバックのアプローチを完全にサポート。実際には男性6人、女性5人であるマテル社の役員を全員男性として描くことにも異議を唱えなかった。強烈にフェミニストなこの映画に抵抗を持つ保守派の男性からは、ここも事実と違うと批判が出たが、“元ネタ”であるマテル社は、そこに不満はないのだ。

脚色部門のほか2本の候補作の1本、「アメリカン・フィクション」は、パーシヴァル・エヴェレットが書いた小説「Erasure」を映画化したもので、主人公のキャラクターや展開を含む基本的な部分は同じ。もう1本の「オッペンハイマー」は、カイ・バードとマーティン・J・シャーウィンが書いたノンフィクション本「American Prometheus」にもとづくもの。この本の映画化にはサム・メンデスやオリバー・ストーンが興味を示した時期もあったものの、アプローチを見つけるのが難しく、映画化は無理なのかと著者たちは悲観していたという。ついに映画化され、大ヒットしただけでなく、オスカーに最多部門で候補入りして作品賞のフロントランナーにまでなったことを、著者たちは今どう感じているのだろうか。