『リオパラリンピックが終わって……』
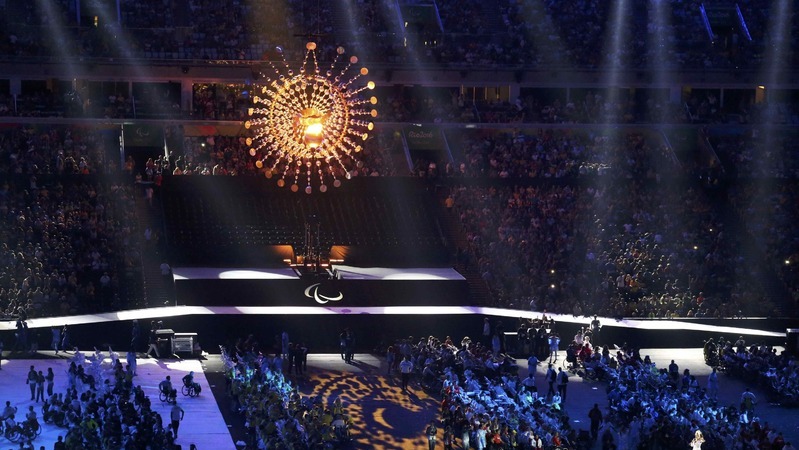
今年のリオ・パラリンピックは、例年になく多くの人たちの目に、耳に触れた大会だったと思う。NHKの連日にわたるライブ中継やプロモーション番組の効果もあった。東京2020まで、彼ら、彼女らに関心を持ち続ける気運が続いて欲しいと切に思う。
ただ相変わらずの「涙と感動」は、果たしていつまで続くのだろうか。
障がいのことにはほとんど触れず、競技、そして競技者そのものを切り取って伝える、そんなスタイルも増えた。あくまでも、ひとりのアスリートとしての視点で取り上げる。筆者も共鳴するところだ。しかし、触れなさすぎると今度はなにやら不自然さを感じてしまう。
なぜ彼が、彼女がその競技に打ち込むことになったのか。視線の向こうには、どんな目標や課題があるのか。障がい者ならずとも、選手たちの背景には、必ずなにがしかの契機、あるいは動機がある。パラリンピアンの場合、それが過去の大病やケガ、生まれ持ったものだったりすることが多い。ならばわずかプロフィール程度の触れ方で片付けていいものなのか。
選手によってはそれを望む人もいる。ただ取材者は、被取材対象者の「負の部分」まで可能な限り理解に努め、近づくことで(あるいは近づくことを許して貰うことで)、初めて距離を縮めていけるのだと思う。
彼女の脚の欠損が、跳ぶ動作にどのような影響を与えているのか。彼の目が見えないことが、いわゆる健常者のフォームとなにが違いとなり、それをいかに克服してタイムを上げているのか。彼ら、彼女らの「負の部分」は、必ずパフォーマンスと無縁ではない。それはアスリートの一端を表現することをも意味する。そしてそれが表現できたとき、負の部分は負ではなくなる。
そうした踏み込み方のリポートも、勿論あった。ただそれらも最終的には「すごい」と括り、「超人」と賛辞する。金メダルしか望まないと目標を立て、しかし戦い敗れ銀メダルに終わった選手がいた。それでも「銀メダルおめでとう」と言葉をかける、その難しさ(これは一般競技でも同じことだが)。
障がい者競技を報じることは、殊の外、難しい。しかし腫れ物に触るようなアプローチでは、本当に彼ら、彼女らを知ることには結びつかないと思う。
※ ※
競技としては金メダル0という現実が残った。数に目標設定を置くこと自体ナンセンスだとは思うが、頑張った選手たちがことごとく、2着、3着に留まったことはどう受け止めるべきなのか(日本は銀10、銅14)。
大会前、取材である選手がこういっていた。
「日本記録を持っていたってなんにも誇れない」
「自己記録更新? だからなにって感じ」。
パラリンピックには、ふたつの面がある。ひとつは障がいを持った選手が、自己との戦いに挑む側面。そこには記録も、順位も度外視した充足感がある。もうひとつは世界との戦い。
今大会、ひとりのスイマーがいた。ブラッドリー・スナイダー(アメリカ)。2011年、アフガニスタンでの任務中に爆破に遭い、目を奪われた32歳の元海軍兵士だ。海軍兵学校では水泳をしていたため、帰国後はパラリンピックを目標に、心血を注いできた。ロンドン大会では2つの金メダルを、そしてリオでは50、100、400の自由形と3つの金メダルを獲得した。彼に象徴されるように、アメリカでは退役軍人の生活保障のみならず、その後の人生のバックアップとして、パラリンピックへの出場の後押しをしている。いわば国家が後ろ盾となっての参加だ。
そうしたいわば「猛者」たちと、日本のパラリンピアンはいかに対峙していくのか。どれだけ記録を度外視した臨み方でも、やはり銅より銀、銀より金がいいに決まっている。それは今大会での選手たちの表情が示していた。他方、男子走り幅跳びでは、マルクス・レーム(ドイツ)が8メートル21の大会新記録でオリンピック選手に肉薄している。車椅子テニスでは、世界ランク1位のステファン・ウデ(フランス)の車椅子が、1500万円相当ということで話題にもなった。競技はひとり歩きしていく。
いずれにせよ、もうすでにパラリンピックは「涙と感動」の舞台ではない。
そんな中、我々一般の者が出来る応援とはなんなのか。
リオ大会は終わった。けれど国内での各種競技の大会はいくらでもある。競泳、車椅子バスケ、陸上…。ぜひ、ローカルな大会にも足を向けよう。レベルは低いかも知れない。パラリンピックのようにはいかないかもしれない。それでも見ることは間違いなく、彼、彼女らへの応援となるのだから。










