桂宮治という落語家の畏るべき本性 NHK舞台袖で見せたその異様な姿
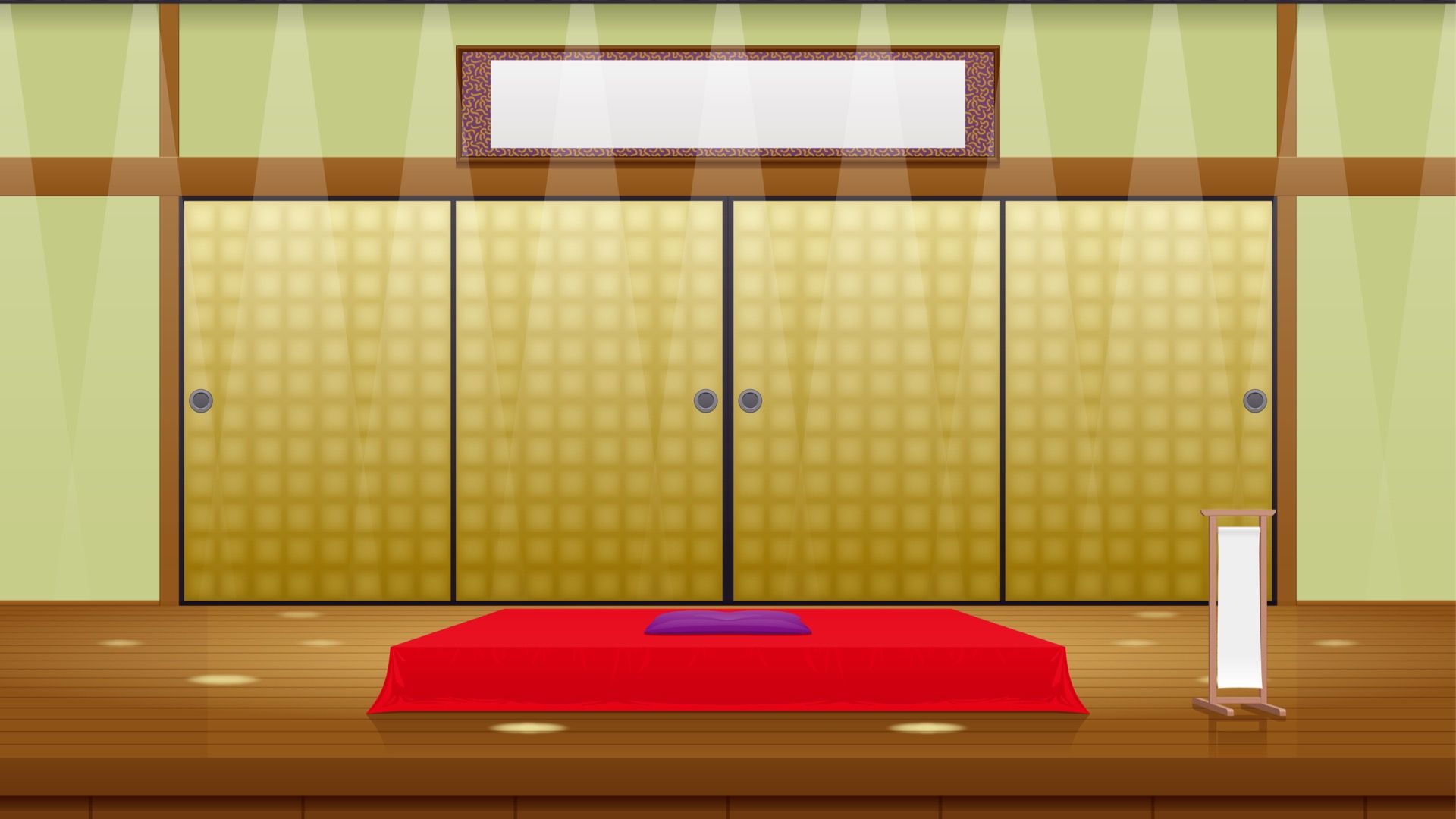
末広亭での公演が「前売り」となった桂宮治
新宿末広亭で二月、「桂宮治主任公演」があった。
二月中席だから十一日から二十日までの十日間興行。
通常の公演なのだが、入場券はイープラスでの前売りとなった。ふつうの売り方ではない。異様な人気があるからだろう。
ただ、桂宮治は「みなし陽性」となり、彼は七日目からの四日間だけの出演となった。
九日目のチケットを売っていたので、九日目(宮治主任としては三日目)の公演を見た。
新宿末広亭の「意味のわからない傾斜のついた桟敷席」の最後尾で見た。
満席の熱気あふれる興行だった。
寄席で「アリーナっ!!」と叫ぶ異様な風景
桂宮治は勢いよく登場してきた。
そのまま座布団に座らずに下手(しもて)の端まで行って、そこにあるスタンドマイクを片手に、「二階席っ〜!!」(末広亭には二階席がある)、「桟敷っ〜!」「アリーナっ!!」と声を掛けて盛り上げた。
落語家が寄席で立ったまま「アリーナっ!!」と叫んでいるのを見たのは初めてだったし、アリーナ席(つまり正面の椅子席)の客が一斉に落語家に手を振るのも初めて見た。
とんでない熱気が渦巻いていた。
桂宮治は、立ったまま、喋り続ける。
落語の前のお話、いわゆる“マクラ”を立ったまま喋っているというスタイルだが、あまり見たことがない。
途中、春風亭昇也が袖から出てきて「座れ! 座ってやれ!」と注意したのだが、宮治は聞き入れず、すでにそれがコントのようであり、どこまでも悪ふざけが続く。
桂枝雀を彷彿とさせた桂宮治「手水廻し」
やがて座布団に座り、でもハイテンションのまま“マクラ”は続いて、そのヨモヤマな無駄話は15分以上続いた。(手元での計測によりますと15分36秒)
そのあとやっと落語に入った。
落語は「手水廻し」。
めちゃくちゃ受けていた。(落語時間は19分39秒)
音は、かなり桂枝雀そのままであった。
私は1970年代に桂枝雀ばかりを聞き続けていた時期があって、枝雀の音が身体中に刻まれているような感覚があり、枝雀をコピーした音には即座に反応してしまうのだが、この日の『手水廻し』はずっと枝雀が乗りうつっているような「音」であった。
たぶん観客の多くは枝雀の音かどうかは気にしてないだろう。私個人の感覚である。
それに、宮治はべつだん枝雀を再現しているわけではなく、ただ、目の前の客を喜ばせるためにあらゆるものを動員しているばかりで、そこに「枝雀の音そのもの」も入っている、ということのようだ。
凄まじい高座姿である。
「手水廻し」をテンポよく聞かせる力量
聞き終わって、楽しかった! という感想を抱いた。
「手水廻し」は、やや昔話/おとぎ話じみているので(つまり誰にでも想像できる展開がつづくので)、テンポよく進めないとうっすら退屈させてしまうのだが、桂宮治の高座ではそんな瞬間が一瞬たりとも存在しない。
いろんな手立てで客を飽きさせず、最後まで突っ走る。
見事な一席であった。
とんでもないところに到達しそうな桂宮治の怖さ
桂宮治の凄みは、この「どんなことをしても客を楽しませる」という一点に尽きるだろう。
いまはまだ、テレビでも見かける楽しそうな兄ちゃんという気配であるが、このまま「とにかく人を笑わせること」に邁進しつづけたなら、とんでもないところに到達しそうな怖さがある。
これはかつて見たことのない場所にたどりつくのではないか、というその一点において「畏るべき」存在におもえてしまう。
前座のころから目立つ存在であった
桂宮治は前座のころから目立っていた。
寄席でも前座なのにしっかり受けていた。
何者だこいつ、と初見のときからおもった。
二ツ目昇進がきまったころには(つまりまだ前座の時代の後半に)個人の会を開き、それが人気であった。ちょっと考えられないポジションを獲得していた。
二ツ目に昇進したのは、平成二十四年(2012年)春である。
ここからがプロの落語家としてのスタートになる。
春に昇進して、秋に「NHK新人演芸大賞」を受賞した。
これは、落語界のM−1的な(R−1的でもいいけど)「若手落語家を表彰するコンテスト」であるが、それを二ツ目になって半年で奪い取ったのである。
桂宮治が取るのではないかという下馬評
下馬評ですでに桂宮治が取るのではないかとおもわれていた。
演芸大賞の前、ある寄席関係者は「宮治は二ツ目をもう少し経験してから、さっと新人演芸大賞を取って、そのままの勢いで真打に昇進するというのが、いろいろにぎやかになっていいとおもうんだけど」という話をしていたのだが、桂宮治はそういう枠にはまるタイプではなかった。
二ツ目になったとたんにさっくりと大賞を奪い、そのあとも仲間たちと目立つ興行をいろいろと行い、落語界をかなり活性化して、そういう勢いをつけて真打に昇進した。
本番直前の出演者は異様に緊張する
桂宮治が大賞を取った「NHK新人演芸大賞」で、印象的なシーンがあった。
この平成二十四年の会は、私も現場にいたので、本番直前の舞台袖で、出演者一同と一緒になった。
太鼓や鳴り物を鳴らす場所がしつらえてあり、そこに控える前座さんたちも動きまわっているなか、係員に連れられて出演者五人が入ってくる。
本番直前なので、出演者は全員、緊張している。顔色が悪い。
いうなれば「これから重大な判決を受ける法廷前で待機している被告人」という風情である。
実際のところ、審査の結果しだいでいろいろ変わることもあるから(M−1ほど劇的には変わりませんけど)、判決前の被告人という比喩は、それほど遠いわけではない。
何度かこの現場にいたことがあるが、出演者がみな恐ろしい緊張の中にあり、声を掛けるのは憚られる空気になる。
若いお姉ちゃんと談笑していた桂宮治
そのとき、桂宮治は談笑しながら入ってきた。
先導してもらっているスタッフの若い女性(NHKのスタッフだとおもうが、ひょっとしたら劇場の案内係だったのかもしれない)、その女性とやたら楽しそうに話しながら入ってきたのである。
何者だこいつ、とすごく驚いた。
若いお姉ちゃんがいたら、とりあえず話しかけて、ちょっと笑わせようとおもうじゃないっすか、と、これは私が勝手に想像しているセリフではあるが、宮治に聞いたら、そう答えそうな雰囲気であった。
なんか楽しそうなのだ。
それもどこまでも自然に楽しそうなのだ。
重罪かどうか判決前の被告たちふうの中に混じって、彼だけ楽しそうだった。
この人はよほど人と話すのが好きなんだろう
もちろん桂宮治の心情まではわからない。
緊張しすぎて話していたのかもしれない。(違うとおもうけど)
ただ、コンテスト本番直前に、出演者がスタッフと談笑している風景は異様であった。
このときおもったのは、この人はよほど人と話すのが好きなんだろうな、ということであり、目の前の人を楽しませたいというのが止まらないのだろう、ということである。
尋常な人ではない桂宮治
べつに口説いていたわけではないだろうし、女性スタッフと仲良くなるつもりで話していたのではないだろうが(でもこれもまた想像でしかない)、でも少し離れたところから見ているかぎりは、「若いお姉ちゃんと楽しそうに話している」ようにしか見えなかったのだ。
ステージ脇の風景として、かつて見たことなく、その後も見たことがない。
本番前にそんな雰囲気だったのは桂宮治だけである。
しかもカメラがまわっているわけでもなければ、そのシーンを誰かに見せているわけでもない。私も手持ち無沙汰だから何気なく見ていただけである。
ごくごく自然体で話していた。
尋常な人ではない。
桂宮治の「芸人としての芯の強さ」
そのとき感じたのは、桂宮治自身が持っている「芸人としての芯の強さ」である。
落語家になる前にかなり長く働いており、それも喋りが中心の営業職であり、かなり優秀だったらしい。(本人がそう語っている)
またすでに結婚して子供もできて、とにかく早く売れないといけないと強くおもっていたようだ。
腹の据わりようが、ちょっとちがっていた。
それに加えて、芸人としての貪欲さを強く感じる。
彼はとにかく目の前の人を楽しませたいのだ。それが徹底している。
桂宮治が出る落語会は見て損がない
落語家であるかぎりは、落語で楽しませるのが早いので、落語を勉強していろんなネタを披露する。
でもおそらく彼にとって落語は道具だろう。
落語の芸をきわめたい、というよりは、落語を使って、目の前の多くの人を楽しませたい、そういう芸人だとおもう。
だから、楽しい。見ていて間違いがない。
桂宮治の名前が入っている落語会なら、行って損はない。
そうおもわせているし、実際にそうだろう。
凄まじい落語家になるのではないか
入門したのが遅かったのですでに45歳と年は食っているが、でもまだキャリア14年目でしかない。落語界ではまだ「若手」に入る年数である。
その時点で、客に必ず受ける落語を展開し、落語の力だけで人気者となり、そして『笑点』にもレギュラー出演するようになった。
全国的に認知が広まるだろう。
『笑点』は出続けているだけで認知が広まり、自分の落語会に客を呼ぶことができる。うまくやらないと芸人そのものが番組に飲まれるという事態も起こるが、宮治は大丈夫だろう。
たぶん、だけど。
四十代後半から五十代にかけての桂宮治の活躍が、どう広がっていくのか、いまのところ予見できない。
凄まじい落語家になるのではないか、とぼんやりと予想するばかりである。
目を離させてくれない落語家
お笑いのおもしろい第一線に十年以上いつづける芸人は、おもしろい人でありながら、やがて修羅を背負ったような雰囲気を出していくようになる。
ライブで身近で見てるときにかぎり、一瞬だけ凄まじい気配を放つのを感じることがある。大笑いしている観客をすっと肌で鋭く測っている。
そういう動物的な気配である。
いずれ宮治にはそれが身につくのではないか。
そうなってからの桂宮治の姿を、寄席で身近に見るのが楽しみである。
十年後、十五年後のそういう「凄まじさを持つ」桂宮治が見たい。
(ま、何かが違ってくる可能性もあるのだけれど)
目が離せないし、そもそも目を離させてくれない落語家である。










